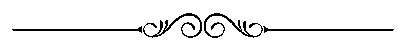二項対立を考える
政治に関する考察には、二つの項の対立という見方が頻繁に出てきます。自由と平等、自由と権威、改革と秩序、縦型の支配と横型の統合、等々です。二項対立の見方には、政治に限らず、人間にかかわるさまざまな物事、さらには、自然現象についても、数多くあるようです。
注意しなければならないのは、こういう二項対立の見方が、思考の対象となっている物事自体に内在しているものなのか、それとも、私たちが物事を考える際に混乱に陥らないための便宜的手段なのか、という点です。手段として便利だからといって、そのことは、二項対立を思考対象に内在する本質とみなす根拠になるとは限りませんし、たとえある物事では本質だと言えても、他の物事でも同じだと考えてよい理由にもなりません。さらに言うと、二項対立を内在的なもので避けられないとする見方は、しばしば、どちらか一方の項が正しく他方は正しくないという、一元的評価基準を前提にしています。逆に言うと、そういう一元論があるからこそ、二項対立が起こってくるわけです。
二項対立に関するこのような反省は、何らかの問題に関して自分自身が二項対立的な見方に巻き込まれていると、むずかしくなります。私がミルの研究を始めた頃のさまざまなミル解釈の場合もそうでした。ミルは自由主義者だ、いや権威主義的な側面もある、個人主義者だ、いや集団主義的な面があるといった具合で、いずれの面も否定できないとなると、ミルは折衷主義者だ、過渡期の思想家だ、という説明になっていました。こういう二項対立的な見方には、明らかに、自由主義と社会主義の対立といういイデオロギー対立が少なからず反映されていました。そのため、二項対立的な見方は、政治においては、どうやらイデオロギーや党派の対立と親和性があるようだ、と若い頃の私は思ったものです。
しかし、実際には、二項対立の問題点は、そのような政治的党派性の問題に限られていないようです。自然科学や形而上学の分野にまでおよぶ根深い問題と言うべきなのです。その点に私が気づいた経緯を回顧的に書き留めておきたいと思います。
二項対立の問題を考える以前に、私が直面していたのは決定論の問題です。そこからやがて、二項対立の問題に気づいていった、という経緯です。
18世紀から19世紀にかけての人間にかかわる物事の考察(政治理論、道徳哲学、心理学、経済学、社会学等々)は、自然科学、とりわけ、ニュートン力学のパラダイムに強く影響されていました。カントの『純粋理性批判』やミルの『論理学大系』は、その典型的な例です。ニュートン力学のパラダイムは、特定の原因は必ず特定の結果をもたらすという、決定論を採用していました。しかし、これを人間にかかわる問題系列に適用すると、西欧思想が古くから重視してきた人間の自由意志という考え方と衝突してしまいます。カントの『実践理性批判』は、人間の自由意志を道徳性の公理的前提に設定して強行突破しましたが、ミルの繊細な精神は、人間や社会の科学的客観的認識の必要性と、自由な行為主体という自己認識が持つ人間的価値との板挟みに苦しみ続けました。
ミルほど深刻ではなかったのですが、決定論の問題は私にとっても悩みの種でした。その壁は、なんとか突破できたように思えても、形を変えながらぶつかることを繰り返していました。最終的な脱却を助けてくれたのは、オルテガの議論だったように思います。今は、この点に立ち入りませんが、つねに将来に向かって存在している人間という見方で腑に落ちたのでした。「存在」の捉え方という形而上学の問題を避けている限り、つまり、認識論哲学をよりどころにする啓蒙主義的な立場に固執する限り解決しない問題なのだな、とつくづく思ったものです。
複雑系という自然科学の新しい理論があることに気づいたのは、そのあとのことです。決定論の問題は、自然科学においても克服すべき課題だったことを知りました。そして、決定論の問題は、二項対立の問題とも関連しているのではないか、と思うようになったのです。
複雑系の見方が注目するのは、因果的に一義的には決定されずに、しかも、一定の秩序を保ちながらも動的な自己組織化が進んでいく現象で、生命現象はその端的な一例です。自然科学に関してまったくの素人である私が魅力を感じたのは、この見方の中で出てくる「カオスの縁(the edge of chaos)」という言葉でした。「縁」は、より正確に言うと、無秩序な暴走状態であるカオスと接するばかりでなく、凍りついた動きのない固定状態とも接し、両者の中間に位置する境界領域を指しています。生命などの複雑系は、この領域で自己組織化し進化していく、ということです(S.カウフマン『自己組織化と進化の論理』、筑摩学芸文庫(2008年)や、M.ワールドロップ『複雑系』、新潮社(1996年)を参照)。
複雑系の生命的な性格に関する興味深いエピソードが、ワールドロップ『複雑系』という本で紹介されています。1970年代、ケンブリッジのコンピューター科学者が、コンピューター・プログラムの退屈なデバッグ作業の合間に、気晴らしで、複雑系の概念にもとづいて作られたゲーム(game of life、日本ではライフゲームと呼んでいる)を動かしていました。ふと気づくと、ゲームを表示しているディスプレイの方に、何か生きものがいるような気配を感じたというのです(M.ワールドロップ『複雑系』、269頁)。今ではこのゲームはWindows 版もあるので、私も試してみたことがあります。鈍い私には、さすがに生命の気配までは感じられませんでしたが、何か不思議な感じがしたのは確かです。機械的でもなければ完全にランダムでもない動きが、不思議感を与えるのでしょう。
複雑系の考え方は、自然科学を大きく変えつつあり、社会科学でも、たとえば、進化論経済学などの企てと連動しているようです。とはいえ、複雑系の考え方が突き抜けていくことになったガラスの壁、つまり、一義的な因果的あるいは論理的な見方の壁にぶつかった思想家は少なくないように思います。哲学者の鶴見俊輔は、ある新聞記事の中で、非常に興味深い指摘をしていました。
| 第2次大戦中、ハーバード大学生だったころ、後にノーベル文学賞を受ける哲学者ラッセルが「疲れて家に帰ったとき、自分が言ったことは全部間違いだと思う瞬間がある」と言ったのをこの耳で聞いた。「言うこと全部が間違い」と言うこと自体が矛盾だが、学者としてではなく人間として生きるときには、その一瞬の感情を否定できないんだ。哲学者ホワイトヘッドの講演も聞いた。「精密であることは、つくりもの(フェイク)だ」と言った。矛盾のないことを目指す記号論理学体系の「プリンキピア・マテマティカ」の共著者2人が、ほぼ同時代にこう語っている。(2006年12月27日朝日新聞(朝刊)13面、「鶴見俊輔さんと語る ― 生き死に学びほぐす」) |
| フェヒネルは或朝ライプチヒのローゼンタールの腰掛に休らいながら日麗に花薫り鳥歌い蝶舞う春の牧場を眺め、色もなく音もなき自然科学的な夜の見方に反して、ありの儘が真である昼の見方に耽ったと自らいっている。私は何の影響によったかは知らないが、早くから実在は現実そのままのものでなければならない、いわゆる物質の世界という如きものはこれから考えられたものに過ぎないという考を有っていた。まだ高等学校の学生であった頃、金沢の街を歩きながら、夢みる如くかかる考に耽ったことが今も思い出される。(版を新にするに当って、昭和11年10月、西田幾多郎『善の研究』、岩波文庫、7頁) |
|
日本人の思想的事実を可能ならしめた論理は単なる矛盾律によっては規定され得ぬこと、これを単にネガティヴにではなく、ポジティヴに理解せしめ得るものは西欧的思想のカテゴリーとは異なるものであことは明らかである。(下村寅太郎「日本人の心性と論理」、『下村寅太郎著作集・第12巻』、みすず書房(1990年)所収、555頁) |
論理を徹底的に追求することや決定論ですべてを説明しようとすることによって、リアリティの感覚が失われるのだとすれば、それはつまり、現実が矛盾や非決定性を含んでいる、ということを意味しています。「絶対矛盾の自己同一」という西田の難解な言葉も、そのことを指しているのだと思われます。
矛盾するものの並存を論理でねじ伏せ一元的に理解しようとする西欧思想の支配的な流れへの異議申し立ては、よく見ると、西欧思想の歴史自体の中にも現われています。ただ、ほとんどの哲学史や思想史が一元的な見方の支配下にあるため、目につきにくいのです。
実のところ、二項対立を一元論でねじ伏せる流れに同調しているように見えるミルも、そこに収まらないものに敏感でした。
ミルは、すでに述べたように、決定論の持つ宿命論的性格に悩まされた自由の哲学者でもあり、その根底には、人間の生命や心の複雑さに対する鋭敏さがあったように思われます。たとえば、ミルは『功利主義論』の中で、幸福を論ずる際に、人間が動いていることで得られる幸福感と静止していることで得られる幸福感について、いずれも欠くことのできない二大要素として言及しています(ミル『功利主義論』(井原吉之助訳)、世界の名著・49、中央公論社、474頁)。また、ミルの『代議制統治論』には、次のような一節もあります。
|
人間にかかわる万事において、対立しあう影響力は自らの固有の有用性のためにも、それぞれ、生き生きとした活力を保つ必要がある。よい目的でも、並存すべき別の目的をなおざりにしてそれだけを追求すると、最終的には、一方が過剰で他方が不足するばかりでなく、排他的に重視してきたものまでが衰退し消滅してしまう。」(『代議制統治論』関口正司訳、岩波書店、第6章、106-107頁) |
この見方では、対立しているそれぞれと、相互の対立関係は、いずれも消滅し解消することはけっしてありません。解消するというのがヘーゲル哲学の本当に正しい理解なのかについては、非専門家の私にはわかりませんが、ヘーゲル左派の流れをくむと自称していたマルクス主義の唯物弁証法では、正(テーゼ)と反(アンチテーゼ)の対立は止揚(アウフヘーベン)されて合(ジンテーゼ)となり、対立は克服され最終的に消滅すると見ていたようです。共産主義革命による「歴史の終焉」ということでしょうか。総じてこれは、マルクス主義に(永久革命論というのもありはしましたけれども)多少なりとも影響を受けた私たちの世代までぐらいを、強く呪縛していた見方だと思います。終末論的性格を持った論証抜きの形而上学的な迷信といってもよいかもしれません。ところが、動的平衡の見方では、対立は消滅しません。対立にともなう緊張や苦悩も同様です。対立は消滅するのではなく、新たな意義を与えられて受容されるのです。無力感に打ちのめされた末の諦念とは違います。受容し耐え工夫してやり過ごす力を得ようとする前向きな何かがあります。この意味でなら、「悟り」と呼んでもよいし、また、「進化」と呼んでもよいように思います。【補注】
【補注】長寿に恵まれた日野原重明さんは、神に身を捧げ他者に奉仕する人生を送り多くの人の死も看取りましたが、亡くなる少し前に、やはり死は怖い、と言っていました。これほどの人なのに死について悟りはなかったのか、と若い頃の私なら思ったでしょうが、「悟り」の意味がわかっていないとそう思ってしまうのです。死を怖いと思いつつ、それに耐え向かい合える境地が「悟り」の意味だ、というのが今の私の理解です。
こうした「対立物の結合」とか「対立物の一致」という発想は、古くはヘラクレイトスにまで遡るようです。西欧思想史では裏街道的なものとして扱われがちだったように思われますが、けっして途絶えはしませんでした。この系列の大物思想家はたくさんいます。まず、この系列の巨星として、キリスト教の教父であるアウグスティヌスをあげてよいと思います。青年時代のアウグスティヌスは、キリスト教に懐疑をいだき、一時期、マニ教の信者となりました。キリスト教の神は、全能と善の両方の属性を持つとされているが、これではこの世の悪を説明できないのではないかと考えたのです。善なる神は善ゆえに悪を創造できないのであれば全能ではないし、悪をも創造する全能な神は善とは言えない。いわゆる神義論の問題です。理屈っぽい議論のように思えますが、実はアウグスティヌスにとって、これは知的パズル解きの問題ではありませんでした。自分の中にもある悪というものへの感度の高さがアウグスティヌスにはあり、それが彼の思想の深さにつながっています。見て見ないふりをして、きれい事だけを言うということに甘んじられない人なのです。自分にも、教会の中にさえも、悪は実在する。世界を善なる神と悪魔との対立という二元論的観点から説明するマニ教は、悪の実在性を痛感しているアウグスティヌスにとって、当初は知的に納得できるものに思えたのでした。
しかし、マニ教には論理的な整合性はあっても、悪を克服し心を救う能動的な契機が貧弱だと気づいたアウグスティヌスは、やがてマニ教から離れ、キリスト教に復帰します。彼が一度は見限ったキリスト教に戻る際に大きなきっかけとなったのは、新プラトン主義との出遭いでした。それをつうじて、現世と来世をまったく別のものと二分するのではなく、両者の混在を引受けようとする境地に達したのです。たとえ、いずれは終末に至る有限の現世であっても、愛すべきものは現に存在している。そんなものは無価値だと退けるのではなく、そうした愛すべきものを愛してよいのである。それは、有限な現世の中で神が与えているものなのである。しかしまた、そうであればこそ、執着しすぎてもいけない。現世を機械的に否定してしまう彼岸主義でもなく、かつ無限定の現世肯定でもなく、そのあいだを、神の愛と神から与えられた自由意志によって進もうとするところにアウグスティヌスの思想のダイナミクスがあります。「神の国は巡礼の途上にある」という有名な言葉はこういう考え方の到達点でした。(アウグスティヌスについては、私の恩師である半澤孝麿先生の講義、それに山田晶『アウグスティヌス講話』(講談社学術文庫)から多くを学びました。)
ルネサンス以降代降であれば、ジョルダーノ・ブルーノ、ニコラウス・クザーヌス、コールリッジなどの名前が思い浮かびます。オルテガは、直接にヘラクレイトスの名前をあげて、反一元論の発想の重要性を指摘しています。それは、ネオ・プラトニズムや錬金術の経路からユングにもつながっています。また、西田幾多郎も、『善の研究』の中でヘラクレイトスの名前に言及しています。近年では、生物学者の福岡伸一さんが、自らの動的平衡論と西田哲学との対話を試みているのが注目されます。(福岡伸一・池田善昭『福岡伸一、西田哲学を読む』、明石書店、2017年)
二項対立の考え方を超えようとする思想の歴史が書ければと思いますが、私の力量ではとうてい無理な話です。西欧にとどまらないグローバルな思想史にならざるをえないので、なおさらです。後続する世代の集団的努力に期待しましょう。とはいえ、自分としても、気にかかっているところで、少しずつエッセイの形で書き重ねていくことができればと思います。もちろん、それに劣らず重要なのは、この考え方を自分自身の残された人生に反映させていくことでしょう。自分の政治哲学的思考に活かしていくことも、その一部だと思っています。