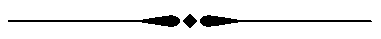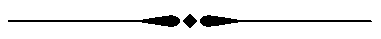学生:ルソーがフランス革命の思想的源流だという見方は、これまでの勉強で卒業できたと思うのですが、ルソーの市民宗教の議論には、やはり、フランスのような世俗的社会の強烈な反宗教感情やそれに根ざした不寛容に通じる要素があるような気がしてなりません。
教師:そういう印象を共有している人は少なくないと思います。ただ、それには、ルソーの「市民宗教」が排他的な国家宗教と混同されたり、宗教的寛容が最大の強調点になっている点が見落とされていたり、ということが大きく影響しているように思えます。さらに言うと、そもそもルソーの「市民宗教」が宗教と呼べるのか、呼ぶべきなのかも私は疑問に思っています
学生:それは、どういうことなんでしょう?
教師:ルソーの議論を検討する中で、おいおい明らかにしていきたいと思います。その前にまず、検討のとっかかりとして私の方から質問です。ルソーはこの章で、宗教を何種類に分類していると思います?
学生:まず、次の文章で二種類、登場しています。太字で示します。
|
社会は一般社会か特殊社会かであるが、この社会との関連において、宗教もまた二つの種類に区別されうる。すなわち、人間の宗教と市民の宗教である。前者は、神殿も祭壇も儀礼もなく、至高の神への純粋に内的な礼拝と、道徳の永遠の義務とに限られているような、純粋で単純な福音の宗教、真の有神論であり、自然的神法とも呼びうるものである。後者は、特定の一つの国においてのみ制度化され、この国にその神々、すなわち固有の守護神を与えるものである。この宗教は、その教義、その儀礼、そして法律の定める外面的な礼拝を持っている。これを信奉している唯一の国民を除けば、すべての者がこの宗教にとって不信の徒、異邦人、野蛮人である。この宗教は人間の義務と権利とを、その祭壇の範囲にしか広げない。原始民族の宗教はすべてこのようなものであった。それは、国家的あるいは実定的神法と名づけることができる。(第4篇第8章、203頁:p.348)
|
一般社会というのは世界全般、特殊社会は個々の国々だと思います。宗教の種類に関しては、さらに、もう一種類が加わります。
|
もっと奇妙な第三の種類の宗教がある。それは、人々に二つの法体系、二人の首長、二つの祖国を与えて、人々を矛盾した義務に従わせ、人々が信者と市民の役割を使い分けるように仕向けるものである。ラマ教や日本人の宗教がそうであり、ローマのキリスト教もそうである。それは、僧侶階級の宗教(la religion du Prêtre)と呼ぶことができる。この宗教からは、名前のつけようもないよう、混合した反社会的な一種の法が生ずる。(第4篇第8章、203頁:p.348)
|
つまり、①人間の宗教(la religion de lʼhomme)、②市民の宗教(la religion du citoyen)、③僧侶階級の宗教(la religion du Prêtre)の三種類です。
教師:まずは、その三種類ですよね。
学生:「まずは」というのは、ちょっと微妙な言い方ですね。
教師:はい、その意味は、もう少しあとで示したいと思います。さしあたりここで注目する必要があるのは、これらの宗教に対するルソーの視点の置き方です。
宗教が人間にとって切実なニーズであるのは、人は誰でも、親しい人の短くもあり必ずしも思い通りにならなかった人生の終わりを目にしたときに、また、自分自身の同様の人生の終りを考えたときに、底知れぬ悲しさやさびしさや空虚感を経験するからだと思います。もちろん、これとは別の考え方もあるでしょうが、ともかく、宗教それ自体を論じるという意味での宗教論は、人生の有限性という条件の下での自他の魂の救い、という問題が中心になると思います。
しかし、ここでのルソーの議論は、そういう意味での宗教論ではありません。宗教そのものの質についても評価していますが、中心的な関心は、政治的な効用です。そのことは、三種類の宗教のいずれも、「自然的神法」、「国家的あるいは実定的神法」、「反社会的な一種の法」と呼び換えられていることにも示されています。人々の政治的服従を強化し政治秩序を支える契機、という視点から、つまり、政治的な効用の見地から、ルソーは宗教にアプローチし分類しているのです。
学生:たしかに、三種類の宗教はいずれも、そういう意味での政治的効用の基準から、長所や短所が指摘されています。
|
政治的な観点から考察すると、これら三種の宗教はどれも、それぞれに欠点を持っている。第三の宗教がよくないことはあまりにも明白だから、そのことを論証して楽しむのは時間の浪費というものである。社会的統一を破るものは、すべてなんの価値もない。人間を自分自身と矛盾させるような制度は、すべてなんの価値もない。(第4篇第8章、203-204頁:pp.348-349)
|
これは、僧侶階級の宗教への評価です。
教師:それでは、ついでに、他の二種類の宗教に対する評価も整理してください。
学生:うまくまとめる自信がないので、引用で勘弁してください。市民の宗教に対するルソーの評価は、政治的効用の観点に加えて、宗教自体の質の観点からも行なわれています。
第二の宗教は、それが神への礼拝と法への愛とを結びつけるかぎりにおいて、また祖国を市民たちの熱愛の対象とさせ、国家に奉仕することがとりも直さず守護神に奉仕することになるのだ、と教えるかぎりにおいて、よい宗教である。それは一種の神政であって、そこでは統治者以外には教主はありえず、行政者以外には僧侶もありえない。……
しかし、この宗教が、誤謬と虚偽にもとづいており、そのために人々を欺き、軽信的、迷信的にし、また神への真の礼拝を空虚な儀式のなかにおぼれさせてしまうなら、そのかぎりにおいて悪い宗教である。それは、排他的、圧倒的となって、人民を残忍に不寛容にするときもまた、悪い宗教である。そうなれば、人民は、殺人と虐殺のみを熱望し、彼らの神々を認めない者はだれでも容赦なく殺しながら、神聖な行為をしているのだと思いこむ。そのために、このような人民は、他のすべての人民〔国民〕と戦う自然状態に陥るが、その状態はこの人民自身の安全にとってもきわめて有害である。(第4篇第8章、204頁:p.349)
|
もう一つの人間の宗教についても、ルソーは、宗教の質と政治的効用の二点から評価を行なっています。
そこで、人間の宗教、すなわちキリスト教が残る。しかし、それは今日のキリスト教ではなく、福音書のキリスト教であり、今日のそれとはまったく異なったものである。この神聖で崇高で真実な宗教によって、同一の神の子である人間たちは、すべて互いに兄弟と認め合うのであり、彼らを統一する〔霊の〕社会は〔この世において〕死滅しても解体することはない。
だが、この宗教は、政治体となんら特別の関係を持っていないので、法律に対しては、法自身から出てくる力を認めてやるだけで、それに別の力をなんらつけ加えるわけではない。このために、特殊社会の偉大なきずなの一つが、効力を発揮しないままに放置される。それだけではない。この宗教は、市民たちの心を国家に結びつけるどころか、彼らの心を地上のすべてのものから引き離すのと同じように、国家からも引き離してしまう。社会的精神にこれ以上反するものを私は知らない。(第4篇第8章、204-205頁:pp.349-350)
|
細かい点についての質問になるかもしれませんが、人間の宗教が、今日のキリスト教ではないのだとすると、今日のキリスト教はどんな宗教だとルソーは考えているのでしょう? カトリックが僧侶階級の宗教であることは、ルソー自身が明言していますが。
教師:細かい点ではなく重要な点の質問だと思いますよ。ルソーは明言していないので推測ですが、キリスト教が旧東ローマ帝国の諸国や、あるいはイギリスやドイツの一部のように国教会制度になっている場合は、「市民の宗教」か、それに非常に近いものではないかと思います。
学生:ジュネーヴの場合はどうなんでしょう?
教師:カルヴァンの時代だと神政政治と言われていましたから、教会が国家に対して優位な体制だったと考えられますが、この時代のジュネーヴがどうだったかは不勉強でわかっていません。でも、ある程度のことは言えるかと思います。ルソーは、ジュネーヴを離れて一時期カトリックに改宗していましたが、再度、ジュネーヴに戻り市民権を回復します。その際には、ジュネーヴ教会への再加入が必要で、再改宗が本物かどうか教会関係者による確認手続が求められたようです。このことから、市民の資格と教会のメンバーシップが表裏一体だったことは、少なくとも推測できます。また、ルソーがジュネーヴを追われるようになったときの理由は、『社会契約論』が反政府的であるというだけではなく、『エミール』の議論が非キリスト教的だという点にもありました。遅くとも、この迫害を受けた段階では、ジュネーヴの宗教は実際には、排他的で不寛容な「市民の宗教」だ、とルソーは考えたことでしょう。それを示すものとして、『山からの手紙』の一節を引いておきます。ルソーは、『社会契約論』で指摘していた三種類の宗教のそれぞれの弱点を再説したあと、次のように言っています。
|
以上がしたがって、政治体との関係における双方にとっての弊害とそれから生じる不都合であります。しかしながら、国家が宗教を持つということは重要なことです。それにはいくつかの重大な理由があるのですが、そのことについては私はいたるところで力説しておきました。しかし、法律さえもねじまげ、市民の義務にさからうような野蛮で迫害的な宗教を持つくらいなら、持たないほうがまだましであります。私に関してジュネーヴで起こったいっさいのことは、まさにこの章を実例において提示するものであり、私の説いた道理の正しさが、私の一身上の出来事によって証明されたにすぎないと言えるでしょう。(「第一の手紙」、ルソー全集・第8巻、217頁)
|
学生:政治的観点からは三種類の宗教のどれにも弱点があるとすると、「市民宗教」(la religion civile)というこの章のタイトルの積極的な意味がなくなって、宙ぶらりんになる気もするのですが。でも、ちょっと待ってください。三種類の宗教の弱点を指摘したあとでも、宗教に関する議論はもう少し続いていて、章のタイトルと同じ「市民宗教」(la religion civile)という言葉も出てきますね。これは、先ほどの「市民の宗教」(la religion du citoyen)と同じものなのでしょうか?
教師:その疑問は当然です。私が最初に、「まずは」三種類と言った理由はそこにあります。ルソーが排他的で不寛容だとした「市民の宗教」(la religion du citoyen)と、今、登場してきた「市民宗教」(la religion civile)は、実際のところ、まったく別のものなのです。この両者が混同されて、国家主義者ルソーといった見方が出てきてしまいました。でも、「市民宗教」は、この章に登場する四番目の「宗教」なのです。これを宗教と呼べるのかどうかは、議論の余地があるとは思いますが。【補注】
【補注】「市民の宗教」や「市民宗教」という訳語は、ルソーのわかりにくい議論で戸惑っている読者をますます混乱させるものだと思います。ルソーがそれぞれについて与えている内容に適合した訳語に代える必要があります。今の場合、la religion du citoyen は一つの国の国民にだけ信奉されている宗教であり、国民宗教とでも訳した方がよさそうに思えます。他方、la religion civile という言葉は矛盾した奇異な表現です。なぜなら、civile は世俗的・非宗教的という意味を持っているからです。「市民宗教」という訳語ではそのニュアンスが伝わりません。「公民宗教」という訳語もありますが、「国民宗教」との違いが伝わりにくい感じです。よい対案はありませんが、公共体(res publica)信仰とでも言えるようなものです。ピタッとくる訳語をめざしたルソー専門家の今後の奮起を期待します。
学生:なるほど。三種類ではなくて、四種類なのですね。そこで四番目の「市民宗教」についてですが、これに関する説明の最初の部分がよくわかりません。
|
しかし、政治的考察を離れ、権利の問題に立ち返って、この重要な点についていくつかの原理を定めよう。社会契約によって与えられる主権者の臣民に対する権利は、先に述べたように、公共の利益(lʼutilité publique)という限界を越えるものではない。だから、臣民は、自分の信条が共同体にかかわってこないかぎり、その信条を主権者に向かって告げる責任はない。ところで、各市民に自分の義務を愛させるような宗教を持つということは、国家にとって、まことに重要である。しかし、この宗教の教義が、国家やその構成員の関心をひくことがあるとすれば、それは、その宗教を信じる者が他人への実行を課せられている道徳や義務に、この教義がかかわってくる側面に限られる。その他の点では、各人は自分の好むままの信条を抱いてよいのであり、それは主権者の関知すべきところではない。なぜなら、主権者は彼岸の世界においてはなんの権限も持たないから、臣民たちがこの世においてよい市民でありさえすれば、来世において彼らの運命がどうであろうと、それは主権者にはかかわりのないことだからである。(第4篇第8章、209頁:p.353)
|
「政治的考察を離れ、権利の問題に立ち返」る、というのはどういうことでしょうか?
教師:政治的服従を強化するという政治的効果の観点からではなく、政治的服従の正当性という観点から考える、ということだと思います。つまり、社会契約のそもそも論に立ち返ると、政治的服従の強化といっても限度がある、その限度は、各人の自由や安全の確保という各人の共通利益=公共の効用(lʼutilité publique)という社会契約の目的から生じる、ということです。そうした限度はあるにしても、政治的服従を強化するような宗教、「各市民に自分の義務を愛させるような宗教」はやはり必要だ、というわけです。
学生:人々の自由と安全を確保するために課される義務を尊重することはたしかに重要でしょうが、そういう尊重の気持ちを強化するものを「宗教」と呼ぶ必要があるのでしょうか。
教師:ルソーは、政治的義務の厳粛で死活的な重要性を当時の人々に真剣に受け止めてもらうために、「宗教」という言葉を使う必要を感じていた、ということではないでしょうか。先の引用にあったように、この「宗教」は、来世での救いにはまったく無関心です。救済論のないものを「宗教」と呼べるのか、大いに疑問ですが、ともかくルソーは、今だったら、市民意識とか市民精神とか公共精神と呼べるものに、もっと重々しさを加えようとして、次のようにも言っています。
|
それゆえ、純粋に市民的な信仰告白が必要であり、その箇条を定めるのは主権者の役目である。この箇条は厳密には宗教の教義としてではなく、それなくしてはよい市民にも忠実な臣民にもなりえないような社会性の感情として定められるのである。主権者は、それを信じることを何びとにも強制することはできないが、それを信じない者はだれであっても、国家から追放することができる。主権者は、彼を不信心な人間として追放しうるのではなく、非社会的な人間として、法と正義とを誠実に愛することのできない人間として、また、必要のさいに自己の生命を義務のためにささげることのできない人間として、追放しうるのである。(第4篇第8章、210頁:p.354)
|
現代の日本では、大臣のような特別公務員のことは知りませんが、一般公務員の場合は、就任するときに憲法の遵守を宣誓するよう求められます。私も公立大学の助手になるときに経験しましたが、宣誓というのは、非宗教的なものであっても、それなりに重みがあります。ルソーは同じような形で、社会契約によって正当性を得ている国制であることを自明の前提にした上で、そうした国制への忠誠(政府への忠誠ではない)を、全市民に求めているわけです。しかも、ルソーは「この箇条は厳密には宗教の教義としてではなく」と言いながら、「信仰告白」という言葉を使い、宗教に匹敵する厳粛な意味を持つことを伝えようとしています。
学生:でも、たんに宗教になぞえるというだけではなくて、次のような「積極的教義」についてのルソーの説明には、本来的な宗教の色合いが出ているようにも見えるのですが。
|
この市民〔国家〕宗教の教義は、単純で数少なく、説明や注釈なしで、的確に表現されなければならない。強く、賢く、慈愛に満ち、予見し配慮する神の存在、来世、正しい者の幸福、悪人への懲罰、社会契約および法律の神聖性、これらが積極的な教義である。消極的な教義については、私はそれをただ一つにとどめる。それは不寛容である。不寛容は、われわれが排除した諸宗派に属するものである。(第4篇第8章、210頁:p.354)
|
教師:ここで述べられている「積極的な教義」に、ルソーの「歴史的な制約・限界」を見る議論はあるでしょうが、そういう評価と、ルソー本人やルソーが説得しようとした人々がどう考えていたかの理解とは、やはり、別の問題として考えた方がよいと思います。
学生:別の問題として考えるというのは、具体的にはどういうことでしょうか?
教師:政治的服従の動機を強化するために動員できる厳粛さをそなえた既存の資源として使用可能な宗教的信条を、ルソーがどう考えたかに着目する、ということです。つまり、ルソーや当時の人々が持っていた宗教的信条の最大公約数として、たがいに折り合えそうなラインがこの「積極的教義」あたりにあった、少なくともルソーはそう考えただろう、ということです。そういう共通項があれば、それを市民宗教の教義として主権者が定めても、どの宗教的立場も損ねることにはならないはずです。現実問題としては、ジュネーヴ教会の信徒とジュネーヴ市民とが重なり合っているわけですから、ジュネーヴ教会が「積極的教義」と対立しない立場をとり、また、不寛容でない限り、それでよろしい、ということになります。こういう条件なら、ジュネーヴにとって無理難題ではなく、十分満たすことができるだろう、とルソーは期待していたのだと思います【補注】。
【補注】このような見方で、仮にルソーが同時代あるいは連邦憲法制定後のアメリカを見ることがあったら、どう論評しただろうと、思うことがあります。主権者は明文的に市民宗教を規定してはいないものの、独立以前から、習俗として、あるいは憲法の精神的基盤となる政治道徳の次元で、国民のキリスト教信仰と宗教的寛容の双方が自明の前提として確立しているので、市民宗教が実質的に機能している、とルソーは評価しなかっただろうか、と想像してしまうのです。そして、のちにトクヴィルがこれに類似した評価をしたのは、同じようなルソー的な見方があったからではないか、というところにまで想像が広がっていきます。
学生:ルソーは、まったく新規に市民宗教を作ろうとしてるのかと思っていました。
教師:19世紀になると、フランスのサン・シモンやコントが、キリスト教に代わる社会統合の手段として、世俗的宗教の教団作りを本気で考えるという例がありました。また、フランス革命時にも、宗教的儀式をなぞるような世俗的な祭典を国民統合に利用する企てがあったようです。そういうこともあって、ルソーの場合も、新規に作り出すべきものとして市民宗教を提唱しているように受けとられがちです。しかし、実際には、ルソーは、先ほど示したような形で、市民宗教に既存の宗教が折れ合えるかどうかを見定めようとしていたように思います。
学生:急進的で理想主義的で、その分、抽象的でもある政治思想家というルソー・イメージとは、ずいぶん違っているのですね。
教師:自分が生まれ育った大事な土地のことですからね。他人事のような議論はできないはずです。そうそう、他人事にできない話として、一言、重要な点を付け加えさせてください。今日はもう、これまでにないほどの長丁場になっていますので、これを最後の一言にします。よろしいですか。
学生:最終回ということで時間はたっぷり確保してありますので、どうぞお願いします。
教師:ありがとう。付け加えておきたいのは、ルソーがこれほど市民宗教の問題を重視したことを、過去の他人事のように扱うべきではない、ということです。正当な政治社会における政治的義務が厳粛であることを実感させてくれるものとして、宗教に代わるどんなものがあるのか、ありえるのかという問題は、現代でも避けて通れない問題だと思います。もっぱら道徳的な基礎付けに集中するタイプの政治哲学は、この問題に正面から向かい合っていなかったように思えます。権利や効用を本当に確保するためには、権利や効用という言葉では言い尽くせない何かが必要なのではないか、という問題です。政治の世界にはいつでも、文字通りに死活的な、人々の生命を左右する問題が潜在しています。潜在どころか、顕在している地域もたくさんあります。世俗の問題をもっぱら扱うはずの政治は、究極のところで、生死の意味という、政治の次元では答えきれない性質の問題を抱え込んでいます。
もちろん、この点については、さまざな考え方があるでしょう。しかし、どのように考えるにせよ、少なくとも、ルソーの「市民宗教」が「消極的な教義」として不寛容を強く禁じている点を想い起こすことは、非常に重要だと思います。ルソーは、共通利益の追求という点で一致した政治社会を維持しようとしました。市民宗教が求める寛容は、そういう一致があるという意味での社会の一体性、国民(市民)の一体感に不可欠の要素でした。こういう見地からルソーは、以下に示すように、不寛容に厳しく対処することを求めたのでした。
|
排他的な市民〔国家〕宗教(religion nationale exclusive)がもはや存在せず、また存在しえないいまとなっては、教義が市民の義務に反するものをなんら含んでいないかぎり、他の宗教に対して寛容であるすべての宗教に対して、人は寛容でなければならない。しかし、「教会の外に救いなし」とあえて言う者があれば、国家が教会でもないかぎり、また統治者が教主でもないかぎりは、何びとであっても国家から追放されるべきである。(第4篇第8章、212-213頁:p.355)
|
後半のセンテンスの「国家が教会でもないかぎり」、「統治者が教主でもないかぎり」という表現は、国家と教会の一体化を肯定的に見ているのではないかと感じさせるかもしれませんが、しかし実際のところは、国家が教会になり、統治者が教主になることなど、ルソーにとって認めがたい事態だったことは間違いないでしょう。ですから、そういう認めがたい事態において、不寛容を主張する者が追放されるどころか歓迎されるといったことがあったとしても、まっとうな政治社会では宗教的不寛容の主張には厳しく対処すべきだ、というのがルソーの考えだったと見てよいと思います。宗教的な不寛容は政治的な不寛容と切り離せないのであり、排他的で不寛容な宗教は、たとえ政治権力と一体化していなくても、市民の内面の自由ばかりでなく世俗面での権利や自由も侵害し、そうすることで、世俗の問題を管轄する政治的主権を簒奪していることにもなる、非常に危険だ、ということです。ルソーは、宗教的信条を理由にジュネーヴを追放されたとき、先ほど引用した『山からの手紙』の一節に書かれているように、自分の危惧が的中してしまったとつくづく実感したことでしょう。
学生:ルソーは本当に気の毒だと思いますが、その一方で、不寛容な人間は「国家から追放されるべき」というルソーの主張は、やはり過酷な印象を与えます。ルソーの市民宗教が警戒される一因にもなっていると思います。しかし、ルソーの考えからすれば、主権の簒奪にもつながる宗教的不寛容は、すべての市民の利益や権利の保護という社会契約の趣旨を破壊する致命的な害悪であり、社会契約からの除外を意味する国家からの追放という厳しい処置に値する、ということなんですね。
教師:そういうことだと思います。その点に大いに関連しているもう一つ重要なセンテンスが『社会契約論』の中にあるので、それを、今回の議論、そして、これまでの読解全体の締めくくりとして、最後に引用しておきたいと思います。
|
「共和国においては」とダルジャンソン侯は言う、「各人は、他人に害を及ぼさないかぎり、完全に自由である」と。ここに不変の限界がある。この限界をこれ以上正確に定めることはできない。私は、世に知られてはいないものの、この手稿を、ときおり引用する喜びを禁じえなかった。(第4篇第8章・原注、210頁:p.353)
|
私も、ルソーのこの一節を引用する喜びを禁じえません。ここで言及されている境界線は、のちにミルが『自由論』で、個人の思想と行為の自由が無条件に認められるべき境界線を示す原理(自由原理)として提唱したものに他なりません。「市民宗教」を抑圧的なものだと決めつける前に、宗教的不寛容を許さない原理を含んでいる点をよく見ておく必要があるでしょう。宗教的不寛容を退けるために設定されているこの限界は、政治的不寛容を許さない原理でもあります。自らの上位にある権力を否定する主権論の言説を使いながらも、主権が受け容れるべき実際の限界について、ルソーはあえて論じているわけです。そういうとことん突き詰める知性のあり方に私は敬意を覚えます。
長くなってしまいましたが、これで、最終回も終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。
学生:稚拙な質問の連続に根気よくつきあってくださって、ありがとうございました。今度は、別の古典を持って参上したいと思います。
教師:大歓迎です。いつでもいいですよ。待っています。 【終わり】