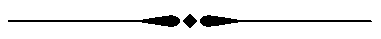習俗と立法者
教師:何度も繰り返すことになってしまいますが、第4篇の趣旨は、共通利益の追求が部分的利益(党派的利益)によって損ねられる状況を念頭に置いて、一般意思=主権者の意思という抽象的な原則だけでは対処できない問題を拾い上げることにあります。第7章「監察制度について」の場合は、主権者の意思=一般意思の表現である法と、法の実効性を左右する世論や習俗との違いが注目されています。
学生:この章の冒頭にある次のセンテンスに関して、いくつか質問したいことがあります。
|
一般意志の表明が、法によって行なわれるのと同様に、公衆の判断(le jugement public)の表明は、〔戸口〕監察制度によって行なわれる。世論(lʼopinion publique)は一種の法であり、その執行者は〔戸口〕監察官である。そして、彼は、統治者と同じように、この法を個々の場合に適用するだけである。 だから、監察官の法廷は、人民の世論の審判者であるどころか、その表明者であるにすぎないのであり、もし人民の世論から離れるようなことがあれば、その決定はたちまち空虚な、効力のないものになってしまう。(第4篇第7章、192-193頁:p.340) |
監察官(ケンソール)の制度は、古代ローマの制度ですよね。市民の資格や担税能力を調べたり元老院議員の品行を評価したりする業務を所掌する上級官職であり、人口調査や検閲という意味のcensorshipという英語の起源にもなった、と高校の世界史で習ったように思います。この制度は、ルソーの時代のジュネーヴと何かかかわりがあるのでしょうか?
教師:はい、かかわりがあるんです。ルソーは『社会契約論』の本文では明言していませんが、ヒントになるのは、原注で自分の書いた『ダランベール氏への手紙』(以下、『手紙』と略記)に言及していることです(第4篇第7章、194頁:p.341)。
この『手紙』における論点の一つは、ジュネーヴに劇場を建設する計画の是非です。ダランベールは-『百科全書』の「ジュネーヴ」の項目の中で、この計画を推奨していました。ルソーは劇場がジュネーヴ市民の習俗に悪影響を与えるという見地から、『手紙』で反対を表明しました。その議論の中で、ルソーは、ジュネーヴには道徳と宗教に関する問題を取り締まる長老会議が、監察制度の役割を担うものとして存在していると述べているのです(『ダランベール氏への手紙』西川長夫訳、ルソー全集・第8巻所収、93頁)。
学生:カルヴァンの神政政治の名残みたいなものですね。それを念頭に、監察制度を当然あってよい制度のようにルソーが論じているということだと、画一的社会への志向が強いというルソー・イメージにも、一理ありそうに思えてきます。
教師:多様性のある社会として、現代のわれわれが思い浮かべるものにくらべると、ルソーの考えている社会が窮屈なのはたしかです。しかし、われわれの多様性イメージと合致しない見方が、すべて同程度に、画一主義で権威主義かというと、これはまた別の話だと思います。ルソーは、少なくとも習俗に関する問題を法的強制で解決できるとは考えていません。
学生:だとすると、世論の執行者である監察官が使える力としては、どんな力があるのでしょうか?
教師:世論の力です。ある行為が世論=社会通念=常識に反するものであったとき、監察官はそうであることを宣言し、そうした行為は不名誉なものとして世間から軽蔑されるのだということを、行為者に思い知らせるわけです。
学生:世論そのものが誤りに陥った場合には、どうなるんでしょう?
教師:それは重要な問題提起だと思います。のちにミルが、「世論の専制」として注目した点です。ただし、そのミルでも、個人の行為への批判は許容していますし、また、社会的な非難を向けても正当な場合があることを否定しているわけではありません。干渉と不干渉とのあいだの境界線をどこにどうやって引くのかという問題は、その境界線を誰が引くのが正当なのかという問題も絡んできて、扱うのがやっかいな問題です。
ともあれ、世論が誤ったものとなる可能性は、ルソーも認めています。一例としてルソーが取り上げているのは、フランスにおける決闘です。決闘で介添人を立てる慣行を卑怯なものとして禁止する勅令は世論の支持を受けて効果を上げたが、決闘そのものの禁止は実力による名誉回復に執着する世論の支持を得られず実効性を持てなかった、という例です。だから、先の引用にもあったように、「監察官の法廷は、人民の世論の審判者であるどころか、その表明者であるにすぎない」ということになるわけです。
学生:監察制度は、個人レベルでの逸脱には世論の力を背景に規制力を持つけれども、世論自体の是正には非力ということですね。ルソーの劇場建設反対論は、劇場での猥雑な演劇という個別的逸脱を抑止するためにジュネーヴの謹厳な世論に訴えるということになるわけですね。
ただ、世論が法の持てないような力を持っていて、しかも世論は誤ることもあるとすると、一般意思の表現である法との関係はどうなるのでしょう? 世論が主権者の意思である法と整合しないことがあるとすれば、ルソー自身の主権論と矛盾してしまうように思えますが。
教師:大難問ですね。結論から言うと、この大難問をルソーは解決していないと思います。理由は二つあります。第一に、主権という概念を用いた議論(言説=ディスコース)は、基本的に、競合する権力を理論的に否定することに調整されていて、主権を制限するという観点が内在していないためです。将棋の駒にたとえると香車みたいなもので、まっすぐ前に行くことしかできないという、融通の利かない議論です。そのため、人民主権と世論との対立はありえない、という建前論を超えられません。にもかかわらず、ルソーは、あくまでもフランスの事例に関してですが、建前論を一歩踏み越えた議論をしているわけです。このような突き詰め方には敬意を表したいところです。第二に、世論と一般意思の対立は、ジュネーヴがすぐれた国制である限り、うまく抑え込まれているはずだ、という想定があるためです。
学生:第二の理由は、まだよくわかりません。
教師:その説明をする前提として、言葉の問題を処理しておきたいと思います。まず、公衆の判断(le jugement public)の表明であるとされている世論(lʼopinion publique)です。世論は、場合によっては、公共の事柄に関して共有されている意見という意味で、一般意思と実質的に同じ意味で使われることがあります。その場合だと、世論と一般意思の対立は論理的にありえないことになります。しかしルソーは、少なくとも今の文脈では、社会全般の意見という、今日のわれわれが考えているのとほぼ同じ意味で使っているようです。そのため、世論が誤っている可能性や一般意思と対立する可能性もありうるわけです。
もう一つ取り上げておく必要があるのは、「習俗moeurs」という言葉です。これは、政治社会の維持への影響の有無という観点から見た、社会全般の人々のものの感じ方・考え方を指しています。社会全般の価値観とか常識とか心の習慣と言い換えることもできるでしょう。そのため、ルソーは次の一節で、習俗を世論と交換可能な言葉として使っています。
|
一つの人民の世論(les opinions dʼun peuple)は、その法制(constitution)から生まれる。法(la loi)は習俗を規定(règle)しはしないが、習俗を生ぜしめるのは法体系(législation)である。法体系が弱まるとき、習俗は堕落する。だが、そのとき、法の力がなしえなかったことは、監察官の判定もなしえないであろう。 したがって、監察制度は、習俗を維持することには役立ちうるが、それを建て直すことにはまったく役立たない。法律が活力を保っているあいだに監察官を設けるがよい。法律がそれを失うやいなや、すべては絶望的である。法律がもはや力を持たなくなれば、他の正当なものもまた、どれ一つとして力を保てなくなる。(第4篇第7章、193頁:p.340) |
この一節は、実のところ、先に示した第二の理由と密接な関連があります。最初のセンテンスは、訳文だと読み取りにくいかもしれませんが、人民の意見=習俗は、一般意思の最初の表現である国制(constitution)から生まれる、つまり習俗は、国制の設計者という意味での立法者による国制の導入という行為(législation)から生まれる、そして、いったん国制が導入されやがて習俗が確立すると、その習俗を後から個別の法(la loi)で規制(règle)することはできない、規制しても効果が出ないということです。
学生:今の説明を聞いて、ずいぶん前の第2篇のところでも、立法者と習俗の関連を論じたところがあったのを思い出しました。
| これら三種類のほかに、第四の法、すべての法のなかでもっとも重要な法が加わる。この法は、大理石柱にも青銅板にも刻まれていないが、市民の心に刻まれている。これこそ国家の真の骨組みを成すものであって、日々新たな力をかち得るもの、他の法が老い、または滅びてゆくときに、これらに生気を吹きこみ、またはこれらの代わりを務めるものであって、人民のなかにその建国の精神を保たせ、いつのまにか、権威の力を習慣の力に置きかえるものである。私が述べているのは、習俗、慣習、とりわけ世論のことである。法のこの部分は現代の政治学者たちに知られていないが、他のすべての法の成否はこの部門にかかっている。偉大な立法者は、個々の規定のことしか考えていないように見えるときにも、ひそかにこの部門に心を配っている。(第2篇第12章、85頁:p.251) |