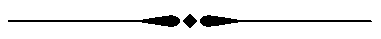選挙・民会・護民府・独裁
教師:前回、指摘したように、 第4篇の趣旨は、共通利益の追求が部分的利益(党派的利益)によって損ねられる状況を念頭に置いて、一般意思=主権者の意思という抽象的な原則を説くだけでは対処できない問題を拾い上げることにあります。この理解を前提にして、今日は、第3章から第6章にかけての、選挙、民会、護民府、独裁に関するルソーの考察を見ていきたいと思います。
学生:最初に、選挙をトピックにしている第3章の中で、質問したい点があります。貴族政がエリート(選ばれた人々)による統治という意味で、ルソーによって高く評価されていることは、「ジュネーヴと貴族政」の回で確認しましたし、この第3章でもその見方が保たれていることは見て取れます。質問したいのは、民主政と抽籤に関してです。ルソーの考えだと民主政は人民全員による行政的決定への参加だったと思うのですが、なぜ、さらに、特定の人を抽籤で指名する必要があるのでしょう?
教師:ルソーは明言していないので推測ですが、多人数で行動するときには、みんながまとまって効果的な行動をすることは、たとえ簡単な仕事の場合でもむずかしいからでしょう。少人数の人々が分担すれば済む仕事もあるでしょうし、多人数で行動する仕事の場合は、個人や少人数の集団が音頭を取る必要があります。しかし、どちらの場合であっても、誰が担当してもよいということが、民主政の原則です。とはいえ、仕事が複雑困難でこなせない人が出てくる場合には、そうした人が選ばれる可能性のある抽籤は、危ないやり方です。つまり、市民の役務に関して人々を能力で区別せず平等に扱うという、民主政の原則は採用できないことになります。経験や専門的知識のある人を選出する(貴族政にする)必要が生じてくるわけです。アテネの民主政でも、ポリスの死活に関わる軍隊の司令官を抽籤で選ぶことはしませんでした。
抽籤という方法が採用されるのは、ルソーが明言しているように、民主政での行政の実務担当者には役得というものがなく、むしろ負担と感じられて、なり手がいないためです。町内会とかPTAの役員を決める場面を思い浮かべればよいでしょう。抽籤で決めて恨みっこなしにするわけです。ルソーは触れていませんが、輪番も同じ性格の仕組です。
学生:人民集会に関して、ルソーは、第二の議案の段階で、人選という個別的決定を行なうために人民集会自体が一時的に行政組織に変貌して民主政の政府となり、為政者を選挙(実際には留任に関する可否投票)することを提案していました。抽籤ではないですよね。
教師:それは、第一の議案ですでに、人民集会終了後の政府形態は貴族政を継続、と決定しているからです。
学生:その貴族政と選挙との関連で、ヴェネツィアとジュネーヴの対比の議論が出てきますが、ちょっとわからないところがありました。元首である統領を選ぶ過程に抽籤が入り込んでいるので、ヴェネツィアは混合形態だとルソーは言っていますが、どういう意味で混合形態なのかがわかりませんでした。
教師:私もヴェネツィアの仕組はよく知らないのですが、次のようなことだと思います。ルソーによれば、大評議会の構成員は貴族だということにはなっているが、数も多く特権もないので普通の人民と変わらない。そのため、統領を選ぶ際の選挙人の選出(これ自体を何段階か繰り返す)は、民主政的な方法である抽籤で行ない、最終段階でようやく選挙を行なう。選挙をするという意味では貴族政の性格をこの最終段階で持つことになる。おそらく、統領に限らず、政府を実際に動かしているのもごく少数の人々でしょう。だから、全体として見ると民主政(抽籤)と貴族政(選挙)の混合形態と言える。こういう説明をルソーはしているのだと思います。
学生:ヴェネツィアの政府は、「われわれのものと同様あまり貴族的ではない」(第4巻第3章、167頁:p.318)というのは、よくわかりません。どう理解したらいいんでしょう。
教師:G.D.H.コールの英訳でも no more aristocratic than our own となっていますが、not more aristocratic than our own じゃないかと思います。原文は、son Gouvernement nʼest pas plus aristocratique que le nôtre です。実際、岩波版では「その政府はわれわれのもの以上に貴族的でない」と訳されていますし、中公版でも「その政府は、ジュネーヴのそれよりも、貴族政的であるとはいえない」となっています。
文法や文脈から判断しても、「ヴェネツィアの政府は、われわれ(ジュネーヴ)の政府以上に貴族政的というわけではない」になるのだと思います。ヴェネツィアの大評議会構成員が名目的に貴族と呼ばれていても、ジュネーヴの市民と実質は変わらない。ジュネーヴで人民集会(市民総会)への参加資格を持つ市民は、ジュネーヴの全住人の一部でしかない。そのような市民が人民として、さらに少数の為政者を選んでいる。つまり、少数の為政者を選んでいるという意味で、ジュネーヴは貴族政である。その点では、ヴェネツィアも変わらない。政府の実際の形態は、どちらも貴族政である。ヴェネツィアに貴族身分があるからといっても、それはジュネーヴの市民とほぼ同格だから、それを理由にして、ジュネーヴ以上に貴族政的だとは言えない、むしろ、抽籤という民主政的なものすら混入している、ということだと思います。ちなみに、白水社版の訳文は(コールの英訳も)、民主主義者ルソーが賞賛しているジュネーヴは民主政のはずだ、という先入見に影響された可能性も考えられます。
学生:高校時代の英文法の授業を思い出しました。でも、ルソー観の影響があるかもしれない、というのは考えさせられますね。ところで、次の第4章ですが、ローマの民会についての長々とした議論で、ジュネーヴとは直接関係がないように思えたのですが。 教師:ローマの3種類の民会について比較評価した次の文章を見ると、そうとも言えないと思います。
| これ以上細部に立ち入らなくても、いままでに明らかにしたところから、地区の民会は人民政治(Gouvernement populaire)にもっとも好都合であり、ケントゥリアの民会は貴族政にもっとも好都合であったということになる。ローマ市の下層民だけで過半数を占めていたクリアの民会について言えば、僧主政治と悪だくみを助長することにしか役立たなかったので、煽動家たちでさえ、自分たちの企てがあまりにもむき出しになるような手段は差し控えていたにもかかわらず、この民会は評判を落とさざるをえなかった。たしかに、ローマ人民の尊厳が惜しみなく発揮されたのは、もっぱらケントゥリァの民会においてであり、これだけが完全であった。なぜなら、クリアの民会には田園地区が欠けていたし、地区の民会には元老院と貴族とが欠けていたからである。(第4巻第4章、182頁:p.331) |
このようにルソーは、上流層と中流階級ばかりでなく下層民が民会に加わることや、さらに、そのような民会が立法だけでなく行政にも関与して民主政的になることを問題視し、その観点から、ケントゥリアの民会を好意的に評価しています。やはり、ジュネーヴの人民集会の望ましいあり方を念頭に置いた評価と見るべきでしょう。他にも、人民の堕落にともなって、当初の公開投票制よりも秘密投票制が適合的になったという議論も、ジュネーヴとかかわりがありそうです。政府の権力が強まると、政府に批判的な意見を公然と表明しにくくなる、といった問題が生じるからです。ただし、そのような争点がジュネーブで実際にあったのかどうか、今の私の限られた知見では確認できていません。ルソー専門家による解明に期待しましょう。
学生:次に、第5章の護民府に関してです。これはジュネーヴとどうかかわっているのでしょう。
教師:次のような議論ですね。
|
この団体を、私は護民府と呼ぶことにするが、それは法律と立法権の維持者である。護民府は、ときにはローマの護民官のように、政府に対して主権者を保護し、ときには現在のヴェネッィァの十人評議会のように、人民に対して政府を支持し、また、ときにはスパルタの監督官のように、両者の均衡を維持することに役立つ。 護民府は都市〔国家〕の構成部分ではなく、したがって、立法権、執行権を一部でも分かち持ってはならない。だが、まさにこのゆえに、その権限は両者よりも大きい。なぜなら、みずからは何もなしえないことになっているからこそ、すべてを阻止することが許されるからである。それは法の守護者としての資格において、法を執行する統治者や、法を制定する主権者よりも、いっそう神聖であり、いっそう尊敬される。(第4巻第5章、185頁:p.334) |
ジュネーヴで政府当局と市民が激しく対立したときフランスが調停に入った事実を、ルソーは念頭に置いているのかもしれません。『山からの手紙』の第九の手紙に、この件への言及がちょっとだけあります。外国による調停ではなく、国内にそのような非常設の権威ある仕組があればもっと望ましい、という示唆に思えます。ただし、この点も知識不足のため未確認。あくまでも推測です。
ついでにちょっとだけ脱線すると、トクヴィルは、こういう権威ある自前の仕組をアメリカの連邦最高裁判所に見出したのではないでしょうか。実際の訴訟案件があってはじめて介入するという点で、機能的な意味では非常設的な性格も持っています。ルソーがもう少し長生きしてアメリカの連邦憲法を目にすることができたら、アメリカの連邦制度や連邦最高裁判所についてどうコメントしただろう、ルソーを大いに研究していたトクヴィルと、けっこう近い見方になったのでは、などと想像してしまいます。
脱線はこれまでとして、第6章の独裁に関する議論を取り上げておきましょう。ルソーの次の説明に注目したいと思います。
| もし、危険に対処するのに、政府の活動力を増大させるだけで足りるのなら、その構成員の一人または二人に政府の力が集中される。この場合、変更されるのは法の権威ではなく、たんにその執行の形態である。もし、危険が深刻であって、身を守るのに法律という装置が障害となるほどであるのなら、すべての法律を沈没させ、主権を一時停止するような最高の首長一人が任命される。このような場合にも、一般意志は疑いもなく存在し、人民の第一の意向が、国家を滅ぼさないことにあるのは明白である。したがって、立法権の停止はけっして立法権の廃止ではない。立法権を沈黙させるこの行政官は、それを語らせることはできない。彼はそれを支配しはするが、代表することはできない。彼はあらゆることをなしうるが、法をつくることだけはできない。(第4巻第6章、188-189頁:pp.336-337) |
教師:そうだと思います。政府権力=統治担当者の権力が、例外状態において一時的に強大化することを自分は問題視しているのではない、とルソーは言いたいのだと思います。主権=立法権の停止は、それを廃止することではない。人民集会は、特異な事情があれば開催できないこともあるだろう。しかし、まったく開催しないとなると話は別である。それは、統治担当者が立法権を主権者から奪い取ることであり、つまり、主権の簒奪なのだ、という論旨です。 学生:これでいよいよ、残りは3章、『社会契約論』の最後の部分に近づいてきました。 教師:最後まで気を抜けません。第7章の習俗の議論もていねいに読む必要がありますし、市民宗教を取り上げている第8章は、一般意思の無謬性の議論や立法者論と肩を並べるほどの大難問です。 学生: なんとか乗り切れるよう、もうひと頑張り、予習をしておきます。