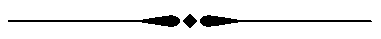立法者論
学生:前々回、一般意思がつねに正しいかどうかの問題を考えたとき、人民は腐敗しないが欺かれることはあるという点の検討を積み残していましたが、それと同様の記述が、立法者に関するルソーの議論の中に再登場しているのに気づきました。
| 一般意思はつねに正しいが、それを導く判断はつねに啓蒙されているわけではない。一般意思に、対象をあるがままの姿で、ときにはあるべき姿で見させることが必要である。……個々人は幸福がわかっていてもいても、これを退け、公衆は、幸福を欲していても、それがわからない。両者とも等しく導き手が必要なのである。……こういうわけで、立法者が必要になってくるのである。(第2篇第6章、62頁:p.231) |
【補注】「ダブルヘッダー」とは、日本のプロ野球で、日程消化のために同じチームどうしの試合を1日に2試合すること。現在では、ドーム球場が増えて雨天中止がなくなったおかげで、ほとんど行なわれていない。死語同然になっていて今の学生さんには通じないのだか、先生は気づいていない。幸いここでは、「長丁場」という言葉があったので、要点は通じている。
学生:はい、長くなっても、大丈夫です。
教師:わかりました。まず、立法者が人民に与える法についてですが、ルソーが中心的に取り上げているのは、統治やその構造に関する基本的な規範、つまり、憲法のようなものです。
社会契約をするために集まっているふつうの人々は、自分たちの共通利益にかなった統治や統治体制を望んでいますが、その願望は自由で平等なよい統治、といった漠然としたものにとどまっています。社会契約をするまでは社会経験がない、という想定になっていますから【末尾の補論を参照】、当然、具体的な方策やルールについての知識は持っていません。人々の意図は善良で正しくても、契約の趣旨を実現する実際の仕組を考える段階で、知識や経験の不足による勘違いとか迷いとかのために失敗する可能性があります。結局、こうした点に関しては、くわしい専門家に頼らざるをえません。しかし、たちの悪い専門家にだまされる危険もあります。ルソーによれば、次のような専門家=立法者が理想だということになります。
| それぞれの国民に適した最良の社会規範を発見するためには、すぐれた知性が必要であろう。その知性は、人間のあらゆる情念をよく知っているのに、そのいずれにも動かされず、われわれの性質とまったく似ていないのに、それを底まで知り尽くし、自分の幸福はわれわれとはかかわりがないのに、しかもわれわれの幸福のために喜んで心をくだき、なお最後に、進みゆく時のかなたに遠く栄光を展望しながら、ある世紀において苦労し、別の世紀においてその成果を享受することのできる、そういう知性でなければならないだろう。人間に法を与えるためには神々が必要であろう。(第2篇第7章、62-63頁:p.232) |
『社会契約論』は、従来、フランス革命とか、戦後日本の民主化とか、政治体制の新規構築を念頭に置きながら読まれることが多かったように思います。つまり、過去を清算した上であらためて社会契約をし、政治体制を設立するための手本と受け取られてきました。たしかに、『社会契約論』は、新規に出発するかのような順序で議論が進んでいます。でも、初回で取り上げた『山からの手紙』を思い出してください。ルソーは、『社会契約論』はジュネーヴの歴史を書いていると読者に受け取られるだろうし、自分もそのつもりで書いたのだ、と言っています。この点を、後世の読者は見落としてしまいました。
ルソーは、ジュネーヴにとって立法者の問題を、これからの問題としてではなく、解決済みの歴史的出来事として扱っているのです。保守すべき国制が素晴らしいものであれば、設計者の宗教的権威が過去にどう働いたにせよ、ともかく素晴らしい国制が受け容れられ今まで続いてきたわけですから、そのこと自体が何よりも設計者の超人性の証拠になります。だから、ルソーは、カルヴァンについて次のように言うことができるのです。
| 時代が移って、われわれの信仰にどんな革命が起ころうとも、祖国と自由への愛がわれわれのあいだから消えないかぎり、この偉大な人物の記憶は、いつまでも祝福されることであろう。(第2篇第7章原注、65頁:p.234) |
この問題は、統治担当者と政治参加の資格を持つ一般市民とのあいだに知識や経験の差がある限り、程度の大小はあるにせよ、必ず生じてしまいます。これは、一般的な表現で記述できるという意味では「永遠の問題」ですが、答は状況ごとに違ってこざるをえないので、その意味では普遍的解決策のない普遍的問題です。政治哲学が実際に直面するのは、このような性格の問題であるがふつうのように思えます。契約説の抽象的一般論だけで片付く問題ではありません。
学生:先生の今のお話は、実際の統治体制の運用に関してだと思いますが、政治体制の新設や大規模な変改の場合は、どう考えたらいいんでしょう?
教師:そもそも、ルソーの議論でなぜ立法者が必要とならざるをえなかったのかを考えるとよいと思います。その理由は、自然状態と社会状態のギャップが大きすぎることにあります。なぜ、ギャップが大きくなってしまったかと言えば、人間関係のしがらみの影響を完全に排除した自由な同意・契約こそが正当な義務の根拠だという前提に対応しようとして、自然状態という非現実的で抽象的なものを導入したからです。そのために、契約の具体的内容というところで、社会に関する経験も知識もない人々に関して、インフォームド・コンセントの条件が満たせなくなり、立法者の宗教的権威を引っ張り出さざるをえなくなったのです。
ルソーの立法者は、マキアヴェリの言う「武装せざる預言者」のようなものですから、暴力で最善の国制を押しつけることはできません。立法者の本音としては、場合によっては「高貴なウソ」かもしれませんが、ともかく、神の権威しか頼れるものがないのです。
神の権威に頼らないとなると、無謬のエリートとか前衛党を無条件に信じることでしょうか? でも、それは、歴史上の豊富な失敗例に目をつぶって、ということになります。それとも、カントの定言命法のような非経験的な(ア・プリオリな)観念論にもとづいて、個々人の理性に期待することでしょうか? でも、感情にまったく左右されずに公平な道徳的判断ができる人間を前提としたあの難解な議論は、ふつうの人(私も含めて)を説得するには非現実的です。そこに自律的な人間の尊厳があるのだと慰められても、やはり、各人は神のようであれという、無理なことを言われている気がするでしょう。
神の権威に頼らないとなると、無謬のエリートとか前衛党を無条件に信じることでしょうか? でも、それは、歴史上の豊富な失敗例に目をつぶって、ということになります。それとも、カントの定言命法のような非経験的な(ア・プリオリな)観念論にもとづいて、個々人の理性に期待することでしょうか? でも、感情にまったく左右されずに公平な道徳的判断ができる人間を前提としたあの難解な議論は、ふつうの人(私も含めて)を説得するには非現実的です。そこに自律的な人間の尊厳があるのだと慰められても、やはり、各人は神のようであれという、無理なことを言われている気がするでしょう。
立法者の権威には以上のような問題があるのですが、それでも、ジュネーヴの場合のように、過去から引き継いでいるすぐれた国制を保守するよう人々を説得することが課題であれば、解決済みの過去のものとしてやり過ごせるでしょう。「結果を原因に変える」という、立法者に託された課題は、すでに解決しているからです。つまり、立法者が与えた国制の下で、この国制の存続に必要な経験や知識や動機を今の市民はすでに獲得していて、だからこそよい国制が続いているわけですから、今さら立法者の権威が介入する必要もありません。(もっとも、実際には、ルソーの現状診断では、自分が説得に乗り出すことが必要となるような危うい事態になっているわけですが。)
ところが、フランス革命や戦後日本の民主主義体制のように、国制を新規導入する時点の議論としては、超人的立法者など現実にはありえない、という問題にぶつかってしまうのです。新しく望ましい体制のために過去の体制を完全否定して、さらに、旧体制の影響を多少なりとも受けているという理由からふつうの人々の社会的な経験や知識まですべて完全にリセットしてしまうと、立法者問題が出てきてしまう、ということです。しかし、ルソー流の立法者は現実にはいないのですから、新しい体制でも活かすことのできるふつうの人々の経験や知識を見分けそれを伸長させる以外に、新しい体制を実際に安定した形で存続させ動かしていくことはできせん。政治革命が、文字通りに「自由を強制」したり、徹底した人間革命(つまりは非人間的な革命)を要求したりすると、無理が重なって必ず失速し、悲惨な結果になってしまいます。また、外見上はなんとか持続しているように見える場合があったとしたら、そうさせているものは何なのか(それは当初の革命の理想なのか)と問う必要があるでしょう。
こういうふうに言うと、微温的で腰の引けた保守主義的主張だ、と受け止める見方もあるかもしれません。でも、これは政治イデオロギーの問題ではなく、一定の社会状況を支えたり制約したりしている社会的因果性という事実の問題です。評価の仕方はいろいろあるでしょうが、改革を望むにせよ現状維持を望むにせよ、考慮に入れるざるをえない事実を指摘している、ということです。
学生:先生が、ヒュームやバーク、ミルやバジョット、それにクリックやジョン・ダンといった、イギリスの政治思想家・政治哲学者たちに特に注目している理由が少しわかってきたような気がします。ところで、熱気のこもったお話はもっと続きそうですが、だいぶ遅い時間になってしまったので、今日はこれで失礼したいと思います。すみません。 教師:つい夢中になってしまい時間を忘れてました。どこかで区切ることを意識して話さなくちゃね。申し訳ないです。次回の政府論も、めまいがするぐらいに面白くなると思ってます。楽しみです。 学生:がんばって予習します。缶コーヒー、ありがとうございました。次回は、めまいにそなえて、自分で用意してくることにします。
【補論】社会経験のない白紙の状態(いわばルソー流の「無知のヴェール」がかかった状態)での社会契約という条件設定は、立法者というアドホックな要素の必要性という難問とともに、もう一つの難問も生み出しています。つまり、ルソーが賞賛し保守を訴えているジュネーヴ国制が導入されたとき、あるいはより正確に言うと、その直前の時点で、人々は社会契約時に求められる白紙の状態だったのか、という問題です。この問題にルソーがはっきりと気づいていたことは、次のような、初期状態へのリセットという、特別の(アドホックな)例外をジュネーヴに認める議論に見て取ることができます。
|
ひとたび慣習が確立し、偏見が根を張ってしまうと、それらを改革しようとするのは危険で無駄な企てである。……〔もっとも〕ある種の病気が人間の頭を混乱させ、過去の記憶を喪失させるように、国家の存続するあいだには、ときとして激動の時期がやってこないともかぎらない。この時期において、ある種の発作が個人に及ぼすのと同じ作用を、革命が人民に及ぼし、過去への恐怖は過去の忘却と変わり、国家は内乱によって焼かれながらも、いわばその灰のなかからよみがえり、死の腕から脱出して青春の活力を取り戻すことがある。リュクルゴス時代のスパルタ、タルクイニウス家の後のローマはこれであり、今日においては、暴君どもを追放した後のオランダやスイスがこれである。 しかし、こうした出来事はまれである。それは例外であって、その理由は、いつもその例外的な国家の特殊構造のうちに見いだされる。こういうことは、同一人民において二度と起こりえないであろう。(第2篇第8章、69-70頁:pp.237-238) |