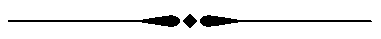一般意思と全体意思
学生:一般意思と全体意思との関係について、ルソーは次のように論じていますが、何を言っているのかさっぱりわかりません。
| 全体意志と一般意志とのあいだには、しばしばかなり相違がある。後者は共同の利益だけを考慮する。前者は私的な利益にかかわるものであり、特殊意志の総和にすぎない。しかし、相殺される過不足分をこれらの特殊意志から引き去れば、残り分の差の総計が一般意志である。(第2篇第3章、46頁:pp.218-219) |

学生:特殊は個人のことですから、特殊意思とは各個人の利益追求の意思ということでした。
ただし、個人の利益は、三つの成分から構成されています。つまり、①他者と共通する利益、②他者の利益と衝突せず自分にだけかかわる利益、③他者の利益と衝突するような利己的利益です。例の図を再度、示しておきたいと思います。
ルソーが上の文章で「私的な利益」と言っているのは、この特殊利益=個人的利益のどの部分にかかわるんでしょう?
ただし、個人の利益は、三つの成分から構成されています。つまり、①他者と共通する利益、②他者の利益と衝突せず自分にだけかかわる利益、③他者の利益と衝突するような利己的利益です。例の図を再度、示しておきたいと思います。
ルソーが上の文章で「私的な利益」と言っているのは、この特殊利益=個人的利益のどの部分にかかわるんでしょう?
ただ、各個人の意思の総和=全体意思というルソーの説明には、率直に言って、問題があるように思います。全体意思は、la volonté de tous と単数で扱われていますけれども、共通利益のところを除くと、他は各個人で内容がばらばらで全体として統一してませんから、その点に着目する限りでは、「全体」は単一の意思主体になっておらず、構成員の人数に相応した複数雑多な意思しかないように思えるからです。全体を統一体のようにして「全体意思」という概念を引っ張り出したことで、一般意思との区別がかえってわかりにくくなり、さらには、言葉の連想だけで、全体主義者ルソーなどという、トンデモな解釈にまで飛躍しそうでもあります。 学生:全体意思の主体という点に詰めの甘さあって誤解をもたらしているとしても、それはひとまず措いて、ルソーの思考の中での全体意思の位置というか役割はどうなんでしょう? 教師:本筋に引き戻してくれてありがとう。重要な点は、全体意思は、共通利益への志向も含んでいる特殊意思=各個人の意思の総和だから、たんなる利己的利益追求の総和ではなく、一般意思の成分を含んでいるということです。つまり、全体意思=一般意思+X ということです。 学生:ルソーは、上の文章で、「相殺される過不足分をこれらの特殊意志から引き去れば、残り分の差の総計が一般意志である」と言っています。つまり、一般意思=全体意思-X で、X=相殺される過不足分、ということになりますね。でも、これって何ですか? 教師:数式や図形が苦手の私でも作れる数式(風のもの)で考えてみましょう。
|
(「これらの特殊意志」-x ) の総計=一般意志
左辺の括弧をはずすと、
「これらの特殊意志」の総計-x の総計=一般意志
ところで、「これらの特殊意志」の総計=全体意志 だから
全体意思-x の総計=一般意志
移項すれば
x の総計=全体意志-一般意志
となる。これを、
各個人のレベルに戻してみると、
x =各個人の特殊意思-各個人の共通利益追求の意思 |
でも、これ以上詮索する必要はないのかもしれませんが、どうしてルソーは、全体意思に含まれる不純物を「相殺される過不足分」と呼んだのでしょう? 教師:③の利己的利益が持っている性質のためだと思います。②は他者の利益に影響しませんから、今の議論では、中立的なものとして捨象できます。③が不純物ということになります。これは各人ばらばらで、しかも、他者の③とぶつかり合う性質をもっています。しかし、ばらばらに対立している利益は、その対立状態を維持したままであれば、一つのどんぶりにまとめて放り込んでも、矢印の向きがばらばらなベクトルの和のように相殺されてしまいます。そういう相殺状態が確保できれば、言いかえれば、それぞれの勝手な利益主張のどれも、主張者以外に支持者がいないようにしておけば、一般意思への悪影響は抑えられるだろう、ということです。
ただし、そのためには、小さなかけらとしてばらばらに対立させておくことが大事で、ばらばらなものがまとまる(部分集団=党派を作ろうとする)傾向を抑える必要があります。
【補注】次の一節も、このようなルソーの考え方を示しています(太字は引用者による強調)。
ルソーは次のように説明しています。訳文の後半部分はわかりにくい(ルソーが言っていることについて十分に具体的なイメージが湧かないまま訳している可能性がある)ので、少し時間がかかりますが、根気よく解きほぐしてみましょう。
| それゆえ、一般意志が十分に表明されるためには、国家の中に部分社会が存在せず、おのおのの市民が自分だけに従って意見を述べることが必要である。偉大なリュクルゴスの独特で卓抜な制度はこのようなものであった。いくつかの部分社会があるときには、ソロン、ヌマ、セルヴィウスの行なったように、その数をふやし、その間の不平等を防止しなければならない。こうした周到な用意こそ、一般意志がつねに輝きを失わず、人民が誤りを犯さないための唯一の良策なのである。(第2篇第3章、47-48頁:p.219) |
| 人民が十分な情報をもって討議するとき、もし、市民相互があらかじめなんの打ち合わせもしていなければ、わずかな差が多く集まって、その結果つねに一般意志が生み出されるから、その結果はつねによいものとなろう。ところが、部分的結社である徒党が、大結社を犠牲にして作られると、これらの部分的結社のおのおのの意志は、その構成員に対しては一般的であるが、国家に対しては特殊的となる。その場合には、もはや人々と同じ数の投票者があるのではなくて、部分的結社と同じ数の投票者があるにすぎなくなると言えよう。差の数が減少すると、その結果として一般性の程度も減少する。ついには、これらの結社の一つが非常に大きくなって、他のすべての結社を圧倒するようになると、結果は、もはやさまざまのわずかの差の総和があるのではなく、ただ一つの差だけがある、ということになる。そうなれば、もはや一般意志は存在せず、勝利をしめる意見は、特殊な意見であるにすぎない。(第2篇第3章、47頁:p.219) |
たとえば、ある地域で小学校を新設するという共通利益があるとします。実際にはありえないことですが、ルソーの議論に合うような想定として、用地に制限はなくどこでも立地可能だとしておきましょう。当然のことながら、住民はそれぞれ、自分の家の近くに立地されることに自己利益を持ちます。しかし、自宅から小学校候補地への距離は、必然的に、誰かに近ければ他の誰かには遠くなるので、希望候補地は各人ばらばらになります。「人々と同じ数の投票者がある」というのは、人々と同じ数の投票先(候補地)がある(どの候補地も一票しか得票できない)、ということです。
ところが、一部の住民がグループになって話し合い、各人の自己利益がグループごとに整理されると、つまり、「だいたい同じ近さだよね」というようにすり合わされ集約されてしまうと、グループごとの共通利益ができあがります。そうなると、「部分的結社と同じ数の投票者がある」ということになります。正確に言い直すと、「同じ数」というのは実際の得票数のことではなく、投票先=候補地の数と、それぞれの候補地を支持するグループの数が同じだということです。
「差の数が減少する les diffrénces deviennet moins nombreuses」というのは、これも得票数のことではなく、意見を異にしているグループの数が減少することを指しています。そうなると、グループ間の利益対立がますます鮮明になり、社会全般の共通利益がますます顧みられなくなります。つまり、「一般性の程度」が「減少」していきます。今の例だと、小学校の候補地がAとBに絞り込まれた上で、それぞれを支持する勢力のあいだで足の引っ張り合いが強まり、そのために共通利益であるはずの小学校の建設が進まなくなってしまう、ということです。また、もし一つのグループが非常に大きくなって他のすべてのグループを圧倒するようになると、実質的な対立軸は、一強の多数派と、それ以外の弱小党派との対立一本に収斂する(「ただ一つの差だけ」となる)事態も生じます。しかし、こういう場合、一強の多数派であることで「勝利をしめる意見は、特殊な意見であるにすぎない」とルソーは言うのです。 学生:そういう状況では、「決まらない政治」も「決められる政治」も、どちらも問題ありですね。 教師:ともかく、ルソーの考えでは、不公平・不平等をもたらすような党派対立を防止し、共通利益が際立つようにするために、利己的利益がばらばらなままで相互に打ち消し合うようにさせておこう、ということになるわけです。
【補注】ちなみに、こういう見方は他の思想家にもあって、たとえば、トクヴィルは、言論の自由がどうしても節度を失いがちな点に関して、アメリカでは偏った意見が非常に多様でそのためそれぞれの支持者の規模が小さく、それらがたがいの力を相殺する効果を持つことで、節度のなさという欠陥が補なわれている、と指摘しています。(『アメリカのデモクラシー・第1巻(下)』松本礼二訳、岩波文庫、30頁)あくまでも推測でしかありませんが、トクヴィルはかなり深くルソーを研究し理解していたのではないかと、私は思っています。
学生:なるほど、ずいぶんと複雑な論点が、足し算・引き算の背後にはあるんですね。しかし、ともあれ、中心的論点はよくわかりました。個人の利益の中には、利己的なものもあれば、それを抑えて他者と共存する統治の仕組を持つことで得られる利益もあり、そういう共通利益を確保する切実な必要に迫られて人々は社会契約を結び、一般意思の求める自由・平等・公平・正義に即した政治社会が設立され維持されていく、ということですね。ようやくそこにたどりつくことができました。
教師:でも、次の難関が待ち構えています。それは、立法者の問題です。ルソーの言う立法者とは、政治社会が設立されたあとの、通常の法を起草したり制定したりする人を指すのではなく、政治社会設立時の統治の基本構造を設計し、それを人々に受け入れさせる人を指しています。次回は、これに取り組むことにしましょう。
学生:先生の力のこもった口調からすると、教科書の説明をうのみにするだけではだめみたいですね。もちろん、教科書もいくつか目を通すつもりですが、自分の頭を使いながら格闘することに主軸を置いてがんばります。
教師:非常に結構です。急いで答を出そうとするよりも、問いが論理的につながって連続的に出てくることをめざしてください。