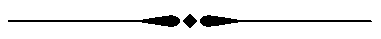契約と義務
学生:ルソーの議論はロックの議論を参考にしているところが多いように思えます。でも、社会契約そのものに関する議論で批判しているのは、ロックだとフィルマーの家父長権力論ですが、ルソーの場合はグロチウスの征服説になっています。どうしてなんでしょう?
教師:いい質問ですね。特定の思想家、今ならルソーですけれども、ルソーが誰のどんな主張を批判の対象として意識しながら議論をしているのか、という視点はとても大事です。もちろん、論敵と言っても、同時代の同じ社会状況に直面している思想家の場合がある一方で、過去の外国の思想家への理論的挑戦の場合もあります。ロックの場合は、ロックの政治的立場と対立する陣営が、過去の思想家であるフィルマーの作品を引っ張り出してきたので、それが批判の標的になった、という複合的な例になります。
学生:たしか、グロチウスは、ルソーより少し前の世代のオランダの法学者でしたよね。ロックの場合のような複合的な性格もあったのでしょうか?
教師:私の見る限り、少なくとも『社会契約論』の文言からは、ルソーの同時代の誰かがグロチウスを援用していたためにルソーがグロチウス批判をしていたのかどうかは分かりませんでした。しかし、グロチウスがラテン語で書いた『戦争と平和の法』はフランス語訳が出ていますし、グロチウスの国際的影響力は、ルソーの世代になってもかなり大きかったのでしょう。
いずれにしても、ルソーがこの批判をつうじて主張しているのは、契約を道徳的に義務づけるのは支配者の力ではなく当事者間の自由で自発的な同意だ、という命題です。
いずれにしても、ルソーがこの批判をつうじて主張しているのは、契約を道徳的に義務づけるのは支配者の力ではなく当事者間の自由で自発的な同意だ、という命題です。
学生:近代的でわかりやすいですね。
教師:「近代的」という形容の仕方が本当に適切かどうかは、再考してもいいんじゃないかと私は思っています。よく、社会契約説の近代性などと言われますけどね。ヨーロッパ近代が16世紀ぐらいに始まると考えられている、としてみましょう。でも、政治的服従の義務の根拠を自由な同意に置く議論は、古代のキケロや中世のトマス・アクィナスにもあります。政治よりも身近な民事領域で言うと、ローマ法はどうだったんでしょう。西洋の中ばかりでなく、西洋と東洋のあいだでも東洋の中でも、「約束は守るべきだ」という前提がないと、たとえば安定的な商取引はできなかったはずです。理論的にどう説明するか以前に、おたがいに約束を守らないとおたがいに困ったことになるという、人類の普遍的経験がずっと前からあったのではないでしょうか。ですから、説得対象が、自由な同意は同意した本人を義務づけるということを自分の生活領域のどこかで実感している社会であれば、どんな社会でも、契約説が説得力を持つ可能性はあります。「身分から契約へ」という、ざっくりとした単線的な発展図式にはなかなか収まりきれないように思えます。また、契約説の思想だけに注目していると視野の外になってしまいますが、西洋の近代においても、政治的服従の義務を契約で説明し正当化すること一色だったわけはないことも、注意が必要でしょう。
学生:そういえば、前回の先生の話の中で、そもそも約束をなぜ守らなければならないのかを契約説は説明できない、というヒュームの指摘が紹介されていましたね。
教師:黙約(convention)という考え方を前提にした指摘ですね。いずれじっくり考えてみたいと思います。自生的秩序の議論にもつながっていきそうです。
ヒュームが指摘するように、社会契約説というのはどう考えてもフィクションで、つまりウソの話です。どんなに頭のよい人のウソでも、あちこちでつじつまの合わないことがどうしても出てきてしまいます。刑事コロンボの名台詞で言えば、「完全犯罪なんて存在しない」ということです。フィクションをあえて受け容れる成熟した精神、などという言い方もあるのでしょうが、それはそのフィクションを受け容れる動機が本人にとってリアルなものとして先行しているときの話です。相対主義の毒に当たってそういうリアリティの感覚が持てなくなっている場合は、フィクションにもとづいた思想や行動は、途方もないニヒリズムになってしまいます。それよりは、懐疑的ではありながらも、だまされても損にはならない、という「パスカルの賭け」みたいな打算が入っている方が,私には精神の成熟を感じさせます。
もちろん、黙約論の方も、推測的な抽象論にならないために、いろいろな裏づけが必要でしょう。今のところ全然勉強不足なので、法制史とか法人類学ではどんな議論があるのか、専門の先生にうかがってみたいと思っているところです。
学生:政治哲学の守備範囲って、思ったほど広くないんですね。
教師:問題はむしろ、だんだんに狭くなってきているところにあるように思います。とはいえ、やはり、足りないところをきちんと自覚することが大事じゃないかな。一人で何でもかんでもやるのは無理ですけれども、足りないことがあるという自覚を持ち続けながら、少しでも視野を広げる必要があると思います。自分の専門に徹しろという指示は、時と場合をふまえた(たとえば研究者をめざして修士論文を書こうとしている院生とかに対する)思慮的な忠告としては適切だとしても、禁止命令として絶対化してしまうと探究心を萎縮させる「鉄の檻」になってしまいます。
脱線してきたので、話を本筋に戻しましょう。ルソーがグロチウスの征服説を批判するときのポイントは、力は義務を生じさせないということにありました。
学生:ヒュームの批判があるにしても、ルソーのこの指摘は、とても説得力があるように思いました。
教師:私もそう思いますが、ただ、同意が義務を生じさせる、という表現には注意が必要です。義務と権利は裏腹の関係にありますから、同意が権利を生じさせる、という言い方だってできるはずです。義務という言葉をなんとなく重苦しく感じる人には、権利のほうが前向きに感じられるんじゃないでしょうか。
学生:もしルソーが民主主義者だったら、国民には政治に参加する権利がある、というような感じになりますよね。先生はそういうルソー解釈をしないんでしょうけれど。
教師:ルソーの議論が「鉄鎖」から始まったことを思い出してほしいですね。なぜ、社会の決めたことに個人は従わなければならないのか、そうした服従が正当と言える社会はどのようにできているのか、という問題設定が出発点でした。つまり、服従=政治的義務の議論なわけです。社会契約説は政治社会の構成原理だという解釈がありますけれども、そういう解釈を抜きにしたすっぴんの姿は政治的義務論です。これはルソーに限らず、ルソーが言及しているロックやホッブズの場合も同様です。統治者と被治者のあいだにある支配と服従という立場の違いを前提に、服従してもよい統治とはこれだ、という議論の立て方になっています。ロックの議論のように、服従しなくてよい統治もあるという含みを持たせる場合があるにしてもです。
学生:だとすると、次の一節は「鉄鎖を飾る花」という皮肉な見方もできそうですね。
| 自然状態から社会状態(政治社会の状態)のこの推移は、人間のうちにきわめて注目すべき変化をもたらす。というのは、人間の行為において、正義を本能に置きかえ、これまで欠けていた道徳性を人間の行為に与えるからである。そのときはじめて、義務の呼び声が肉体の衝動に、権利が欲望にとって代わり、そのときまでは自分のことしか考えなかった人間が、以前とは別の原理によって動き、自分の好みに耳を傾けるまえ理性に問い合わせなければならなくなっていることに気づく。……このような高所に達するので、もしこの新しい状態の悪用のために、彼が脱出してきたもとの状態以下に堕落するようなことがなければ、彼をもとの状態から永久に引き離し、愚かで視野の狭い動物を知的存在でありかつ人間たらしめたあの幸福な瞬間を、彼はたえず祝福しなければならないだろう。(第1篇第8章、34頁:pp.208-209) |
教師:自然状態を最善と見るのなら、間違いなくそう言えるでしょうね。でも、ここでのルソーが、社会の掟に従っている人間に道徳的な尊厳を認めているのは、その掟が心から自由に同意できるものだから、つまり、合理的である(理性に即している)からであって、服従することはどんな場合でも道徳的だと言っているわけではありません。その意味で、ここでの「祝福」は正当化できる「鉄鎖=政治的義務」に向けられており、言葉の上だけの「花飾り」ではないと思います。
学生:とすると、道徳的な存在になるために人々は社会契約をした、ということになるのでしょうか?
教師:それはそれで、また別の話だと思います。行為の動機と行為の結果は同じでなくてもよい、とルソーは考えていたように見えます。そこが、のちのカントとの大きな違いでしょう。ルソーは次のように言っています。
| 各個人が自然状態にとどまろうとして用いる力よりも、それにさからって自然状態のなかでの人間の自己保存を妨げる障害のほうが優勢となる時点まで、人間が到達した、と想定してみよう。そのとき、この原始状態はもはや存続しえなくなる。だから、もし生存様式を変えないなら、人類は滅びるだろう。(第1篇第6章、26頁:p.202) |
ここでは、生存の確保という「必要=効用」に議論のフォーカスがあります。ルソーの言う「正義と効用」の一致というのは、動機としての効用と結果としての正義の一致というか、効用を安定的に確保しようとすると正義(相互性=おたがいさま)の原則が入ってきてしまうことを指しているように見えます。もちろん、いったん社会が成立してしまえば、正義の感覚は道徳的に推賞すべき重要な動機になるでしょうし、人々が進んで秩序を守ることで法律や政治にかかる負荷を軽減させるためにも、大いに必要になるでしょう。とはいえ、この動機は、ロックのように自然法で律せられた自然状態を想定しない限り、社会の存在を前提としていますから、正義の感覚が動機になって社会を作る契約を結ぶというのでは、原因と結果が逆になってしまいます。
学生:一つ引っかかっている点があります。同意が義務の根拠だとすると、ルソーの次の一言がすごく気になるんですが。
|
ダランベール氏は、この点において誤ることなく、項目「ジュネーヴ」のなかで、わが都会に住む人々の四身分を(たんなる外国人も勘定に入れると五身分も〔シトワイヤン・市民、ブルジョワ・町人、アビタン・在留民、ナチフ・二世在留民、シュジェ・隷属農民〕)――そのうち二身分のみが共和国を構成するのだが――はっきり区別した。(第1篇第6章原注 30頁:p.204) |
共和国を構成しているのが主権者で、彼らは社会契約の当事者のはずです。でも、ここでの記述だと、そのような市民はシトワイヤンとブルジョワだけです。女性も入っていないと思います。こういう市民以外の人々の義務や権利は、いったいどうなるんでしょう?
教師:少なくとも『社会契約論』を見る限りでは、ルソーは何も言っていないと思います。市民以外の人々をアウトロー(法による保護対象から除外されている人々)や奴隷として扱うことにルソーが賛成したとは考えられないけれども、彼らの「人権」や「自然権」を特に強調するような議論も見当たりません。『社会契約論』でのルソーの関心は、あくまでも政治的共同体の構成員であり、ルソーもその一員だった市民の義務、という問題です。自由も平等も、あくまでもそのような市民や為政者との関連での話です【補注参照】。
学生:フランス革命のときの「人間と市民の権利」に比べても、目配りの範囲が狭いんですね。教科書のルソー・イメージとますます離れてきたような感じです。
教師:別の話になるのですが、市民の権利や義務との関連で、注意しておきたい点を一つだけ追加させてください。ルソーは、市民とか臣民とか主権者といった用語について、次のように説明しています。
| この結社行為は、直ちに各契約者の個々の人格に代わって、一つの精神的で集合的な団体を生みだす。その団体は集会の有する投票権と同数の成員からなり、この同じ結社行為から、その統一、その共同の自我、その生命、その意志を受け取る。このように、おのおのの個人がすべての他者と結びつくことによって形成されるこの公的人格は、かつては都市(Cité)、いまは共和国(République)と名づけられている。それが受動的な面でとらえられるばあいは、その成員によって国家(Etat)と呼ばれ、能動的な面でとらえられる場合は、主権者(Souverain)と呼ばれる。他の同様の公的人格とくらべるときは国(Puissance)と呼ばれる。構成員について言えば、集合的には人民(peuple)という名称を持ち、主権者として参加する個々の単位としては市民(Citoyens)、国家の方に従うものとしては臣民(Sujet)と呼ばれる。(第1篇第6章、29頁:pp.204-205) |
注意しておきたいのは、受動的な面でとらえると「国家」で、能動的な面でとらえると「主権者」だと言っている点です。能動的というのは、一般意思の主体集団として見た場合だと思います。だとすると、受動的というのは、一般意思の客体としての人間集団ということになります。そのような客体としての個々の人間を指す場合は臣民=被治者ですが、そういう人々を集団としてまるごと見た場合は国家だというわけです。今日のわれわれは、機構とか組織として国家をイメージしがちですが、ルソーの場合は人的団体なんです。これはルソーの独創ということではなく、おそらく、キヴィタス(古代ローマの都市国家)の古典的なとらえ方に即したものなのでしょう。
一般意思の指示を個別状況での指示に変換する装置が政府で、その政府の具体的指示の下で行動する市民集団というのがルソーの国家イメージです。(政府については、政府形態をめぐるルソーの議論の中であらためて取り上げます。)市民から税金を集め、それを使って業務請負集団に政府の指示を執行させるやり方を、ルソーは嫌っています。ルソーがよいと思っているのは、町内会執行部の音頭で実施される町民総出の一斉清掃みたいな国家活動です。こういう発想を見ていると、ルソーはわれわれとはかなり違った世界の人間に思えてきます。実際、そう見ておいた方が、ルソー本人が言いたかったことを誤解する危険が少なくなるようですね。
学生:ルソー本人が言いたかったことの中で、自分がいちばん知りたいと思っていることの一つは、ルソーは「一般意思」を持ち出してくることで何が言いたかったのか、また、それ以前に、ルソーの言う「一般意思」とはそもそも何なのか、なんです。次回は、そこをお願いします。
【補注】ルソーは、次のように述べている。
|
しかし、われわれは、この公共の人格〔国家〕のほかに、これを構成している私人たちを考慮しなければならない。そして、後者の生命と自由とは、本来前者とは独立のものである。そこで、市民たちと主権者との、それぞれの権利をはっきり区別し、また、市民たちが臣民〔被治者〕として果たすべき義務と、市民たちが人間として享有するはずの自然権とを、はっきり区別することが問題となる。 (第2篇第4章、49頁:pp.220-221) |
「自然権」という、『社会契約論』ではほとんど使われていない言葉が登場しているが、あくまで「市民たちが人間として享有するはずの」権利として言及されていて、市民以外の人々も「人間として享有」できる権利かどうかは述べられていない。