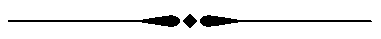|
ああ、いとわしい人間的俗事のなかにあって、いったいどんな幸福が同胞の血によってあがなわれる価値があるでしょうか。自由でさえもこの代償にはあまりに高くつきすぎるのです。(『山からの手紙』川合清隆訳、「第八の手紙」、『ルソー全集・第8巻』、白水社、380頁) 大部分の国家において、内乱は理性を欠いた愚かな下層民によって誘発されます。最初彼らが耐えがたい憤りから興奮し、次には、なんらかの権力を握っていて、それを拡張したいと願っている巧妙な挑発者によって扇動されるのです。しかし、ジュネーヴの市民階級、少なくともそれらのうちの法を維持しようとして権力と対決する部分に対して、このような考えを適用することほど誤ったことはありません。あらゆる時代を通じて、つねにこの部分は、金持ちと貧乏人、国家の指導者と下層民との中間に位置する階層でした。財産、身分、教養においてだいたい平均した人々から成るこの階層の立場は、特権を持つほど高くはなく、それかといって失うべきものはなにもないというほど低くもありません。彼らの最大の利益、彼らの共通の利益は、法が守られ、為政者が尊敬され、国家が安泰であることです。この階級には、いかなる点でも、自分の個人的利益のために他人を動かせるほどの優位を他人に誇れるような者はだれもいません。これは共和国のもっとも健全な部分、人々が彼らはその行動において全員の利益以外の目的をめざすことはありえないと確信しうる唯一の部分なのです。それゆえ、彼らの共同行動はつねに、礼儀、節度、敬意ある確固とした態度、自分たちの権利の正当性を自覚し、義務を遂行する人間のある種の荘重さが見られるのです。(「第九の手紙」、440-441頁) |
|
私の著書の、この簡略でありのままの梗概をお読みになって、貴殿は何をお考えになったでしょうか。私には察しがつきます。あなたはご自分にこう言いきかされたことでしょう。これこそジュネーヴ政府の歴史である、と。それは、あなたがたの国制を知っている人が、この作品を読んだときにかならずもらす感想です。 実際、この原初契約、主権の本質、法の支配、政府の設立、各段階で政府の権威を力によって埋め合わせ政府を縮小して行くやり方、侵害的傾向、定期集会、それを廃止する巧妙さ、そして最後に、遠からず訪れてあなたがたを脅かす、私が防ごうとしたところの破壊、このどれ一つをとってみても、それはまぎれもなく誕生から今日にいたるまでのあなたがたの共和国の姿ではありませんか。 私は、あなたがたの政体を立派であると思ったからこそ、私はそれを政治制度のモデルとして取りあげ、そしてあなたがたを全ヨーロッパに手本として示したのです。あなたがたの政府の破壊を求めるどころか、私はそれを維持する方法を明らかにしたのです。この政体は、非常にすぐれてはいるけれど、欠陥がないわけではありません。人々はそれが変質をこうむるのを防ぐことができたし、今日陥っている危険からそれを守ることもできたのです。私はこの危険を予測し、それをわかってもらおうとしました。そして、予防策をも示唆したのです。 ……〔私を迫害した〕人々は『社会契約論』を、プラトンの『国家』や、『ユートピア』や『セヴァランプ』とともに、空想の国へと追放して満足したに違いありません。しかし、私は実在の対象を描きました。(「第六の手紙」、345-346頁) |