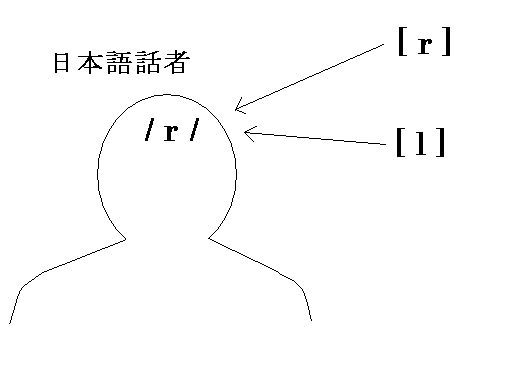音韻論
おんいんろん
1.音素
音韻論 (phonology) は、ある特定の言語の構成にかかわる音がどのような構造を持ち、また、それらがどのような振る舞いを示すかを明らかにしようとする学問分野である。
ある特定の言語において、語の意味の区別に使われる、概念としての音のことを音素(phoneme)とよぶ。音素は、形態素を構成する単位で、形態素がさらに語を作り、語が並んで文を作る。よって音素は、言語を組み立てるパーツの中では、下位のレベルにあるものだと言える。
音素は「概念」であるから、話者の頭の中に存在するものだと言える。概念としての音である音素は、さまざまな要素が捨象されて認識されている。たとえば、日本語を構成している /あ/ という音素がある(音素は、スラッシュ / / でくくって表記する)。/あ/ は、誰が発音しても /あ/ であって、声が大きい男性が発音しても、声の高い女性が発音しても /あ/ の同一性は認識され、コトバの意味は通じる。このことは、言語音では音の3属性のうち「音の大きさ」と「音の高さ」という2要素は認識されていないということを表している。音素が持つ要素は「音色」という要素であり、音色によって音素は互いに区別されている。/あ/ と /い/ が区別されるのは、主に音色が異なっているからだと言える。
一方で、音声学という学問もあるが、音声学はヒトが発する言語音の特徴を厳密に分析し、それを科学的に表現する学問である。たとえば、独自の記号を与えて客観的に書き表す学問は調音音声学という。このように音声学が研究対象とする客観的な言語音を、ふつう音声という。音素が概念的なものであるのに対し、音声は客観的・物理学的な対象だと言えるだろう。表記の上では、音声はIPA (International Phonetic Alphabet) などの音声記号で表され、角のあるカッコ [ ] でくくって表記される。
以上の内容を、表にしてまとめよう。
| 音声 | 音素 |
| 客観的で厳密な音 | 概念としての音 |
| IPA等を [ ] で囲う | 音声記号または他の記号を / / で囲う |
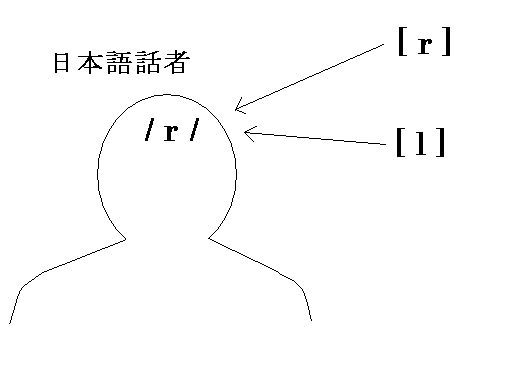
例としてよく知られている事例を挙げると、日本人は[r] と [l] を聞き分けられないことが多い。この2つは客観的には違う音声なのであるが、日本人は聞き分けができず、同じ音に聞こえてしまう。
これはなぜかというと、英語の rice と lice のように r か l かの違いで意味が違ってくるような語が、日本語には無いので、日本語話者の中に r と l の聞き分け能力が育たないからである。
すなわち、日本語には、音素/r/と/l/とが並存していないのである。
日本語の「ら行」の音は、どちらかといえば [r] のほうに近い音なので、「日本語では /r/ という音素しか存在していない」と表現できる。なので概念上では[r]も[l]も、一つの音素/r/に収束してしまうというわけだ。
人間が本当に音素という単位で音を認識しているのかという問題は、音素の心理的実在性の問題と呼ばれ、言語学の分野でその実在性を確かめる研究が行われてきている。結果は音素という単位を設定することは妥当であると一般に認められている。
2.異音
音素は常に同じ音声で現れるとは限らない。以下の例を見てみよう。
| 文字表記 | 音素表記 | 音声表記 |
| 三段 さんだん | /sandan/ | [sandan] |
| 三本 さんぼん | /sanbon/ | [sambon] |
この表に挙げたように、日本語の「ん」で表記される音素は /n/ であるとみてよいのだが、後ろに唇音(b,p,m)が続く場合には、調音点がそれに同化して、音声としては[m]で実現する。日本人は、普通この事実を意識しない。これに気づくのは外国語話者かまたは音声学者である。つまり、日本語話者の持つ概念としては n なのだが、発音は実際は無意識のうちに m になっているのである。このように、調音点が後続する音の調音点に同化してしまう現象は、しばしば観察される。
このように概念としては /n/ だが、変異形として実現した [m] を、n の異音(allophone)という。これを以下のように表記する。
| / ん / |
→ |
[ n ] |
通常 |
| → |
[ m ] |
唇音の前で |
また、ここでの n とその異音 m の関係は、交替(こうたい alternation)という。
言語学の本によっては、この場合の n と m をともに異音と呼んでいることもある。また、異音を説明する際に、「異音が集まって音素を成す」などという記述をしている本があるが、これはあまり分かりやすい言い方ではないように思われる。「異音→音素」という向きで考えるよりは、「音素→異音」という向きで考えたほうがよいだろう。すなわち、ある音素には、実現する際の基本となる音声があって、ほとんどその音声でもって実現するのであるが、稀に特定の環境におかれると、基本とは異なる音声で実現するのだと考えるのである。たとえば上の例では、基本となる音声的実現は、あくまでも [n] であって、 [m] はどちらかといえば例外的な実現である。その例外的実現を、異音と呼ぶのだと理解したほうがよいと思う。(これをelsewhere conditionなどと言うことがある)
これはつまり、概念としては同じものだが、実現される音声としては異なってくるということである。この「音素とその実現としての音声」という図式は、「形態素とその実現」という図式とパラレルな関係である。以上をもとに語の分析を行って過去の言語を推定していくこととなる。
3.音価
過去の言語を調べる比較言語学では、過去の音を論じることになるが、2000年以上前の言語の音など実際に聞くことはできない。よって、資料に記された文字から、過去の言語の音を推測するしかない。このことは留意しておかなければならないことである。たとえばサンスクリット語が文法家の時代にどのように発音されていたのかは、厳密にはわからないので、推測するしかないのだ。そのためには、音があらわされているであろう文字について、よく理解しなくてはならない。いったい、文字というのは何を表わしているのかについて、適切に理解しておくことが重要だ。
文字は様々なものを指し示しうるのだが、その表わす対象によって、文字の種類分けをすることができる。まず、表意文字(ideogram, もしくは表語文字(logogram))は、たとえば漢字がその代表例だが、なんらかの意味ある概念を表わしている文字である。概念がある単位は、つまり形態素である。よって、表意文字が表わすのは、形態素であると言えるだろう。これに対して、表音文字(phonogram)は、「音」を表わす文字であると言われる。では、表音文字が表わす「音」とは、音声のことだろうか? それとも音素のことなのだろうか?
結論から言うと、表音文字が表わすものは音声ではなくて音素であると考えたほうがよさそうだ。というのも、音声というのは数限りなく変異する多様なものであるので、文字が音声を正確に厳密に表わすのは非常に難しいのだ。事実、音声を表わす記号であるIPAは、通常用いられているアルファベットが音声を表現するには不足しているという理由で作られ、用いられるのである。したがって、ある言語に表音文字がある場合、それは通常は音素を表現していると考えたほうがよい。このように、ひとつの音素に対して、ひとつの文字を対応させるという原則を、字母的表記の原則というらしいが、「字母的」表記というのは、あまりいい和訳でない気がする。字母というのは音素を指すわけではないからだ。なので、代わりに音素的表記の原則とでも呼んで、気にとどめていればよいだろう。
また、複数の音素を組合せて音節を表わしている文字もある。たとえば、「か」の文字は ka という2音素による1つの音節をあらわしている。日本語のひらがな、カタカナはこのように音節を表現する文字といえるだろう。これも表音文字の一種ではあろうが、とくに音節文字(syllabary)ということがある。
4.非音韻化
音韻論は音を意味の区別に用いるかという観点で分類して音素を認定するのであるが、意味の区別に用いられなくなることがある。
これを非音韻化という。音素の合流ということもある。
たとえば日本語で、「じ」「ぢ」は、まったく同じ音と認識する話者が多いのではないかと思う。これは、同じ音素であると考えられているということだ。しかし、起源的には違った音であった。「じ」は /zi/ であったし、「ぢ」は /dzi/ であった。よって字は今でも使い分けるものの、音としては今となっては同じだと認識されているだろう。
いまではこの2つは「同じ音素の異音」として言語学的に取り扱われている。語頭および「ん」の前では [dz] が音声的に実現する。一方、母音間では、[z] が音声的に実現する。
参考文献
吉田和彦『言葉を復元する』三省堂
もどる