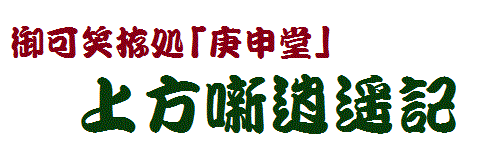 |
||
| 大坂の陣400年の2014年、戦国時代の悲劇のヒロイン・淀殿の400回忌の年でもありまして、ちょいと御縁を頂いて奉納講談の台本を作らせてもらいました。ほんで、にわか勉強でいろいろ歴史書を読み漁ったり、ゆかりの土地を訪ねたりしておりますが、本日は、豊臣秀吉最晩年、最後の大散財のとでもいうべき「醍醐寺の花見」の舞台となりました、京都・山科の醍醐寺を訪ねてまいりました。 | ||
 |
||
| そういうことなら、桜の季節に行けばええもんを、梅雨の晴れ間の新緑の境内でございます。観光に訪れる方も少なく、のどかな雰囲気です。 | ||
五十町といいますから、今でいう5キロ。その範囲の四方の山々には23か所の警護を置き、伏見より下醍醐の道筋は小姓、馬回りなど、今で申しますセキュリティー・ポリス、SPがびっしりと警戒に当たります。醍醐寺周辺も柵を立て回しまして一般人は出入り禁止でございます。 警護の侍が「準備相整いましてございます」と平伏いたしますと、太閤さん鷹揚に立ち上がりまして「では参るぞ」と輿へと乗り込みます。 この時、供奉したお輿の次第は「一番政所さま、二番西の丸さま、三番松の丸さま、四番三の丸さま、五番加賀さま、六番大納言御内」と記録に残っております。 <奉納講談・淀殿始末より> |
||
秀吉は、この花見に大層入れ込んでおりまして、側近の五奉行の一人、前田玄以を「桜奉行」に任じまして、会場整備にいそしんでおります。 「江州、河州、和州、当国(山城)の四か国」から桜を移植して吉野のようにしようとしたといいます。 度々、醍醐寺に来ては「泉水には橋を架けて滝を二筋落とせ」とか、「仁王門は二階門にしろ」とか、直々に指図をしたと、醍醐寺三宝院の門跡義演の「義演准后日記」に記録されております。 |
||
お寺のホームページによりますと 「醍醐寺の寺宝・伝承文化財は、国宝69,419点、重要文化財6,522点、その他未指定を含めると仏像、絵画をはじめとする寺宝・伝承文化財は約15万点」 だそうでございます。 明治維新の廃仏毀釈の折にも、様々な困難にもめげずに、寺宝の流出を防いで、危機を乗り越えたとのこと。 古都京都の文化財として世界遺産にも登録されております。 そういえば、6月4日の新聞に、醍醐の花見で秀吉や淀殿の詠んだ歌の短冊がデジタル化した複製が作成されたという記事が載っていました。 豊臣秀吉による「醍醐の花見」で詠まれた和歌を記した「醍醐花見短籍(たんざく)」(重要文化財)のデジタル複製が完成し、3日、醍醐寺(京都市伏見区)に寄贈された。(読売新聞) 現物は7月19日から奈良国立博物館(奈良市)で始まる「国宝 醍醐寺のすべて」展に出展され、デジタル版はお寺の方で公開されるらしいです。 |
||
あひおひの松も桜も八千代へん 君かみゆきのけふをはじめに |
||
| 短冊に残されております、淀殿のお歌でございます。 本日の逍遥は、これまで。 |


