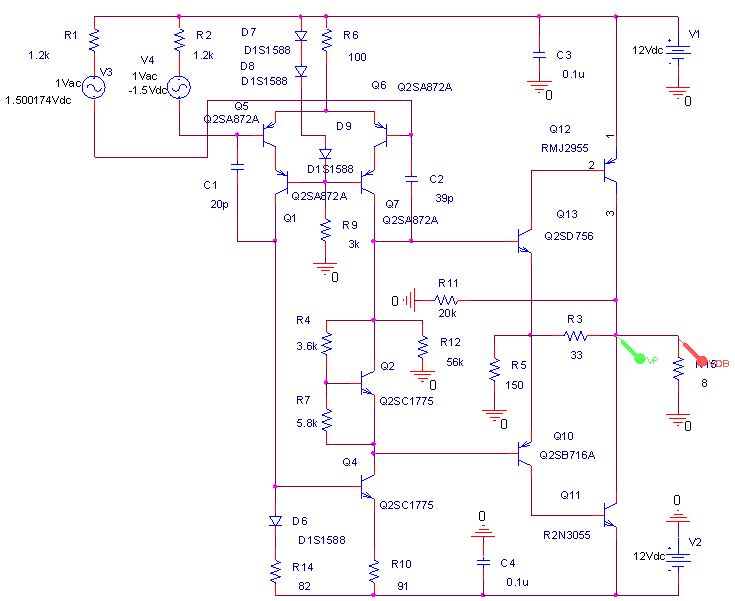
PSpice(評価版)でモータードライブアンプを考える
妖しきシミュレーション。今回のテーマはモータードライブアンプ。
モータードライブアンプなんて、かつて回転系が追求されていた10数年前まではK式でも多少はお馴染みだったのだが、今はごくごくマイナーだ。2003年2月のNo-171のテクニクスSL-1200MK3D用ターンテーブル制御アンプにおいて実に11年振りに復活した懐かしのモータードライブアンプである。
そして、今月末には発売されるという“例”の下巻には、なんとSP-10用の最新ターンテーブル制御アンプが発表されるということではないか。なんと発売が待ち遠しいことか。
と、この時期にモータードライブアンプを考えるのも時宜を得ていることだろう。(^^) と思うのは自分だけか・・・(^^;
さて、下は我がSP-10mkⅡターンテーブル制御アンプのモータードライブアンプだ。
実機は2段目差動アンプ部が2SA798、終段ドライバーが2SA607-2SC960であるが、ここでは2SA872、2SB716、2SD756のモデルで代用する。終段バイアス発生回路のR7が5.8kΩと実機より小さいがこれは素子のばらつきによるものでこれで終段アイドリング電流は適正値である。
また、終段インパーテッドダーリントン回路はNo-171と同様に僅かに電圧ゲインを持たせるものになっている。最近実機も改造したばかりなのだ。が、電圧ゲインといっても僅かなもので計算上は1.7dB程度である。なお、終段MJ2955と2N3055のPSpiceモデルはオンセミコンダクタのWebで提供されていたものを使う。
ところで、シミュレートする回路に初段部がない。のは、評価版のためシミュレーション回路に組めるトランジスタ数が10個に制限されるためだ。モータードライブアンプのシミュレーションをこの制限下で行うとなれば初段を省略することになる。現実初段は利得は僅少であり、ゲイン-周波数特性、位相特性も2段目、終段よりはずっと理想に近いので、ここでは初段出力代わりに位相反転した電圧源で2段目バイアス電圧と1Vac信号を加えてやれば2段目以降の動作は実機とほぼ同様な状態で解析できるはずだ。
というわけで、早速終段負荷を8Ωとして、出力電圧及びその位相の周波数特性を観る。
その前に各部の動作点を観る。
ごくごく正常動作であることが分かる。終段Trのアイドリング電流も19mA程度と指定どおりだ。
結果がこれ。
あらま・・・(。。)
勿論赤が電圧利得で縦軸は左の1の方である。すなわち低域で電圧利得は79dB程度。緑はその位相特性で縦軸は右側の2。これで利得が低域の-3dB、位相が-45°の第1ポールは700Hz程度であることが分かる。このfcは通常のK式パワーアンプとしてはかなり低いように思えるが、低域での電圧ゲインが79dBとかなりハイゲインに設定されているのがその理由だろう。ハイゲインである理由は勿論2段目の対アース抵抗が56kΩと大きいためだ。これで2段目の位相補正Cが39pFなのだから第1ポールが低域に降りるのは当たり前。No-171ではこの位相補正Cは56pFなのだからその第1ポールはもっと低いものと想像されるのだが、何故そうするのか?がこれからの解析で果たして分かるか否か(^^;
さて、問題は位相特性だ。位相回転が-90°で止まらず100kHzで-155°まで回転してしまっている。その後位相回転は反転し5MHz付近で-100°弱まで戻って再回転に転じるというとても不思議な振る舞いだ。
ふ~む。これは何とも最初から不思議な振る舞いにびっくりではないか。
100kHzまでにおいて位相回転が-90°を超えて-180°に向かうということは、その間にポールが2個あるのだと考える以外にない。さらに位相回転が-180°に達する前に反転して位相が戻ると言うことは、2個目のポールはステップ位相補正型のポールあるいは連星効果的ポールであると考えられるだろう。
100kHzで位相回転が-155°に達するとなるとNFBを掛けた場合にアンプが発振しないかと心配になる。が、モータードライブアンプのクローズドゲイン設定は26.44dBであるから、利得特性からして80kHz付近でループゲインは0dBに沈むので案外ぎりぎりセーフなのかもしれない。が、それはちょっと楽観か。(^^; 実機に不安定な感じは何もないのだが・・・
さてさて、我がモータードライブアンプ。何とも不安な波乱含みの幕開けだわなぁ・・・(^^;;
次に進む前にここで2段目差動アンプ左側の位相補正Cを取り去ってみる。
GOA時代にはここに右側の半分の位相補正Cを入れるのが通則だったのだが、No-171では省略されている。
もとより左側と右側ではそれぞれに掛かる電圧振幅が大きく異なり、これを1:2にする理由は論理的とはとても言えないものだと思うのだが(^^;、取りあえず特性的に意味があるものなのか検討しておく。
100kHz付近までは何も違いがないように思えるが、それ以降の位相回転の戻り具合は明らかに違う。位相の戻りは6~7MHzで-70°までにもなる。
何故か? は、分からない(^^;
が、2段目差動アンプ左側の位相補正CはMHzを超える領域において影響があるらしいものの、それより低域においては特段の影響を考えずとも良いようではある。
以下においてはこの左側の位相補正Cは取りあえず省略して検討しても良さそうだ。
2段目差動アンプ右側の位相補正C2を5pF、10pF、20pF、40pF、80pFとした場合のパラメトリック解析でこのアンプの挙動をもう少し詳しく観てみる。
凡例はともに左からC2=5pF、10pF、20pF、40pF、80pF。
何とも面白いですなぁ。
その位相特性において位相補正Cが大きいほど低域から位相回転が大きくなり、高域側では位相戻りも大きくなるというのは、まさしくステップ、あるいは連星効果的にこのC2が働いているということに違いないと思えるし、そのカーブからしてやはり10kHz前後に第2ポールが出来ていると考えるしかないのではないかと。
う~む。こんなに近接した低域に2つもポールがあってはNFBアンプとしての成立は困難なような気が・・・(^^;
仮に安定条件を位相回転-120°以内においてループゲインが0dBに沈むこととすると、この結果からの予測では位相補正C2=320pFぐらいは必要な感じも・・・。No-171の位相補正が56pFと大きめなのはこの辺にその理由があるのだろうか・・・。
う~ん。これは困った困った・・・、と、心は千々に乱れあれこれ悩んでいたところ、遠くから天の声が・・・
「君のモータードライブアンプは8Ωの抵抗をドライブするのかね?」
え、いや、それは勿論抵抗ではなくモーターのコイルを駆動するのですが・・・。えぇ!?、もしやインダクタンス負荷では違った振る舞いになるってことで??
確かに負荷はあのぐるぐる巻のコイルだ。純抵抗ではない。要するにインダクタンスのLだ。
そうか。じゃぁ負荷はLにしてみよう。
が、モーターコイルがどれぐらいのL分なのかは全く検討もつかない。(^^; のでまず適当に10μHを負荷にして同様に測定してみる。
えぇぇぇぇぇ・・・・・・(OO)!!
これはこれはビックリ仰天、驚いた。なんと位相回転が+90°から始まるとは・・・
そうなんですかぁ・・・
負荷がL分であると勿論Lの等価インピーダンスが低域で僅少で周波数のアップと共にインピーダンスも上昇する訳なので、アンプの電圧利得は低域で低く周波数と共に上昇するという特性になることは分かる。多分本当は最大で80dB程度まで電圧利得は上昇すべきところ、アンプの高域限界により利得が上昇しきれないうちに下降に転じてしまう結果がこの電圧利得曲線の姿なのであろう。
あわせての問題が位相特性だ。これは何と言っていいのか・・・(^^;
位相回転は10Hzを基準にすれば20kHz~100kHzで-170°にもなるのだが、その値は10Hzで+90°、20kHz~100kHzで-80°だ。その後位相は反転してC2の値によって-45°~-70°程度まで戻って再回転する訳だが、これなら出力の位相が±120°の範囲にある帯域が非常に広く、NFBアンプとして安定に動作させることは極く容易になる。ちょっと電圧ゲインが不足だと思える点を別にすれば、これならクローズドゲイン設定26dBならば位相補正C2の値はどれでも全く安定のはずだ。
SP-10Mk2のモーターのインダクタンスは如何ほどか全く分からない。ので、負荷を100μHにして同様に観る。
う~ん、上手い。(^^)
全体的に等価インピーダンスが増加したためだろう。電圧ゲインも全体的に増加した。3~4kHzにおいては8Ω負荷と同程度の利得に達している。
もしやSP-10Mk2のモーターのインダクタンスはさらに10倍の1mHぐらいあるのでは? ということで負荷を1mHのインダクタンスにして同様に観る。
さらに電圧ゲインがアップして1kHzで80dBに達している。10Hzでも52dBだ。利得的には十分になってきたような感じだ。
しかも位相が-120°に達する付近でループゲインが0dBに沈む付近がC2によって微妙に動くポイントに重なっていて、なんとなく現実の姿に近いような気がするではないか。(^^;
が、またしても天の声が・・・
「あれだけ細い線をぐるぐる巻いているコイルがインダクタンス分だけで出来ていると思うのかな・・・」 はっ m(__)m
そうでした。当然いわゆる抵抗成分ももともとあるはずと思いますです。(^^;
と言うわけで、制御アンプからモーターへのコネクターを外してテスターで抵抗値を実測してみたのだった。回路図からしてこれで2相分のLの直列抵抗値になると思うのだが22Ω程度と出た。これを3個のドライブアンプで駆動した場合のアンプ1個当たりの実効抵抗値がいくらになるのか不明だが、とりあえず22ΩとL分が直列になると考えれば良いのでなかろうか。
で、まず負荷を10μH+22Ωとして同様にやってみると・・・
へ~~(。。)
電圧ゲインは低域で80dB。こうしてみるとこの回路構成では負荷のインピーダンスより2段目の対アース抵抗56kΩによって低域電圧ゲインの最大値は規定され、それが80dB程度なのだろう。
問題の位相特性の方は0°が出発点に戻っている。-90°を超えて100kHzで一度最大に回転した後位相が戻りMHzを超えてから再回転に転じるという、定抵抗負荷の場合の姿に戻ったようである。が、100kHzでの位相回転も-130°でありこれなら不安定になる心配はなさそうだ。
インダクタンスを100μHとして同様にやってみる。
(゜゜)! なんとも驚きである。
-100°なので決してそうだとは言えないのだが、まるで低域でのポールが1個であるかのような特性ではないか。そのfcはC2=5pFで5kHz、10pFで2.5kHz、20pFで1.25kHz、40pFで700Hz、80pFで400Hz程度であり、これであればNFBを掛けてもクローズドゲイン設定26dBなら位相補正C2=5pF以上で全く安定なはずだ。
22Ωと直列のインダクタンスが1mHであればどうか。
多少の違いはあるがインダクタンスが100μHの場合と基本的に同じだ。
もし、現実のモータードライブアンプの動作状態がこれに近いものと仮定した場合、モータードライブアンプ自体には100kHz付近までに2つのポールがあるにもかかわらず、負荷にインダクタンス分が含まれるが故に2つ目のポールがキャンセルされる効果が生じ、結果NFBアンプとして安定な動作をしているのだ。ということになる。
すご~い。(^^) と思うが、ほんとかいな(^^;
ついでにこのシミュレーションは2段目以降なのでこの場合位相補正は5pFでも全く安定という結果だが、実機はこれに初段が加わり、その位相回転効果がちょうど10MHz付近に現れるだろうことを考えると、実機ではもう少し早くループゲインを0dB以下に沈めることが必要で、したがって位相補正C2はもう少し大きいものが必要になるのだろう、という感じになるわけだ。
へぇ~。出来すぎのような(^^;
非常に巧妙な終段ゲイン付きモータードライブアンプの成り立ちが観えたようにも思えるが、なお観ておくべき点がある。
このモータードライブアンプも最初の調整時には無負荷状態で調整するのだ。インダクタンスが負荷につながらない無負荷状態では8Ωインピーダンス分のみが負荷の場合と同様な不安定状態にならないのだろうか?
そこで負荷を取り去って無負荷状態をシミュレートしてみる。
なんと!無負荷では安定なのだ。
上手く出来ていますねぇ・・・(^^)
さて、何となくキツネにつままれているような気もするが、終段ゲイン付きモータードライブアンプは内部に近接したポールがありながら、インダクタンスを含んだ負荷をドライブするという条件下で、結果的に取りあえず安定動作をしているということは分かった。
が、やはり2段目差動アンプの位相補正C2により出来る以外のもう一つのポールの正体は何なのかを明らかにしなければならない。
やはり怪しいのはゲインを有する終段だろう。終段はたった1.7dBとはいえ電圧ゲインを有している。大抵“電圧ゲインあるところポールあり”なのだ。
ならば終段のゲインを無くせば何か分かるはずだ。それには終段を普通のインバーテッドダーリントンに変更すればよいのだ。
これで負荷を8Ωの抵抗に戻して同様に観るべし。
なんと・・・。(。。) 予想は見事に外れ終段にゲインがある場合と殆ど変わらないではないか。位相戻り前の最大位相回転量が僅かに少ないぐらいの差か。
ところで、電圧ゲインをみると終段ゲイン付きの場合の低域でのオープンゲインは79dBであったが、こちらは78dB弱といったところだ。計算上終段の電圧ゲインは1.7dBなのだが実際は1dB程度の電圧ゲインにしかならないということらしい。
・・・そうなのか。この程度の差にしかならないのか。終段をゲイン付きに変更した際にとっても音が良くなったと感じた我が耳は大丈夫なのだろうか(^^; < またしても駄耳の証明か?とほほほほ・・・ な~んて。ほんの1dBでも電圧ゲインを持つことに大きな意味があるに違いないわさ。 < ただの強がり(--)
が、まだポールの原因について終段ゲイン説が捨てられない。上は2段目の対アース抵抗が56kΩと高く、終段が完全なフォロア動作状態になっていないためのものなのではなかろうか。と、じだばだする(^^;
それを確かめるには、対アース抵抗を5.6kΩにして同様に観れば良い。
この場合の動作点。
う~む・・・(^^;; 同じだ。
終段に電圧ゲインがなくともやはり100kHz未満の領域にポールが2つある。
このうちの1つが位相補正C2によるポールであることは対アース抵抗が5.6kΩと1/10になったことに伴い最低ポール位置が1桁上昇したことで明らかだ。
が、今ひとつは何だろう。終段が電圧ゲインを有しなくとも10kHz前後にポールを持つ要因はあるだろうか。終段TrのCob? それとも2段目に何か他に低いポールの要素があるのだろうか。
ところで、2段目対アース抵抗が5.6kΩと1/10になったことに伴い低域における電圧ゲインも60dB弱と56kΩの場合の-18dBとほぼ1/10になっている。これは仕上がりでNFB量が10倍違ってくるということだ。終段の変更によるゲイン差が1dBに過ぎないことからすれば、このNFB量の差に音の違いの原因を求められたtetsuさんの見解の方が妥当そうですね(^^;
さて、2段目に別のポールがあるのか、やはり終段にあるのかを確かめるには、2段目の出力点と終段の出力点における電圧利得特性とその位相特性をそれぞれ観測すれば分かるだろう。
さっそくプローブを取り付けて観測だ。先ず2段目対アース抵抗は5.6kΩである。
そうか・・・、そうなんですか。
これでもう一つの低いポールの原因は終段であることが明らかだ。
そうか・・・、こういうことか。インバーテッドダーリントンは100%ローカルNFBが掛かるので等価的にエミッタフォロアであるとしても、個別のトランジスタの動作はエミッタ接地だ。特に最終段のMJ2955&2N3055は考えてみれば何もローカルNFBの掛かっていないエミッタ接地動作だ。とすれば、終段インバーテッドダーリントン全体としてローカルNFBの掛け具合により電圧ゲインが0dBの状態であろうと終段エミッタ接地動作由来のポールが発生すると考えて何ら不思議はないのだ。というより気付いてしまえば発生するのがあたりまえではないか。 < とろい。(--)
それにしても終段のポールも随分と低いところにある。どうみても10kHz前後ではないか。どうしてこんなに低いのだろう。
あわせて100kHz付近を底として反転するその位相特性。何故こうなるのだろう。
は、不明だが、このポールの存在により終段出力の電圧利得は2kHz以上の高域で2段目出力のそれよりも小さくなってしまうわけだ。2kHz以下の低域でこれらが一致しているのは終段インバーテッドダーリントン出力段が等価的にエミッタフォロア動作しているからであるが、こうしてみるとインバーテッドダーリントン出力段が等価的にエミッタフォロアなのは2kHzまででそれ以上の周波数では残念ながらエミッタフォロア動作にはなっていないということになる。これがダーリントン接続のエミッタフォロアならばずっと高域まできちんとフォロア動作をするはずだ。この意味ではインバーテッドダーリントンはダーリントンに劣っていると言わざるを得ないのかもしれない。
が、2段目の対アース抵抗を56kΩにしてみると・・・(^^;
あやや? 10kHz付近の終段のポールはどこへいったのか、まるで消えてしまったかのよう。
終段がほぼ2段目出力にフォロウしている状態になってしまった。
連星効果か?
・・・なんとも難しいものだ(^^;
ならば各部の電流出力の状況を電流マグニチュードプローブで観よう。
各部の電流出力の周波数特性からポールの所以が分かることを期待しよう。
まず2段目対アース抵抗が5.6kΩの場合。
あっ!! そうか。(。。)!分かった。
一目瞭然だ。なんとあの低いポールは終段パワートランジスタのfT=トランジション周波数(要するに高域限界)によるものだったのだ。な~んと。
下図の上から2本目と3本目の線がMJ2955と2N3055のエミッタ出力点の電流出力の周波数特性なのだが、これにより10kHz付近からその電流出力が低下し、1MHzにおいてはその下の線の2SB716と2SD756のエミッタにおける電流出力に一致してしまっていることが分かる。これはすなわちその10kHz付近がfb=ベータ遮断周波数であり1MHzにおける一致点がfT=トランジション周波数であることを表しているものなのだ。したがってその10kHz前後にあるのがそのベータ遮断周波数による疑似ポールなのである。
その辺の理屈はM-NAOさんに教えていただいたとおり、黒田某先生の「基礎Tr設計法」に、「Tr内部のキャリアの蓄積はゆっくり立ち上がるので、1次遅れ要素を生み、これによるB-E間の(擬似的な)Cをベース拡散容量と言い、これとHieを含むベース・エミッタ間の抵抗とでLPFを形成する。これによるHfeのカットオフ周波数をfb(ベータ遮断周波数)といい、Hfeが1になる周波数をfT(トランジェンション周波数という。低周波領域のHfeをβoとすると、fbが-3dbポイントで、以後-6dbで減衰し、fTでHfeが1となり、この関係は、fb×βo=fTとなる。」と解説されているということなのだ。
そういえば件の2N3055。規格上そのfT=0.8MHz(4V、1A)だったではないか。現代パワーTrではこれは20~30MHz程度でいにしえのNECの名パワーTrでも7~10MHzだったのだからこのfTは非常に低いものなのだが、今回モデルに使ったオンセミ製の2N3055のモデル、これからすればまさにfT=0.8MHzではないか。 まさに規格どおりではないか。(^^;
だからこれをエミッタ接地動作させエミッタ電流帰還も掛けなければ10kHz前後にポールが発生するのは道理というのものだ。MJ2955の方はこれがfTが6MHzなのに同様な状態になるのはPP動作が故なのだろう。多分(^^;
変わることはないと思うが、念のために対アース抵抗が56kΩの場合についても同様に観る。
2段目電圧ゲインが約10倍になったことに伴い終段各部の電流出力も10倍になっている点以外有意な差はない。
やはりそうなのだ。
インバーテッドダーリントン。その本質はエミッタ接地動作であって、等価的にエミッタフォロア動作をすると言ってもいわゆるダーリントン接続によるエミッタフォロアとは別物なのだ。って、あたりまえか(^^;
ということは、100%ローカル帰還を掛けてエミッタフォロア的に使う場合でも終段パワートランジスタのfT由来のポールの処理をどうするかという問題が本質的に付きまとうのがインバーテッドダーリントンである。ということになる訳だ。この点、インバーテッドダーリントンは完全対称と同様なのだ。
なるほど。これは普通の見方からはダーリントンに対するインバーテッドダーリントンの欠点、使いにくさと評価されるだろう。
世の中の半導体パワーアンプが終段ダーリントンばかりになるのも宜なるかなといったところか。(^^;
分かったところで、モータードライブを想定した負荷22Ω+100μHの場合の動作を観る。
まず、2段目対アース抵抗5.6kΩ、終段電圧ゲインなし。
これまでの解析から負荷にインダクタンス成分が含まれている故としか考えられないのだが、1MHzまではポールが1個という様相を示している。
位相補正C2=5pFで安定だ。本当に驚きだ。
次に、2段目対アース抵抗56kΩ、終段電圧ゲインなし。
これも同じ。低域でのオープンゲイン79dB。全く驚きだがポールは1個としか見えない。C2=5pFで全く安定だ。
次に、2段目対アース抵抗5.6kΩ、終段電圧ゲイン1.7dB設定。
終段電圧ゲインなしの場合と比較すると、以下のことが分かる。
①低域で終段自体の電圧ゲインが1.3dBあること。
②が、終段自体の電圧ゲインが正なのは10kHz付近までであり、それ以上の周波数では終段自体のゲインは負となり、結果2段目出力の電圧ゲインよりアンプ出力点での電圧ゲインが小さくなっている。終段電圧ゲインの正負の交代ポイントはパワートランジスタのベータ遮断周波数によるものと考えられる。
③パワートランジスタのベータ遮断周波数によると思われる10kHz付近から終段出力が2段目出力より減衰してしまうのは終段に電圧ゲインのない場合も同様だが、高域での乖離は終段に電圧ゲインがある方が大きい。
次に、2段目対アース抵抗56kΩ、終段電圧ゲイン1.7dB設定。
①低域で終段自体の電圧ゲインが1.3dBあること。
②が、終段自体の電圧ゲインが正なのは10kHz付近までであり、それ以上の周波数では終段自体のゲインは負となり、結果2段目出力の電圧ゲインよりアンプ出力点での電圧ゲインが小さくなっている。終段電圧ゲインの正負の交代ポイントはパワートランジスタのベータ遮断周波数によるものと考えられる。
③パワートランジスタのベータ遮断周波数によると思われる10kHz付近から終段出力が2段目出力より減衰してしまうのは終段に電圧ゲインのない場合も同様だが、高域での乖離は終段に電圧ゲインがある方が大きい。
以上の終段電圧ゲインなしとの違いは2段目対アース抵抗が5.6kΩの場合と同様だ。
ここで終段電圧ゲイン設定をあえて6dBと大きくしてみる。
設定の6dBには達していないが低域で終段自体のゲインは5dBと大きくなっている。
ベータ遮断周波数により数10kHz超の周波数から上では終段の減衰が大きくなり位相も回転が大きくなっている。この結果からすると終段に与える電圧ゲイン設定が大きいほど高域での利得減衰、位相回転とも大きくなるようだ。
これだけ観ると終段6dB設定でも可能なような気がするのだが・・・
が、アンプ負荷を純粋な8Ω抵抗に交換するとそれが負荷のインダクタンス成分でもたらされた幸運でしかないことが分かる。
終段による利得減衰及び位相回転がこのように大きくなるのである。これだと100kHz付近の最大位相回転に対応するため位相補正にはやはり40pF~80pFが必要だろう。No-171の位相補正が56pFなのはやはりこれが理由なような気がする。
多分シミュレーションだから出来る実験として、終段電圧ゲインを10dBに設定してみる。
こりゃ駄目だ。(^^;
確かに低域で8dB程度の電圧ゲインが終段で獲得されている。が、10kHz以上における終段での利得減衰も位相回転も大きくなってしまう。
やはりインバーテッドダーリントンの応用で終段に電圧ゲインを持たせる手法は、K先生おっしゃるとおり、欲張らずにほんの少しが吉なのだ。それはPP動作の上下Trの特性が違いすぎてまともにPP動作しないと説明されたのだが、この結果を観ると終段にこの回路形態で電圧ゲインを大きく与えると終段自体に出来るポールの影響が大きくなってNFBアンプとして成立しなくなるというのが本質的理由なのではなかろうか。
この方式では終段電圧ゲイン設定は最大でも3dB。実はNo-171のように150Ωと33Ωで1.7dB設定が良いところなのかもしれない。
さて、お遊びにはなるが、それでも負荷にインダクタンス成分が含まれる場合、終段電圧ゲイン10dB設定でも実用になるという不思議を観ておきたい。
どなたか識者の方、この理屈をご教授下さいませ。m(__)m
さて、以上モータードライブアンプを考えてきたのであるが、それは電圧ゲインを有する終段インバーテッドダーリントンの限界を観てきたものであるような気がする。
であれば、次のステップはあれしかないのではなかろうか。そう。“完全対称型”だ。
勿論電源電圧利用率の観点からすれば完全対称型は有利な訳ではない。2段目プラス側は対負荷フローティング動作であるからその電源電圧利用効率は終段フォロア動作の場合と同じだ。終段電源電圧を最大限利用しようとすれば2段目までの電源電圧はそれ以上にしなければならずその場合プラス側2電源化が必要になる。マイナス側もNo-139型式であれば1電源で可能だが定電流回路が必要となるとマイナス側も2電源化しなければならない。モータードライブアンプが4電源というのは非常に大袈裟だ。この点からも完全対称型モータードライブアンプの可能性は高くないような気はするが、パワーアンプにおいてインバーテッドダーリントンを超えたものが完全対称型であったことを考えると、モータードライブアンプでも完全対称型の導入を検討してみるのも大いに意味のあることではなかろうか。
という訳で完全対称型のモーラードライブアンプを考えた。
のがこれである。
って威張ってもしょうがない。まぁ、誰が考えてもこうなるか・・・(^^;
とりあえずNo-139形式だ。
負荷はモーターを仮定した100μH+22Ωである。
位相補正のC2は同様に5pF、10pF、20pF、40pF、80pFのパラメトリック解析。
いいんじゃないでしょうか。(^^)
実に素直な位相特性でこれなら位相補正は5pFで十分。利得は低域で60dBでfc=60kHzと実に広帯域が得られている。
とっても良さ気(^^)
だが、負荷同条件で電圧ゲイン80dBが得られている対アース抵抗56kΩのインバーテッドGOAと同様にするためにさらに+20dBの電圧ゲインが必要となるとこのシンプル型では追いつかない。
その場合は、2段目に定電流回路を付加すると共に終段ダーリントン前段のベース抵抗を大きくし、もって電圧ゲインの増大を図ることになる。
このように(^^;
ここでは定電流回路は電流源で代用する。だからマイナス電源も1電源のままですんでいる。現実の場合は無理かなぁ・・・
動作点はこう。
結果がこれだ。(なお、これ以降2段目の電圧利得の位相特性についてはそれを-180°演算し、対比しやすくしているものである。)
う~ん。とっても素晴らしい。としか言いようがないのではなかろうか。(^^;
勿論下の2つのグループが電圧利得であり、下が2段目の電圧ゲインをR12の両端で図ったものであり、真ん中が出力点での電圧ゲインである。即ち2段目の電圧ゲインが44dB、終段の電圧ゲインが32dB、あわせてトータルオープンゲインは76dB得られた。これならゲイン的にも対アース抵抗56kΩのインバーテッドGOAに引けを取らないはずだ。(^^)
そして特筆すべきはその位相特性なのである。誰も語らないのだが完全対称型の神髄は実はここにある。
2段目の電圧利得曲線と出力点における電圧利得曲線を観られたい。併せて一番上に重なっているその位相特性曲線を観ても分かるのだが、44dBと32dBという大きなゲインをそれぞれ有している2段目と終段のポールがひとつなのである。2段目と出力点における電圧利得の減衰カーブの傾きが一致し、その位相特性の回転カーブが重なっているということがそれを表している。
勿論本当にひとつなのではなく連星効果のなせる技だと思うが、このおかげで大きなゲインを有する2段目と終段がポールを共有することによって完全対称型はまるで2段目と終段が大きなゲインを有する1段アンプのように動作するのである。なんとも素晴らしい回路構成の妙としか言いようがない。これこそ完全対称型の存在意義というべきものなのだ。(勿論全ての場合においてこういう理想状態になる訳ではないと思うが)
これで音も従来の次元を超えるとなればなおさらである。(^^)
これが終段インバーテッドダーリントンのように他の回路型式であればエミッタ接地動作が2段重なることによってポールが二つとなり、その位相回転に難儀することになってしまうのである。2段目及び終段がこんな大きな電圧ゲインを持ちながら位相的に安定な完全対称型のアドバンテージは実に大きい。と私は思う。
ということの結果、これで位相補正C2は5pFで十分なのである。
いや、それは負荷にインダクタンス分を含んでいるからそう見えるだけではないのか。
インバーテッドダイリントンの場合もそれで上手く行っていたじゃないか。完全対称型の場合もそのおかげでポールがひとつ消えたように見えただけではないのか? という疑いももっともである。
負荷を単なる8Ωの抵抗にして同様比較すればそれは明らかになる。
終段負荷が8Ωを下がったため終段電圧ゲインが比例して小さくなってしまったが、他は負荷にインダクタンスが含まれていた場合と比較して何ら本質的変化はない。
この場合もクローズドゲイン26dBのNFBアンプとして位相補正C2は5pFで十分だ。
これと上のインダクタンス負荷を含んだ場合、そしてこれらに対応するインバーテッドダーリントンの場合を比較考量すると、インダクタンスを含んだ負荷にも影響を殆ど受けない完全対称型のアドバンテージが一層際立つではないか。
では、純インダクタンス負荷ではどうか。
勿論影響はちゃんと受けている。
というより純インダクタンスの場合は理論的にこうなるという姿がそのまま現れているようだ。
電流出力(完全対称)と電圧出力(GOA)の違いによるのかもしれない。
インバーテッドダーリントンGOA同様に各部の電流出力を観てみよう。
インバーテッドダーリントンGOAと殆ど変わらないではないか。
やはり回路内で最も低いポールは出力トランジスタ2N3055のベータ遮断周波数であり、2N3055自体のfTも1MHz程度であることがここでも現れている。
にもかかわらず、その2N3055に30dBを超える電圧ゲインを持たせて安定に動作させることが出来るのが完全対称型なのだ。インバーテッドダーリントンでは良くて3dBのところをである。回路構成が生み出す魔法であるかのようだ。
以上のシミュレーション結果からすると、完全対称型はモータードライブアンプとしても大きな適性があり、インバーテッドダーリントンに代えて活用すべきもののように思える。
もしかすると下巻に発表されるらしい最新型SP-10ターンテーブル制御アンプのモータードライブアンプは完全対称型になる可能性があるのではないだろうか。
というのは全くの推測に過ぎないのだが、電源電圧利用率からすると問題もあるし、温度補償の問題もあるだろう。と考えればやはり従来どおりゲイン付きインバーテッドダーリントンGOAかなぁ・・・(^^;
「自分で試してみてはどうかね・・・」 ははっ m(__)m
さて、毎度のことだが以上のシミュレーション結果及びその解析には何の保証もない。ので悪しからず。また、登場した素子モデルについては何もお答えできないので重ねて悪しからず。(^^;
(2004年5月1日)