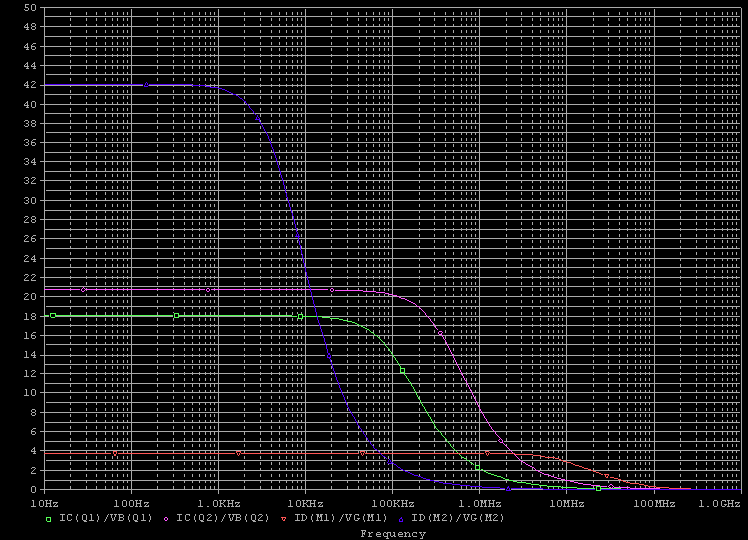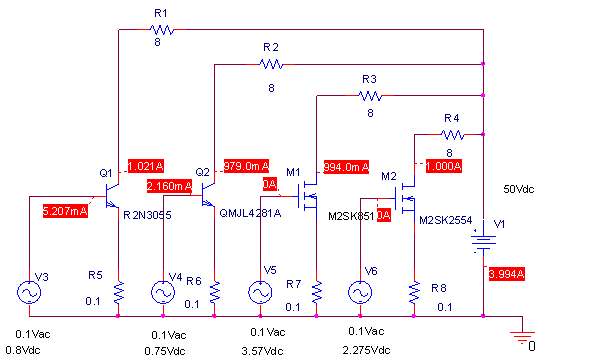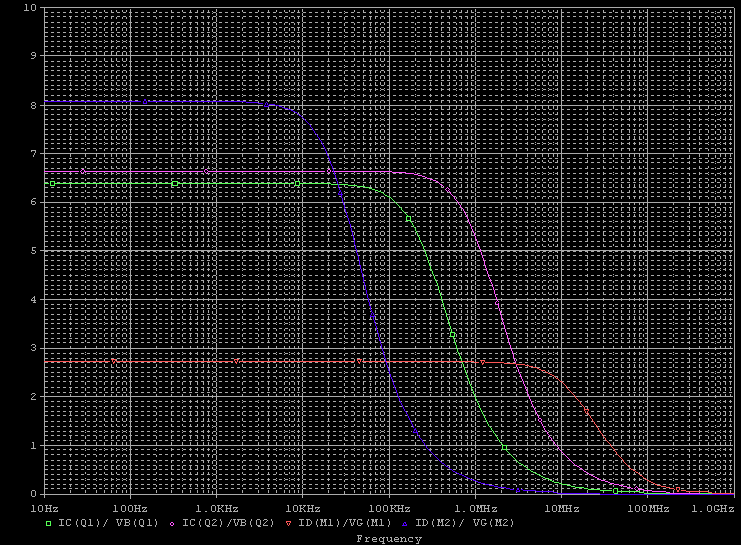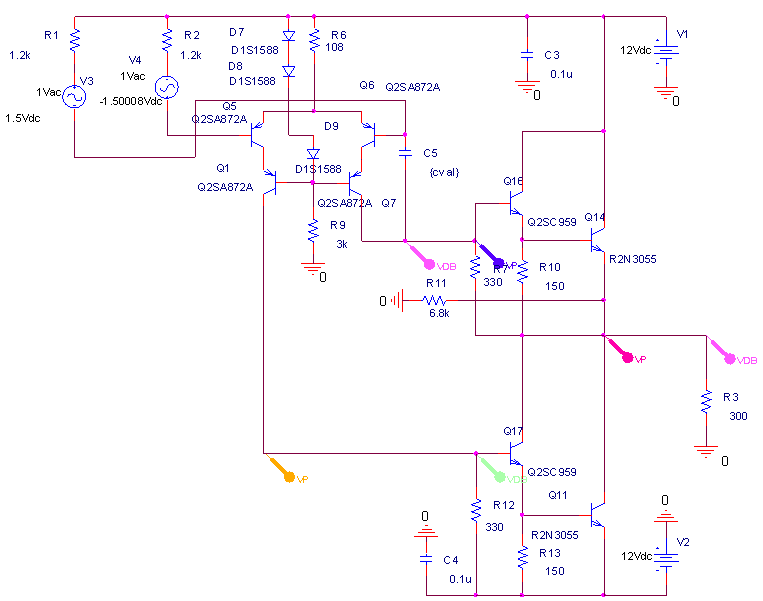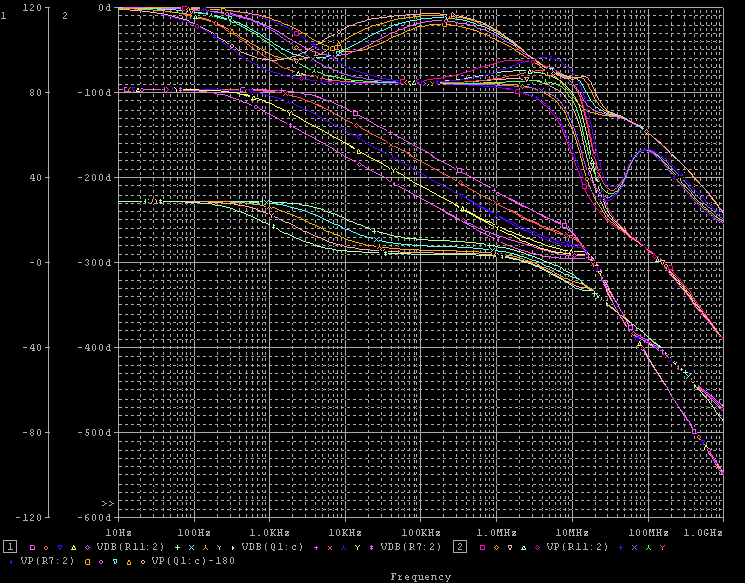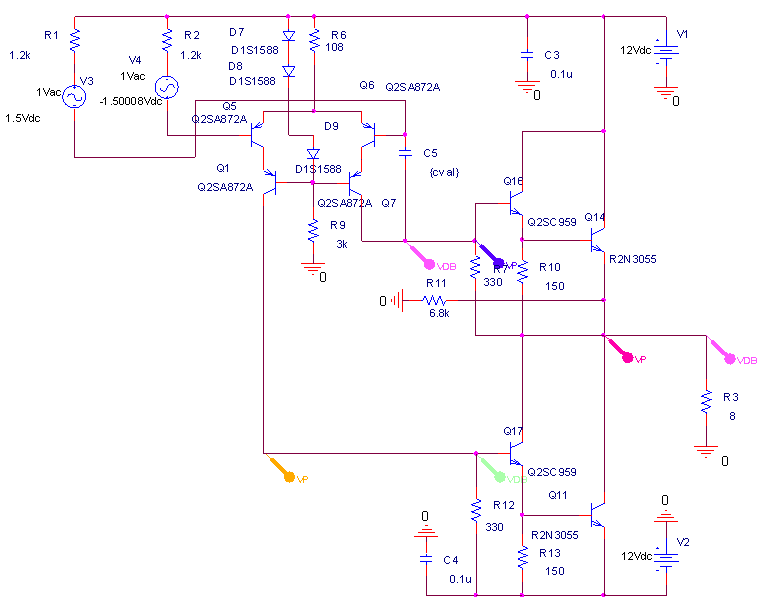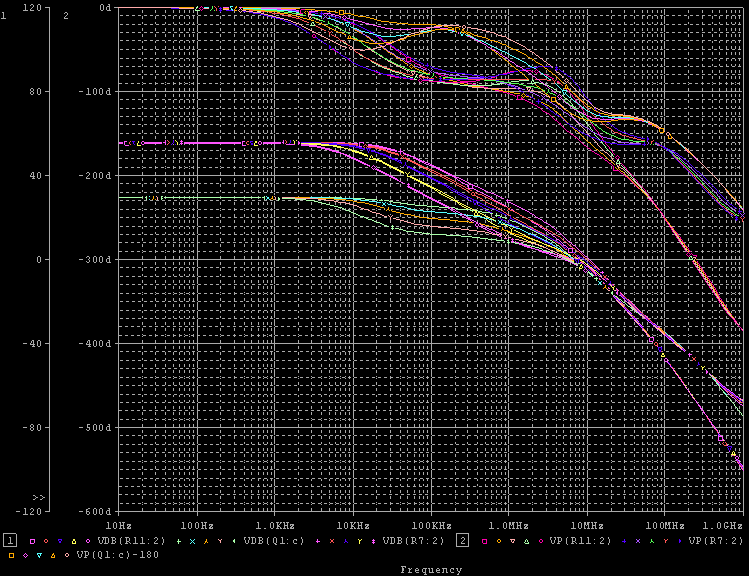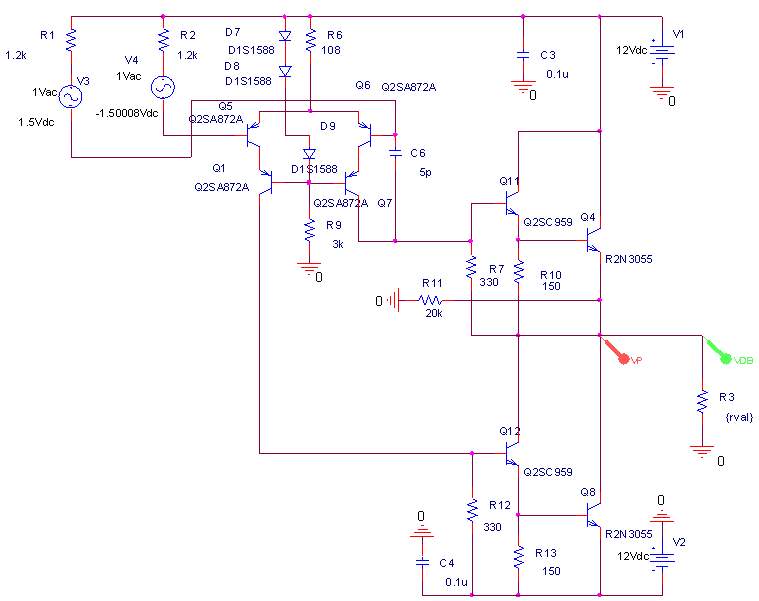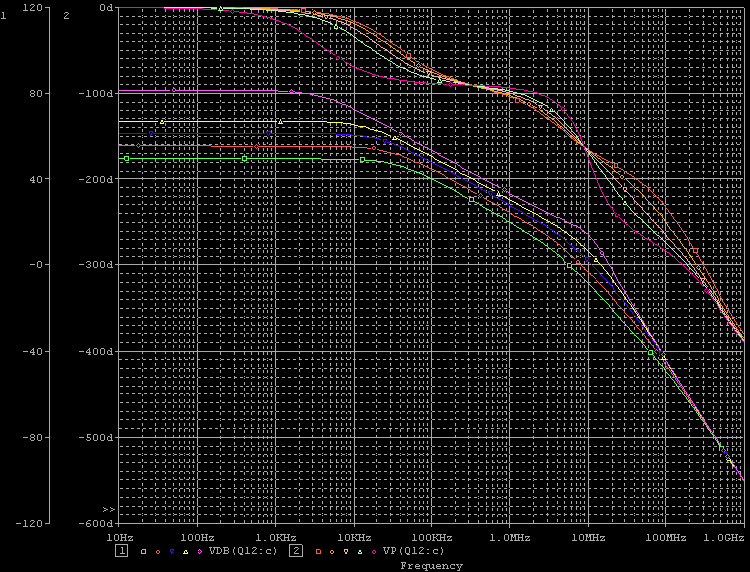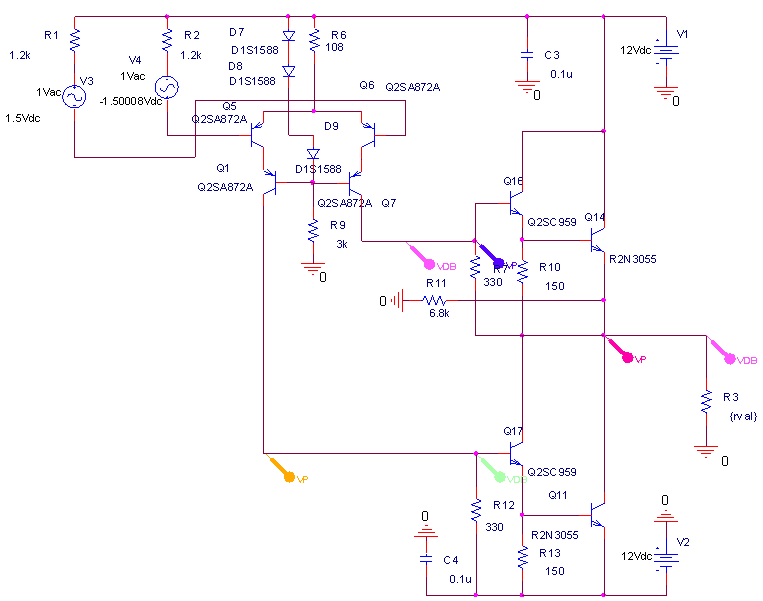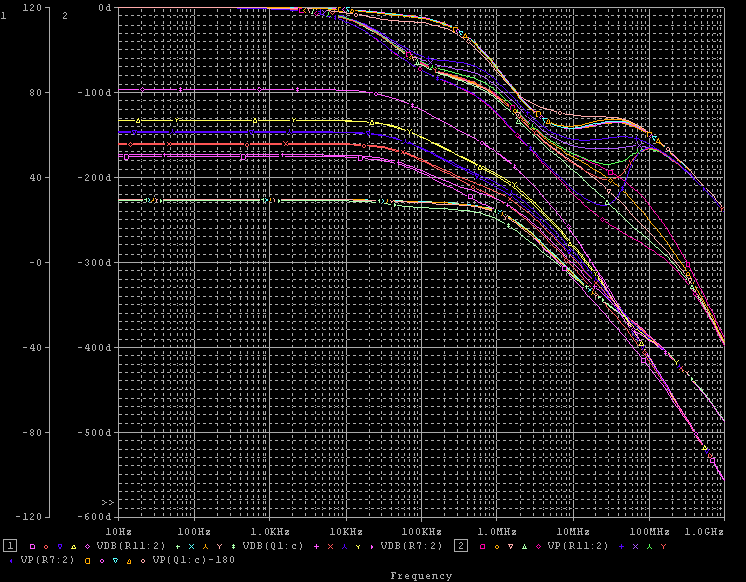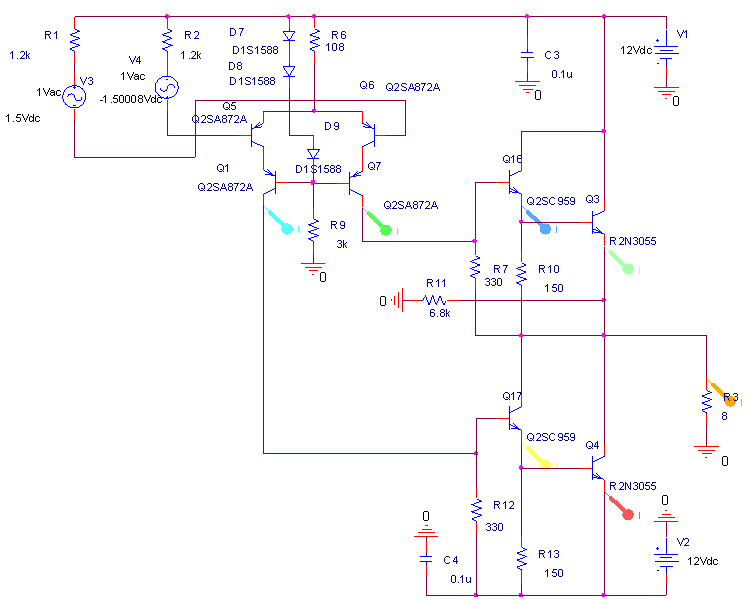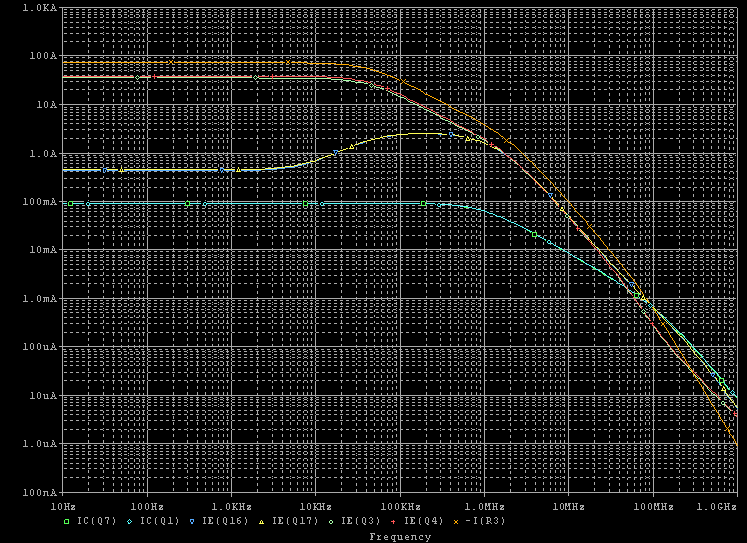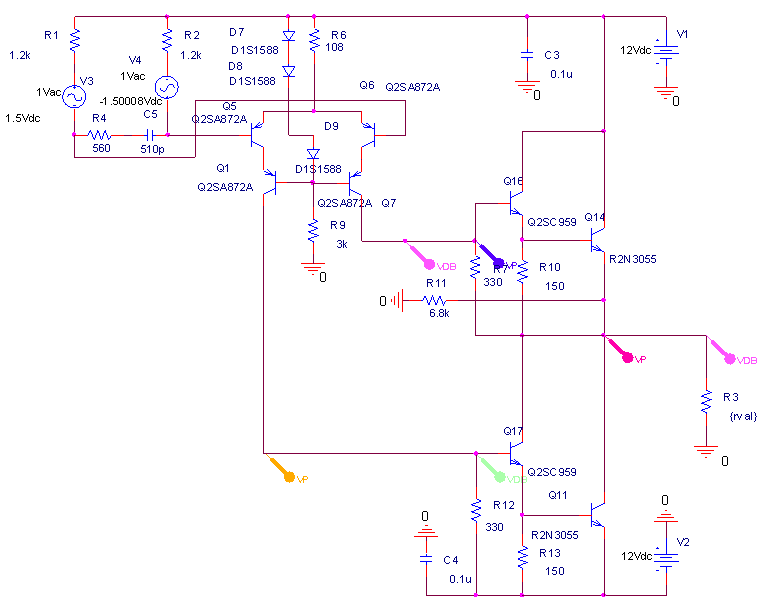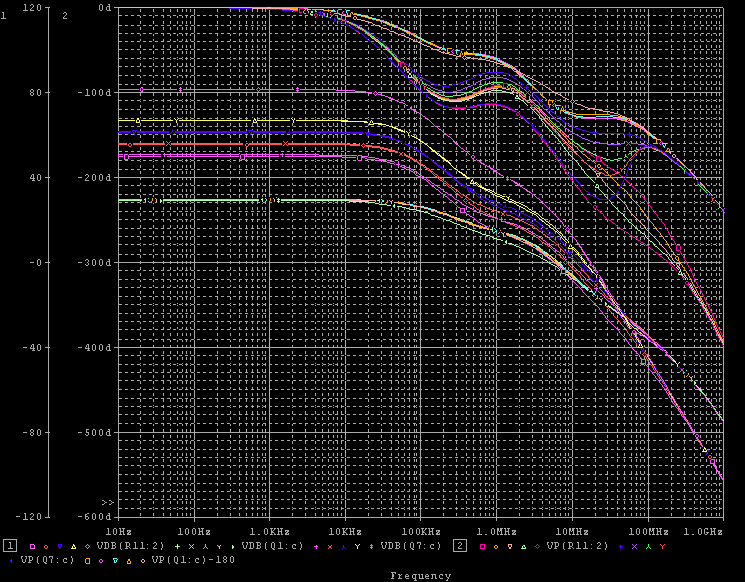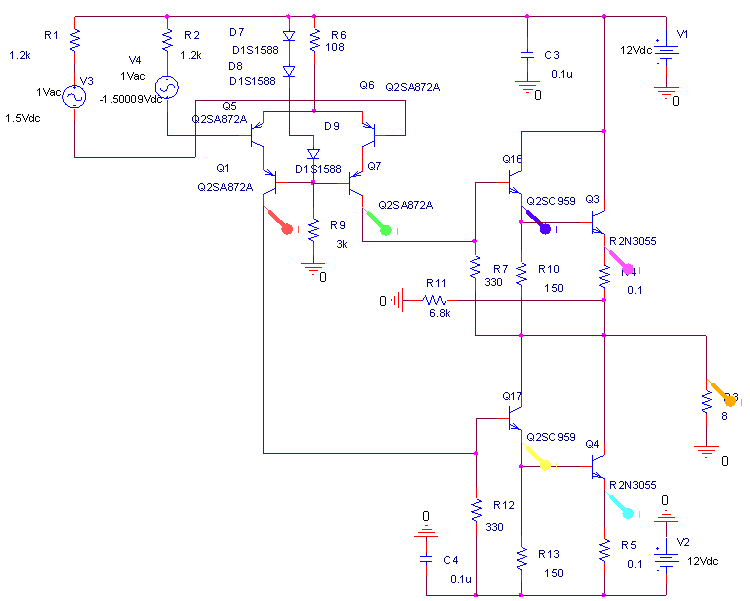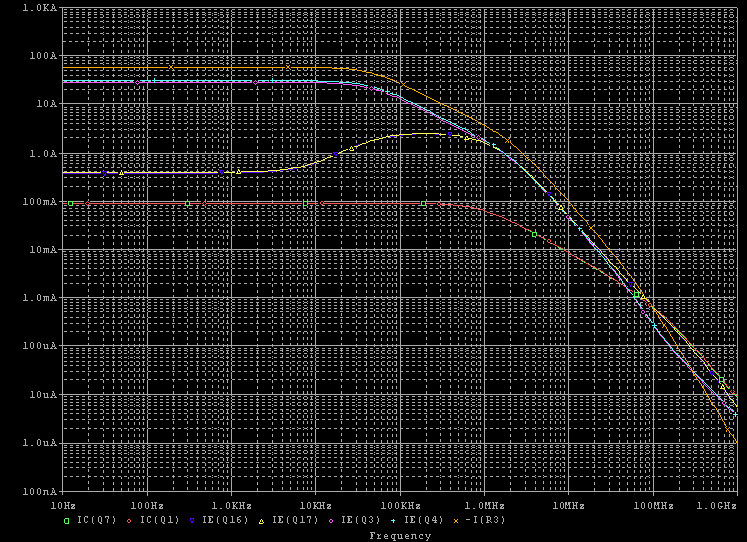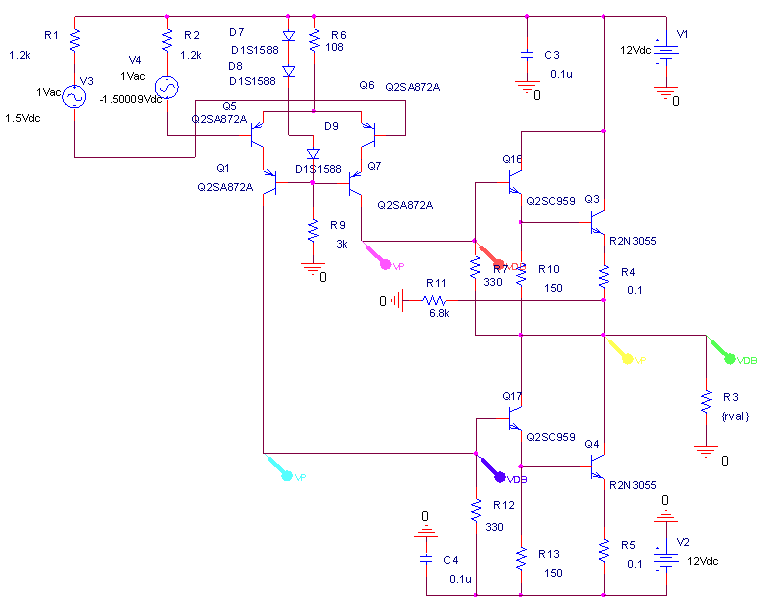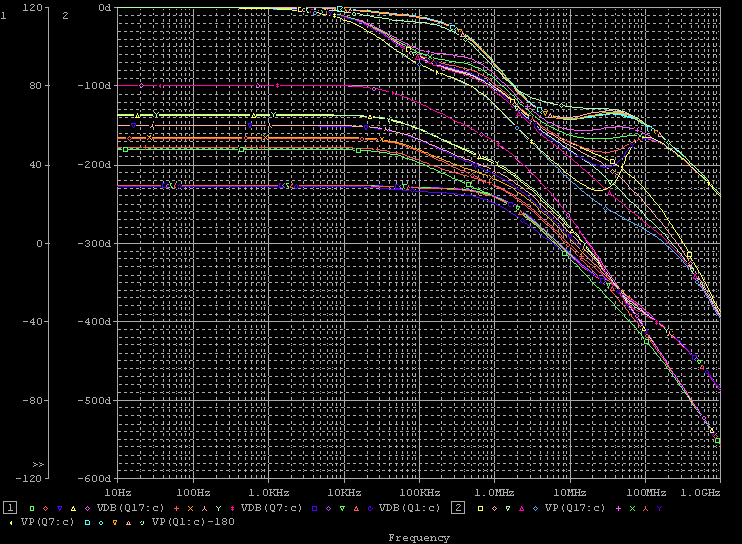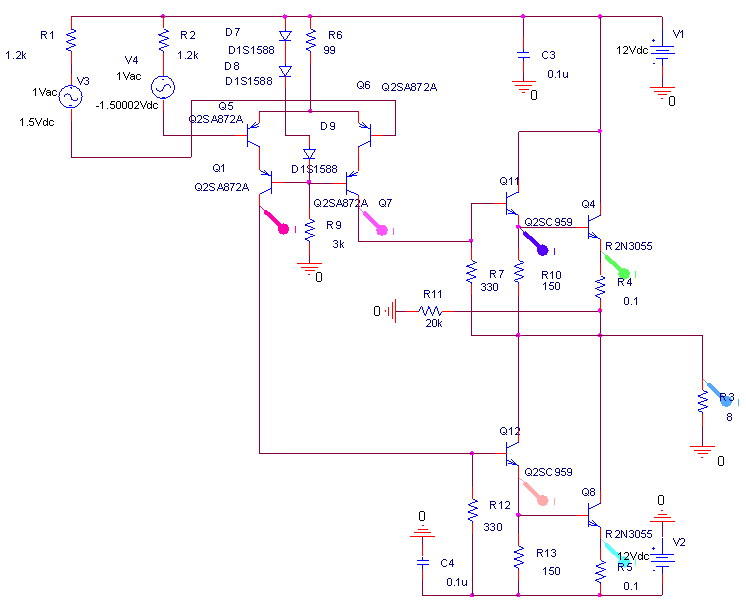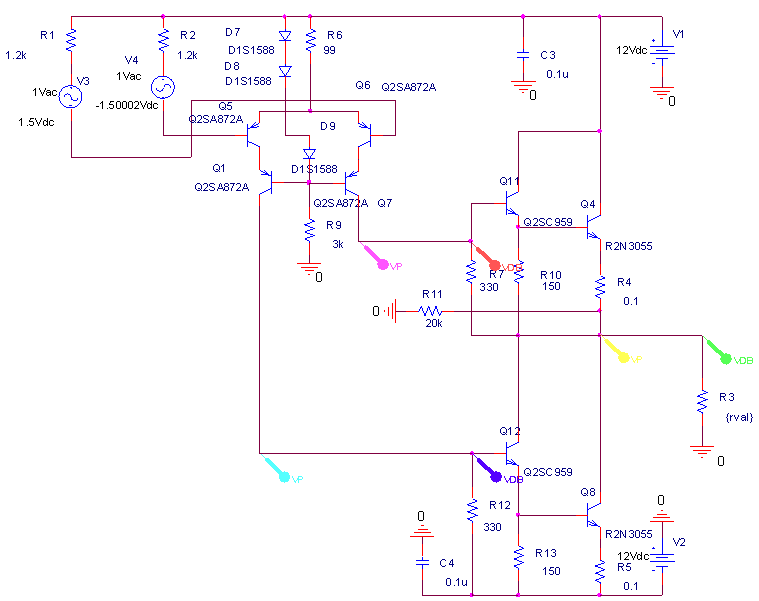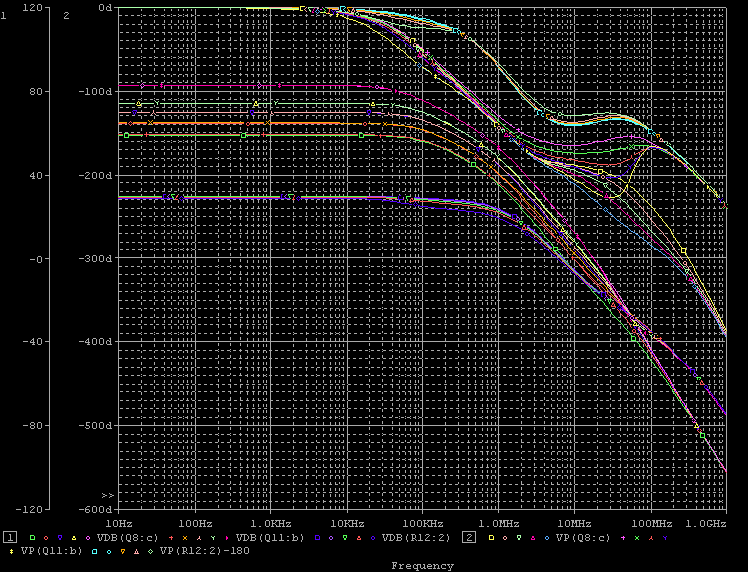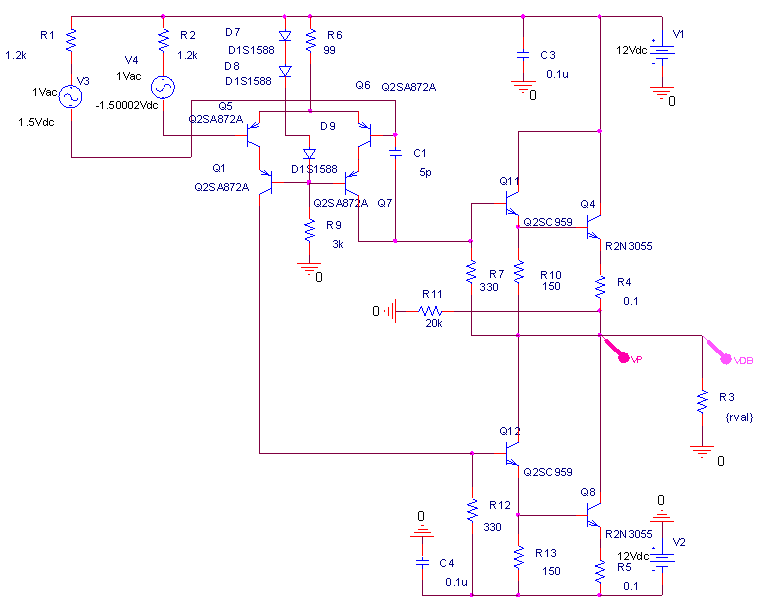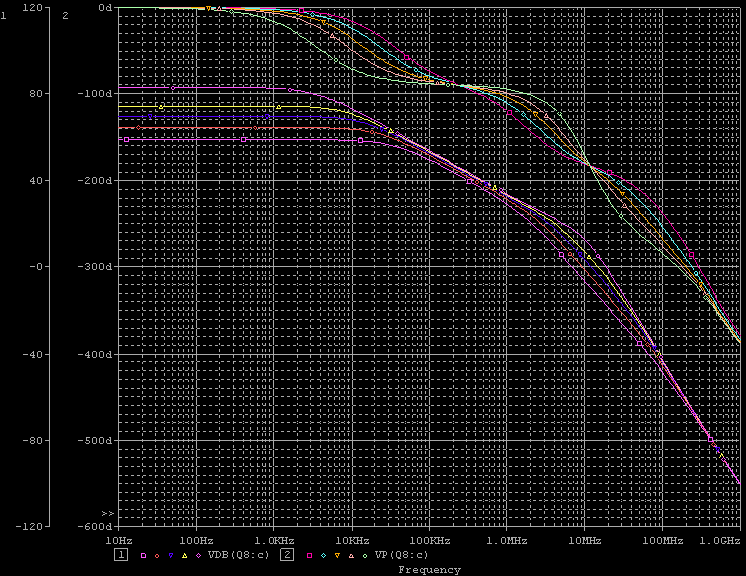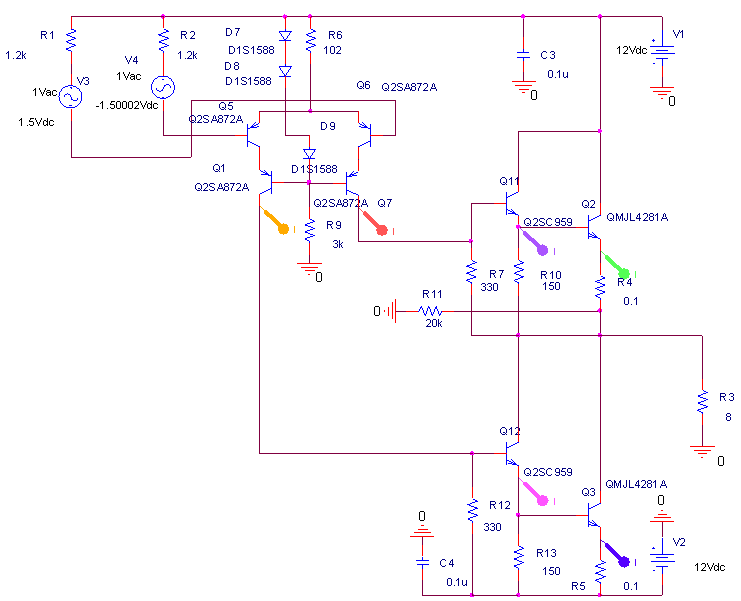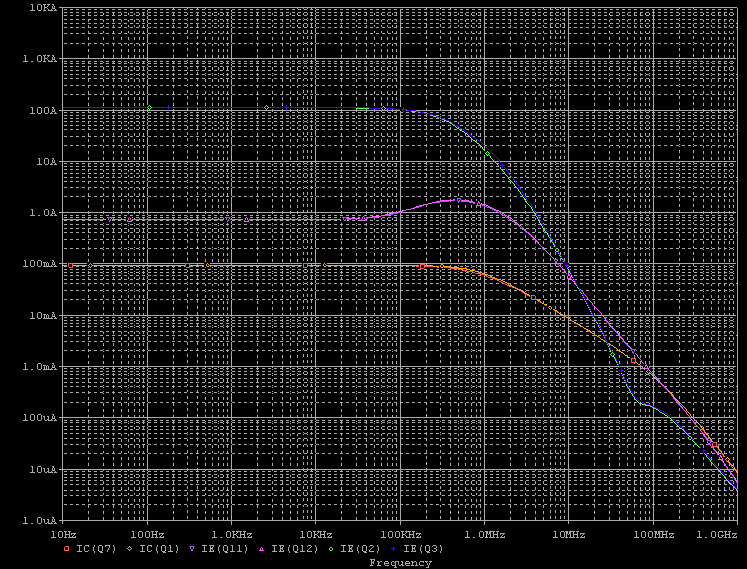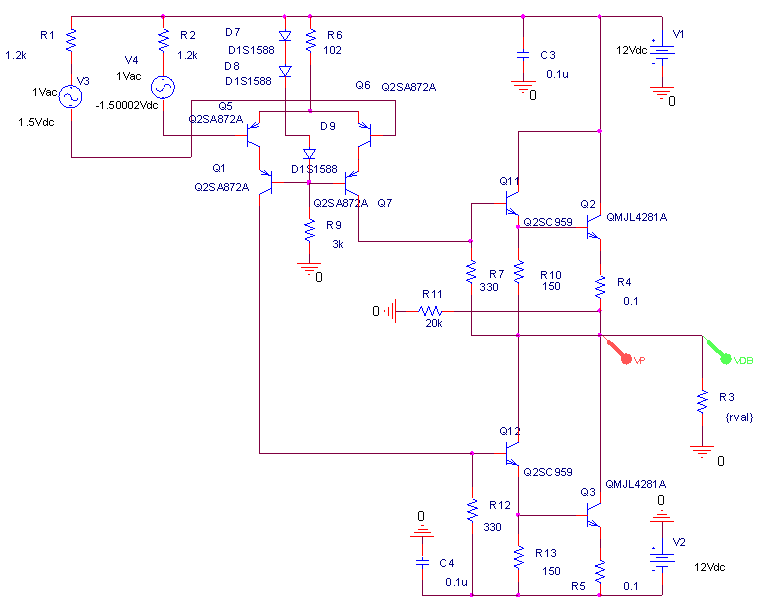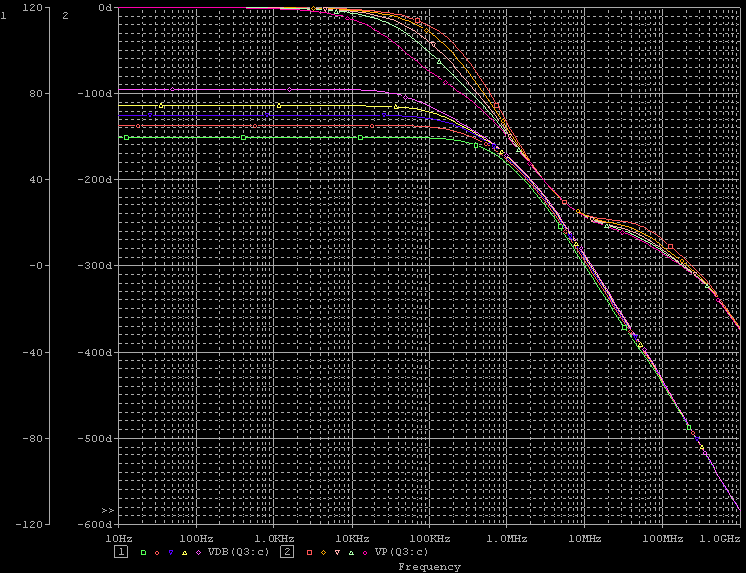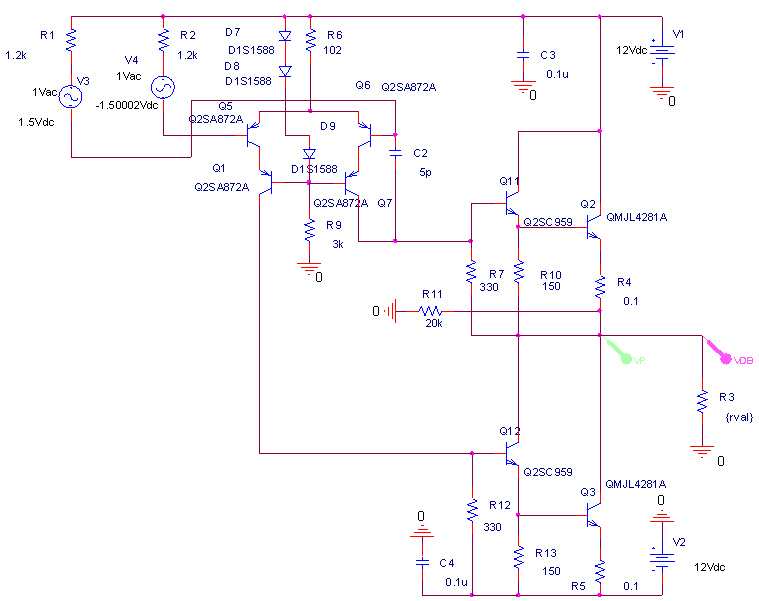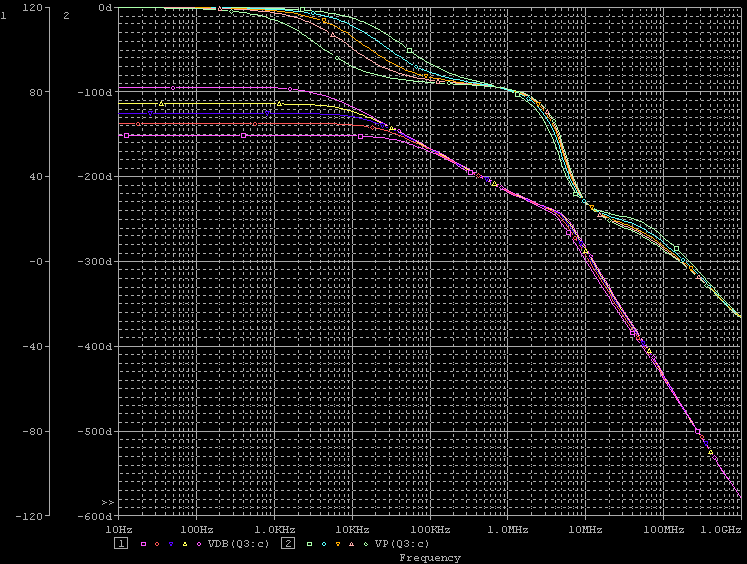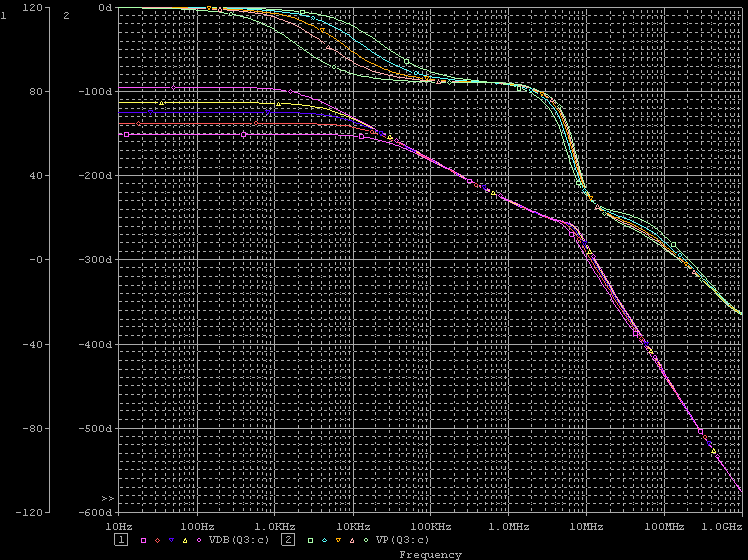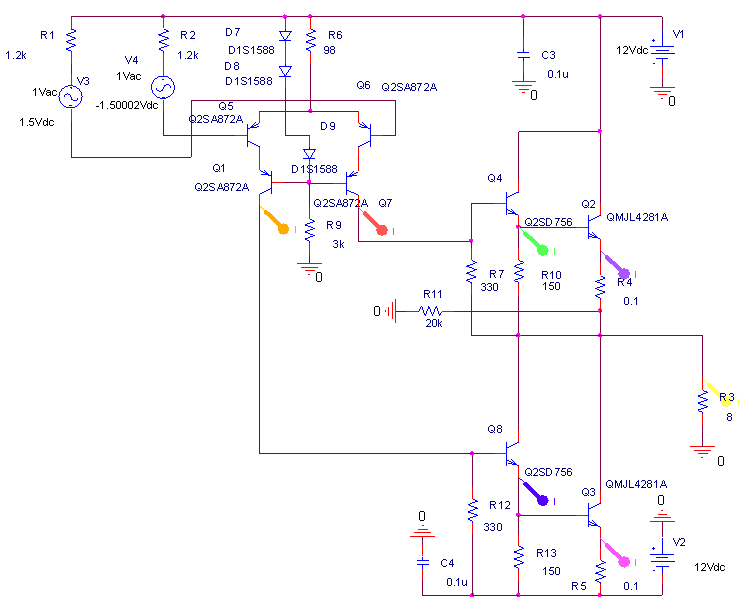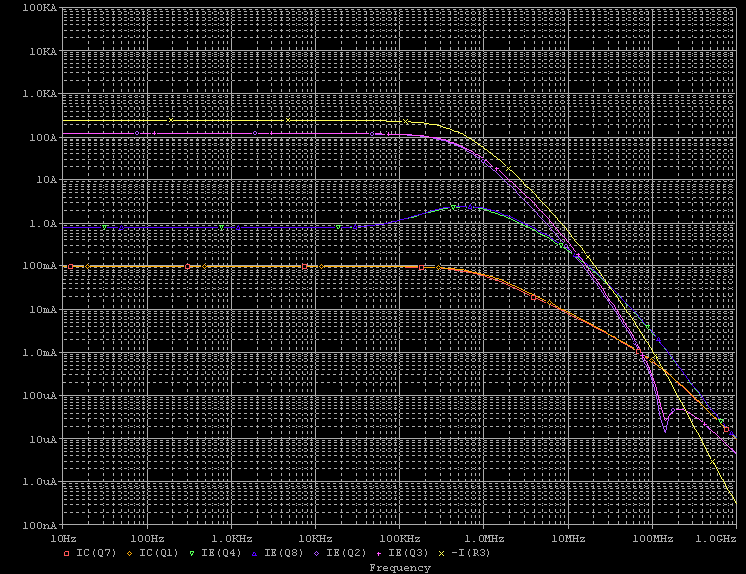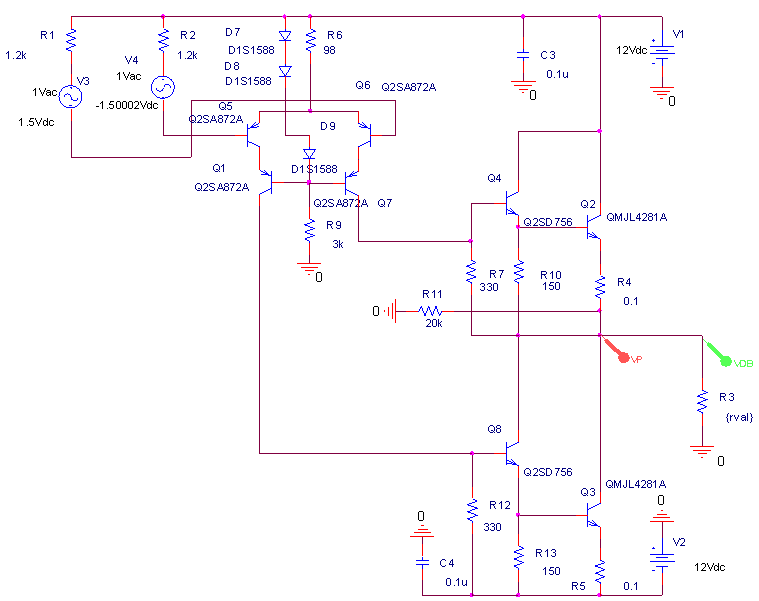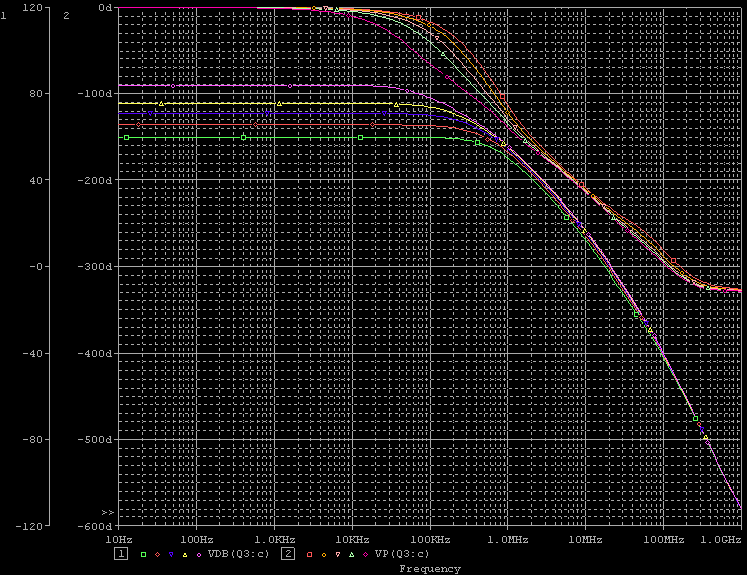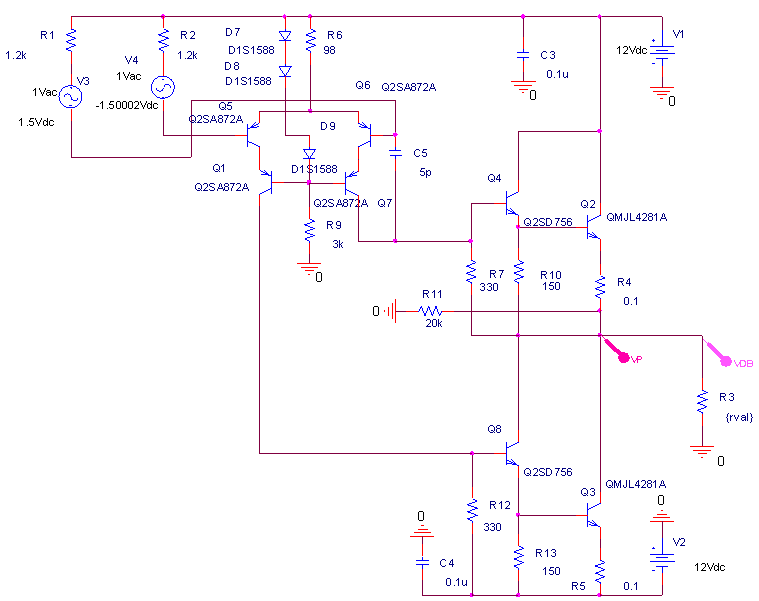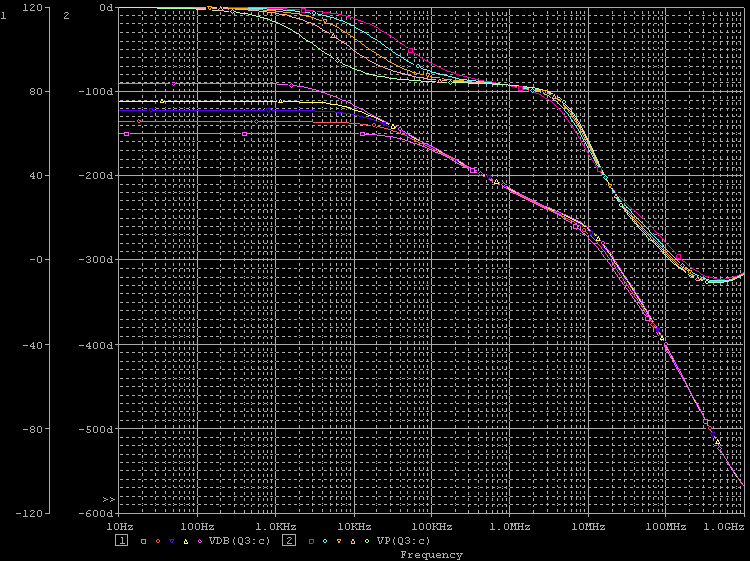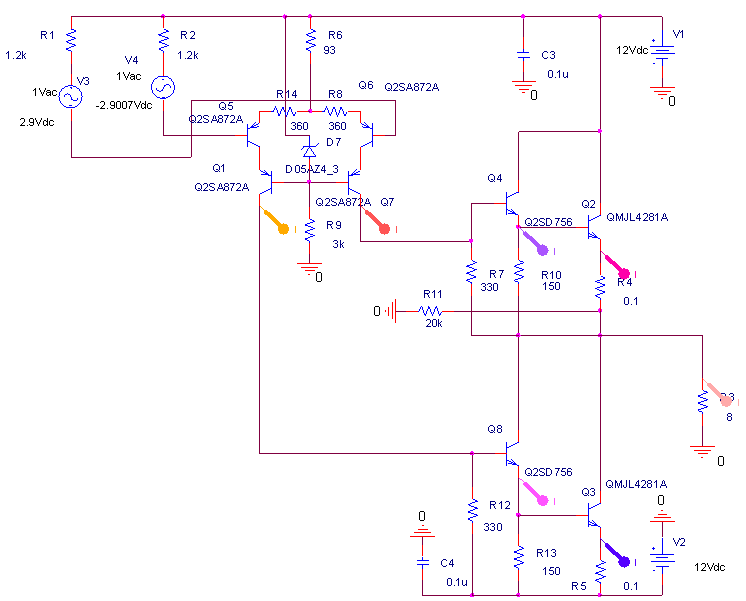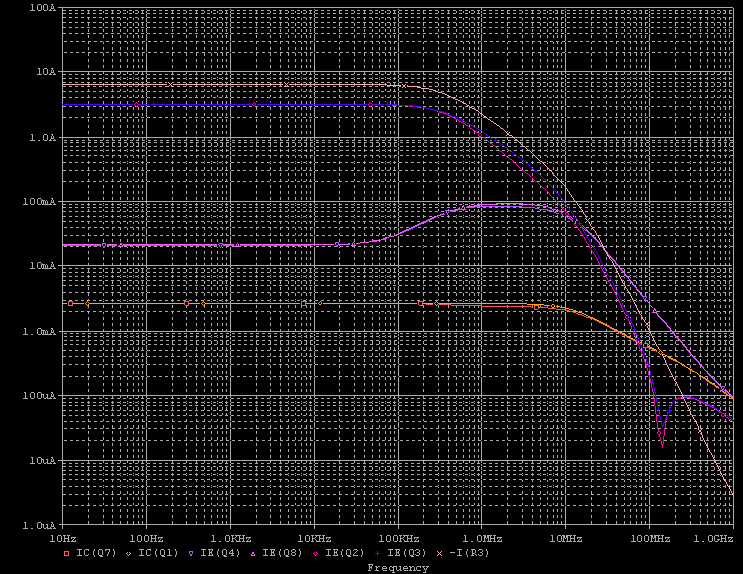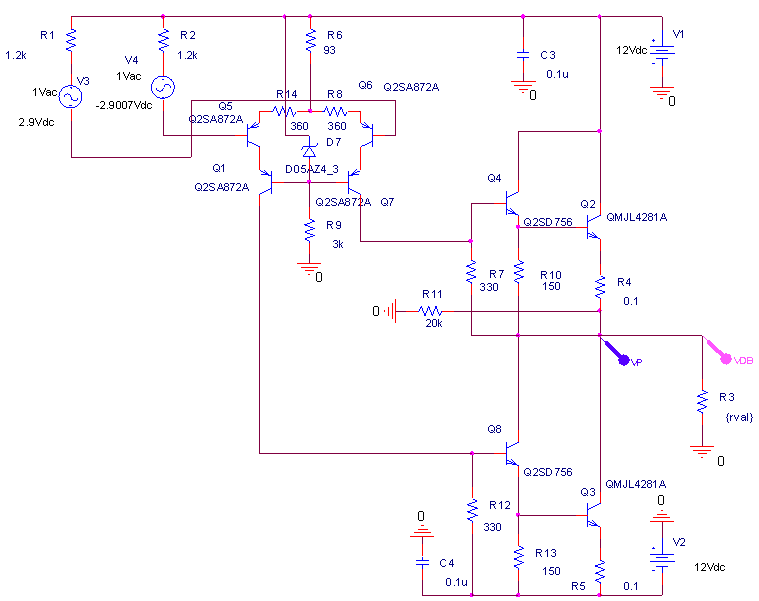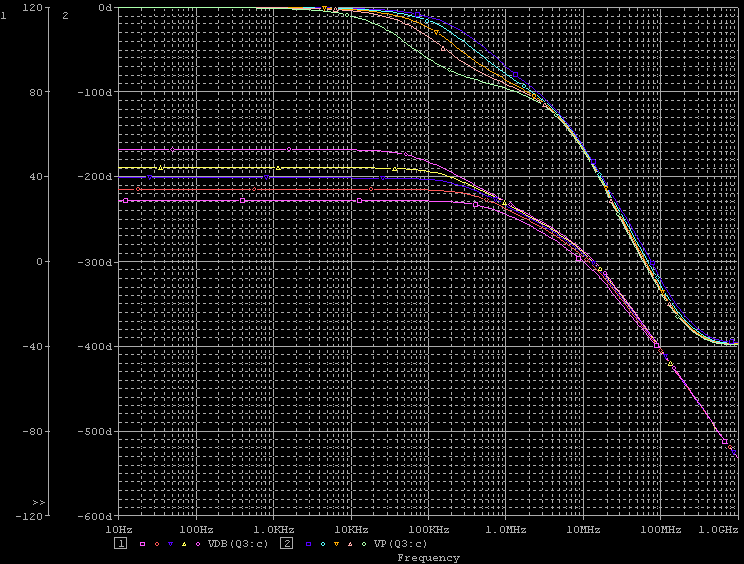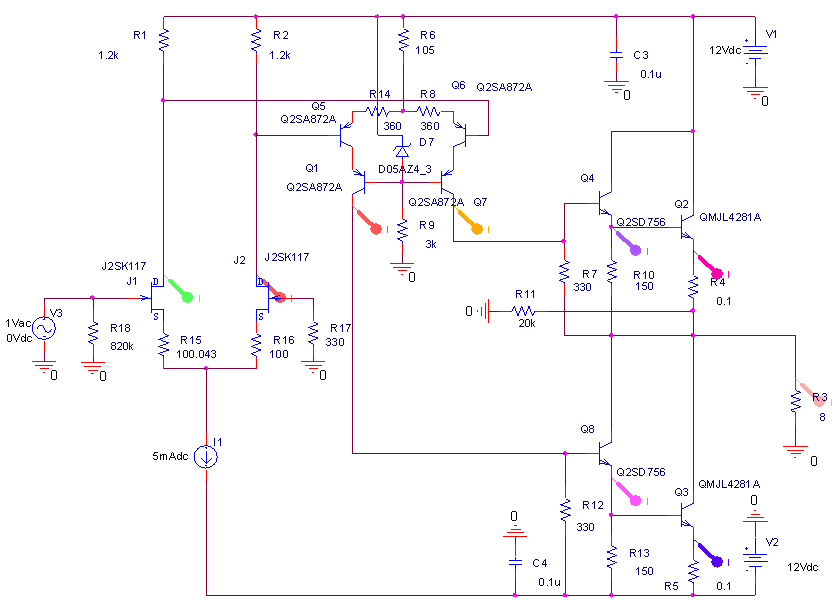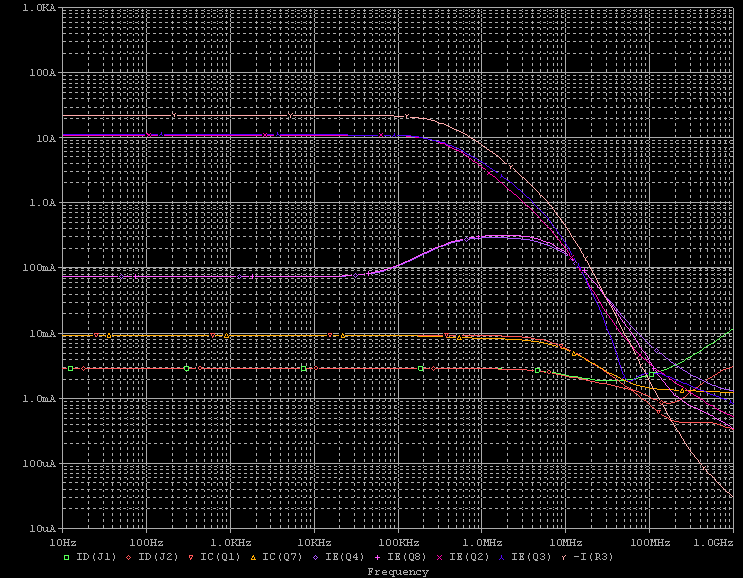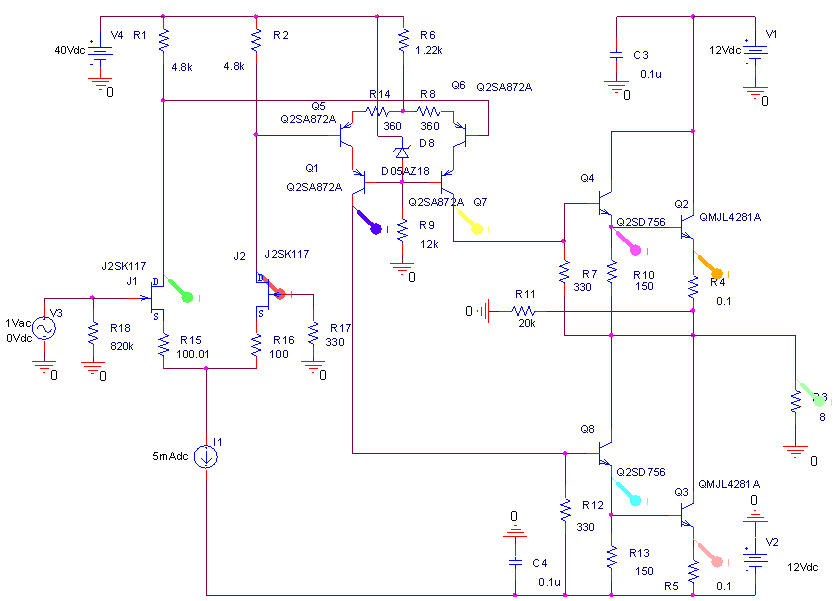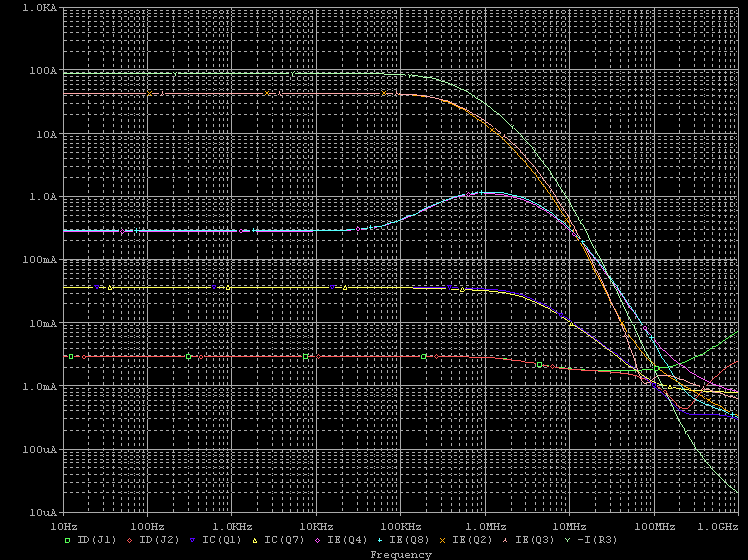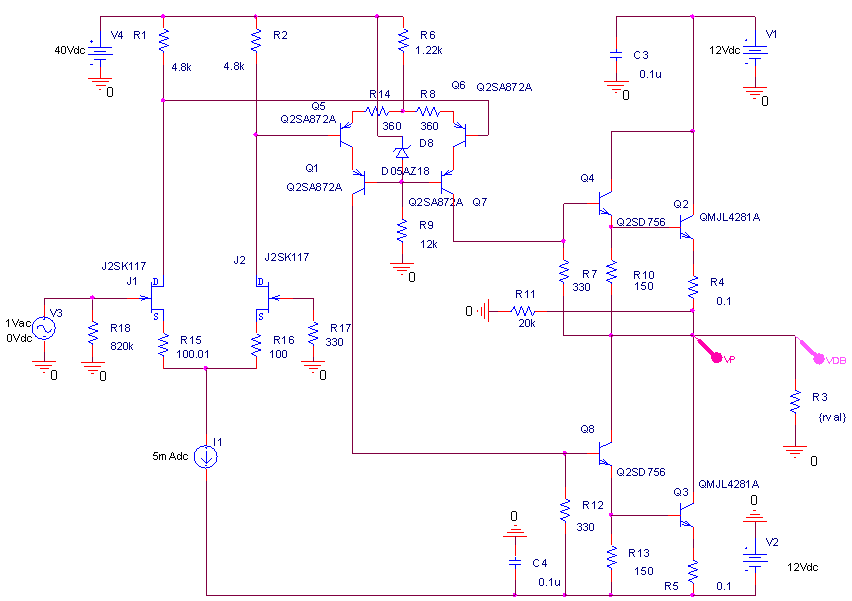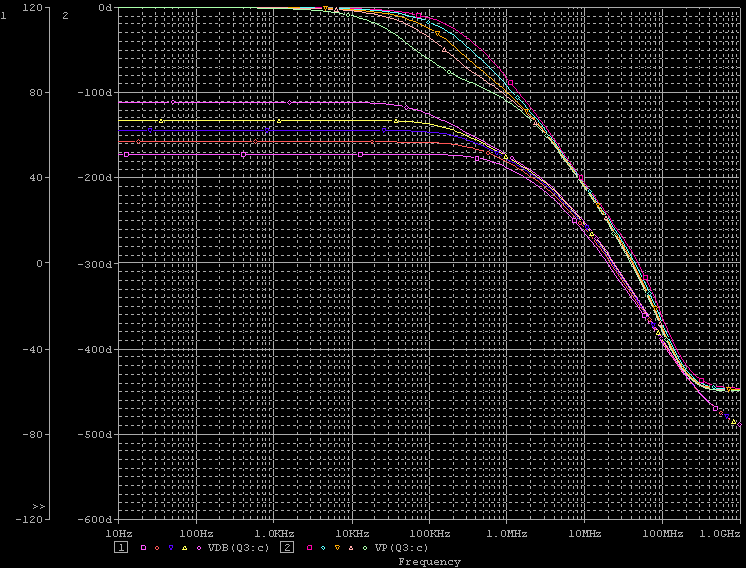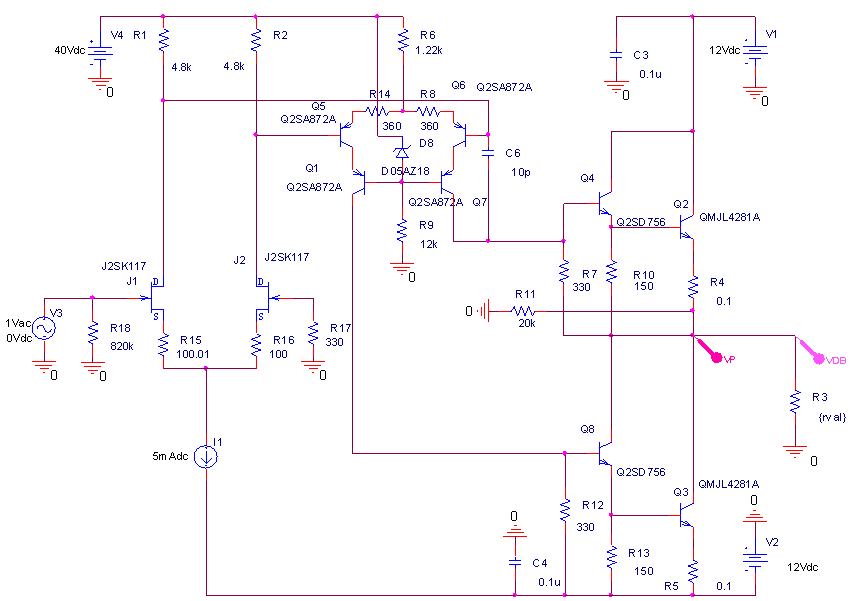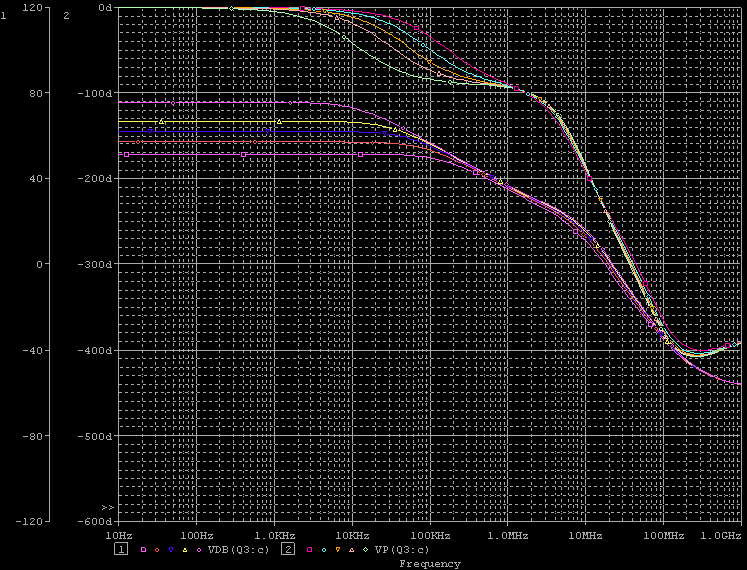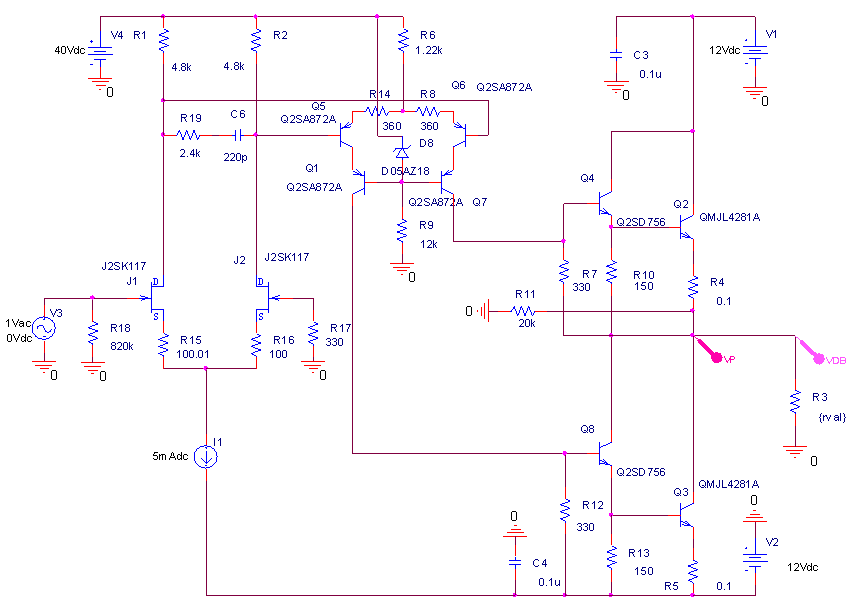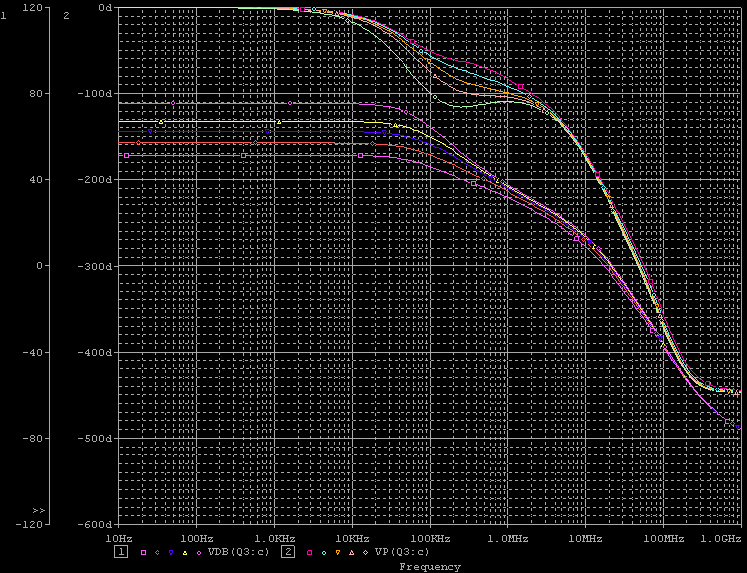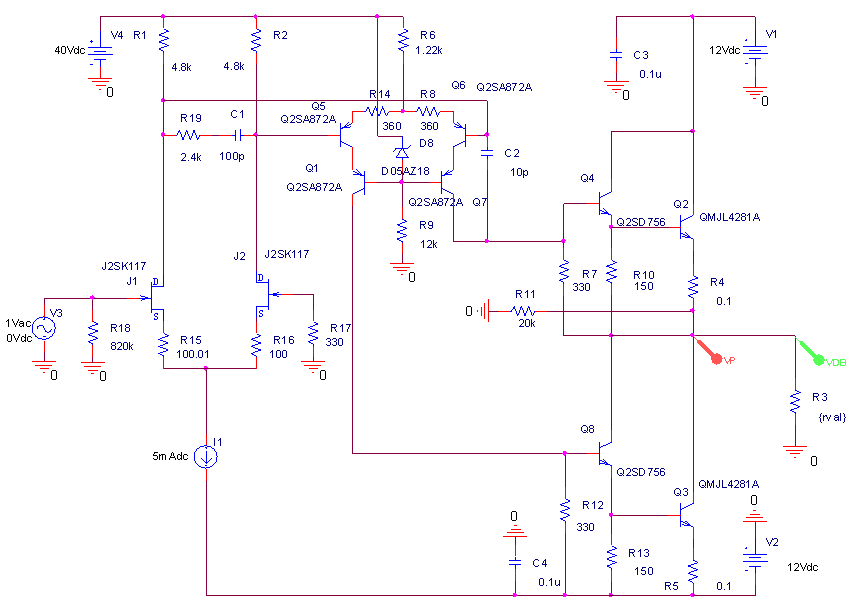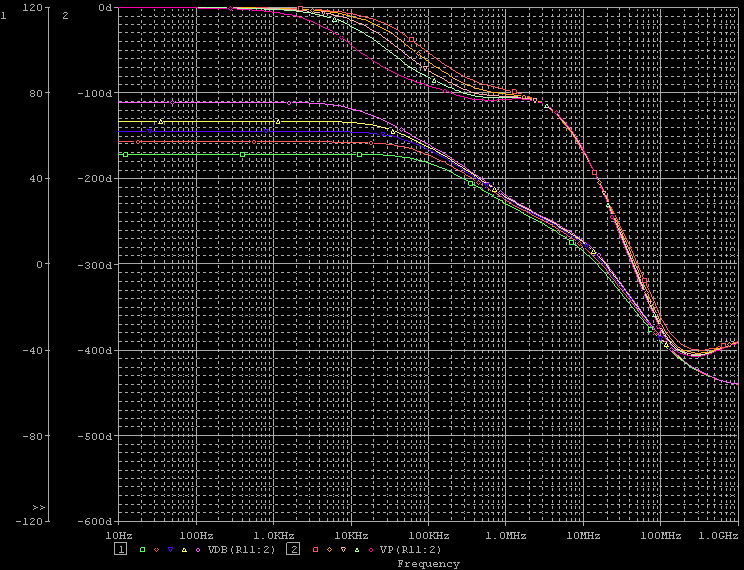俹俽倫倝們倕乮昡壙斉乯偱
揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾傪僔儈儏儗乕僩偡傞
偦偺俀
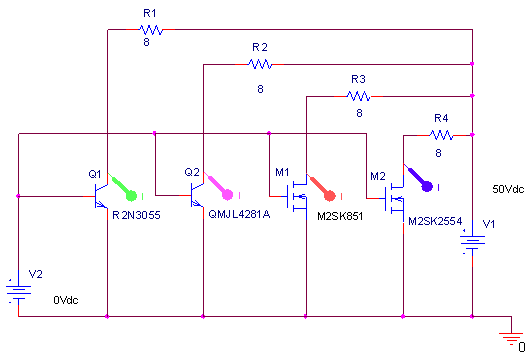
塃偼揹尮揹埑俆侽倁丄晧壸俉兌偵偍偗傞Vbe亅俬們乮俿倰乯丄倁倗倱亅俬倓乮俵俷俽乯摦摿惈偺寁應丅
僄儞僩儕乕偟偨偺偼丄
嘆俀俶俁侽俆俆乮僆儞僙儈乯丒丒丒偄偵偟偊偺僩儔儞僕僗僞戙昞
嘇俵俰俴係俀俉侾倎丒丒丒撻愼傒偼側偄偑僆儞僙儈僐儞僟僋僞偐傜嵟怴僆乕僨傿僆梡僷儚乕僩儔儞僕僗僞偲偟偰弌応丂倖俿亖俁俆俵俫倸丄俠倧倐亖俇侽侽倫俥
嘊俀俽俲俉俆侾丒丒丒戝揹棳宆俵俷俽戙昞丅崱偲側偭偰偼拞揹棳宆
嘋俀俽俲俀俆俆係丒丒丒戝揹棳宆俵俷俽偺戙柤帉
偙傟偱憹暆擻椡偺尮愹偱偁傞倗倣傪斾妑偟傛偆偲偄偆庯岦偱偁傞丅乮丱丱乯
寢壥
嘆俀俶俁侽俆俆丒丒丒俬們亖侾俙乣俁俙偺椞堟偱倗倣佮俀侽俽庛丅偦傟埲忋偺俬們椞堟偱偼倗倣偼偙傟傛傝掅壓偡傞丅偄傢備傞僐儞僾儗僢僒乕摿惈偩丅
嘇俵俰俴係俀俉侾倎丒丒丒俬們亖侾俙乣俁俙偺椞堟偱偼倗倣佮俁侽俽丅偦傟埲忋偺俬們椞堟偱偼傗偼傝倗倣偼偙傟傛傝掅壓偡傞偑俀俶俁侽俆俆傎偳偱偼側偄丅偙偺掱搙側傜儕僯傾摿惈偲尵偭偰椙偄偲巚偊傞丅
嘊俀俽俲俉俆侾丒丒丒傑偝偵俥俤俿傜偟偄擇忔摿惈偵側偭偰偄傞丅俬們亖侾俙乣俁俙偺椞堟偱偺倗倣佮俆俽丅俀俽俲侾俁係摍偺偄傢備傞僆乕僨傿僆梡墶宆俵俷俽亅俥俤俿傛傝偼偢偭偲戝偒側倗倣偩偑幚偼偙偺椞堟偱偼偄偵偟偊偺僩儔儞僕僗僞偱偁傞俀俶俁侽俆俆偵傕媦偽側偄丅戝揹棳宆俵俷俽偺嫄戝倗倣偼戝揹棳宆偵憡墳偟偄傕偭偲戝揹棳傪棳偟偨椞堟偱摼傜傟傞傕偺側偺偱偁傞丅
嘋俀俽俲俀係係俆丒丒丒俬們亖侾俙乣俁俙偺椞堟偱倗倣佮俆侽俽偼偁傞丅戝揹棳宆俵俷俽偵偲偭偰偼偛偔掅揹棳椞堟偱偙偺倗倣偼杮摉偩傠偆偐乮丱丱丟丂偑丄偙傟偑帠幚側傜戝揹棳宆俵俷俽偺柺栚桇擛偲偄偭偨偲偙傠偱偼偁傞丅
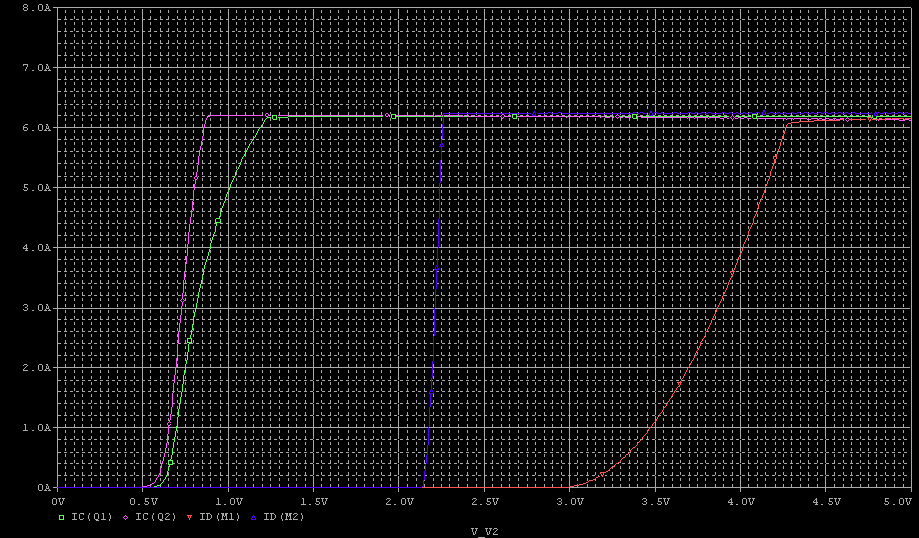
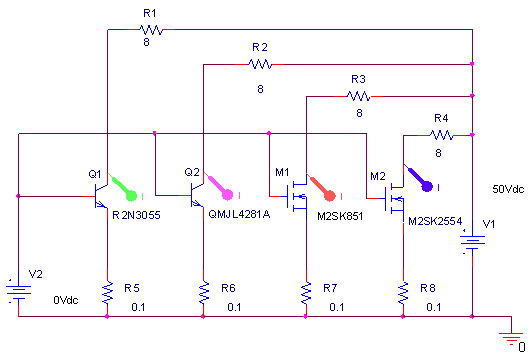
幚嵺偼塃偺傛偆偵僄儈僢僞乮僜乕僗乯偵彫掞峈傪擖傟傞丅
偨偭偨偺侽丏侾兌偩偑丄傕偲傕偲偺慺巕倗倣偑戝偒偄傎偳偵偙偺侽丏侾兌偵傛傞揹棳婣娨俶俥俛嶌梡偑戝偒偔摥偒丄儕僯傾儕僥傿偑夵慞偝傟傞丅
変偑俶倧亅侾俁俋乮傕偳偒乯払偵偼巊偭偰偄側偄偺偩偑丄敿摫懱姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偵偼巊傢傟偰偄傞傕偺偱偁傞偐傜丄偙偙偱偦偺岠壥傪妋擣偟偰偍偔丅
忋偲斾妑偡傞偲偦偺岠壥偼堦栚椖慠丅
侽丏侾兌偵傛傝揹棳婣娨俶俥俛偑妡偐傞偺偱偳傟傕偦偺暘倗倣偑尭彮偟偰偄傞偑丄偦傕偦傕偺倗倣偑戝偒偄傕偺傎偳儕僯傾儕僥傿偑傛傝戝偒偔夵慞偝傟僇乕僽偑捈慄偵嬤偯偔丅俀俽俲俀俆俆係偲俵俰俴係俀俉侾倎偼杮摉偵捈慄偲尵偭偰椙偄偖傜偄偩丅
僐儗僋僞乮僪儗僀儞乯揹棳侽俙偐傜俇俙偱倗倣傪寁嶼偡傞偲彫偝偄曽偐傜弴偵俀俽俲俉侾俆偼俁丏俀俆俽丄俀俶俁侽俆俆偼係丏俉俽丄俵俰俴係俀俉侾倎偑俇丏俇俽丄俀俽俲俀俆俆係偼俉丏俇俽偱偁傞丅偟偐偟偙傟傎偳尒帠側捈慄惈傪妉摼偱偒傞偺側傜丄倗倣偼彫偝偔側傞傕偺偺傗偼傝侽丏侾兌傪擖傟偨偄傕偺偩丄偲偄偆姶偠偵偼側傞寢壥偩丅
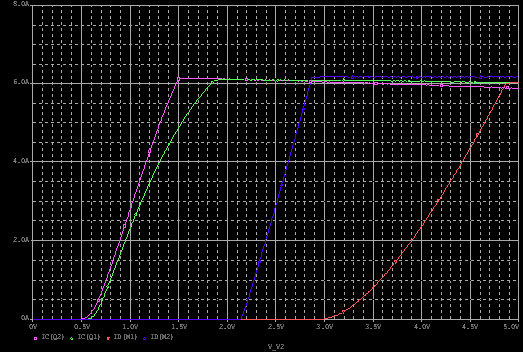 偲偄偆偙偲側偺偩偑丄埲忋丄壗傪尵偄偨偄偺偐丅偲偄偆偲丄傾儞僾幚梡堟偱峫偊傟偽僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺倗倣偼戝揹棳宆俵俷俽偵摿偵堷偗傪庢傞傕偺偱偼側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅戝揹棳宆俵俷俽偺戙柤帉偱偁傞俀俽俲俀俆俆係偵摨摍側偺偩丅偦偺僄儈僢僞乮僜乕僗乯偵揹棳婣娨掞峈傪擖傟傟偽偦偺嵎偼偝傜偵弅傑傞丅暿偵巊偄傕偟側偄僂儖僩儔僴僀揹棳擻椡偲偦偺椞堟偱偺僴僀倗倣傪偆傫偸傫偡傞偺傕埆偔偼側偄偑丄幚梡堟偱廫暘偵戝揹棳宆俵俷俽偵旵揋偡傞倗倣傪桳偡傞僩儔儞僕僗僞偵傕傕偭偲栚傪岦偗傑偟傚偆偲丅乮丱丱丟
偲偄偆偙偲側偺偩偑丄埲忋丄壗傪尵偄偨偄偺偐丅偲偄偆偲丄傾儞僾幚梡堟偱峫偊傟偽僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺倗倣偼戝揹棳宆俵俷俽偵摿偵堷偗傪庢傞傕偺偱偼側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅戝揹棳宆俵俷俽偺戙柤帉偱偁傞俀俽俲俀俆俆係偵摨摍側偺偩丅偦偺僄儈僢僞乮僜乕僗乯偵揹棳婣娨掞峈傪擖傟傟偽偦偺嵎偼偝傜偵弅傑傞丅暿偵巊偄傕偟側偄僂儖僩儔僴僀揹棳擻椡偲偦偺椞堟偱偺僴僀倗倣傪偆傫偸傫偡傞偺傕埆偔偼側偄偑丄幚梡堟偱廫暘偵戝揹棳宆俵俷俽偵旵揋偡傞倗倣傪桳偡傞僩儔儞僕僗僞偵傕傕偭偲栚傪岦偗傑偟傚偆偲丅乮丱丱丟
偲偄偆傢偗偱丄崱夞偼倖俿亖俁俆俵俫倸丄俠倧倐亖俇侽侽倫俥偺僆儞僙儈尰戙僆乕僨傿僆梡僷儚乕僩儔儞僕僗僞俵俰俴係俀俉侾倎傪慺嵽偲偟偰丄変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾傪峫偊傞偺偱偁傞丅
壗屘俵俰俴係俀俉侾倎側偺偐丠丂偦傟偼偨偩僆儞僙儈偺倂倕倐僒僀僩偱偦偺俹俽倫倝們倕儌僨儖偑採嫙偝傟偰偄偨偐傜丅偱偁傞丅儌僨儖偑採嫙偝傟偰偄傞偺側傜搶幣側傝僒儞働儞側傝偺崙嶻俿俼傪巊偄偨偄偲偙傠偩偑丄巆擮側偑傜変偑崙儊乕僇乕偼俽倫倝們倕儌僨儖偺採嫙偵忣擬傪帩偨側偄傛偆偩丅
偙偙傪尒偰偍傜傟傞搶幣偝傫丄僒儞働儞偝傫丄儖僱僒僗偝傫偺娭學幰偺奆偝傫丄倂倕倐忋偱偺傛傝堦憌偺俹俽倫倝們倕儌僨儖偺採嫙傪丂倣乮丵丵乯倣丂
側乣傫偰丅尒偰傞恖側傫偐偄側偄偐乮丱丱丟
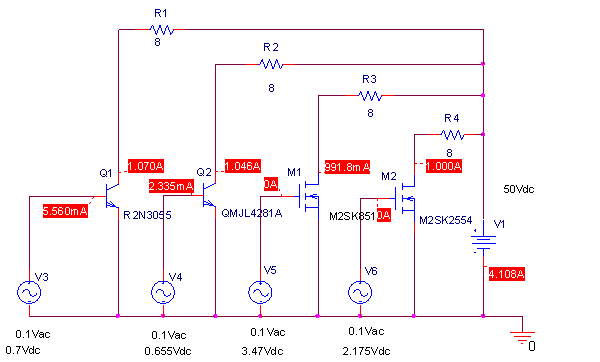 俙俠僗僀乕僾儌乕僪偵傛傝倗倣偺廃攇悢摿惈傪娤傞丅
俙俠僗僀乕僾儌乕僪偵傛傝倗倣偺廃攇悢摿惈傪娤傞丅
愭偢偼僄儈僢僞乮僜乕僗乯掞峈側偟偺応崌丅
僶僀傾僗俢俠揹埑傪偦傟偧傟傾僀僪儕儞僌揹棳偑侾俙掱搙偵側傞傛偆偵挷惍偡傞丅
偙傟偱俙俠僐儗僋僞乮僪儗僀儞乯揹棳曄壔傪俙俠儀乕僗乮僎乕僩乯揹埑曄壔偱彍嶼偡傞偙偲偵傛傝傾僀僪儕儞僌揹棳侾俙偺応崌偺慺巕倗倣偺廃攇悢摿惈偑媮傑傞丅
偙偺応崌僪儔僀僽僀儞僺乕僟儞僗偼侽兌乮姰慡揹埑尮乯側偺偱俠倧倐丄俠倰倱倱側偳偺慺巕婑惗梕検偺塭嬁傪庴偗側偄丅偺偱丄偦偺廃攇悢摿惈偵偼慺巕屌桳偺崅堟尷奅偑昞尰偝傟傞偙偲偵側傞丅
寢壥
偙傟傜偺慺巕倗倣乮俬們丄俬倓亖侾俙乯偼丄掅堟偱俀俶俁侽俆俆亖侾俉俽丄俵俰俴係俀俉侾倎亖俀侽丏俉俽丄俀俽俲俉侾俆亖俁丏俉俽丄俀俽俲俀俆俆係亖係俀俽偱偁傞丅偑丄崅堟偱倗倣偼掅壓偡傞丅偺偼丄崅堟尷奅偱丄僩儔儞僕僗僞偱尵偊偽倖俿娭楢偱倗倣偑掅壓偟巒傔傞晅嬤偑儀乕僞幷抐廃攇悢偲偄偆偙偲偵側傞丅倖俿亖俀丏俆俵俫倸偺俀俶俁侽俆俆乮偄偵偟偊偺婯奿偺婰壇偱偼倖俿亖侽丏俉俵俫倸偩偭偨偼偢側偺偩偑丄夵傔偰僆儞僙儈偺僒僀僩偵偁傞婯奿傪傒傞偲俀丏俆俵俫倸偲偁傞丅傗偼傝帪戙偲嫟偵曄壔偡傞偺偐乮丱丱丟乯偼偦傟偑悢侾侽倠俫倸戜丄倖俿偑俁俆俵俫倸偺俵俰俴係俀俉侾倎偼侾寘崅偔悢昐倠俫倸戜丄俀俽俲俉侾俆偼偝傜偵侾寘埲忋崅偔悢俵俫倸乣悢廫俵俫倸戜偩丅偝偡偑偵俵俷俽亅俥俤俿偼崅堟摿惈偑桪傟偰偄傞丅偲尵偄偨偐偭偨偲偙傠俀俽俲俀俆俆係偺偦傟偼悢倠俫倸戜偱偁傞丅偊偉乣儂儞僩偐偄側乮丱丱丟
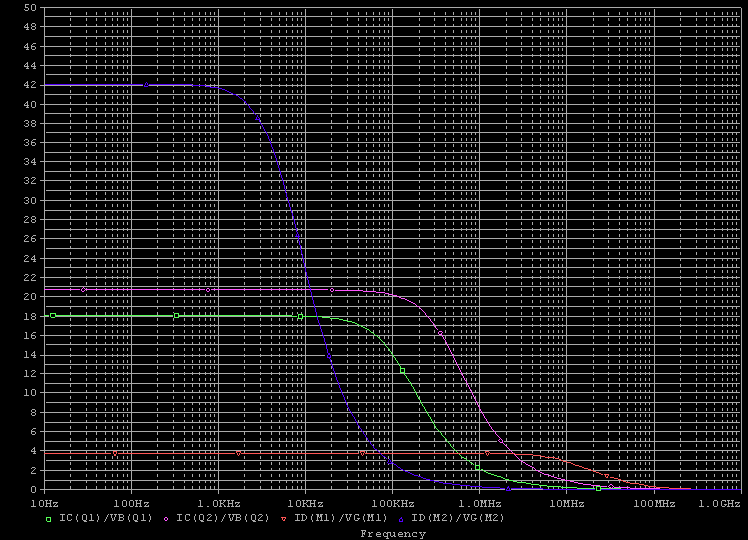
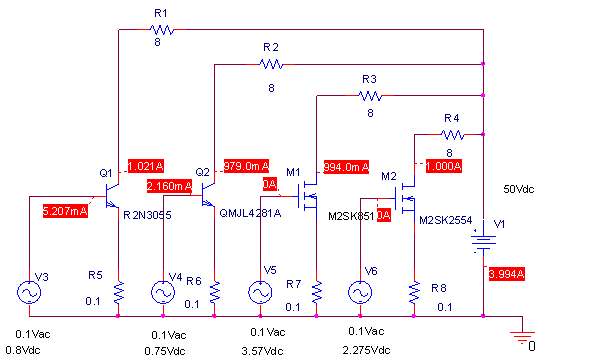
慺巕屌桳偺崅堟尷奅偐傜棃傞儀乕僞幷抐廃攇悢傕丄偦偺僄儈僢僞乮僜乕僗乯偵揹棳婣娨掞峈傪擖傟傞偙偲偵傛偭偰崅堟偵捛偄傗傞偙偲偑弌棃傞丅
塃偺偲偍傝僄儈僢僞乮僜乕僗乯偵侽丏侾兌傪擖傟偰摨條偵應偭偰傒傞丅
寢壥
倗倣乮侾俙乯偼俀俶俁侽俆俆亖俇丏係俽丄俵俰俴係俀俉侾倎亖俇丏俈俆俽丄俀俽俲俉侾俆亖俀丏俈俽丄俀俽俲俀俆俆係亖俉丏侾俽偱偁傞丅
侽丏侾兌偑側偐偭偨応崌偲斾妑偡傞偲丄偦偺倗倣偼俀俶俁侽俆俆偑俁俆丏俇亾丄俵俰俴係俀俉侾倎偑俁俀丏俆亾丄俀俽俲俉侾俆偑俈侾丏侾亾丄俀俽俲俀俆俆係偑侾俋丏俁亾偱偁傞丅傕偲傕偲偺倗倣偑戝偒偄傎偳侽丏侾兌偺揹棳婣娨掞峈偵傛傞倗倣偺掅壓岠壥偑戝偒偄偺偩偑丄偙傟偼俲愭惗偺僆乕僨傿僆俢俠傾儞僾惢嶌偺偡傋偰忋姫偵傕摨條偺偙偲偑彂偄偰偁偭偨丅
偦偟偰丄暪偣偰侽丏侾兌偺揹棳婣娨掞峈偵傛傝廃攇悢摿惈偼夵慞偝傟傞丅偳傟傕侾寘崅堟摿惈偑忋偵怢傃偰偄傞偙偲偑僌儔僼偐傜暘偐傞丅
揹棳婣娨傕梫偡傞偵俶俥俛偩偐傜丄僎僀儞乮倗倣乯偑彫偝偔側傝廃攇悢摿惈偼椙偔側傞偲偄偆捠忢偺俶俥俛偲摨條偺岠壥偑敪婗偝傟傞偺偩丅
偑丄俶俥俛偵傛偭偰傕嵟廔揑側崅堟尷奅偱偁傞倖俿偑崅堟偵怢傃傞栿偱偼側偄丅俶俥俛偵傛偭偰僎僀儞乮倗倣乯偐傑傏偙摿惈偺忋偺曽偑嶍傜傟偨寢壥儀乕僞幷抐廃攇悢偑崅堟偵怢傃偨偵夁偓側偄丅偙偺曈偺帠忣偼僆乕僶乕僆乕儖俶俥俛偺応崌偲側傫傜曄傢傞偲偙傠偑側偄丅乮僩儔儞僗丒僀儞僺乕僟儞僗偺応崌偼堘偆傛偆偩偑乮丱丱丟乯
偦傟偵偟偰傕俀俽俲俀俆俆係丅偙傟偑杮摉側傜偽丄偙傟偺応崌侽丏侾兌偺揹棳婣娨掞峈偑側偄偲幚梡偵側傜側偄崅堟摿惈偱偼側偐傠偆偐丅偙偺儌僨儖丄戝忎晇側傫偩傠偆偐乮丱丱丟
偲偙傠偱偙偺慺巕偺崅堟尷奅偵傛傞棙摼乮倗倣乯尭悐偼埵憡揑偵偼偙偙偵億乕儖偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偺偨傔丄廔抜偑僄儈僢僞乮僜乕僗乯愙抧摦嶌偺姰慡懳徧宆傗丄嵟嬤傛偆傗偔棟夝偟偨乮丱丱丟僀儞僶乕僥僢僪僟乕儕儞僩儞俽俤俹俹弌椡抜偺応崌偼偙偺曈偵廔抜偺億乕儖偑棫偭偰偟傑偆偙偲偵側傞丅偙偺偨傔丄埵憡揑偵旕忢偵傗偭偐偄偵側傞傢偗偱偁傞丅
偙偙偺偲偙傠廔抜慺巕偦偺傕偺偵侾侽侽亾嬤偄揹棳婣娨儘乕僇儖俶俥俛偑妡偐傞偄傢備傞僄儈僢僞乮僜乕僗乯僼僅儘傾俽俤俹俹弌椡抜偺応崌偼丄埲忋偺棟孅偐傜摉慠偱偁傞偑廔抜偺億乕儖偼旕忢偵崅堟偵旘傇偙偲偵側傞丅偺偱丄俶俥俛傾儞僾偲偟偨応崌埵憡揑偵旕忢偵峔惉偑妝偵側傞丅傗偼傝偙偺偁偨傝偺帠忣偐傜傕悽偺敿摫懱僷儚乕傾儞僾偼僄儈僢僞僼僅儘傾俽俤俹俹弌椡抜偽偐傝偵側傞偺偩傠偆丅
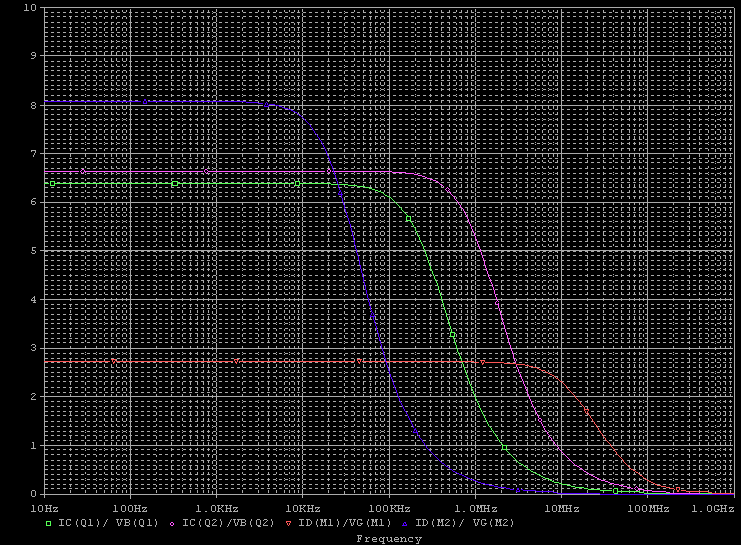
偝偰丄偙傟偑廔抜偵俀俶俁侽俆俆傪婲梡偟偨変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾丅
幚婡偼廔抜僷儚乕俿倰偼俀俽俢侾俉俉偩偑俀俶俁侽俆俆偱戙梡偡傞丅倖俿揑偵傕懡彮偺嵎偼偁傞偺偩偑丄傑偀儌僨儖偑側偄偺偱傗傓傪摼側偄丅俀抜栚嵎摦傾儞僾偲僇僗僐乕僪傾儞僾傕幚婡偼俀俽俙俇侽俈偩偑丄偙傟傕儌僨儖側偄偺偱俀俽俙俉俈俀偱戙梡偡傞丅偝傜偵弶抜傪徣棯偟偰偁傞偑偦偺棟桼偼慜夞偺乬儌乕僞乕僪儔僀僽傾儞僾傪峫偊傞乭偵摨偠丅
晧壸偑俁侽侽兌側偺偼丄偙偺傾儞僾偱偼僀儞僺乕僟儞僗俁侽侽兌偺僿僢僪僼僅儞傕側傜偟偰偄傞偺偱偦偺応崌傪憐掕偟偨傕偺偱偁傞丅偑丄埵憡偺摦岦傪娤傞偺偵傕搒崌偑椙偄偺偩丅
埵憡曗惓偺俠俆亖俆倫俥丄侾侽倫俥丄俀侽倫俥丄係侽倫俥丄俉侽倫俥偺応崌偺僷儔儊僩儕僢僋夝愅偱奺晹偺揹埑棙摼媦傃偦偺埵憡傪娤傞丅
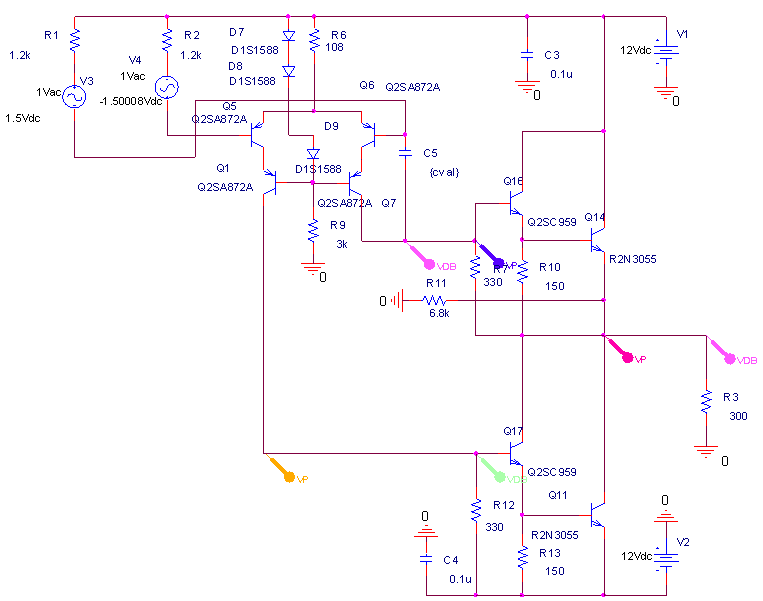
僌儔僼偼俁偮偺僌儖乕僾偵暘偐傟傞偑丄堦斣忋偑埵憡偺僌儖乕僾丄恀傫拞偑傾儞僾弌椡揰媦傃俀抜栚嵎摦傾儞僾塃懁偺弌椡揰偵偍偗傞揹埑棙摼偺僌儖乕僾丄堦斣壓偑俀抜栚嵎摦傾儞僾嵍懁偺弌椡揰偵偍偗傞揹埑棙摼偺僌儖乕僾偱偁傞丅堦斣忋偺埵憡偺僌儖乕僾偺偆偪俀抜栚嵎摦傾儞僾嵍懁偺弌椡揰偵偍偗傞揹埑埵憡偵偮偄偰偼懳斾偟傗偡偔偡傞偨傔亅侾俉侽亱墘嶼偟偰昞帵偟偰偄傞丅乮埲壓偙偺揰摨偠丅乯
恀傫拞偺傾儞僾弌椡揰媦傃俀抜栚嵎摦傾儞僾塃懁偺弌椡揰偵偍偗傞揹埑棙摼偺僌儔僼偼俀杮偺慄偑杦偳廳側偭偰偄傞丅堦斣忋偺偦傟偧傟偺埵憡偺僌儔僼傕摨偠偔杦偳廳側偭偰偄傞丅
偙偺僌儔僼偐傜俀抜栚嵎摦傾儞僾偺揹埑棙摼偑掅堟偱俀俋倓俛丄弌椡抜偺揹埑棙摼偑掅堟偱俆俀倓俛偁傝丄崌寁偱掅堟偱偺揹埑棙摼偼俉侾倓俛偲側偭偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅晧壸偑俁侽侽兌偲戝偒偄偺偱戝偒側揹埑僎僀儞偲側偭偰偄傞傢偗偩丅
埵憡摿惈偐傜埵憡曗惓俠俆亖俆倫俥偺応崌偵崅堟偱弌椡揰偺埵憡夞揮偑亅侾俀侽亱偲側傞億僀儞僩偼俆俵俫倸偱偁傝丄偦偺億僀儞僩偱偺僆乕僾儞僎僀儞偑俀侽倓俛偱偁傝丄偙傟傛傝埵憡曗惓俠俆偑憹偊傞傎偳偵埵憡夞揮偑亅侾俀侽亱偲側傞廃攇悢億僀儞僩偼崅堟偵堏峴偡傞偲嫟偵偦偺億僀儞僩偵偍偗傞懳墳偡傞僆乕僾儞僎僀儞偼媡偵掅壓偡傞偙偲偐傜丄偙偺僔儈儏儗乕僔儑儞偑惓偟偄偲偡傟偽丄偙偺応崌俶俥俛傾儞僾偲偟偰僋儘乕僘僪僎僀儞俀侽倓俛埲忋偵愝掕偡傟偽埵憡曗惓俠俆亖俆倫俥偱埨掕摦嶌偡傞偙偲偑暘偐傞丅
変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾傕夵憿慜偼偙偺忬懺偱俁侽侽兌偺僿僢僪僼僅儞傪柭傜偟偰偄偨偑慡偔埨掕偱偁偭偨丅偦偺僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕偼俀俇倓俛偱偁偭偨偺偩偐傜傛傝埨慡曽岦側偺偱傑偀摉慠偩偭偨偺偩傠偆丅
偦傟偵偟偰傕棙摼偺尭悐僇乕僽偲埵憡偺夞揮僇乕僽傪尒傞偲俵俫倸椞堟傑偱帪掕悢乮億乕儖乯偼侾屄偟偐側偄偑擛偒偱偁傞丅懡暘悢侾侽倠俫倸偵偼廔抜僷儚乕俿倰俀俶俁侽俆俆偺倖俿桼棃偺媈帡億乕儖偑偁傞偼偢側偺偵壗屘偐徚偊偰偄傞丅偦偺俀俶俁侽俆俆偱俆俀倓俛傕偺揹埑僎僀儞傪妉摼偟偰偄傞偲偄偆偺偵偩丅晄巚媍側傕偺偩丅乮丱丱丟
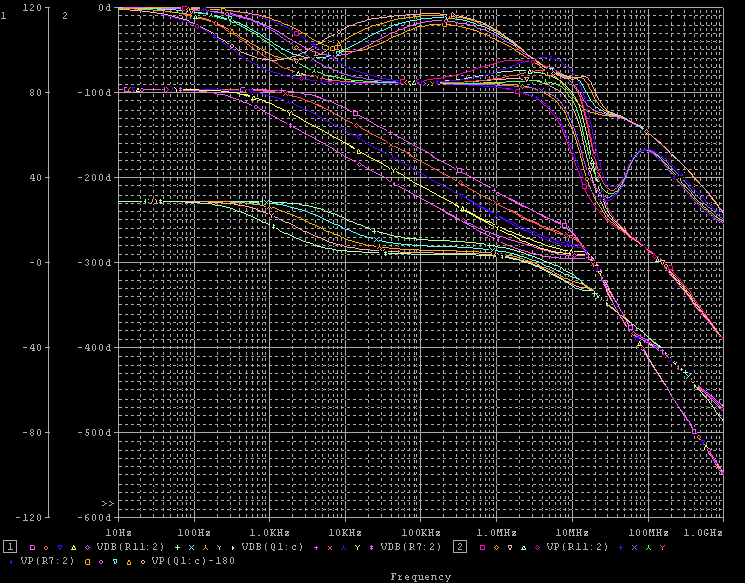
崱搙偼晧壸傪俉兌偲偟丄埵憡曗惓僐儞僨儞僒俠俆傪俆倫俥丄侾侽倫俥丄俀侽倫俥丄係侽倫俥丄俉侽倫俥偲偟偨僷儔儊僩儕僢僋夝愅丅
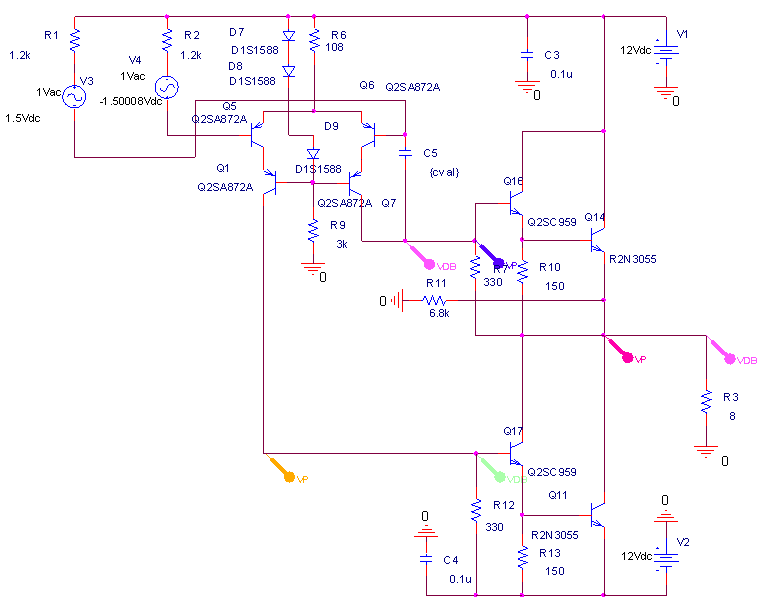
晧壸偑俉兌偲側偭偨偙偲偵敽偄丄俀抜栚嵎摦傾儞僾偺揹埑僎僀儞偼摨偠偔俀俋倓俛偩偑丄廔抜偺揹埑僎僀儞偑俀俈倓俛偵尭彮偟丄掅堟偱僩乕僞儖僆乕僾儞僎僀儞偼俆俇倓俛偲側偭偨丅
埵憡曗惓偺岠壥偼枅搙偍撻愼偩偑偦偺梕検偑戝偒偄傎偳偵埵憡揑偵埨掕曽岦偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕偑俀侽倓俛埲忋側傜偦偺抣偼俆倫俥偱廫暘偱偁傞丅
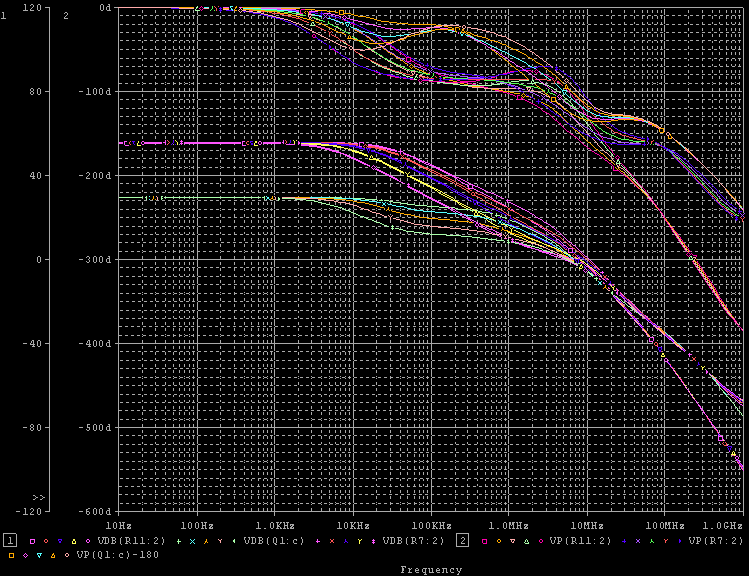
崱搙偼埵憡曗惓俠俇傪俆倫俥偵屌掕偟丄晧壸俼俁傪係兌丄俉兌丄侾俇兌丄俁俀兌丄俁侽侽兌偲偟偰弌椡偺揹埑棙摼偲偦偺埵憡傪娤傞丅
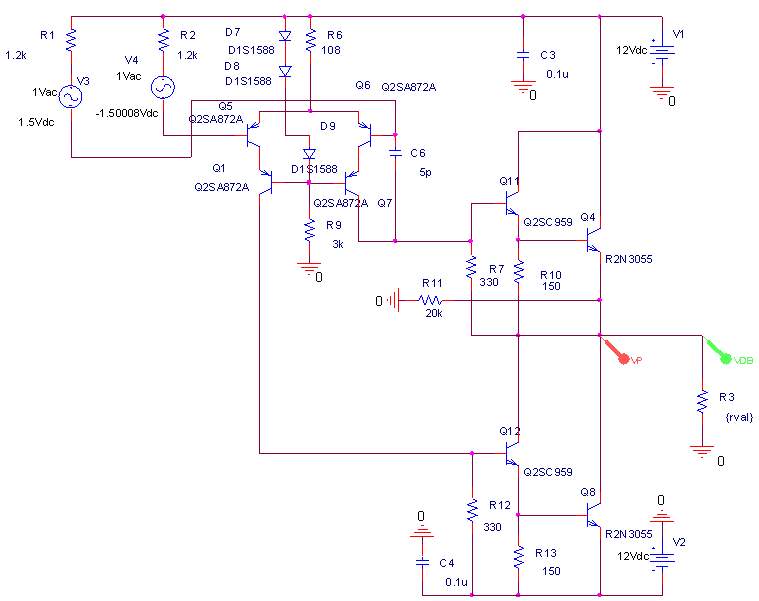
側偐側偐偵嫽枴怺偄丅
揹埑棙摼偑晧壸偵斾椺偟栺俇倓俛枅偵忋徃偡傞偺偼姰慡懳徧宆偑揹棳弌椡偱偁傞偐傜偩偑丄偦偺棙摼偺崅堟偵偍偗傞尭悐僇乕僽偼偐側傝崅堟傑偱暯峴忬懺偑懕偄偰偄傞丅傛偭偰偦偺倖們偑棙摼偵傛偭偰曄傢傜側偄偲偄偆僩儔儞僗僀儞僺乕僟儞僗揑怳傞晳偄側偺偩丅偙傟偼埵憡曗惓俠俇偺儚儞億乕儖偩偗偱側偣傞傢偞偲偼巚偊側偄丅壗偐暿偺梫慺傕嶌梡偟偰偄傞丅
偑丄偦偺帠忣偺偨傔晧壸偑戝偒偄傎偳偵僆乕僾儞僎僀儞偑俀侽倓俛偲側傞億僀儞僩偺廃攇悢偑崅堟偵堏峴偟偰偟傑偄丄偦傟偼埵憡曗惓揑偵偼晄埨掕梫慺偵側傞偼偢側偺偩偑丄偙偺応崌偼晧壸偺憹戝偑俁俆侽倠俫倸偐傜偺埵憡夞揮偺栠偟岠壥傪嶻傒丄寢壥埵憡揑埨掕偑妋曐偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅
偆傑乣偄丅乮丱丱乯
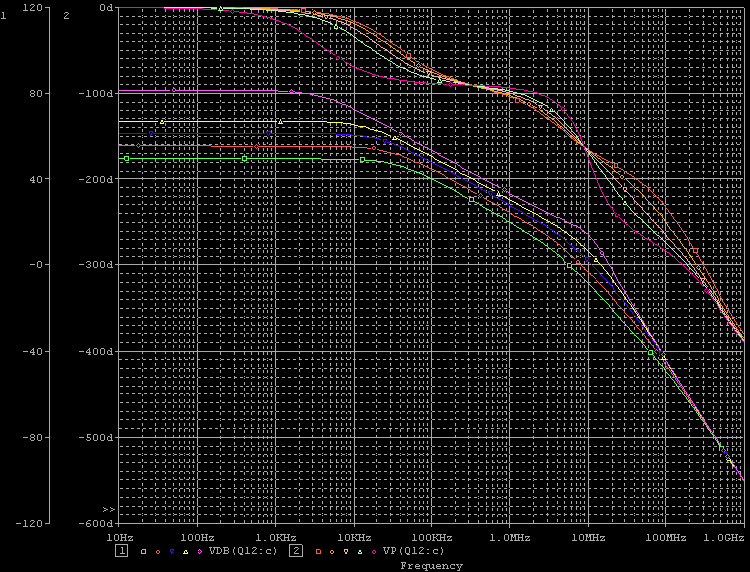
埲忋偑埵憡曗惓俠俇偩偗偱惗傒弌偝傟偰偄傞傕偺偱偼側偄偲偟偨傜壗偑娭學偟偰偄傞偺偐丠
傪峫偊傞偨傔偵丄偦偺埵憡曗惓俠俇傪庢傝奜偟埵憡曗惓岠壥偺側偄慺偺巔傪娤傞丅
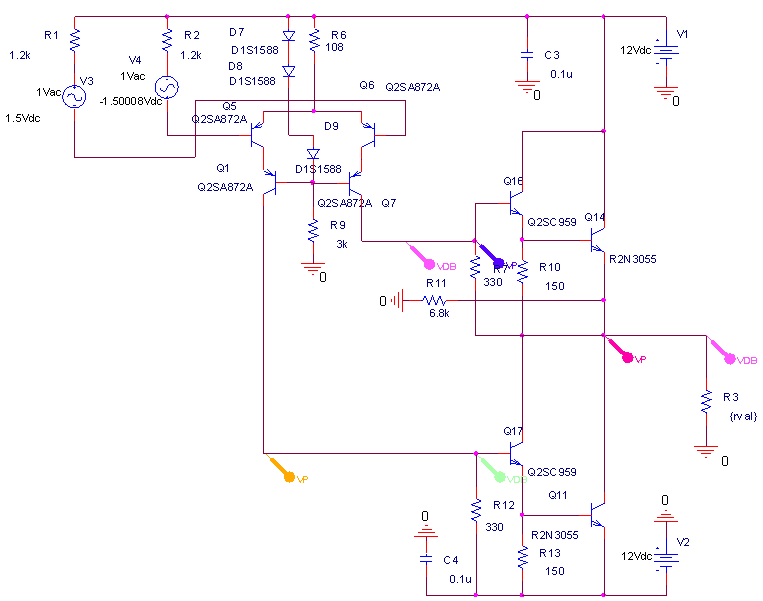
側傞傎偳丅
偦傕偦傕偺廔抜偑慺偱嶌傝弌偡揹埑棙摼偺巔偑倖們悢侾侽倠俫倸偺帪掕悢偱嶌傝弌偟偨棙摼摿惈偺擛偒巔側偺偩丅偙偺応崌捠忢偺帪掕悢偱嶌傝弌偟偨億乕儖偲偺堘偄偼僎僀儞偵傛偭偰傕倖們偵曄壔偑側偄偲偄偆偙偲偩丅偦傟偼侾侽倠俫倸戜偺埵憡嬋慄偵傕弌偰偄傞丅廃攇悢偵傛偭偰傕奺慄偑偁傑傝槰棧偟偰偄側偄丅
僺乕儞乮並並乯両偲棃傞偩傠偆丅偙偺巔傪嶌傝弌偟偰偄傞偺偼僩儔儞僕僗僞偺倖俿桼棃偺儀乕僞幷抐廃攇悢乮媈帡億乕儖乯偩丅偩偲偡傟偽俠偱宍惉偝傟傞億乕儖偲堘偭偰晧壸偺戝彫偱倖們偑曄壔偟側偄偺傕摉慠偩丅偙偺揰偼崟揷朸愭惗偑偙傟傪媈帡億乕儖偲尵偆柤偱捠忢偺億乕儖偲嬫暿偝傟偨強埲偺偲偙傠偩傠偆偐丅
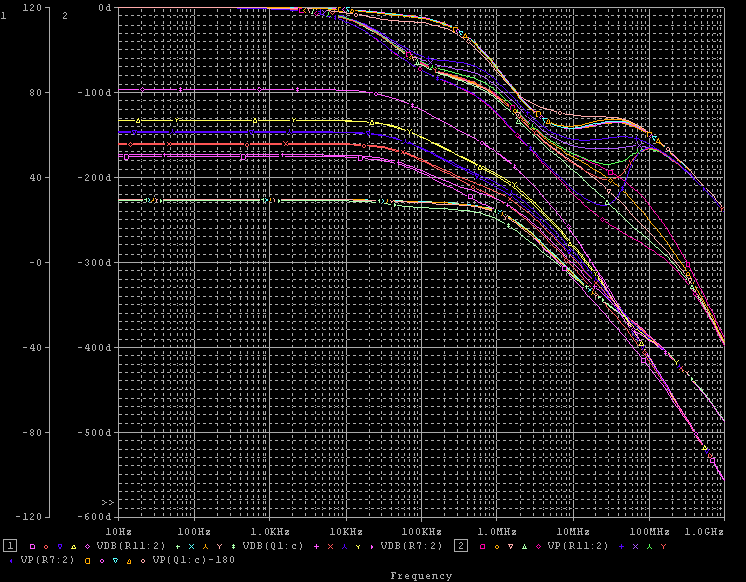
奺晹偺揹棳弌椡傪娤傞偙偲偵傛傝俀俶俁侽俆俆桼棃偺媈帡億乕儖偱偁傞偙偲傪妋擣偡傞丅
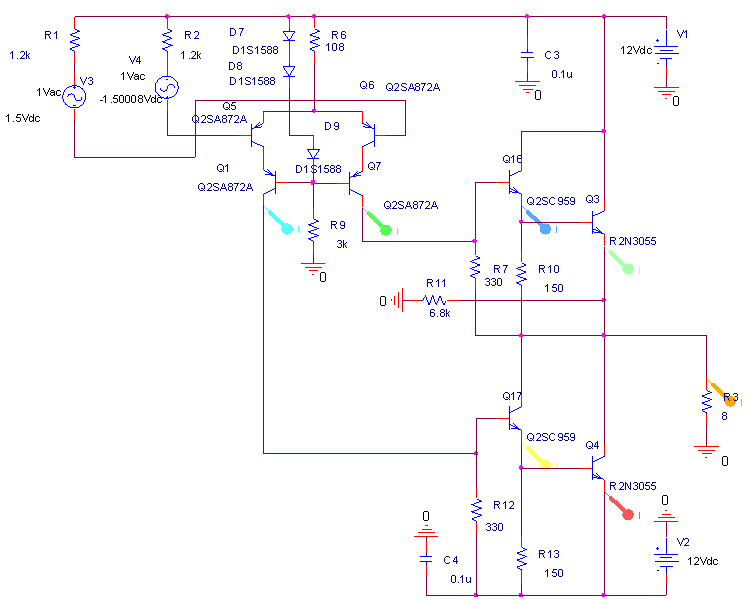
忋偐傜傾儞僾弌椡揰丄偦偺壓偵俀杮廳側偭偰廔抜俀俶俁侽俆俆偺僄儈僢僞弌椡揰丄偦偺壓偑摨偠偔俀杮廳側偭偰俀俽俠俋俆俋偺僄儈僢僞弌椡揰丄堦斣壓偑俀杮廳側偭偰俀抜栚嵎摦傾儞僾偺僐儗僋僞弌椡揰偺揹棳弌椡偺僌儔僼偱偁傞丅擖椡偑侾倁倎們偱偁傞偐傜廲幉偺傾儞儁傾悢抣偑偦偺傑傑偦偺揰傑偱偺倗倣抣偦偺傕偺偱偁傞丅
偱丄忋偐傜俀斣栚偺俀俶俁侽俆俆僄儈僢僞弌椡揰傑偱偺倗倣偺僇乕僽偼丄堦斣忋偺曽偱懠偺俿俼傗俵俷俽偲堦弿偵娤偨俀俶俁侽俆俆偺倗倣偺廃攇悢摿惈偦偺傕偺偩丅
偦偟偰丄偙傟偑倗倣亊晧壸掞峈抣偲偟偰忋偺埵憡曗惓傪庢傝嫀偭偨応崌偺揹埑棙摼摿惈傪宍嶌偭偰偄偨栿偱偁傞丅偩偐傜棙摼偑暯峴堏摦偡傞偺偼摉偨傝慜側偺偩丅
偝傜偵侾俵俫倸偐傜偼俀抜栚嵎摦傾儞僾偺俀俽俙俉俈俀媦傃僪儔僀僶乕偺俀俽俠俋俇侽偺儀乕僞幷抐廃攇悢乮媈帡億乕儖乯偺暘偑壛嶼偝傟偰棙摼尭悐偑媫偵側偭偰偄偔丅忋偺僌儔僼偱偦偺埵憡僇乕僽傪娤傟偽丄傑偢俀俶俁侽俆俆偺悢侾侽倠俫倸偺媈帡億乕儖偱亅俋侽亱傑偱夞揮偟丄俀抜栚嵎摦傾儞僾媦傃僪儔僀僶乕偺俀俽俠俋俆俋偺侾俵俫倸摉偨傝偺媈帡億乕儖偱侾俵俫倸晅嬤偐傜亅侾俉侽亱埲崀傊偲夞揮偟偰偄傞丅偙偺曈偺怳傞晳偄偼捠忢偺億乕儖偵摨偠偩偑丄偦偺棟桼偼丄崟揷朸愭惗偺乽婎慴俿倰愝寁朄乿偵乽俿倰撪晹偺僉儍儕傾偺拁愊偼備偭偔傝棫偪忋偑傞偺偱丄侾師抶傟梫慺傪惗傒丄偙傟偵傛傞俛亅俤娫偺乮媅帡揑側乯俠傪儀乕僗奼嶶梕検偲尵偄丄偙傟偲俫倝倕傪娷傓儀乕僗丒僄儈僢僞娫偺掞峈偲偱俴俹俥傪宍惉偡傞丅偙傟偵傛傞俫倖倕偺僇僢僩僆僼廃攇悢傪倖倐乮儀乕僞幷抐廃攇悢乯偲偄偄丄俫倖倕偑侾偵側傞廃攇悢傪倖俿乮僩儔儞僕僃儞僔儑儞廃攇悢偲偄偆丅掅廃攇椞堟偺俫倖倕傪兝o偲偡傞偲丄倖倐偑亅俁倓倐億僀儞僩偱丄埲屻亅俇倓倐偱尭悐偟丄倖俿偱俫倖倕偑侾偲側傝丄偙偺娭學偼丄倖倐亊兝o亖倖俿偲側傞丅乿偲愢柧偝傟偰偄傞傕偺偱偁傞丅
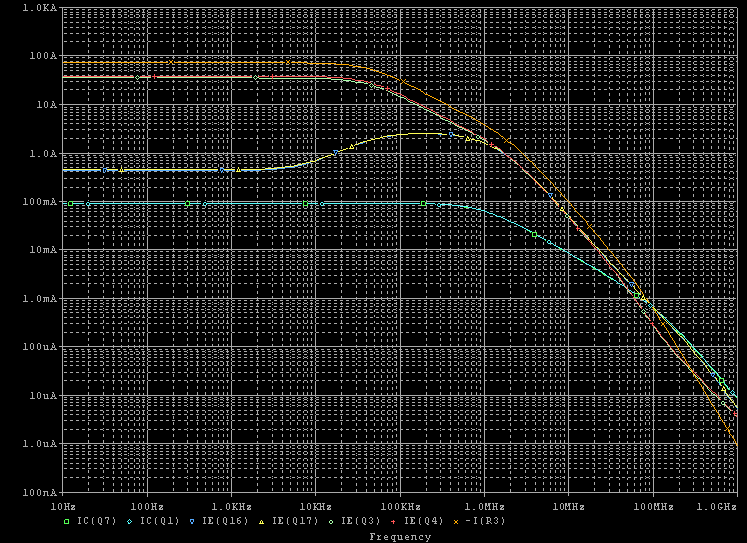
偙偺悢侾侽倠俫倸戜偲侾俵俫倸戜偵偁傞媈帡億乕儖傪偦偺傑傑巊偭偰偟傑偭偨偺偑丄変偑夵憿屻偺揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偲偄偆偙偲偵側傞丅
埵憡偑亅俋侽亱偐傜亅侾俉侽亱傊岦偐偄巒傔傞侾俵俫倸晅嬤偺埵憡夞揮傪弶抜偵擖傟偨僗僥僢僾宆埵憡曗惓偱堷偒栠偟偰壗偲偐側傜側偄偐丄偲峫偊偨栿偩丅
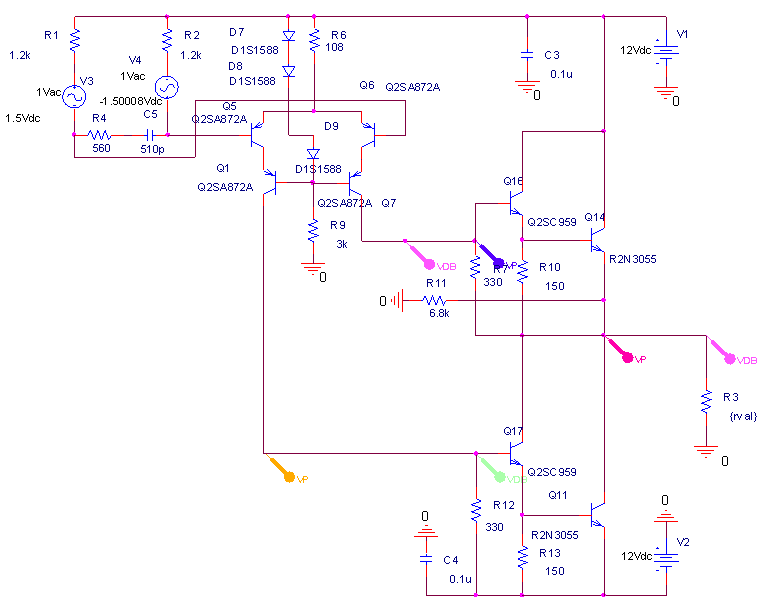
寢壥丄忋偺僗僥僢僾埵憡曗惓偑側偄応崌偲傪斾妑偡傞偲暘偐傞偲偍傝丄侾俵俫倸挻晅嬤偺埵憡夞揮偑旝柇偵栠偭偰丄僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕俀俇倓俛側傜埵憡揑偵戝忎晇偲偄偆忬嫷偵側傞丅乮丱丱乯
偑丄傛偔尒傞偲晧壸俁侽侽兌偱偼埵憡梋桾偑側偔側偭偰偄傞丅偑丄幚婡偼偙偺忬懺偱傕埨掕偱偁傞丅偙偺揰偼偝傜偵弌椡偵僷儔偵擖傟偰偁傞侾侽兌亄侽丏侾兪俥偑棙偄偰偄傞偺偩傠偆偐丅乮丱丱丟
偙偺寢壥丄変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偺僆乕僾儞僎僀儞棙摼摿惈偼乮偲偄偆偙偲偼俶俥俛検傕乯丄壓恾偺傛偆偵挻崅堟傑偱晧壸偵斾椺偡傞偲偄偆丄偁傑傝懠偵椺偺側偄柺敀偄傕偺偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偵側傞丅偑丄偦傟偑壒偵傕岲塭嬁傪梌偊傞偄傞偺偐斲偐偼丒丒丒丄傑偀暘偐傜傫丅乮丱丱丟乮敋乯
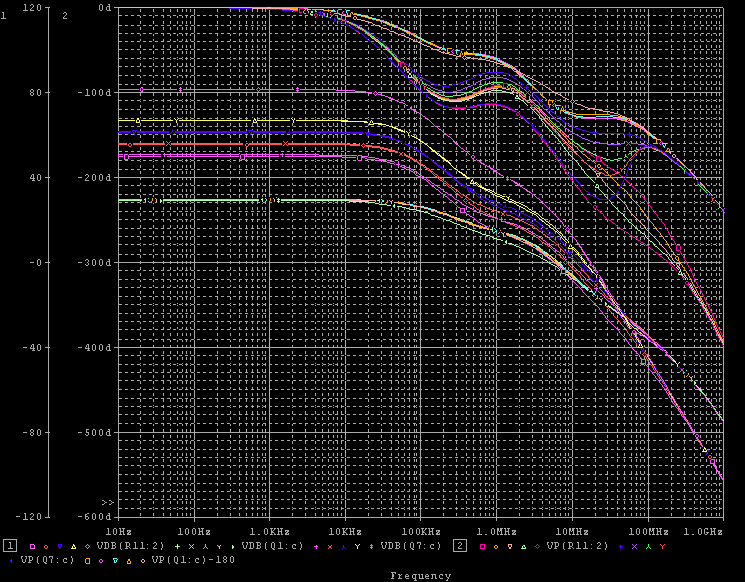
偝偰丄廔抜僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺儀乕僞幷抐廃攇悢偵傛傞媈帡億乕儖傪戞侾億乕儖偲偟偨変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偺幚婡偺僷儚乕僩儔儞僕僗僞偼俀俶俁侽俆俆偱偼側偔俀俽俢侾俉俉偱偁傞丅俀俽俢侾俉俉偺倖俿偼婯奿忋侾侽俵俫倸偱偁傞丅俀俶俁侽俆俆傛傝侾寘埲忋偲傑偱偼峴偐側偄偑偪傚偭偲崅偄偺偱偁傞丅
偙偺応崌倖俿偑崅偄偙偲偼幚偼婐偟偔側偄偺偩丅側偤側傜偦傟偼偙偺応崌埨掕摦嶌傪慾奞偡傞曽岦偱摥偔偐傜偱偁傞丅梫偡傞偵偦偺応崌戞侾億乕儖偲戞俀億乕儖偑嬤偔側偭偰俶俥俛傾儞僾偲偟偰偼晄埨掕忦審曽岦偺梫慺側偺偱偁傞丅
幚婡偼偄偨偭偰埨掕摦嶌傪偟偰偄傞偺偱栤戣側偄偺偩偑丄廔抜僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺倖俿偑崅偔側偭偨応崌偳偆側傞偺偐傪娤偰偍偔昁梫偑偁傞丅
愭偢偼俀俶俁侽俆俆偺僄儈僢僞偵侽丏侾兌傪擖傟偰偦偺揹棳婣娨儘乕僇儖俶俥俛岠壥偱儀乕僞幷抐廃攇悢傪崅傔偰傒傞丅
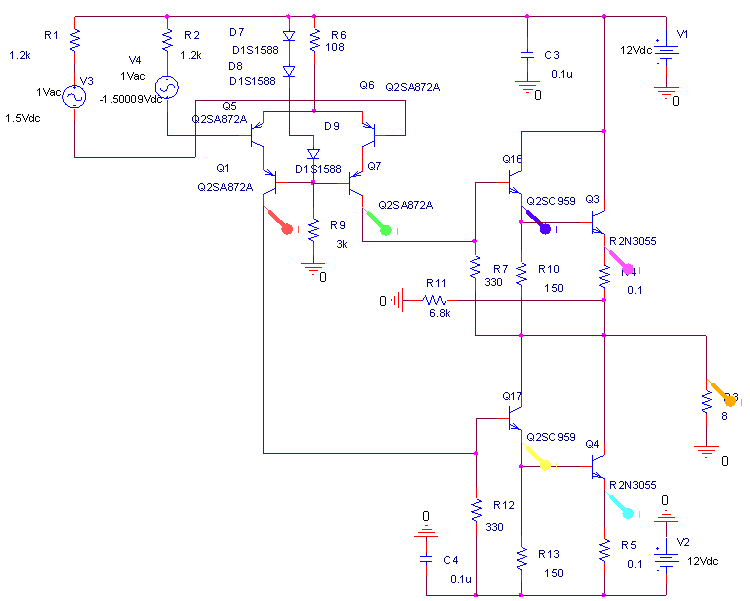
偁傑傝儀乕僞幷抐廃攇悢偑崅偔側偭偨姶偠偼側偄丅偑丄傛偔尒傞偲嬐偐偵崅堟偵怢傃偰偄傞偙偲偼妋偐偺傛偆偩丅偑丄傎傫偺嬐偐偩丅
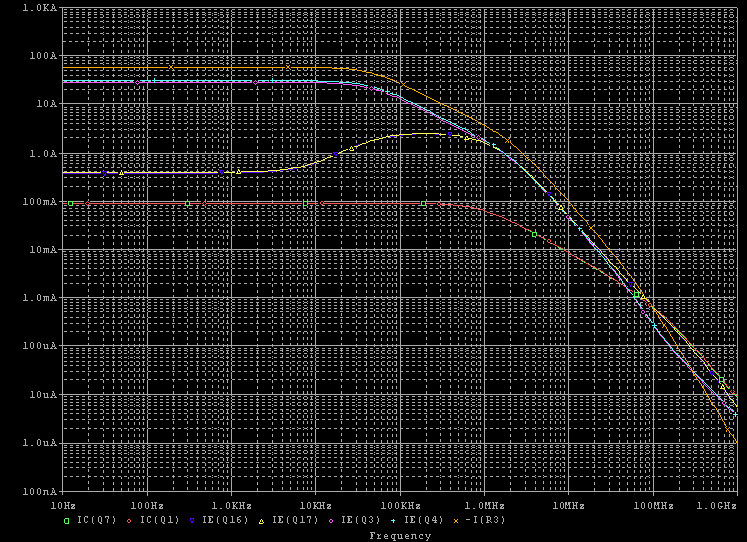
偙傟偩偲寢壥偵偁傑傝曄壔偼側偄傛偆側婥偑偡傞偑丒丒丒
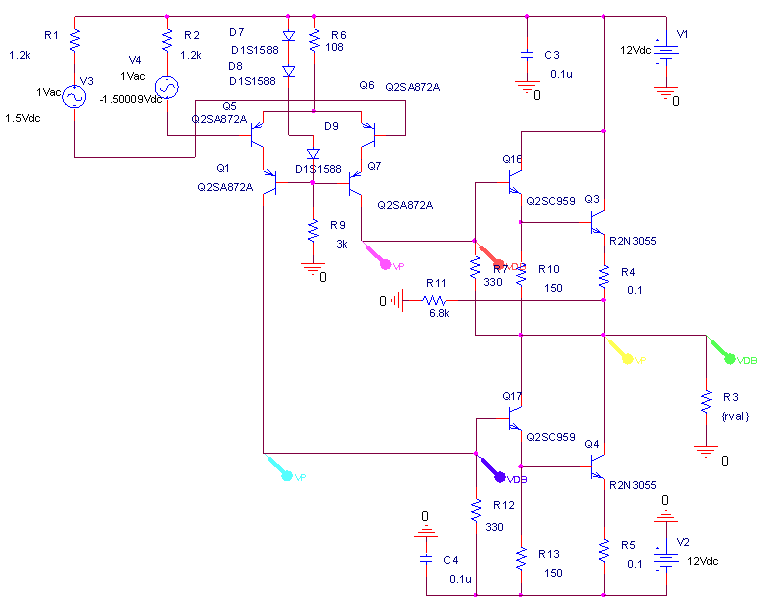
傗偼傝偁傑傝曄壔偼側偄丅
侽丏侾兌偱偼儀乕僞幷抐廃攇悢傾僢僾偺岠壥偼側偄偺偐丒丒丒丅堦斣忋偱偼侾寘傾僢僾偡傞偲偄偆寢壥偩偭偨偺偩偑丒丒丒乮丱丱丟
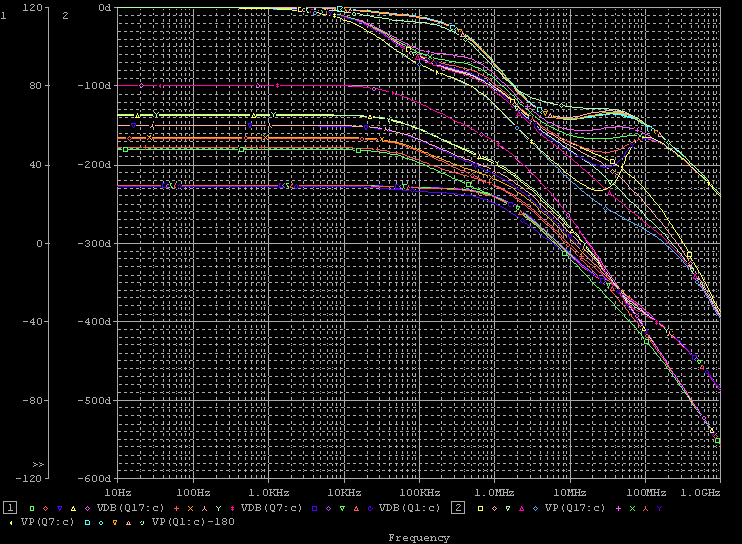
偑丄偦傟偼揹抮幃偲偄偆偙偲偱廔抜傾僀僪儕儞僌揹棳傪僔儈儏儗乕僔儑儞偱傕俁侽倣俙掱搙偵愝掕偟偨偨傔偩偭偨傛偆偩丅擮偺偨傔廔抜傾僀僪儕儞僌揹棳傪俁侽侽倣俙掱搙偵偟偰傒偨偲偙傠丒丒丒
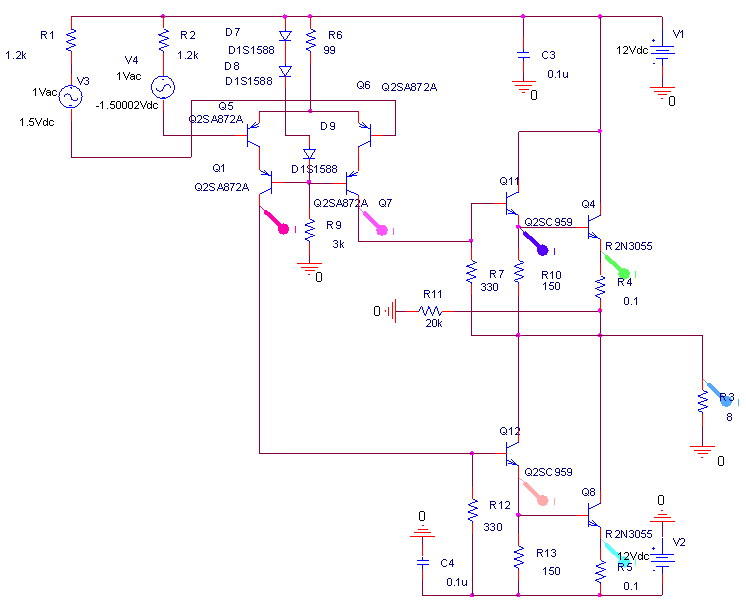
傗偼傝俀俶俁侽俆俆偺儀乕僞幷抐廃攇悢偼崅堟偵堏峴偟丄侾侽侽倠俫倸掱搙傑偱忋徃偟偰偄傞丅

偙偺忬懺偱晧壸係兌丄俉兌丄侾俇兌丄俁俀兌丄俁侽侽兌偱僷儔儊僩儕僢僋夝愅傪偟偰傒傞丅
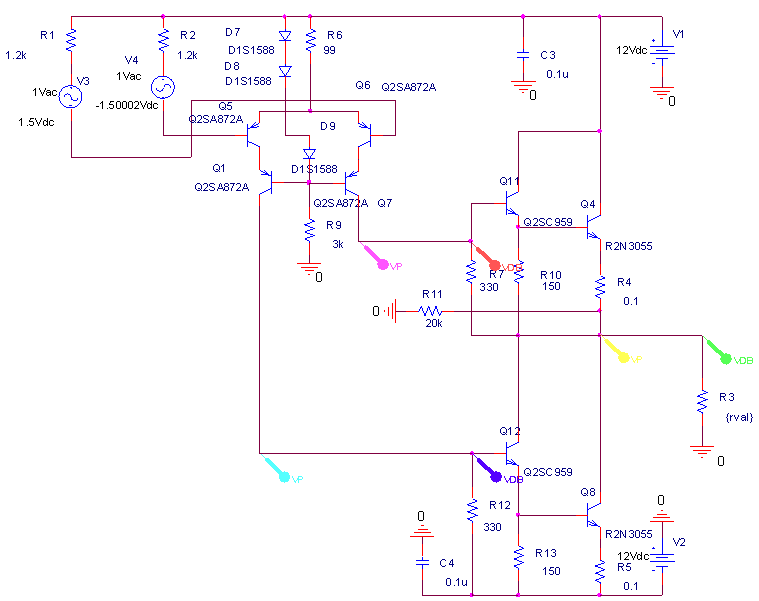
懯栚偩丅戞侾億乕儖偲戞俀億乕儖偑嬤偯偔偲埵憡偼媫寖偵亅侾俉侽偵岦偗偰夞揮偟偰偟傑偆丅偙偙偱偼俇侽侽倠俫倸晅嬤偱婛偵埵憡夞揮偑亅侾俀侽亱偵払偟偰偟傑偆丅偙傟偱偼僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺儀乕僞幷抐廃攇悢傪戞侾億乕儖偵偡傞偙偲偼崲擄偩丅
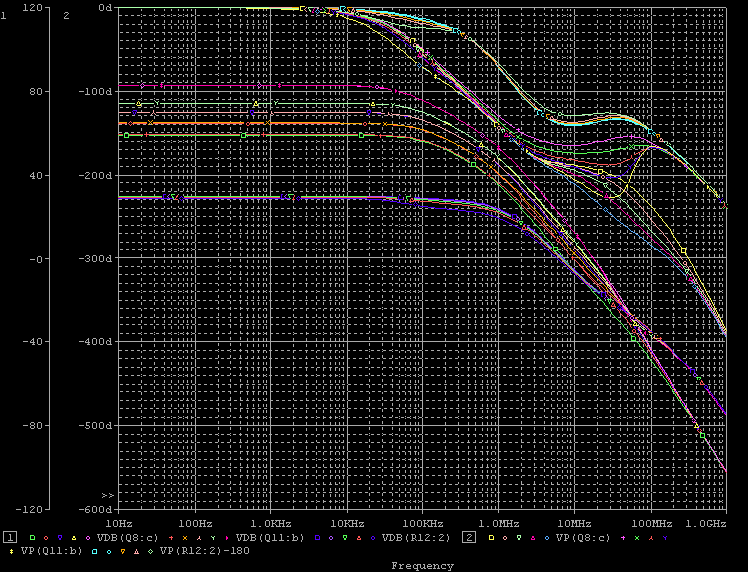
傗偼傝椺偺埵抲偱埵憡曗惓偡傞埲奜偵側偄偩傠偆丅偲偄偆傢偗偱俠侾亖俆倫俥丅
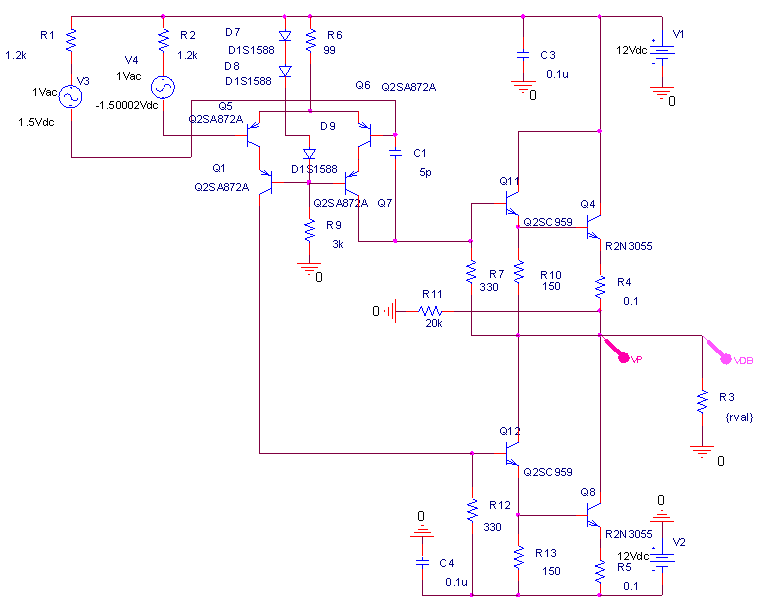
側偤偙偆側傞偺偐棟孅偼僀儅僀僠暘偐傜側偄偑丄庢傝偁偊偢埵憡曗惓俠偵傛傞億乕儖偲僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺儀乕僞幷抐廃攇悢偵傛傞億乕儖偑楢惎岠壥傪婲偙偟偨傛偆偵傂偲偮偵梟偗崬傒侾侽侽倠俫倸晅嬤偺儀乕僞幷抐廃攇悢偵傛傞億乕儖偑徚偊偨丅偺偱丄侾俵俫倸晅嬤偺戞俀億乕儖偱偝傜偵埵憡偑夞揮偟埵憡偑亅侾俀侽亱偵払偡傞慜偵儖乕僾僎僀儞偑侽倓俛埲壓偵側傞傛偆偵僋儘乕僘僪僎僀儞挷惍傪峴偊偽俶俥俛傾儞僾偲偟偰惉棫偡傞忬懺偵側偭偨丅
偦偺僋儘乕僘僪僎僀儞傪俶俥俛傾儞僾偲偟偰惉棫偡傞傛偆愝掕偡傞偲俁侽倓俛掱搙偐丅俶倧亅侾俁俋丄俶倧亅侾係係摍偺敿摫懱姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾戞侾悽戙偺僎僀儞愝掕俁俀倓俛偵偛偔嬤偄丅乮丱丱丟
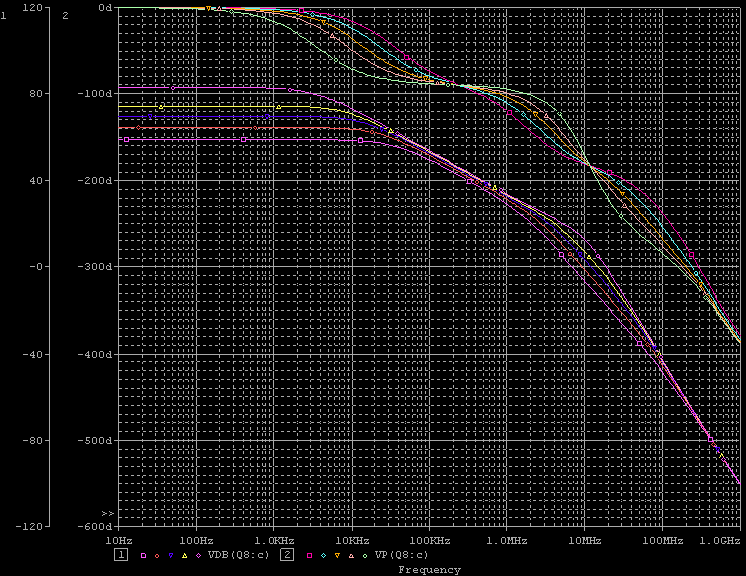
埲忋偐傜丄僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺儀乕僞幷抐廃攇悢傪戞侾億乕儖偲偟偨変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偼丄偳偆傕俀俽俢侾俉俉偲偄偆倖俿偺掅偄僩儔儞僕僗僞傪乮偦傟偱傕俀俶俁侽俆俆傛傝偼崅偄偑乯僄儈僢僞掞峈傕巊傢偢丄偟偐傕彮側偄傾僀僪儕儞僌揹棳偱摦嶌偝偣傞側偳丄摿庩側忦審偱偺傒惉棫偡傞傕偺偱偁傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偒偨丅
偙傟傪妋偐傔傞偨傔偵傕丄師偵倖俿偑俁俆俵俫倸偲崅偄俵俰俴係俀俉侾俙傪婲梡偟偰傒傛偆丅
戝懱暘偐偭偰偒偨偺偱丄俵俰俴係俀俉侾俙偵偼嵟弶偐傜侽丏侾兌偺僄儈僢僞掞峈傪擖傟丄傾僀僪儕儞僌揹棳傕俁侽侽倣俙掱搙偲偡傞丅
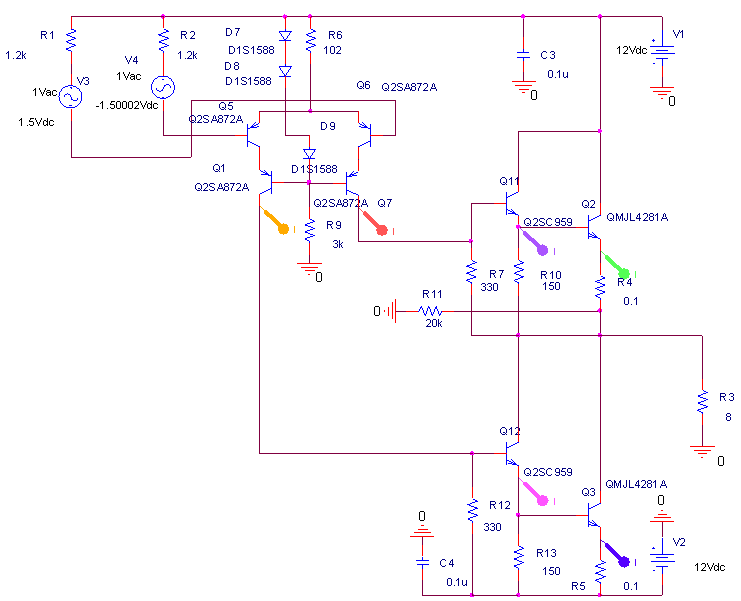
偝偡偑偵倖俿偑崅偄暘崅廃攇摿惈偑椙偄丅偦偺儀乕僞幷抐廃攇悢偼傗偼傝悢昐倠俫倸偲崅偄丅
偑丄偦傟偼婌偽偟偄偙偲偐丅偲偄偆偲偦偆扨弮偱偼側偄丅俀抜栚嵎摦傾儞僾偺俀俽俙俉俈俀丄廔抜僪儔僀僶乕偺俀俽俠俋俆俋丄偦偟偰俵俰俴係俀俉侾俙偺偦傟偧傟倖俿桼棃偺儀乕僞幷抐廃攇悢偵敽偆媈帡億乕儖偑侾俵俫倸廃曈偺嬤偄埵抲偵廤傑偭偰偟傑偆丅媈帡億乕儖偲偄偊偳傕億乕儖偱偁傞丅堦斒揑偵億乕儖偑嬤偄埵抲偵屌傑傞偺偼晄媑偺慜挍偩丅
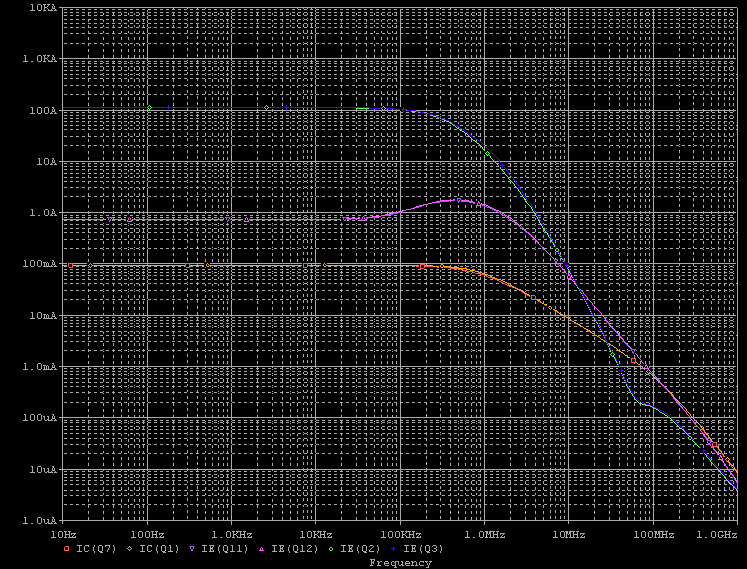
媑嫢偺傎偳傗偄偐偵丒丒丒
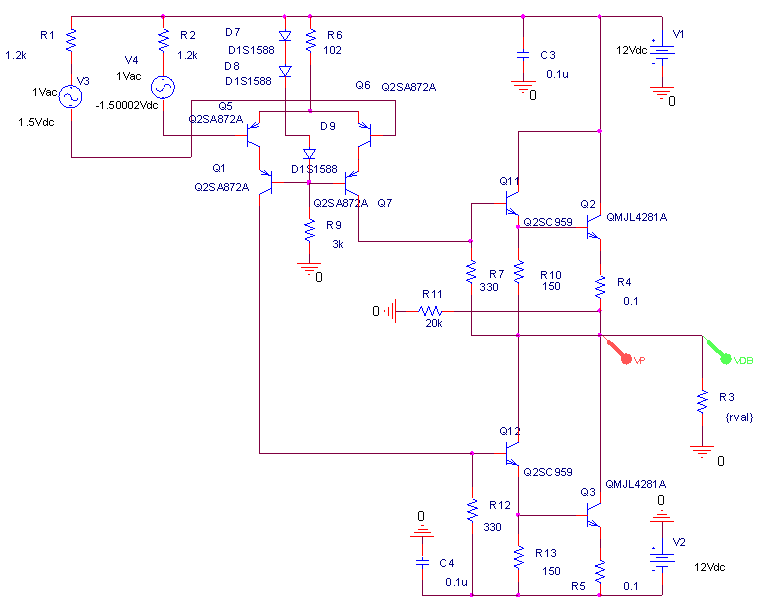
婋湝偟偨偲偍傝偩丅俵俫倸椞堟偱偺埵憡夞揮偑媫偩丅亅侾俉侽亱傕挻偊偰亅俀俈侽亱偵岦偐偭偰偄偔丅
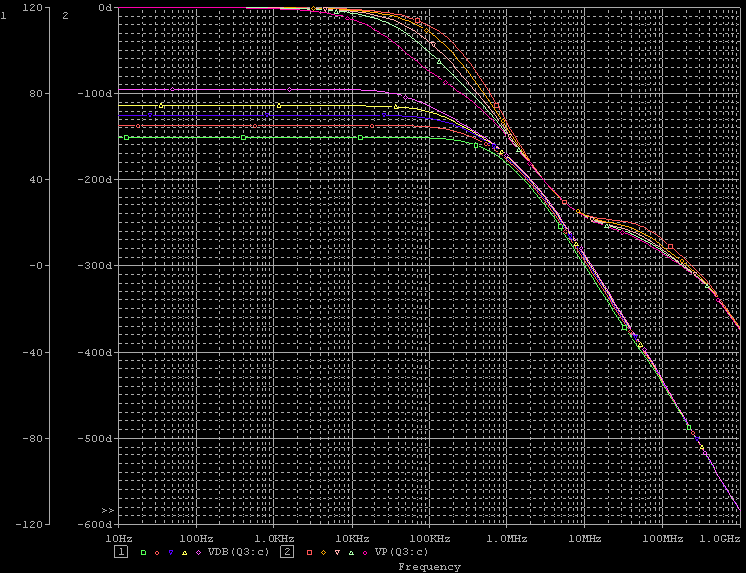
偙偆偄偆応崌偼丄椺偺埵抲偺埵憡曗惓偺嫮椡側擻椡偵婜懸偡傞偟偐側偄丅俆倫俥
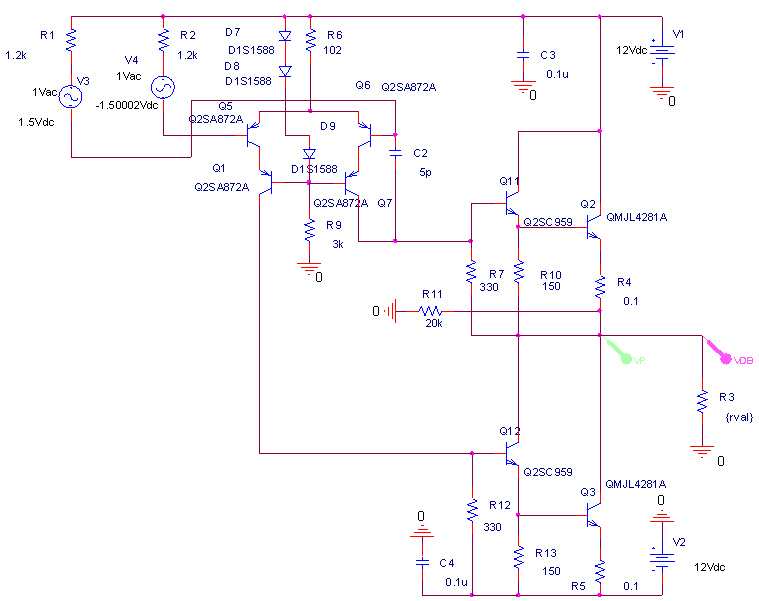
僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕俁侽倓俛側傜戝忎晇偩丅
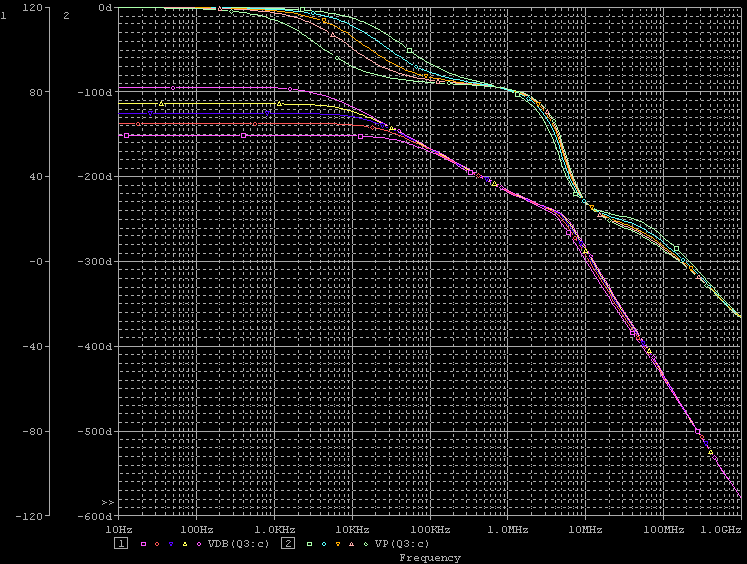
埵憡曗惓俠亖侾侽倫俥側傜僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕俀侽倓俛偱傕壜擻偩丅
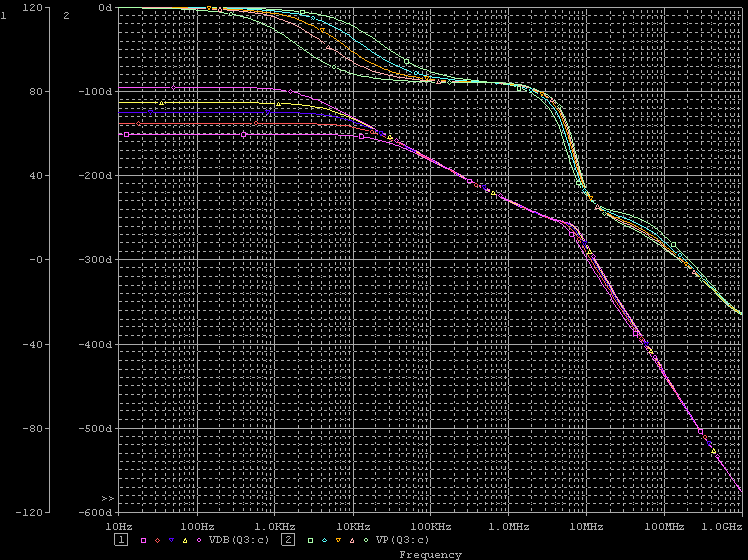
偑丄埵憡曗惓偱埨掕偼妋曐偱偒傞傕偺偺丄偦偺僆乕僾儞僎僀儞偺倖們偼忋偺偲偍傝俉兌晧壸偺応崌偱侾侽悢倠俫倸偲側傜偞傞傪摼側偄偺偱偁傞丅
愜妏僷儚乕僩儔儞僕僗僞偵倖俿偺崅偄崅堟摿惈偺桪傟傞傕偺傪婲梡偟偰傕偦偺桪傟偨崅堟摿惈傪惗偐偣側偄丅壓庤傪偡傞偲僷儚乕僩儔儞僕僔僞偵崅堟摿惈偺桪傟偨僩儔儞僕僗僞傪婲梡偟偨偑屘偵偐偊偭偰敪怳側偳偺僩儔僽儖傪彽偄偰偟傑偭偨傝偡傞偺偱偁傞丅傑偨丄偦偺夞旔偺偨傔偵埵憡曗惓偑媡偵戝偒偔側偭偨傝丄埵憡曗惓偺応強偑憹偊偨傝偲偄偆帠懺偵傕側偭偨傝偡傞栿側偺偩丅
変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾傪夵憿偟丄廔抜僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺儀乕僞幷抐廃攇悢傪戞侾億乕儖偲偡傞傕偺偵偟偨偦傕偦傕偺棟桼偼丄僆乕僾儞僎僀儞帪偺倖們傪崅傔偦偺堄枴偱峀懷堟側傾儞僾偺幚尰傪栚巜偟偨偺偩偭偨丅
偑丄埲忋偺夝愅偐傜偦傟偼傗偼傝尷傜傟偨忦審偱偺傒幚尰偡傞摿堎側働乕僗偱偟偐側偄偙偲偑柧傜偐偩丅
偱偼丄変偑夵憿屻偺揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偵戙傢傞傋偒斈梡惈偺偁傞峀懷堟僶僀億乕儔姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾傪峫偊傛偆丅
偦偺偨傔偺壽戣偲懳墳曽岦偼婛偵埲忋偺夝愅偐傜柧傜偐偱偁傞丅
梔偟偒僔儈儏儗乕僔儑儞僔儕乕僘俶倧亅係偵偍偄偰丄姰慡懳徧宆偺峀懷堟壔偺尷奅傪婯掕偟偰偄傞偺偼掅廃攇彫怣崋梡僩儔儞僕僗僞偺倖俿偱偁傞偲彂偄偨偑丄崱夞偺僔儈儏儗乕僔儑儞寢壥傕摨條偺寢榑傪昞偟偰偄傞丅奺晹偺揹棳弌椡偺僌儔僼傪尒傞偲柧傜偐側傛偆偵丄俀俽俙俉俈俀偱峔惉偡傞俀抜栚嵎摦傾儞僾偺揹棳弌椡傕廔抜僪儔僀僶乕偺俀俽俠俋俆俋偺揹棳弌椡傕儀乕僞幷抐廃攇悢偵傛偭偰侾俵俫倸晅嬤偐傜掅壓偟偰偟傑偄丄寢壥偙偺嬤曈偵億乕儖偑廳側偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅偙傟傜彫怣崋梡俿俼偺倖俿偼侾侽侽俵俫倸撪奜偩偐傜儀乕僞幷抐廃攇悢偑侾俵俫倸慜屻偵廳側傞偺偼崟揷朸愭惗偺夝愢偐傜偡傟偽摉慠側偺偩丅
偩偐傜丄偙偙偵僷儚乕僩儔儞僕僗僞傑偱倖俿偺崅偄崅堟摿惈偺桪傟偨傕偺傪帩偭偰偔傞偲丄侾俵俫倸晅嬤偵傕偆堦偮儀乕僞幷抐廃攇悢偵傛傞億乕儖偑廳側偭偰偟傑偆偙偲偵側傝丄忋庤偔峴偐側偄偺偱偁傞丅壓庤傪偡傟偽巚偄偑搆偵側偭偰敪怳偟偨傝偟偰偟傑偆栿偩丅
偩偐傜偙偺応崌偺惓偟偄夝寛嶔偼傂偲偮偩丅崅倖俿偺僷儚乕僩儔儞僕僗僞傪婲梡偟偦偺儀乕僞幷抐廃攇悢傪忋偘傞偺偵暪偣偰丄偦偺僪儔僀僶乕傗俀抜栚嵎摦傾儞僾偺儀乕僞幷抐廃攇悢傕偝傜偵崅堟偵忋偘傞偙偲偱偁傞丅丂丂偭偰丄偛偔摉偨傝慜偺偙偲偐乮丱丱丟
栤戣偼丄偦傟傪偳偆傗偭偰幚尰偡傞偐丄偱偁傞丅俀偮偺庤抜偑偁傞偩傠偆丅傂偲偮偼扨弮柧夣丄倖俿偺崅偄俿俼傪婲梡偡傞偙偲偱偁傞丅崱傂偲偮偼揹棳婣娨傪巊偆偙偲偩丅偨偩偟揹棳婣娨傪巊偆応崌偼僎僀儞偺掅壓傪妎屽偟側偗傟偽側傜側偄丅
偦偙偱愭偢偼廔抜偺僪儔僀僶乕偱偁傞丅偙偙偼夞楬峔惉忋揹棳婣娨傪偳偆偙偆偡傞偙偲偼崲擄偩丅傛偭偰倖俿偺崅偄僩儔儞僕僗僞偵岎姺偡傞埲奜偵曽朄偼側偄丅偺偱俀俽俠俋俆俋乮倖俿亜俆侽俵俫倸乯傪俀俽俢俈俆俇乮倖俿亖俁俆侽俵俫倸乯偵岎姺偟偰傒傛偆丅
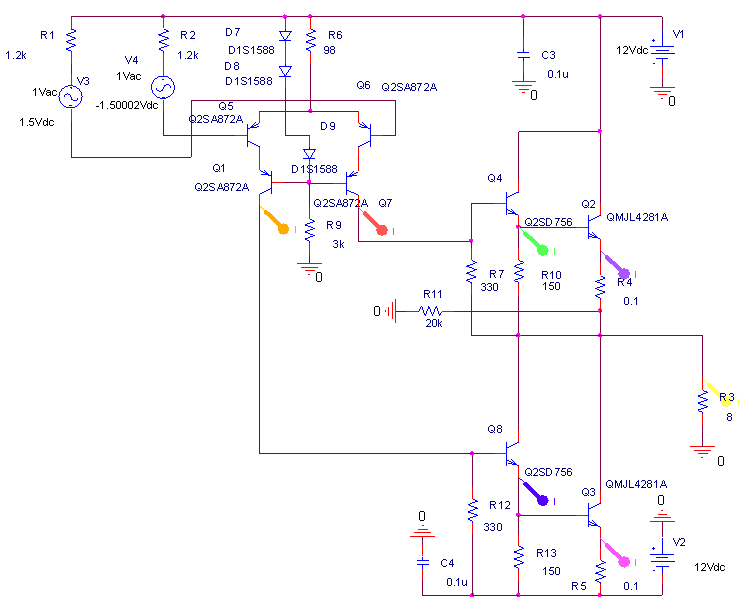
壓偐傜俀斣栚偑偦傟偩偑丄偁傑傝曄傢偭偰偄側偄傛偆偵尒偊傞丅偑丄椙偔斾妑偟偰娤傟偽妋偐偵崅堟偵怢傃偰偄傞偺偱偁傞丅侾俵俫倸晅嬤偐傜僇乕僽偑壓崀偟偰堦尒怢傃偰偄側偄傛偆偵尒偊傞偑偦傟偼堦斣壓偺俀抜栚揹棳弌椡偵捛悘偟偰偄傞偨傔偱丄偦偺俀偮偺僇乕僽偑暯峴傪曐偭偰偄傞偙偲偑俀俽俢俈俆俇偺儀乕僞幷抐廃攇悢偑崅堟偵怢傃偨偙偲傪昞偟偰偄傞偺偩丅偙偺僌儔僼偱敾抐偡傟偽偦傟偼侾侽俵俫倸挻偱偁傞偲巚傢傟傞丅
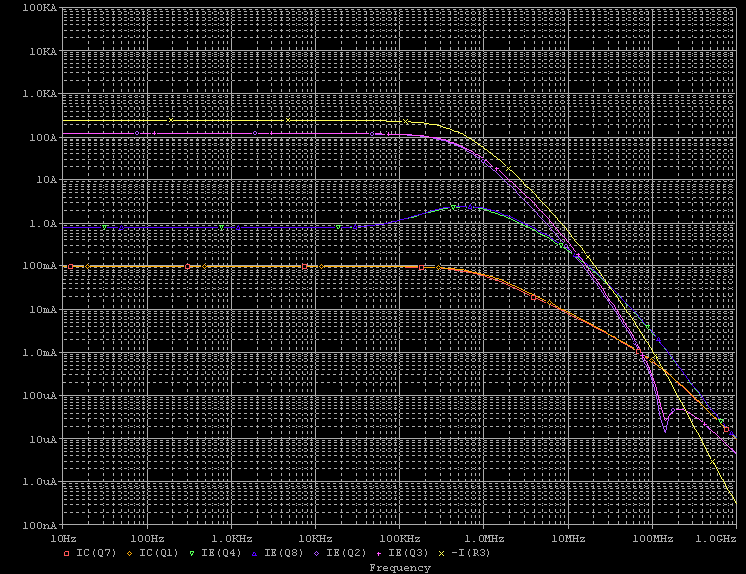
偙傟偱侾俵俫倸廃曈偺埵憡夞揮梫慺偑傂偲偮徚偊傞丅
偦偺岠壥傪娤偰傒傛偆丅
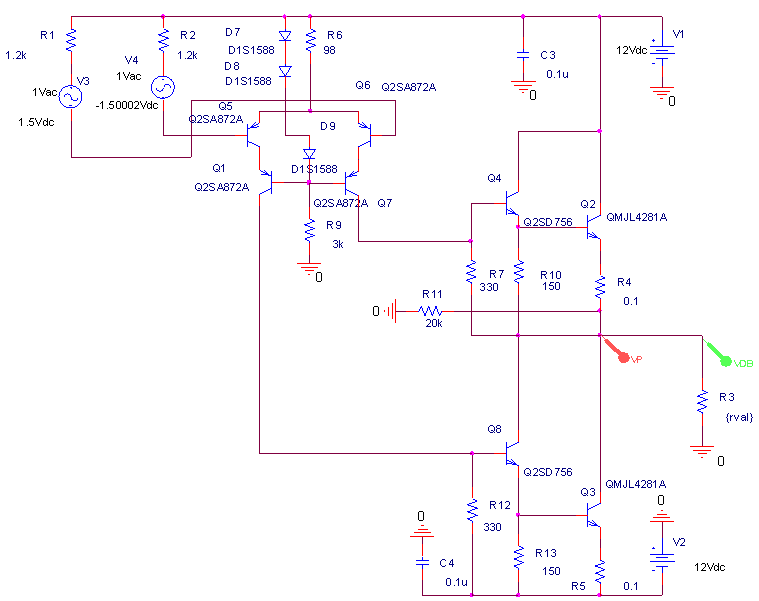
侾俵俫倸埲崀偺埵憡夞揮偑柧傜偐偵娚傗偐偵側偭偨丅俀俽俠俋俆俋偺応崌埵憡夞揮偑亅俀侽侽亱偵払偡傞廃攇悢偑俁俵俫倸偱偁偭偨傕偺偑俀俽俢俈俆俇偺偙偪傜偼俈俵俫倸偩丅
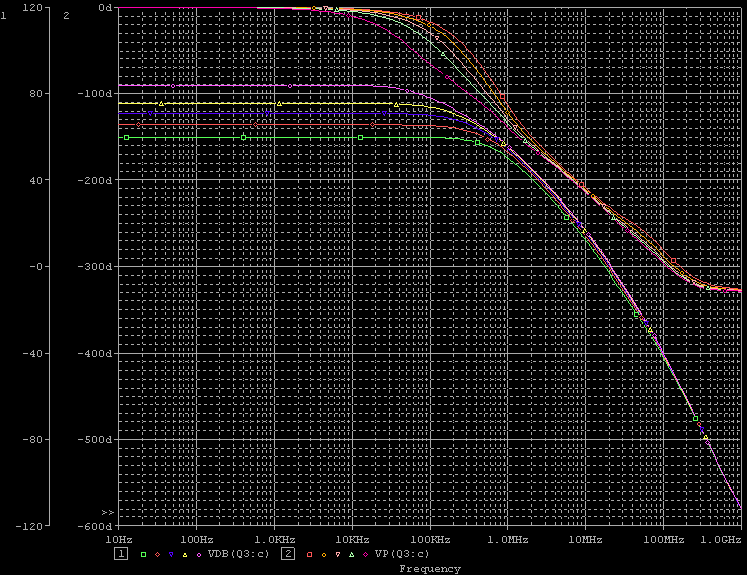
偙傟偩偗偱傕埵憡曗惓揑偵偼偐側傝妝偵側傞丅
椺偺埵抲偺俆倫俥丅
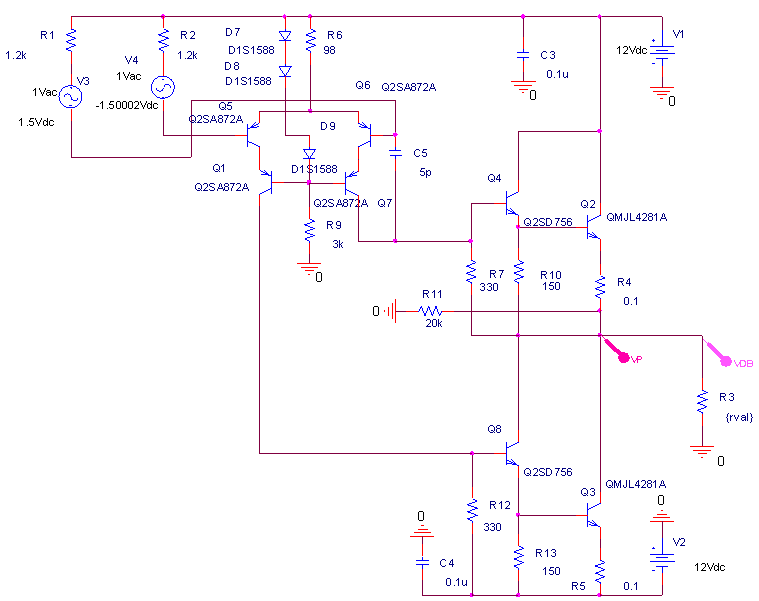
僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕俀係倓俛偱傕埨掕偩傠偆丅埵憡梋桾偑俇倓俛峀偑偭偨栿偩丅
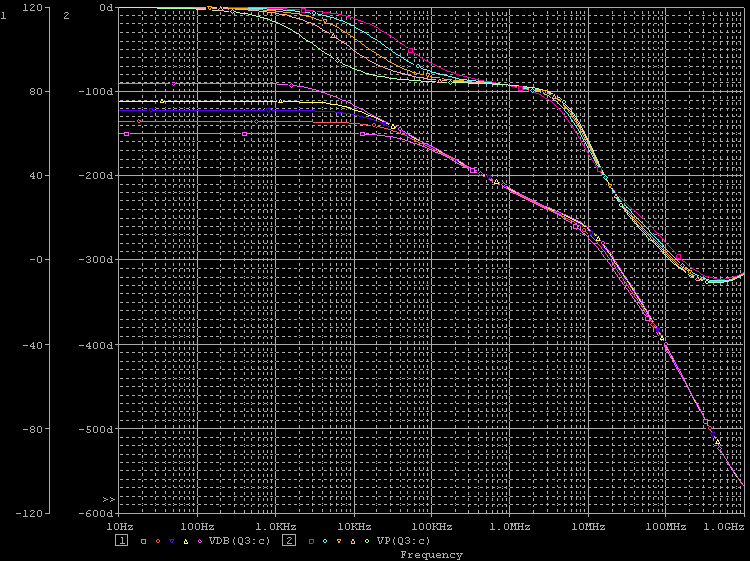
偑丄偙傟偱廫暘偱偼側偄丅杮娵偼俀抜栚嵎摦傾儞僾偺儀乕僞幷抐廃攇悢偩丅偙偺僔儈儏儗乕僔儑儞偱偼俀俽俙俉俈俀俙乮倖俿亖侾俀侽俵俫倸乯偱偁傞偑丄幚婡偼倖俿亜俆侽俵俫倸偺俀俽俙俇侽俇乮俇侽俈乯偩丅峀懷堟壔偺儃僩儖僱僢僋偼幚偼偙偙側偺偱偁傞丅
偙偙傕崅倖俿偺僩儔儞僕僗僞偵岎姺偡傞偲偄偆庤傕偁傞偑丄偙偙偱偼揹棳婣娨偱懳張偟偰傒傛偆丅
偭偰丄側偵傪塀偦偆乮丱丱丟丂幚偼丄怴悽戙偺姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偵偍偄偰俀抜栚嵎摦傾儞僾偑揹棳婣娨掞峈傪擖傟傞曽幃偵側偭偨杮幙揑棟桼偼偙傟側偺偱偁傞丅偦偺儀乕僞幷抐廃攇悢偵傛傞億乕儖乮峀懷堟壔偺儃僩儖僱僢僋乯傪崅堟偵捛偄傗傞偨傔側偺偩丅弌椡僀儞僺乕僟儞僗傪崅傔夁忚側僎僀儞傪梷惂偡傞偲偄偆偺偼晅悘揑側棟桼側偺偱偁傞丅傑丄尵偭偰傒傟偽堦愇嶰捁偱偁傞傢偗側偺偩偑丒丒丒乮丱丱丟
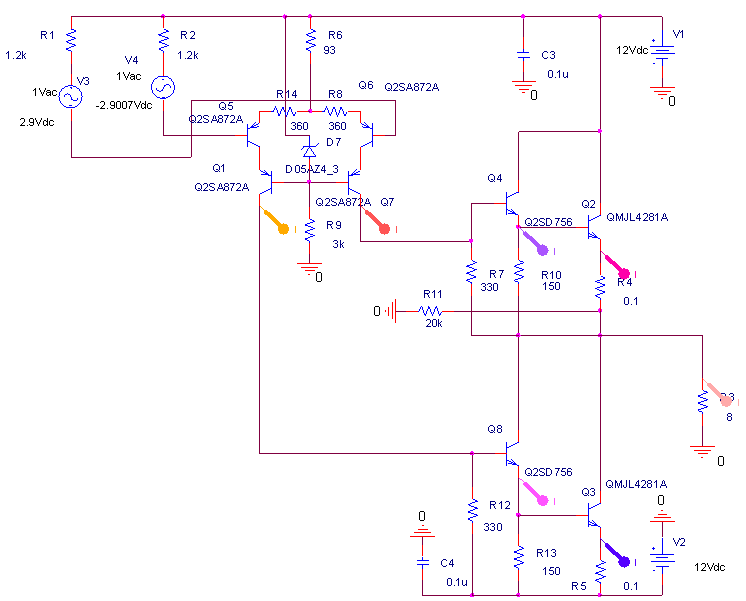
偙傟偱栚弌搙偔俀抜栚嵎摦傾儞僾偺儀乕僞幷抐廃攇悢傕侾侽俵俫倸掱搙偵怢傃傞丅偙偺僌儔僼偐傜俀俽俢俈俆俇偺曽傕偦傟偑偪傖傫偲侾侽俵俫倸掱搙偵怢傃偰偄偨偙偲偑柧傜偐偩傠偆丅
偙傟偱俀偮偺儀乕僞幷抐廃攇悢偵偲傕側偆億乕儖偼僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺儀乕僞幷抐廃攇悢偵傛傞億乕儖偲偼俀寘棧傟偨崅堟偵堏峴偟偨丅偙偺忬懺偼僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺儀乕僞幷抐廃攇悢偵傛傞億乕儖傪戞侾億乕儖偲偟偨変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偲摨條偱偁傞丅
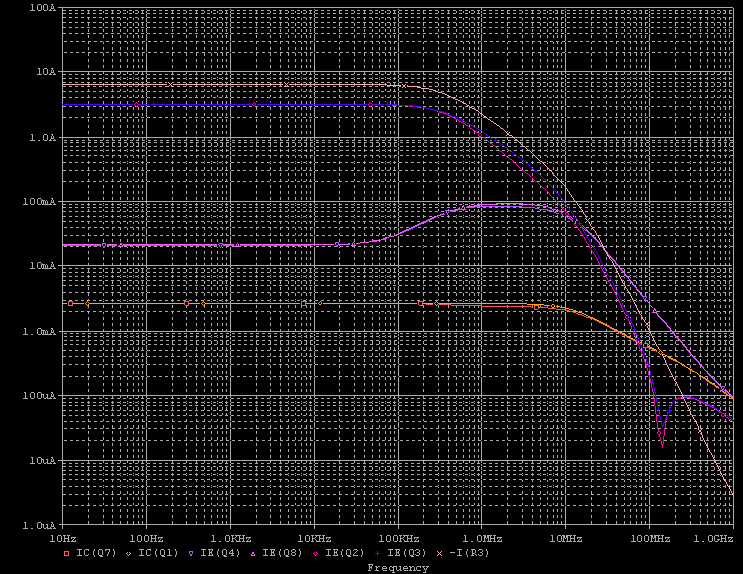
偱偁傟偽丄摨條側峔惉偑壜擻側偺偱偼側偄偐丅
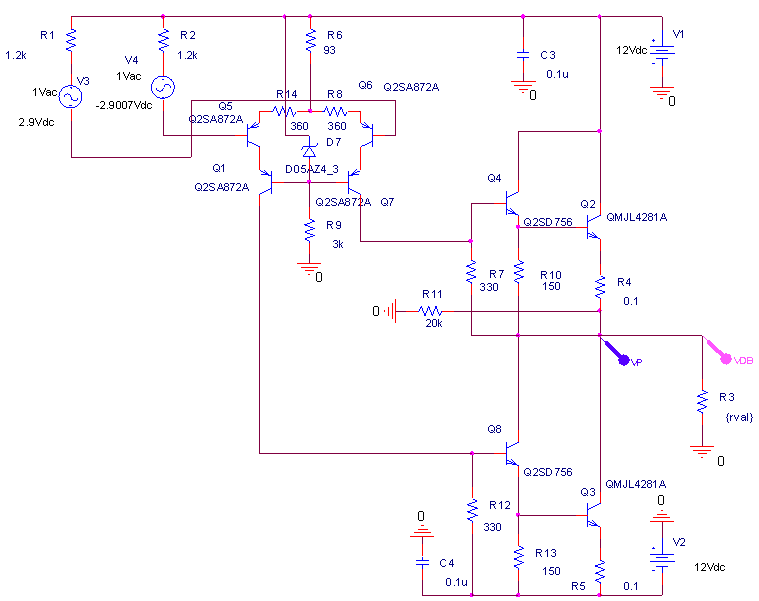
壜擻側偺偩丅乮丱丱乯
僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕侾俉倓俛埲忋側傜偙傟偱懠偺埵憡曗惓偺梫傕側偔埨掕偩丅
偟偐傕晧壸俉兌偱僆乕僾儞僎僀儞倖們佮係侽侽倠俫倸偱偁傞丅挻峀懷堟偩丅
偑丄栜榑俀抜栚揹棳婣娨偵傛偭偰偦偺倗倣偼侾乛俆侽掱搙乮佮仮俁俁倓俛乯偵尭偭偰偄傞丅偦傟偼偪傚偆偳俀抜栚嵎摦傾儞僾晹偺揹埑僎僀儞憡摉偱偁傝丄偦偺寢壥偑壓偺僌儔僼偱傕栺俁俁倓俛偺僆乕僾儞揹埑棙摼偺尭彮偲側偭偰尰傟偰偄傞丅
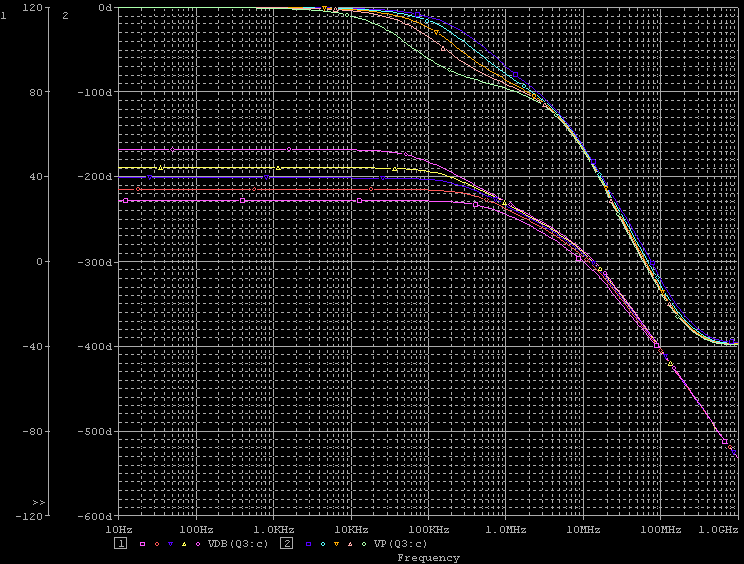
偦偺僎僀儞尭彮暘偼弶抜偱曗偆丅
俁侽倓俛埲忋偲偐側傝偺僎僀儞偑昁梫偱偁傞偐傜倗倣偺戝偒偄俀俽俲侾侾俈傪婲梡偡傞丅
柍棟偲偼巚偆偑丄夞楬峔惉丄夞楬掕悢傪宲彸偟偰庢傝偁偊偢偦偺晧壸傪侾丏俀倠兌偵偟偰傒傞丅
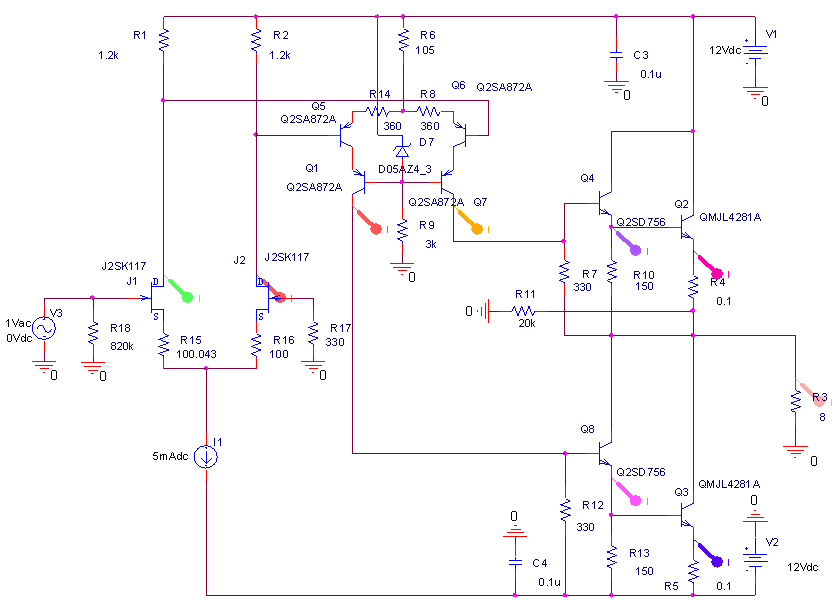
堦斣壓偑俀俽俲侾侾俈偺揹棳弌椡偱偁傞丅
偙偆偟偰傒傞偲俀俽俲侾侾俈偺倖俿傕偦偆崅偄傢偗偱偼側偄傛偆偩丅儀乕僞幷抐廃攇悢乮俥俤俿偺応崌壗偲偄偆偺偐抦傜側偄偺偱庢傝偁偊偢偙偆尵偆乯傾僢僾傪廳帇偟偰僜乕僗掞峈傪侾侽侽兌偲偟偨偺偩偑丄侾侽俵俫倸偵偼払偟側偄傛偆偩丅侾侽侽俵俫倸偖傜偄梸偟偄偲偙傠偩偭偨偺偩偑丄傑偀丄偟傚偆偑側偄丅
僎僀儞揑偵偼偙傟偱侾侽倓俛掱搙偩傠偆偐丅偁偲俀侽倓俛偼梸偟偄丅
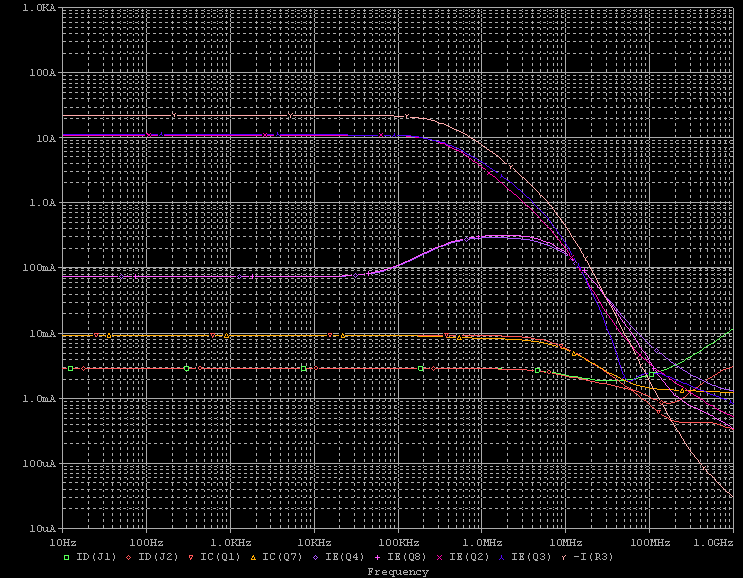
偲側傞偲丄傗偼傝揹尮揹埑傪忋偘偰丄弶抜偺晧壸掞峈傪戝偒偔偡傞埲奜偵側偄丅
俲愭惗偺嵟嬤偺嶌椺偺傛偆偵偝傜側傞僴僀僆乕僾儞僎僀儞傪栚巜偡偲側傞偲傕偆彮偟崅揹埑偲崅掞峈偑昁梫偩偑丄崱偺変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偲摨掱搙偺僎僀儞偲偄偆偙偲偱偁傟偽偙偺掱搙偱椙偄傛偆偩丅
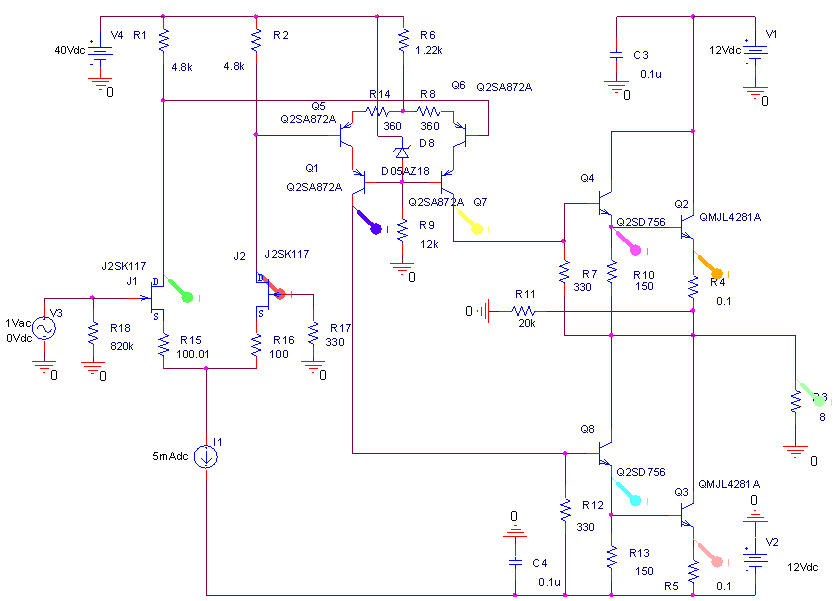
僎僀儞偼偙偺掱搙偱椙偄傛偆偩丅
偑丄弶抜偺僎僀儞傾僢僾偵敽偭偰偦偺儀乕僞幷抐廃攇悢傕柧妋偵壓偑偭偰偟傑偆丅巆擮偩偑偟傚偆偑側偄丅
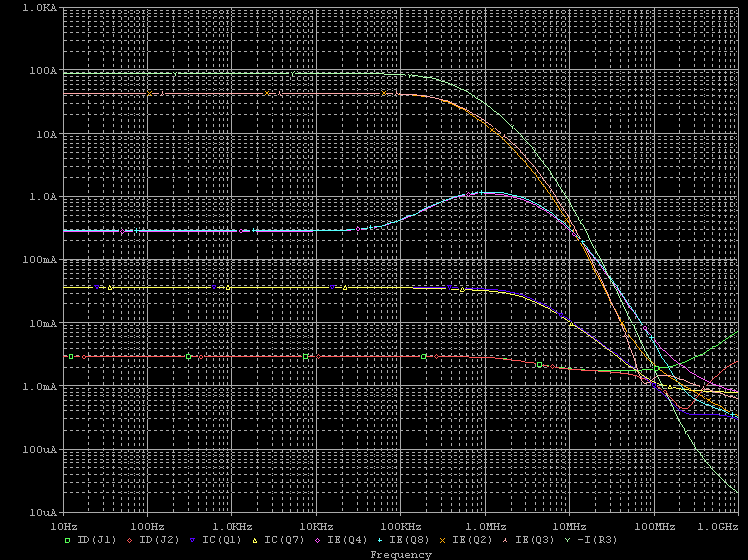
偙傟偱僆乕僾儞僎僀儞偺揹埑棙摼偲偦偺埵憡摿惈偼偳偆偐丅
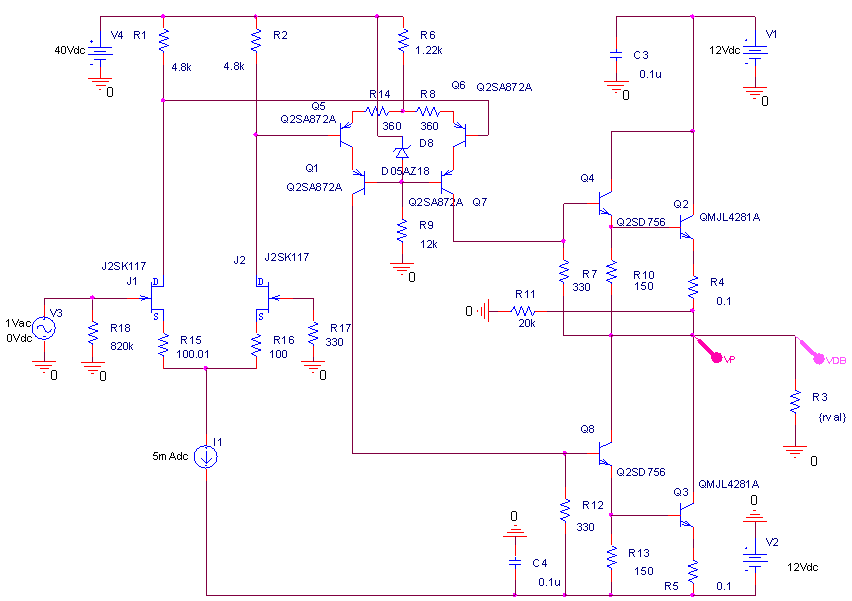
僎僀儞傕廫暘偩偟丄懷堟傕峀偄丅偦偟偰偦偺埵憡夞揮傕娚傗偐偱慺捈偩丅
傑偀傑偀偺弌棃偱偼側偐傠偆偐丅
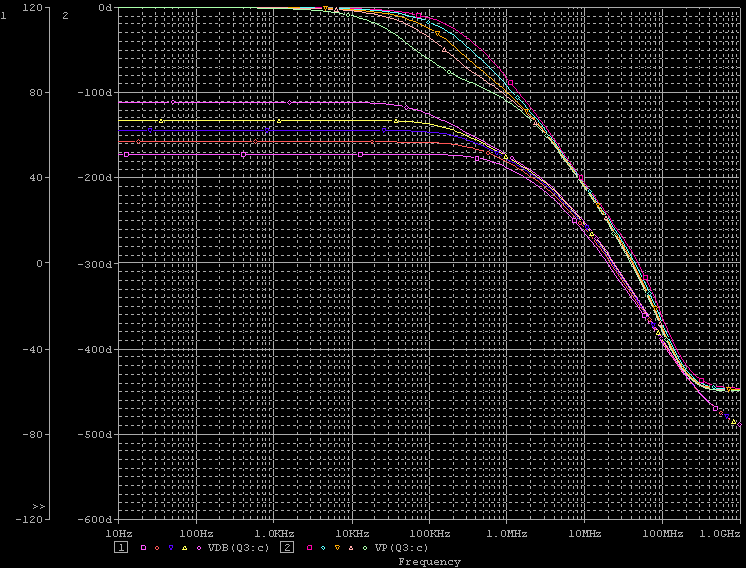
偙傟偱椺偺埵抲傊偺埵憡曗惓侾侽倫
側傫偩丅懡偄偠傖側偄偐丅偲巚偊傞偐傕偟傟側偄偑丄俀抜栚嵎摦傾儞僾偺揹埑僎僀儞暘偺儈儔乕岠壥偑尭彮偟偰偄傞偺偱丄僄儈僢僞揹棳婣娨婣娨掞峈傪擖傟傞慜偵斾傋傞偲幚幙揑偵偼媡偵彮側偄偺偱偁傞丅
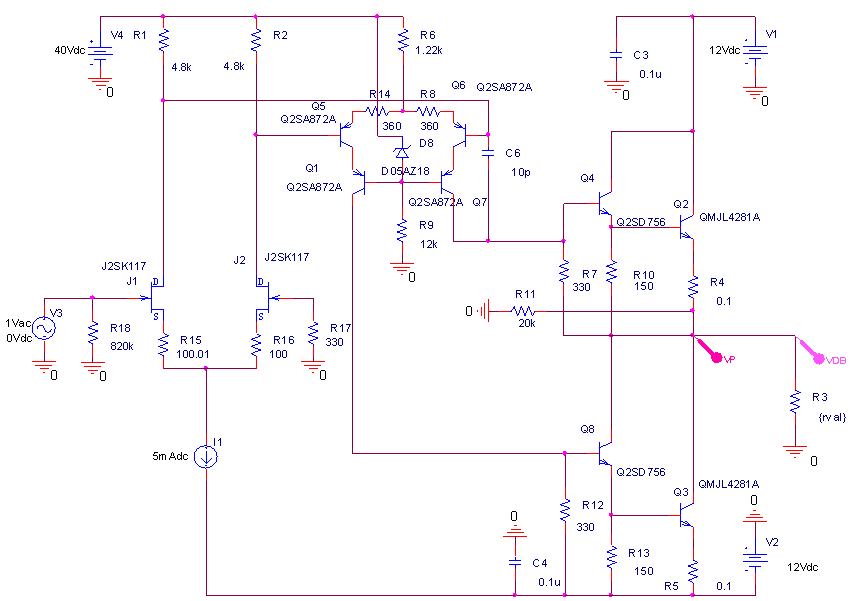
偙傟偱僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕俀俉倓俛埲忋偱埨掕偱偁傞丅栤戣偺僆乕僾儞僎僀儞倖們偼俉兌晧壸偱俉侽乣俋侽倠俫倸偩丅
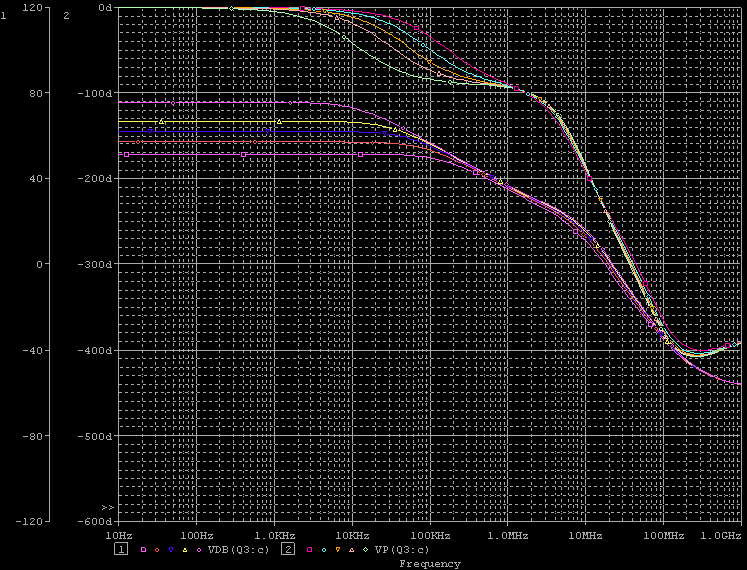
弶抜偱偺僗僥僢僾宆埵憡曗惓傕桳岠偩丅
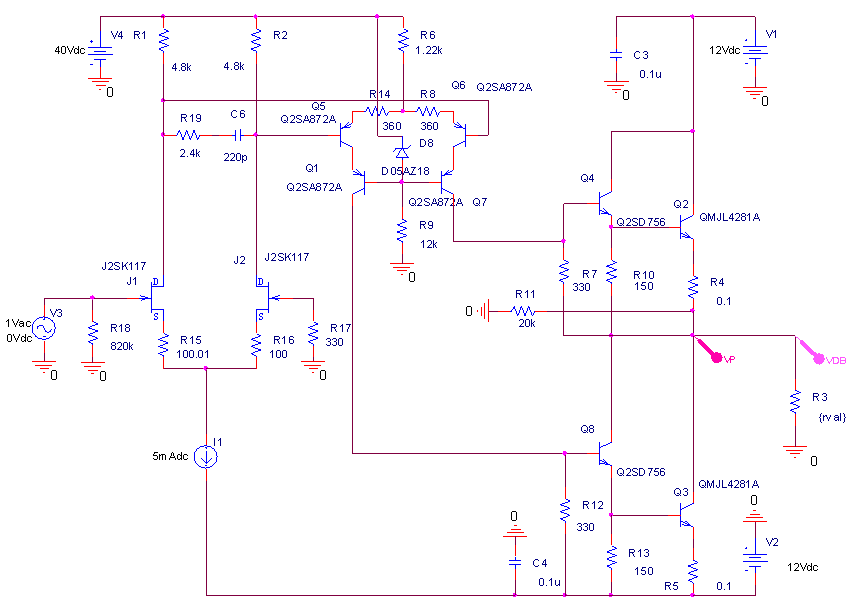
偙偺応崌傕僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕俀俉倓俛埲忋偱埨掕偩丅偨偩偟俉兌帪偺倖們偼俇侽倠俫倸掱搙偩傠偆偐丅
偪側傒偵丄偙傟偼廔抜俀俶俁侽俆俆偺儀乕僞幷抐廃攇悢桼棃偺媈帡億乕儖傪戞侾億乕儖偵偟偨変偑揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偲摨偠惉傝棫偪丅偲偄偆偙偲偵側傞丅
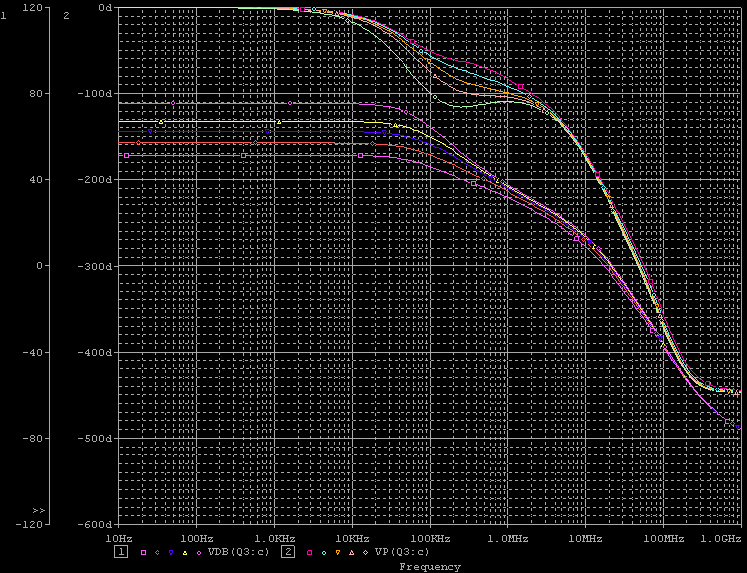
僋儘乕僘僪僎僀儞俀侽倓俛愝掕偼弌棃側偄偺偐丅怴悽戙偺敿摫懱姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偺僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕偼俀侽倓俛掱搙偩丅
偲偄偆梫朷偑偁傞応崌偼丄俶倧亅侾俈係傗侾俈俇偲摨條偵乮俀俽俙俇侽俇偺俠倧倐偑埵憡曗惓俠偲側偭偰偄傞乯偙傟傜偺埵憡曗惓傪暪梡偡傟偽椙偄丅
晧壸係兌丄俉兌丄侾俇兌丄俁俀兌丄俁侽侽兌偺僷儔儊僩儕僢僋夝愅丅
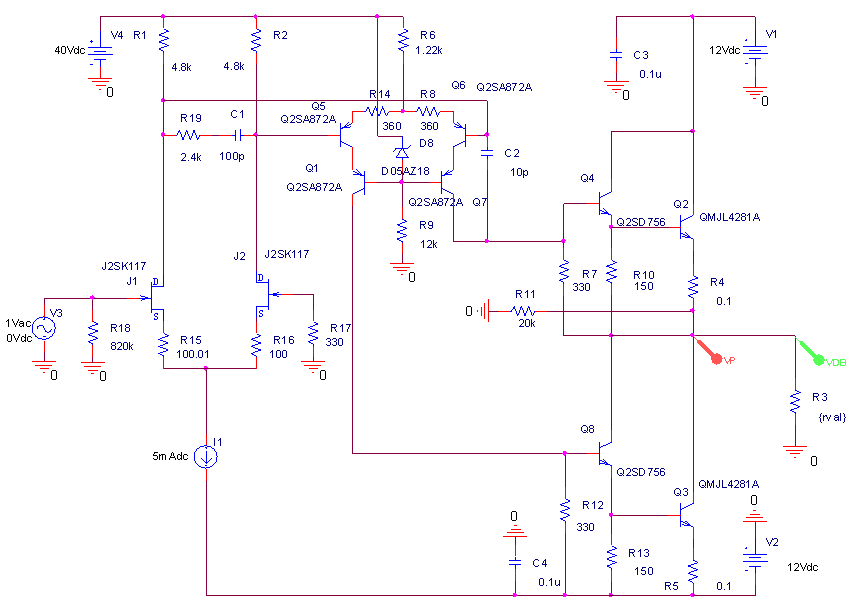
俉兌帪偺倖們偑俆侽乣俇侽倠俫倸偵壓偑偭偰偼偟傑偆傕偺偺偙傟側傜僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕俀侽倓俛偱埨掕偱偁傞丅
偙傟偱斈梡惈偺偁傞峀懷堟揹抮幃姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偑弌棃偦偆偱偁傞丅乮丱丱乯
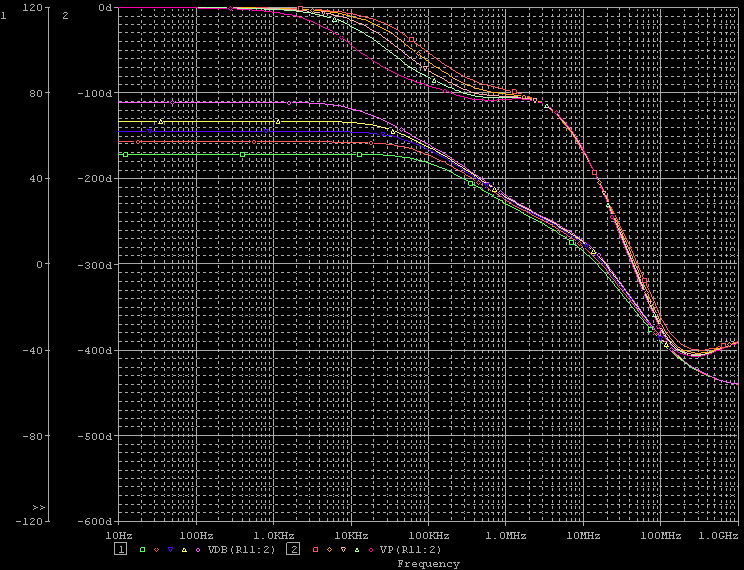
怴悽戙偺敿摫懱姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偑搊応偟偨偺偼丄侾俋俋俋擭俇寧崋偺俶倧亅侾俆俆偩偭偨丅偦偺僆乕僾儞僎僀儞帪倖們偼丄僋儘乕僘僪僎僀儞愝掕俁俀倓俛偱偁傞偲偼尵偊丄俉兌晧壸帪偱侾侽侽倠俫倸偲嬃堎揑偱偁偭偨丅
俶倧亅侾俆俆偵偍偄偰俲愭惗偼乬怴峔憐偵傛傞杮婡偺夞楬乭偲偟偰偙偆弎傋傜傟偰偄傞丅乽丒丒丒僎僀儞傪弶抜偵廤拞偟丄俀抜栚傪嬌傔偰娙寜側峔惉偵偟偰偄傞偺偩丅傾儞僾偺俶俥俛偵懳偡傞埨掕搙偼僇僢僩僆僼廃攇悢傪寛掕偡傞帪掕悢偺悢偲偦偺暘晍偵傛偭偰寛傑傞丅帪掕悢偑彮側偄傎偳丄傑偨帪掕悢偑暘嶶偟偰偄傞傎偳俶俥俛偼埨掕偩丅乿偲丅
偁傟偐傜俆擭丅偦偺堄枴偑儀乕僞幷抐廃攇悢桼棃偺乮媈帡乯億乕儖偺崅堟傊偺暘嶶偱偁傝丄俀抜栚傪嬌傔偰娙寜側峔惉偵偟偨偺傕偦傟偑棟桼偱偁偭偨偙偲傪崱擔偺崱擔偵偟偰傛偆傗偔棟夝偟偨偺偩偭偨丅乮丱丱丟丂亙丂偲傠偄偺偋乮亅亅乯
俶倧亅侾俇俈偵偍偗傞俉兌帪僆乕僾儞僎僀儞倖們俋係倠俫倸側偳戝揹棳宆俵俷俽亅俥俤俿僷儚乕傾儞僾偵偍偄偰僴僀僎僀儞亅僴僀倖們偑幚尰偟偰偄傞棟孅傕懡暘埲忋偵娤偨棟桼偵傛傞偺偱偁傠偆丅偦偟偰丄埲忋偺庤朄偱僷儚乕僩儔儞僕僗僞偵傛傝倖俿偺崅偄俿俼傪摫擖偡傟偽僶僀億乕儔僩儔儞僕僗僞偱偺僴僀僎僀儞亅僴僀倖們傕幚尰弌棃傞偙偲傕暘偐偭偨丅
偙偺偲偙傠俶倧亅侾俈係丄俶倧亅侾俈俇偲丄弌椡慺巕偵僶僀億乕儔俿倰傪婲梡偟偨姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偑敪昞偝傟偰偄傞偑丄捈擖偝傫偵傛傟偽悢擔屻偵敪攧偝傟傞俇寧崋偺俶倧亅侾俈俉傕僶僀億乕儔俿倰偵傛傞姰慡懳徧宆僷儚乕傾儞僾偱偁傞偲偺偙偲丅怴悽戙姰慡懳徧宆偺夞楬偑丄崅倖俿偺僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺擻椡傪惗偐偦偆偲巚偊偽惗偐偣傞傕偺偱偁傞偙偲傪抦偭偰丄偙偆傕僶僀億乕儔偑懕偔偲側傞偲丄傕偟傗丄偄偵偟偊偺俀俶俁侽俆俆偵戙傢傞怴僷儚乕俿俼偺婲梡偑偁傝偊偨傝偡傞偺偱偼側偄偐丄側偳偲巚偆崱擔偙偺崰側偺偱偁傞丅偝偰丄偳偆偩傠偆丅乮丱丱丟
愭惗丄偳偆偱偟傚偆丄偙傫側傕偺偱乮丱丱丟
乽夝庍偼恖偦傟偧傟彑庤偱偁傞丅偑丄恀偼堦偵偟偰梕堈偵摼傞偙偲擻傢偢丅偍偝偍偝懹傞偙偲側偐傟丅乿
偼偭丂倣乮丵丵乯倣
嵟屻偵枅搙偺偍抐傝傪丅埲忋偺僔儈儏儗乕僔儑儞寢壥媦傃偦偺夝庍偵偼側傫偺曐徹傕側偄偺偱埆偟偐傜偢丅傑偨搊応偟偨僔儈儏儗乕僔儑儞儌僨儖偵偮偄偰偼壗傕偍摎偊偱偒側偄偺偱廳偹偰埆偟偐傜偢丅乮丱丱丟
乮俀侽侽係擭俆寧俆擔乯

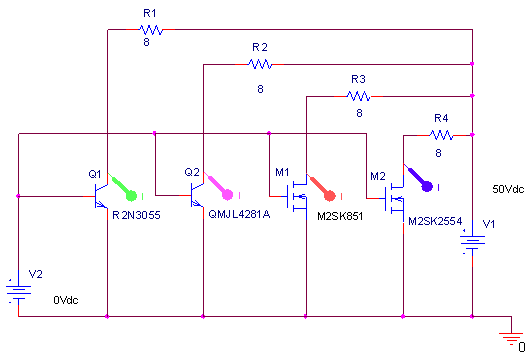
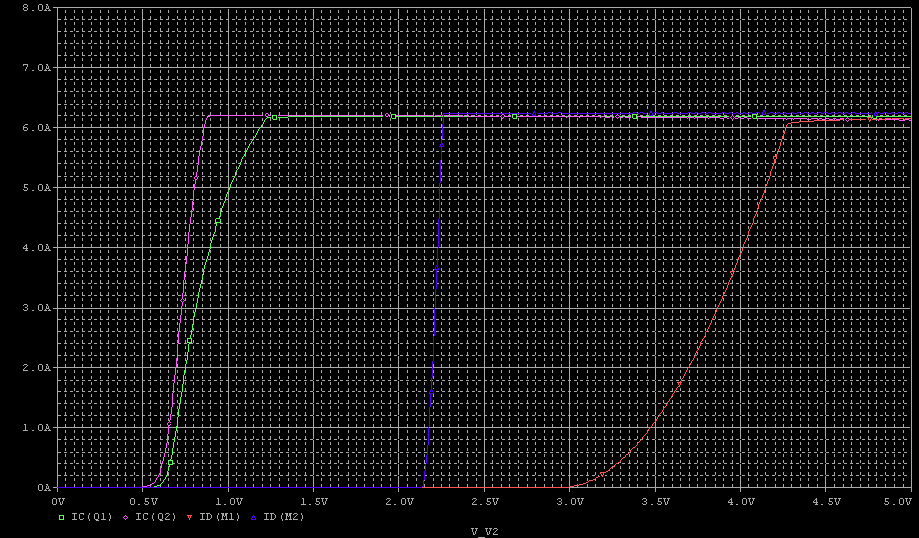
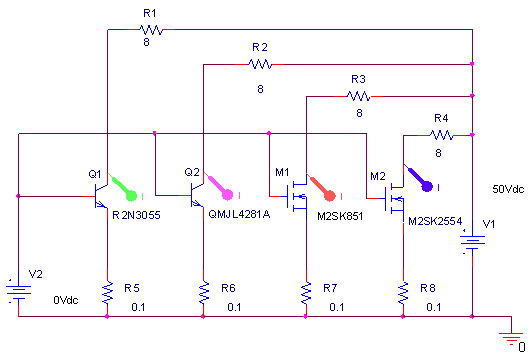
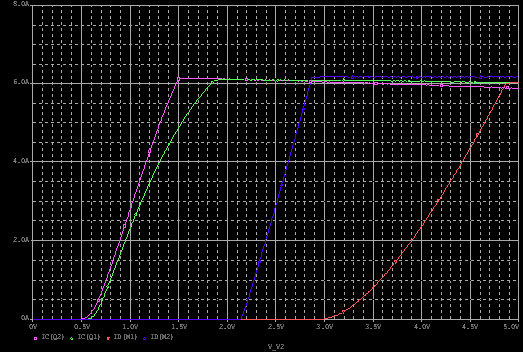 偲偄偆偙偲側偺偩偑丄埲忋丄壗傪尵偄偨偄偺偐丅偲偄偆偲丄傾儞僾幚梡堟偱峫偊傟偽僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺倗倣偼戝揹棳宆俵俷俽偵摿偵堷偗傪庢傞傕偺偱偼側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅戝揹棳宆俵俷俽偺戙柤帉偱偁傞俀俽俲俀俆俆係偵摨摍側偺偩丅偦偺僄儈僢僞乮僜乕僗乯偵揹棳婣娨掞峈傪擖傟傟偽偦偺嵎偼偝傜偵弅傑傞丅暿偵巊偄傕偟側偄僂儖僩儔僴僀揹棳擻椡偲偦偺椞堟偱偺僴僀倗倣傪偆傫偸傫偡傞偺傕埆偔偼側偄偑丄幚梡堟偱廫暘偵戝揹棳宆俵俷俽偵旵揋偡傞倗倣傪桳偡傞僩儔儞僕僗僞偵傕傕偭偲栚傪岦偗傑偟傚偆偲丅乮丱丱丟
偲偄偆偙偲側偺偩偑丄埲忋丄壗傪尵偄偨偄偺偐丅偲偄偆偲丄傾儞僾幚梡堟偱峫偊傟偽僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺倗倣偼戝揹棳宆俵俷俽偵摿偵堷偗傪庢傞傕偺偱偼側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅戝揹棳宆俵俷俽偺戙柤帉偱偁傞俀俽俲俀俆俆係偵摨摍側偺偩丅偦偺僄儈僢僞乮僜乕僗乯偵揹棳婣娨掞峈傪擖傟傟偽偦偺嵎偼偝傜偵弅傑傞丅暿偵巊偄傕偟側偄僂儖僩儔僴僀揹棳擻椡偲偦偺椞堟偱偺僴僀倗倣傪偆傫偸傫偡傞偺傕埆偔偼側偄偑丄幚梡堟偱廫暘偵戝揹棳宆俵俷俽偵旵揋偡傞倗倣傪桳偡傞僩儔儞僕僗僞偵傕傕偭偲栚傪岦偗傑偟傚偆偲丅乮丱丱丟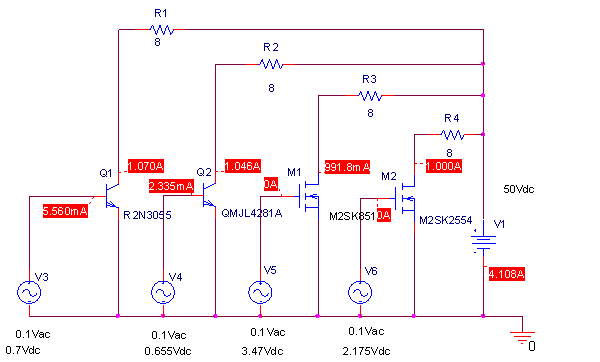 俙俠僗僀乕僾儌乕僪偵傛傝倗倣偺廃攇悢摿惈傪娤傞丅
俙俠僗僀乕僾儌乕僪偵傛傝倗倣偺廃攇悢摿惈傪娤傞丅