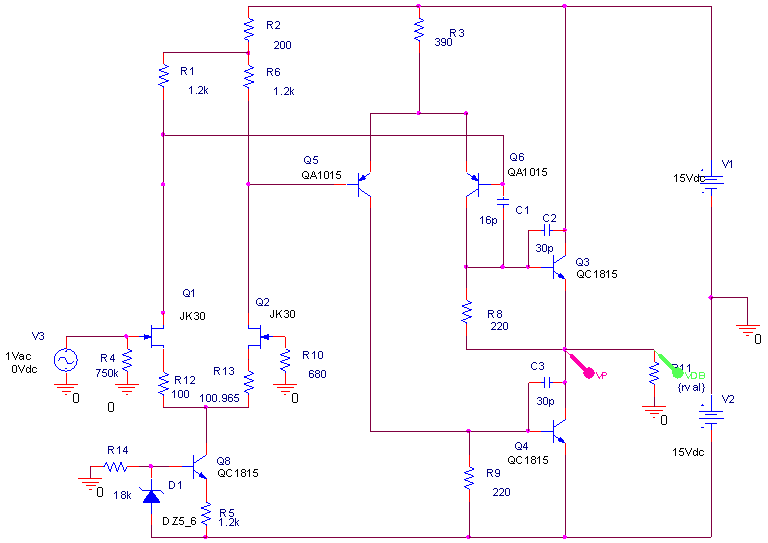
PSpice(評価版)で
完全対称型ヘッドフォン(専用)アンプをシミュレートする
我が完全対称方式のヘッドフォン(専用)アンプのイメージである。
毎度のことだが、A607(606)やC960(959)のモデルはないので、A1015、C1815で代用する。そのままではCobが違いすぎるのでそのB−C間にコンデンサーを挿入してA607(606)、C960(959)のモデルに近づける努力をする。
A1015の方には16pFを外付けし、A1015の規格上のCob4pFと合わせてCob20pFのイメージ、C1815の方は30pFを外付けしC1815の規格上のCob2pFと合わせてCob32pFのイメージだ。
もとより本来のA607(606)、C960(959)のCobはそんなものか?という問題はある。が、その辺はアバウトで良い。それでも傾向は分かるのである。
早速入力に1Vacを加え、出力の電圧利得(db)と電圧位相を観る。
負荷は最初からパラメトリックに、37.5Ω、75Ω、150Ω、300Ω、7KΩである。
37.5Ω、75Ω、150Ω、300Ωは勿論現実のヘッドフォンのインピーダンスをイメージしたもので、分かりやすいように6dbずつ増加させたものであり、7KΩは負荷オープン時のイメージである。
これで一気に状況把握。
その前に各部の電圧、電流の状況を確認しておく。
DCバランスも大体確保され、終段のアイドリング電流も実機の設定にごく近い。
終段のアイドリング電流が上下で3.3mA程度違っており、下側の方が多い。のは2段目差動アンプの右側の動作電流を終段下側が吸い込んでいるためである。そうしないと当然出力にプラスのDCオフセットが生じる。そうならないように初段差動アンプのソース抵抗(実機では半固定抵抗)を調整し、=差動のバランスをやや崩して、終段上下のアイドリング電流値をわざと違えてDCバランスを取っているのである。
その程度は微量だが、これが全体的に対称動作を些か崩していることも事実で、その辺はあとのシミュレーション結果にも出てくる。
世の中には耳の良い人もいるものと感心する。その微妙なアンバランスによる音の悪化を聞き分けて対策を講じている人もいるのだ。私には及びも付かない。
グラフ上が位相特性で、上から負荷37.5Ω、75Ω、150Ω、300Ω、7KΩの場合である。
グラフ下は電圧利得で、上から負荷7KΩ、300Ω、150Ω、75Ω、37.5Ωの場合である。
次に確かめるが、2段目差動アンプのCobによる第1ポールが3.5KHz(負荷7KΩ)から35KHz(負荷37.5Ω)という比較的低い位置に出来て、それ以上ではなんと10MHzという高域まで時定数はないが如きの位相遅れ−90°以内、電圧利得−6db/octが継続している。実機でのクローズドゲイン設定20dbでも全く安定に動作するのは当たり前の超安定な特性になっている。
これは連星効果によるところ大だ。
電圧利得は負荷に比例した6dbステップの増加になっていない。のは、2段目差動アンプにカスコードを付加していないために、出力インピーダンスが十分でないためだ。負荷7KΩでは完全に伸びが止まっている。
が、電圧利得53.5db(37.5Ω)、58.5db(75Ω)、63.5db(150Ω)、67.5db(300Ω)と利得は十分に得られている。
さて、これで問題にするのが第1ポールの位置である。
トランスインピーダンスの電流帰還方式ではゲインと帯域は両立するらしいが、そうでない普通?のアンプはゲインと帯域はトレードオフである。一般にゲインが小さい方が帯域が広く、ゲインが大きい方が帯域は狭い。
ここでも正にそうなっている。
オープンゲインで使おうという訳でもあるまいに、オープン時の第1ポールが低いことに何の問題があるのか?オペアンプなんか10Hz台だ。GB積が十分ならそれで良かろうに・・・。という見方もある。
が、まぁ、K式DCアンプでもあるし、理想NFBの思想で音声帯域ぐらいには位相ずれのないNFBを掛けたい、よってもう少し広帯域化出来ないか、というのが今回のテーマである。
今の状態は、インピーダンス30Ω程度の一般的なヘッドフォンを繋いだ場合にはまあまあの帯域幅になるものの、HD600のようなインピーダンス300Ωのヘッドフォンを繋いだ場合にはオープンゲイン時の第1ポールが7KHzと音声帯域まで降りてきて、結果NFBの位相も20KHzでは−70°ずれている、という状態なのだ。
そこで、負荷インピーダンス300Ω時の第1ポールも出来れば20KHz以上の高域へ移行させ、これをより理想に近づけよう。というわけだ。
が、事はそう簡単ではあるまい。何せゲインが大きいのだ。ゲインと帯域は基本的にトレードオフ。したがってこの第1ポール。1桁でも上へ移行できれば御の字であるように思える・・・
もしそれが困難となれば・・・、トランスインピーダンスの“電流帰還型”に移行・・・?(^^;
と、そこまではまだ考えず、取りあえず低いポールの要因を探る。
まず、2段目にカスコードアンプを入れる。
上の場合の第1ポールが、初段と2段目の入り口で2段目差動アンプのCobがミラー効果で拡大されて出来るポールであることをこれで確認する。
負荷は同じくパラメトリックで37.5Ω、75Ω、150Ω、300Ω、7KΩである。
電圧利得(db)と電圧位相を観る。
やはり2段目のCobに働くミラー効果が排除されて帯域が1桁上に伸びている。
これでカスコードのない上の場合の第1ポールが2段目差動アンプのCobによるものであったことが明らかだ。
今度の第1ポールは終段TRのCobによるものであろうと推測されるが、15KHz(7KΩ)、110KHz(300Ω)、200KHz(150Ω)、300KHz(75Ω)、450KHz(37.5Ω)と非常に広帯域である。
これでもう、目的は達せられた!?(^^;
が、世の中そう優しくはない。
残念ながら、1MHz近辺に第2ポールが明確に現れており、この場合は連星効果もないようで、結果スタガー比が確保できないのである。
したがってこれでは殆どNFBを掛けることが出来ない。
よって、この広帯域はこのままでは生かすことができないのだ。ざんね〜〜ん。
電圧利得は負荷に比例した6dbステップの増加に大体なっている。のは、2段目差動アンプにカスコードを付加した結果出力インピーダンスが十分に高くなったためだ。負荷7KΩでも利得増加の比例関係が保たれている。カスコードアンプの効果はこの点でも非常に大である。
電圧利得53.5db(37.5Ω)、59.5db(75Ω)、65db(150Ω)、70.5db(300Ω)と基本的にはカスコードなしの場合と同じだが、負荷が大きくなるほど乖離が広がるのは勿論カスコードの有無によるものだ。
さらに広帯域化の可能性を探るために、終段C1815に外付けした30pFを外してみる。
上の場合の第1ポールが2段目負荷抵抗と終段TRのCobがミラー効果により拡大されて出来たポールであることも確かめる必要がある。
これで終段のCobはそもそものC1815の規格上のCob=2pFと1/16になる。したがって終段のポールは16倍高域に移動するはずだ。
はたして・・・。これでこのアンプの第1ポールも16倍高域に移動してくれれば事は簡単なのだが・・・(^^;
ちなみにこの状態は、2段目にA726やA872、終段にC1400やC1775を起用したイメージといって良い状態だ。
第1ポールは、110KHz(7KΩ)、650KHz(300Ω)、900KHz(150Ω)、1MHz(70Ω)、1.1MHz(37.5Ω)と超広帯域である。
負荷7KΩの場合は、終段TRのCobによるポールがまだ第1ポールとなっているかもしれない。
が、負荷300Ω以下については、終段TRのCobによるポールとは言えない。
そうではなくて、上の場合の第2ポールが第1ポールの位置に現れてきたもの、といった方が正しいだろう。
しかも利得の下降直線が12db/octであること、位相の回転具合が急であることから、2つのポールが重なっているように思える。
まぁ、非常に広帯域ではあるが、勿論この状態ではNFBはまともには掛けられない。したがってこの広帯域をそのまま生かそうとしても無理である。
問題は、このポールの要因は何か?
ということだが、多分これはA1015とC1815のベータ遮断周波数による(疑似)ポールだ。
A1015、C1815に限らず、K式でも使われる(た)ような低周波小信号用のトランジスタのfTは100MHz内外であり、そのHfeは100内外である。
だからどの低周波小信号用TRを使ったところで1MHz前後にベータ遮断周波数によるポールが生じるのだ。
要するにこれらのトランジスタの増幅能力(=Hfe)が1MHz弱から減少し、100MHz内外のfT(トランジション周波数)で1になる。このことがこの電圧利得特性の高域での姿を形成しているのである。多分(^^;
完全対称型は2段目と終段もエミッタ接地であるから、このヘッドフォン(専用)アンプのようにともにトランジスタを起用してエミッタ抵抗を使用せず最大ゲインで動作させれば、2段目と終段のベータ遮断周波数によるポールが1MHz付近で重なることになる。
それが12db/octで減衰していくこの結果となるのだ。
では、初段は?
あとで見るがFETは1桁限界が高いようで・・・
連星効果はないのか?
ここではもう2段目、終段ともにHfeが減少し増幅能力を失っていく過程であるが故に回復できない。ということなのだろう。
さて、
実は、以上から次の結論が導かれてしまうのである。
完全対称型の広帯域化の限界を規定しているものは、この100MHz内外の低周波小信号用トランジスタのfTである。ということである。
素子のCobとかCrssとかではないのだ。
何故なら、これを第1ポールとして安定なNFBを掛ける手法があれば格別だが、通常はこれを第2ポール以降に配置する以外にない。
となれば、例えば30db(≒35倍)のNFBを予定した場合、必要なスタガー比は35×2=70倍であるから、これを第2ポールとしても1MHz÷70≒14.3KHzに第1ポールを配置しなければならないのである。
100MHzなのに・・・
しばし絶句・・・
そうなのか。
GOA等TR時代のK式の第1ポールが10KHz〜20KHzに配置されていたのは必然だったのだ。
完全対称型の場合も基本的にこの事情は同じだ。
Cobによるものであればカスコードで回避も可能だが、ベータ遮断周波数という素子本来の増幅能力の限界に起因するものではどうにもならない。だから、終段にカスコードを付加したところで無駄というものである。
完全対称型の場合、終段のベータ遮断周波数によるポールについては連星効果によって対処できる場合がありえる、という点はGOAとの違いではある。
が、2段目差動アンプのそれはなんともならない。
せいぜい初段のステップ位相補正で多少の引き戻しを図れる程度である。
実はこれも、ベータ遮断周波数によるポールは増幅能力の喪失と表裏一体のものだから、位相を戻すというだけでは完全な補償は無理なのだ。
結局、トランジスタを起用した完全対称型アンプの広帯域化を考えた場合、ボトルネックは最終的に2段目差動アンプに起用するトランジスタのfTなのだ。
ここにfT=1GHzのトランジスタでも採用できればこれによる第2ポールを10MHzとして、結果第1ポールを100KHz超としたアンプが可能となる。という結論になる。
FETなら1桁高そうだ・・・、もっとfTの高いトランジスタ・・・
これが出来ない場合。エミッタ抵抗による帰還作用を活用してゲインの代わりに帯域を伸ばす。といった方法以外にはない・・・
あらま(−−;
この状態で各部の電流利得を観る。
一番下が初段の電流利得で−59dbである。−59db≒1/900であるから、初段のgm=1/900=1.11mSである。
下から2番目は2段目差動アンプまでの電流利得で−21.5dbである。−21.5db=1/11.9であるから、2段目までのgm=84mSである。初段のgm=1.11mSだったから、2段目自体の電流利得は84/1.11=75.68倍である。
上から2番目は終段上下までの電流利得である。0.5db程度の差があるのは2段目差動アンプの動作電流分上下で動作電流が異なるため、と思われる。
大体15dbである。したがってここまでのgm=5.6Sである。終段の電流利得は5600/86=66.67倍である。
一番上が出力点での電流利得で21dbである。したがってこのアンプのGM=11.2Sということになる。
非常に大きい。のは2段目にも終段にもエミッタ抵抗を入れていないことによるものだが、これによって数十から数百Ωの比較的インピーダンスの低い負荷を出力に繋いでも適度な電圧ゲインが確保されるのである。
ちなみに負荷1KΩから50KΩのプリのフラットアンプ用としてはこれではゲインが過剰だろう。
電流利得の周波数特性をみると、各段のそもそもの増幅能力が分かる。
初段は10MHz程度までの増幅能力がある。
2段目と終段は数百KHz台から徐々に増幅能力を減じ、100MHzでは増幅能力が皆無となっている。
終段の増幅能力の減少が2段目より急激なように見えるが、終段には2段目の減少分も加算されるのだから当然の結果である。
要するに2段目も終段もベータ遮断周波数は1MHz程度でHfeが低域の−3dbとなり、fTの100MHzでHfe=1となっているのである。
したがって、これは素子固有の高域限界であり、これらの素子を用いる限りこれ以上の広帯域化はNFBの力を借りてゲインを削って(=要するに電流帰還を掛けるなどして)達成する以外困難なのだ。
回路に順次低いポールとなる要因を付加して、同様に各部の電流利得を観る。
まず、終段のTRB−C間のC=30pFを元に戻す。
終段のTRのCobにより終段に約100KHzのポールが立ったことが分かる。
これで、この終段Cobによるポールを第1ポールとし、2段目差動アンプと終段の約1MHzのベータ遮断周波数を第2ポールとした構成が考えられる。パワーアンプの場合はパワートランジスタのベータ遮断周波数が100kHz程度に出来るので、それを第1ポールとしても同様な構成が出来る。
が、両者の位置が近いので、この第1ポールをもう少し下げ、あるいは第2ポールの位相進行を少し引き戻し、またはNFB量を少な目にする、などの対策が必要になるはずだ。
続いて終段TRのCobを削除し、2段目差動アンプの例の位置に5pFを入れる。
2段目に5pFによる約20KHzのポールが形成された。
たったの5pFでこれだけ低いポールになるのは、ここに2段目と終段の電圧ゲインが加算され、大きなミラー効果が生じるためである。
終段と出力端の電流利得特性にも約20KHzのポールが形成されたように見えるが、これは2段目のポールによる電流利得特性を終段もそのまま受け継いだだけで、終段自体のものではない。のは、その傾きが2段目と平行であることから明らかだ。
これを第1ポールにすると非常に安定なアンプになるであろうことが推測される結果だ。って、実際そうなのだが(^^;
下は2段目に入れるCを1pFにした場合である。
第1ポールは100KHz程度に上がっている。
この構成では、2段目差動アンプに付加するCで自由自在に第1ポールを動かし、最も安定で広帯域になるポイントを探せそうだ。
初段にステップ型の位相補正を入れた場合にはどうなるか観てみる。
定数は取りあえず680Ω+510pF
Q5、Q6の入力インピーダンスがR1,R6とパラに利くのだが、Q5、Q6の入力インピーダンスはシミュレータの実測では1.43KΩ、簡易計算式では26/Ib(mA)=26/0.16=1.63KΩである。ので、1.43KΩを採用すると、パラで650Ωということになる。
よって
ステップ低域側周波数=159/((0.65KΩ+0.65KΩ)*0.00051uF)≒240KHz
ステップ高域側周波数=159/(0.68KΩ*0.00051uF)≒460KHz
となる。
460KHz付近からは位相の戻し効果が現れるはずだが、果たしてどうだろうか。
低域側は150KHz程度になっている。第2ポールの影響も受けて計算値より低くなるようだ。
問題は高域側だが、明確ではない。
第2ポールとなっている1MHz付近のベータ遮断周波数によるポールが強力なためだ、が、2段目の1MHz前後の領域の減衰カーブが6db/octより心持ち緩やかになっているように見えるがどうだろう。
確かに緩やかになっている。これがステップ高域側の効果だ。
ちなみに、初段のステップ型位相補正で2段目の5pFと同程度の位相補正効果を得て、それを第1ポールにしたい。という場合には、例えばこのような設定になる。
第1ポールは約10KHzに出来た。が、10000pFのSEコンと思うとちょっと不経済である。
不経済ではあるが、完全対称型では、これが終段の負荷の影響を受けることない安定なポールを形成出来る唯一の方法だ。
実に有望な手法ではないか。
が、そうそう上手く問屋は卸してくれない訳でしてね・・・(^^;
次にNFBの効果を観る。
2段目と終段にエミッタ抵抗を入れて、その電流帰還(NFB)により電流利得特性はどうなるか、である。
帯域は伸びるが、ゲインは大きく減少するだろう・・・、というのが予想だ。
まずは2段目差動アンプ。
予想どおり。というべきか。
電流利得は2段目差動出力までで−45dbと23.5dbも減少してしまった。結果全体でも−3.5dbであるから、GM=666mSとなって、負荷の低いヘッドフォンアンプとしては実用性がない。
が、負荷1KΩ以上となるプリのフラットアンプとしては使える。実際No−128(?)の構成は基本的にこうだ。
問題の2段目の周波数特性だが、確かに1桁弱高域に伸びた。が、差動の右側が終段の影響を受けるためかかえって狭帯域になってしまっている。
終段にもエミッタ抵抗47Ωを入れて電流帰還(NFB)を掛けてみる。
終段の周波数特性も高域に伸びたために、アンプ全体としても−3db点が5.5MHzと驚異的な広帯域となった。
が、終段までのゲインは−32dbと、47dbもゲインが減少してしまった。
2段目で23.5dbの減少であったから、終段でも23.5dbの減少である。
結果アンプ全体での電流利得は−25dbであるから、=1/18でGM=55.6mSということになる。
これでも負荷1KΩでは35db、50KΩでは69dbの電圧ゲインが得られるから、フラットアンプとしての適性は高い。
実際やってみよう。
負荷1KΩ、2kΩ、4KΩ、8KΩ、16KΩ、32KΩ、64KΩのパラメトリック解析で電圧利得、位相特性を観る。
ゲインを0dbまで絞るプリアンプのフラットアンプには勿論このままでは使えないが、クローズドゲインを40db程度に固定したフラットアンプとするのであれば、別途位相補正を要さず、例えば負荷50KΩ程度でfc=150KHz程度の広帯域なアンプとして使えそうだ。
それは何? って、まあDCマイクアンプあたりでしょうか(^^;
もう少しゲインを高めたい気がする。
そこで、2段目の負荷抵抗を1.6KΩにしよう。
こうすると2段目は動作電流が減るためにやや電流ゲインが下がるが、終段は電流ゲインが大きくなるはずだ。
そうなった。
が、終段のゲインが大きくなったために、終段Cobによるポールが1MHz〜2MHz付近に立ったようだ。
たったの2pFなのだが、広帯域化はなかなか難しいものだ。
それでも、アンプ全体で−11.5dbとゲインが大きくなったから、−11.5db≒1/3.75で、GM=267mSと、負荷50KΩであれば82.5dbの電圧ゲインが得られる数値だ。
これで安定にNFBが掛けられるのであれば、NFB40dbが確保できて、マイクアンプとしては妥当なものになるように思えるのだが・・・
どうだろうか。
低域の電圧利得75db
利得が上の計算より低い結果となったのは、終段自体の出力インピーダンスが負荷50KΩに対してはこれでも不足しているためだろう。が、これだけ得られれば十分だ。と思う。
fc=40KHz
オープンゲイン40db付近の位相遅れ−110°が得られる。
この場合の第1ポールは終段TRのCobが担っている。
これならクローズドゲイン40dbのDCマイクアンプ用として妥当ではないだろうか。
このままで別途の位相補正はなしでOKだ。
オープンゲインが非常に大きいので、これ以上の広帯域化はちょっと困難と思われる。
また、使用するTRとしては、終段をC1775AやC1400、C984、C1811、D756等のCobの小さいものにしたい。
C959(960)ではCobが大きいため、ゲインやNFB安定度は同じだが、fcが一桁下がって3.5KHzになってしまうのだ。
ただし、音的にはそれでもC959(960)の方が良い、という可能性もあるので単純には言えないのであるが。
なお、
このアンプの出力は、完全対称方式の一般で、相応のハイインピーダンスで受ける必要があるので、それを前提にした使い方をしないと駄目。(^^;
さて、我がヘッドフォン(専用)アンプである。
現状においては、2段目差動アンプに起用しているA607の大きなCob(20pF)がミラー効果によって拡大されて低いポールを形成し、これに完全対称型ならではの連星効果が効果的に働いて非常に安定なアンプとなっているわけだ。
が、やや第1ポールが低い位置にある。
これまで検討してみた結果に基づき、これをもう少し高域に配置して広帯域化を図る。
そのためにはA607のCobにミラー効果が及ばないように、2段目差動アンプにカスコードアンプを導入することが必須だ。
終段は音の点でC960を用いなければならない、とすればそのCobの影響は甘受せざるを得ない。
負荷37.5Ω、75Ω、150Ω、300Ω、7KΩで、最初に見たとおりだが、終段のCobによるポールが第1ポール、2段目TRと終段TRのベータ遮断周波数によるポールが重なって第2位ポールとなっている。
設定クローズドゲイン20dbは勿論、26dbでも32dbでもポール間が近くてスタガー比が取れない。ので、このままでは使えない。
広帯域化へ向けて幾つか策を労してみる。
負荷37.5Ω、75Ω、150Ω、300Ω、7KΩでのパラメトリック解析での電圧利得、位相特性。
その1 初段ステップ型位相補正
位相の引き戻し効果の威力抜群だが、残念ながら1MHz付近の第2ポール自体を高域に移動させる力は初段ステップ型位相補正にはない。
この辺が限界で、帯域自体は広帯域であるが、残念ながらこれでは20db〜30db程度のクローズドゲイン設定は出来ない。
その2 2段目電流帰還+@
2段目のベータ遮断周波数による第2ポールを引き上げるために2段目差動アンプのエミッタに電流帰還抵抗22Ωを入れる。
この場合2段目の電流ゲインが減り、結果総合ゲインが減少することになるので、これを補うために初段にはgmの大きいK117を起用する。
が、それでベータ遮断周波数によるポールが劇的に高域に上昇するという訳ではないので、平行して2段目にミラー効果による第1ポールを形成して、その間隔をスタガー比が確保出来る程度に離す。
この場合、終段のCobによるポールは連星効果で隠れてしまうので、問題はない。
実用的結果になった。
この場合の第1ポールは、250KHz(37.5Ω)、110KHz(70Ω)、70KHz(150Ω)、35KHz(300Ω)である。
が、位相遅れ−120°以内なのは3MHzまでであり、クローズドゲインは30db以上に設定する必要がある。
その3 2段目ミラー効果
その2は策を労しすぎている嫌いがある。
連星効果が見込めるのだから、最初から2段目に必要最小限のミラー効果による第1ポールを形成すれば広帯域化は可能なのではないか。
実はそうだったのだ。
これでも広帯域化の実用的結果になるのである。
この場合の第1ポールは、150KHz(37.5Ω)、90KHz(70Ω)、45KHz(150Ω)、25KHz(300Ω)である。
が、この場合も位相遅れ−120°以内なのは3MHzまでであり、クローズドゲインは30db以上に設定する必要がある。
その2の場合の方がより広帯域であることは確かだが、得られている電圧ゲインを勘案すればこれでも十分ではなかろうか。
その4 クローズドゲイン設定26dbを得るために(最終結果)
クローズドゲイン設定はTR完全対称パワーアンプと同様に32dbでもよかったのだが、この際だから・・・ということで26db設定の可能性を探って得た結果がこれである。
その3の状態に初段ステップ型位相補正を加えたのである。
結果、この場合の第1ポールは、95KHz(37.5Ω、53.5db)、65KHz(70Ω、59.5db)、40KHz(150Ω、65.2db)、22KHz(300Ω、71db)である。
この場合の位相遅れ−120°以内なのは4MHzまでと広がり、クローズドゲインは26db設定も可能となった。
問題は、このシミュレーションの現実妥当性なのだが、シミュレーションとともに行った実機の改良においても、特に位相関係がすぐに不安定&発振という現象で現れるので分かるのだが、それが何故こんなに結果が一致するのかと思えるぐらいに正確なのには恐れ入ってしまった。
よって、我が実機はシミュレーション通りの回路となったのである。
(2003年2月17日)
(おまけの完全対称型マイクアンプの考察)
完全対称型の特徴は終段がいわゆるエミッタ接地動作であることである。だからそのオープンゲインは終段に繋ぐ負荷抵抗に比例する。
負荷が10倍になればオープンゲインも10倍、クローズドゲインが一定ならこれでNFB量も10倍になる。ということなのだ。
しかもこの場合の負荷とは、NFB抵抗と出力に繋がる負荷の並列合成値のことなのである。
だから完全対称型は、その出力に繋がる負荷のことを無視した設計や使い方は出来ない。その意味では一般のアンプのような汎用性はない。
負荷にどういうものを繋ぐのか、あるいは繋ぐことができるのか、を考えて設計し使わなければならない訳だ。
上で考えてみたDCマイクアンプは、実は完全対称型パワーアンプにつなぐ場合のように820KΩぐらいのインピーダンスで受けて欲しい。
などというのは、DCマイク録音などしたことがない者の机上の空論であったか(^^;
考えて見れば、録音アンプの入り口にはそんなにインピーダンスの高くないアッテネータがあるんですよね。
で、あれば、NFB抵抗とアッテネータの並列合成インピーダンスが例えば10KΩになっても必要なオープンゲインが得られるようにしなければならないので、2段目の電流帰還抵抗を47Ωに減らして帰還量を減らしゲインアップを図っておかなければならない。ということになる。とりあえず・・・
低域のオープンゲイン76db、fc=35KHz程度、オープンゲイン40dbポイントの位相遅れは−105°程度だ。
これでよい、のだが、問題は、こうやっていちいち負荷に合わせて専用設計しなければならない! という点だ。
完全対称型は、基本的に後ろにつながる機器に合わせた専用設計なのである。
が、後ろにつながる機器のインピーダンスに合わせたゲイン設定で専用設計にすればよい、というだけですむものでもなくて・・・
対容量負荷安定性はどうだ、というM−NAO氏の問題提起もある。
そもそも、DCマイクはアマチュアのもので、マイクケーブルを100mも伸ばしてその容量が10,000pFになる、などという業務用もどきの使い方をしてはいけない、と思うのだが・・・
一気にfcが2KHzに下がってしまった。
連星効果が利くので安定性は確保されるが、これでは高域でのNFB量が減ってしまう。
オープンゲイン設定を間違って低めにしてしまった場合などはかなり悲惨だろう。
これでは、完全対称型ではDCマイクアンプは実質作れない?
いや。
対応手法としては、NFB回路のインピーダンスを出力に繋がる負荷より低く設定する、ということが考えられる。
NFB回路のインピーダンスを1/100に下げる。
が、こうすると、完全対称型の電圧ゲインはGM×負荷であるから、アンプの電流ゲイン=GMは逆に100倍大きくしないと所要の電圧ゲインが得られない。
よって、2段目と終段のエミッタ抵抗は取り去りこれらを最大ゲインで動作させ、さらに初段のFETをgmの大きいK117に交換する。
出力には10KΩのアッテネータが繋がったイメージだ。
オープンゲイン76db、fc=40KHz、オープンゲイン40dbポイントの位相遅れ−100°がこれで得られる。
それだけではない。
出力に長いケーブルによる10,000pFの容量がぶら下がったところで・・・、
極端にfcが下がってしまう、という問題もなくなるのだ。
が、極端でないだけで、これでもまだ影響を被っている。
この手法をさらに徹底しよう。
NFB回路のインピーダンスをさらに1桁下げる。
こうすると電流ゲインはさらに10倍必要となるので、終段をダーリントン接続にする。C960を繋いだイメージである。この場合30pFのCobがあってもドライブインピーダンスが低いので問題はない。
オープンゲイン75db、fc=45KHz、オープンゲイン40dbポイントの位相遅れ−95°がこれで得られる。
出力に10,000pFの容量がぶら下がっても・・・
その影響を受ける度合いも減ったようだ。
これなら出力に繋がる負荷の影響を受けにくい、汎用性のあるDCマイクアンプとして可能性があるのではないだろうか。
と、確かめるために、出力に10,000pFをぶら下げたまま、その負荷をパラメトリックに、150Ω、300Ω、600Ω、1.2KΩ、2.4KΩ、4.8KΩ、9.6KΩ、19.2KΩと変化させてみる。
殆ど影響を受けない。
これなら良さげ(^^)
いやいや。
位相余裕が超高域でなくなっているではないか。20,000pFがぶら下がったら発振してしまうのではないか・・・
もっともだ。
が、対応策はある。(^^)
出力にシリーズに小抵抗を入れれば良いのだ。例えば47Ωを入れる。
完全に実用的な結果が得られるマイクアンプになったように思うがどうだろうか。
出力に100,000pF=0.1μFがぶら下がったところで・・・
これでも実用的帯域幅が得られるし、位相的にはかえって余裕が広がって安全なのだ。(^^)
これで実機を作るとなれば、初段はFD1841から2SK97への変更が必至だし、消費電流もやや多くなるし、果たして音が良いかどうかは・・・
知らない・・・(^^;
(2003年2月20日)