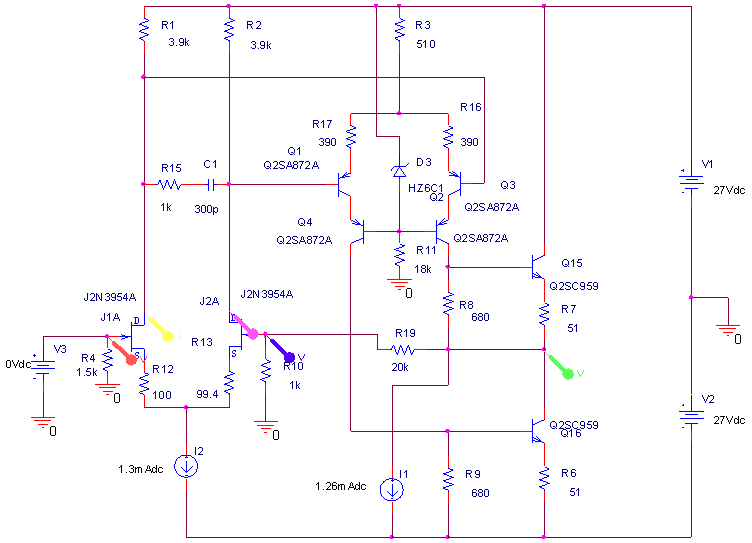
PSpice(評価版)でAOCをStudyする
AOC(オートマチック・オフセット・コントロール)は、半導体に比べ概してゲインが小さく、また、残り少ない希少な素子であるために必ずしも厳密なペアを揃えて使う訳にもいかない真空管を直結アンプ形式で活用するが故に半導体式に比べて出力オフセットやドリフトが大きくなりやすいK式真空管DCアンプにおいて、そのオフセットやドリフトの安定性を高めるために導入されたものである。
と、私は思う。(^^;
あたりまえだろ! と、言われそうだが、まぁ、そのココロはおいおいに・・・(^^;
さて、これはNo−168に触発されて製作した2段目TRによる我がオリジナルCDラインアンプのPSpiceイメージである。
DCアンプである。 って、何をいまさらなことを・・・、なのだが、DCアンプであるから当然直流からゲインがある。ということをアンプの入力に直流電源を加えることによって敢えて観てみる。
そこで、PSpice(評価版)のDCスイープ機能を使い、入力電圧を0Vから1Vまで連続的にスイープしたときのアンプ出力電圧を観る。
合わせて入力電圧と初段差動アンプ反転入力側に加わるNFB電圧、そして初段差動アンプの動作電流の変化も観てみよう。
これがその結果。であるが、縦軸が2つあり左側の1が電圧軸でアンプ出力電圧(緑)、アンプ入力電圧(赤)及びNFB電圧(青)用、右側の2が電流軸で初段差動アンプの入力側2N3954Aのドレイン電流(黄)とNFB側2N3954Aのドレイン電流(ピンク)用である。横軸はアンプ入力電圧である。したがってグラフの赤は横軸値=縦軸値となる。
このCDラインアンプのクローズドゲインはNFB素子に規定され21倍であり、DCアンプであるため直流電圧についてもそれは同じである。グラフからもアンプ出力電圧(緑)がアンプ入力電圧(赤)に比例しておりその比率が21倍になっていることが分かる。
なお、このグラフには表れていないが、実はこの先においてアンプ入力電圧が1Vになる直前でアンプ出力電圧は電源電圧の制限のために飽和してしまう。
さて、以上あたりまえなのだが、このアンプに直流が入力されるとそれがまともに増幅されて出力には大きな直流電圧が発生する。
したがって、この後ろにさらにDCパワーアンプが繋がれてその先にはスピーカーが繋がれる訳だから、間違ってもアンプ入力に直流分が加わることの無いように心して使用しなければならない。のがDCアンプなのである。特に機器の電源入断の際は要注意だ。過渡的に直流電圧が発生したりするからだ。
この点、メーカー製アンプは、だれがどのように使っても問題がおきないようにミューティング回路等の安全装置を導入しているのでほとんどの場合電源の入断の順序に気を使う必要はないようになっている。が、自作アンプの場合はそうは行かないので、電源を入れるときにはソース側から順番に入れ、電源を切るときにはスピーカー側から順番に切る、という常識(少なくとも昔は常識だったが、今は常識ではないのかなぁ・・・)を守って使うことが肝要なのだ。まぁ、K式でもパワーアンプには出力DC漏れを検知して電源を遮断する保護回路は導入されているが、この常識は守るのが吉。(^^)
さて、ここで観るべきなのは、NFB電圧(青)と、初段差動アンプの入力側2N3954Aのドレイン電流(黄)とNFB側2N3954Aのドレイン電流(ピンク)である。
このCDラインアンプのオープンゲインは非常に大きいために(ICオペアンプほどではないが)NFB電圧(青)はアンプ入力電圧(赤)とほとんど同じであることが、それらのグラフがほとんど重なっていることからも分かる。
すなわちこの場合アンプ入力側2N3954AのゲートとNFB側2N3954Aのゲートは動作中においては同電位なのだ。これがいわゆるバーチャルショートっていうやつだ。
が、実はほんの微小な電位差はあるのであって、そのために初段差動アンプのドレイン電流は入力電圧が0Vの時の左右とも650uAであるものが、入力電圧が増えるのと比例して入力側(黄)は666uAまで増加しており、NFB側(ピンク)は対象的に644uAまで減少しているのである。
すなわち、これによってこのCDラインアンプの初段の動作電流はこのアンプ出力が飽和するまで±6uA変動するだけであって、650uAという動作点の設定は出力が飽和する前に初段差動アンプ自体が飽和してしまうことはありえないということが分かるわけだ。この点においては初段差動アンプの動作点の設定は妥当である、と言えることになる。
なお、そのグラフは何故かぎざぎざでありオーバーショートのようなピークが出ている。のは、シミュレーション設定において入力電圧がリニアに立ち上がっているのではなく0.2mV毎の階段状パルスで立ち上がっているからだ。高域に帯域制限のあるNFBアンプなのでこうなる。なかなかにリアルなシミュレーターだ。
これにAOCを搭載してみた。(^^)
このCDラインアンプには本来必要はないのだが、手元にPSpice真空管モデルがないために真空管アンプでのシミュレーションが出来ないので、代役として登場願ったのだ。ちょうど2段目差動アンプにエミッタ抵抗が入っているのでAOC回路がうまく組み込めるからだ。
AOC回路には本当はカスコード回路を付加すべきなのだが、評価版の制限(TR等10個以内)の関係で省略せざるをえない。が、今回のシミュレーション上は特に支障はない。
で、同様に入力電圧を0Vから1Vまで連続的にスイープしたときのアンプ出力電圧、アンプ入力電圧と初段差動アンプ反転入力側に加わるNFB電圧、そして初段差動アンプの動作電流の変化を観る。
上の場合と比べてどうなるだろうか。楽しみ(^^;
結果。
AOCはオフセットやドリフトの安定性を高めるために導入されたものであるが、実はその回路構成からして、入力にDC成分が加わった場合にこれを出力発生させないという、いわゆるDCサーボ?としての機能も果たす。のである。
グラフの青が出力電圧だが、入力電圧が0.16V程度まではなるほど出力電圧が0Vに規制されている。DCサーボ?として機能しているのだ。
が、0.16V以上の入力電圧ではAOCがない場合と同様に出力に直流電圧が発生してしまっているではないか。そしてその増幅率は21倍だ。
何故こうなってしまうのか?
それはグラフの緑と赤の線から明らかだ。これらはAOC側差動アンプ2SK170のドレイン電流値であり、アンプ入力が0Vの時は左右の2SK170とも動作点の電流値1mAであるものが、入力に直流が加わるほどに対称に増減して、要するに左側が2mA、右側が0mAとなった時点で動作が飽和した訳だ。それが入力電圧が0.16V程度のところということだ。
すなわち、この場合においては、入力に加わる直流が0.16VまではAOCがDCサーボ的機能を果たすものの、それ以上の直流電圧が加わった場合にはその機能は失われAOCのない状態と同じになってしまうというである。
さらに、この場合の初段差動アンプの入力側2N3954Aのドレイン電流(黄)とNFB側2N3954Aのドレイン電流(ピンク)にも注目する必要がある。AOCがない場合は初段差動アンプの動作電流は±6uA程度しか変動しなかったものが、この場合は±0.1mAも変動している。これは大きな差異だ。
問題はそうなる理由だが、それはAOCの働きでAOCが機能している間は初段差動アンプにDC帰還が掛からないからだ。
上のグラフからアンプ入力電圧と反転入力側に加わるNFB電圧だけを取り出して縦軸を拡大したのが下のグラフである。
オレンジ色の方がNFB電圧であるが、AOCの効果で出力電圧が0Vに制御されるが故にAOCが機能する間はNFB電圧も0Vになるのが道理だ。
結果として差動アンプを構成する入力側2N3954AのゲートとNFB側2N3954Aのゲート電圧には乖離が生じる。このグラフからそれは0.16Vだ。これが差動アンプ左右の動作電流の変動幅を広げる理由だ。
ということから、AOCについては次のようなことが分かる。
当たり前なのだが、AOCを付加したからといってアンプ入力にDC分を加えて良いということではないということだ。
アンプ入力にDC分が入力されてもそれを出力に出さないというDCサーボ機能?をAOCに期待したK式愛好者はいないと思うのだが、以上観たようにその機能には限界があり、そういう機能をAOCに期待すべきではないのだ。
AOCを構成する差動アンプの動作電流をもっと大きくすればそれも可能では? そのとおりだ。が、そうすると初段にDC帰還が掛からないことによる初段差動アンプの動作電流の乖離が一層大きくなってしまうという問題がより鮮明になる。
AOCを導入すると、初段差動アンプにDC帰還が掛からないことにより、アンプ入力にDC分が加わった場合に初段差動アンプ左右の動作点が乖離してしまうのである。これに伴い初段差動アンプの動作対称性が損なわれ、結果的に歪がより多く発生したり、初段差動アンプの動作が飽和してしてしまわないとも限らない。この点は動作の対称性を追求するK式DCアンプにおいてはより本質的な問題点だ。
要するにAOCによって初段差動アンプのバランスが崩されるのである。これはアンプ入力にDC分を加えないことで回避する以外に方法はない。
すなわち、AOCを搭載したK式DCアンプは、AOCがないK式DCアンプと同様に入力にDC分が加わることのないようにして使用すべきものなのである。
だから、AOCはただ単にオフセットやドリフトの安定性を高めるためのものにすぎない、ということなのだ。
AOCの利きを良くすると、この辺の事情がさらに明確になる。
AOCの利きをよくするためにはAOCを構成する差動アンプの実効ゲインを大きくすれば良い。そのゲインをGとすればG=gm×Rdであるから、gmのより大きいFETを起用するか、あるいはRdを大きくすれば良いということになる。ので、Rdを大きくしてみたのが下の場合である。
AOCを繋ぐ個所を変えたことにより、上の場合はRd=390Ωだったものがこの場合はRd=3.9kΩになる。したがってAOCの実効ゲインは10倍になる。すなわちAOCの利きは上の場合の10倍だ。
またまた、同様に入力電圧を0Vから1Vまで連続的にスイープしたときのアンプ出力電圧、アンプ入力電圧と初段差動アンプ反転入力側に加わるNFB電圧、そして初段差動アンプの動作電流の変化を観てみよう。
AOCの利きが10倍良くなったということは、AOCの電流変化が上の場合の1/10で良くなるということである。それがAOCを構成する2SK170のドレイン電流値(緑と赤)の変化に表れている。こちらの場合、アンプ入力電圧が1Vになっても飽和していない。
また、この間AOCが利いているのでアンプ出力電圧(肌色)も制御され、0Vではないが入力電圧が1V時でも出力電圧は0.1Vに抑制されている。
が、これに伴ってアンプ初段のNFB電圧(濃い紫)はほぼ0Vと初段差動アンプに掛かるDC帰還は僅少となっており、このためアンプ初段差動アンプの動作点(黄とピンク)の乖離はなんと±0.55mAと非常に大きなものとなってしまっている。入力にDC電圧が入った場合、初段差動はこのように動作点が大きく乖離した状態でAC信号の増幅作用を果たさなければならない訳だから、その発生する歪は増大してしまうだろう。
さらに、このまま入力に加わる直流電圧が増加すると初段差動アンプがついに飽和してしまいそうではないか。
ということを観るために入力に加える直流電圧を5Vまでスイープしたのが下のグラフ。
この場合は入力直流電圧が1.3VとなったところでCDラインアンプの初段差動アンプが飽和してしてしまうことが分かる(黄とピンク)。
そのため、アンプ出力のDC電圧(肌色)もその時点の電圧で飽和し、アンプ入力に加わる直流電圧が増加しても出力の直流電圧はそれ以上増加しないで一定値に収束してしまう。これは初段が飽和してしまうのだから当然の結果だろう。
ここで、AOCを構成する2SK170のドレイン電流(緑と赤)も同時に飽和しているように見えるが、これはアンプ出力電圧が収束したことによるもので動作が飽和したことによるものではない。ということはそれぞれの電流値からも明らかだ。
と、以上からAOCについてまた次のようなことが分かる。
AOCの利きを良くすると(利きを良くしなくてもAOCの動作電流を増やしてAOCが最初に飽和しないようにした場合も同じと思われる)、入力に加わる直流電圧が出力に表れないようにするDCサーボ?効果をかなり広範囲で発揮できる。
しかしながら、これに伴ってアンプ初段差動アンプにDC帰還が掛からない範囲が増大し、初段差動アンプの動作点の乖離は大きくなり、歪増大の危険性が高まるほか、結局初段差動アンプが回路中で最も早く飽和してしまう。
回路中の素子動作の飽和は、その時点で回路の動作が正常範囲を逸脱することを意味するから、AOCを付加したこのCDラインアンプは入力に1.3V程度以上の直流電圧が加わった段階でアンプとしては機能しなくなる(歪の発生)のだ。
初段が飽和しても、そのため出力に大きなDCが表れてしまうというような現象は発生しないので、その意味では安全ではあるものの、アンプとして正常動作をしなくなるのだから、これは本末転倒という事態であるというべきだろう。
やはりAOCはDCサーボ?ではないのだ。AOCを搭載したK式DCアンプは、AOCがないK式DCアンプと同様に入力にDC分が加わることのないようにして使用すべきものなのである。
AOCはただ単にオフセットやドリフトの安定性を高めるためのものにすぎないのだ。だからその名称はAOC(オートマチック・オフセット・コントロール)なのである。
なお、ついでながら、AOCを付加した時点でK式DCアンプはDCアンプではなくなる。のは周知のとおりだ。
AOC入力側のローパスフィルターが形成する低域時定数を有するACアンプになる。その実際のローカット度合いはAOCの実効ゲインに比例し、AOCの利きが弱い場合はローカットの度合いも緩やかであり、AOCの利きが強くなるほどにローカットの度合いも急激になる。だからAOCはその利き具合でアンプの音を周波数特性の面からも変化させる可能性がある。
よって、AOCは利きのよいものを導入するほどに入力側のローパスフィルターの低域時定数を低くすべきであるし、そのコンデンサーの質にも留意した方が吉なのだ。
ついでだが、以上で観たように、AOCが付加されるとAOCがない場合と比較して、出力に突然直流分が発生するなどアンプの動作がより危険になるようなことはない。
したがって、K式DCアンプ愛好家としては、従前どうり出力にDC分が現れるような市販品には留意し、そういうものは使わず、また、電源を入れるときにはソース側から順番に入れ、電源を切るときにはスピーカー側から順番に切るという常識を守ってK式DCアンプを使えば良いということなのである。
実はDCサーボというものが本当はどういうものか、良くは知らない。(^^;
ここでは勝手に“入力に加わる直流電圧が出力に表れないようにする機能”としたのだが、気が向いたらそのうち調べてみることにしたい。
で、間違いついでかもしれないのだが、DCサーボってこういうものではなかったかなぁ・・・と考えたのがこれ。
出力のDC分を検出し、これを拡大してNFB回路に戻すものではなかったかなぁ、と。
この拡大するところが味噌で、サーボがなければDC帰還率は最大で100%、すなわちその場合アンプの直流増幅率は1倍になるところ、サーボによってDC帰還率を200%、あるいは300%に増やすことが可能となり、これによってアンプの直流増幅率が0.5倍あるいは0.3倍と、入力に直流が加わっても出力に現れる直流分をそれ以下に抑制できるということではなかったかと。
この例では、DCサーボアンプのゲイン設定は4倍であるが、その出力に1kΩを挿入していることからそれが1/2となってNFB回路に加わることになる。すなわちDC帰還率は200%の設定である。
この場合、入力電圧を0Vから1Vまで連続的にスイープしたときのアンプ出力電圧、アンプ入力電圧と初段差動アンプ反転入力側に加わるNFB電圧、そして初段差動アンプの動作電流の変化はどうなるのだろう。楽しみ(^^;
結果。
アンプ入力直流電圧(水色)と帰還電圧(オレンジ)はほとんど重なっている。
そして、アンプ出力の直流電圧はそれらの1/2になっている。想定どおりの結果であり、DCサーボによる直流抑制効果が発揮されている結果だ。
問題の初段差動アンプの動作電流の変化だが、入力直流電圧が10V変化しているにもかかわらず、電流値は±0.7uAしか増減していない。動作点の乖離は殆どない。素晴らしい。(^^;
これなら、サーボアンプのゲインをより大きくすればアンプ側のAC増幅動作に殆ど影響を与えずに、アンプ入力に直流が入力されても出力には殆どDC成分を出さないアンプが出来そうではないか。
って、実はシミュレーションでそれが出来ないかちょっとやってみたのだが、どこか間違えているのかDCサーボゲインを高めると安定に動作しなかったので、この程度のゲインのサーボアンプにとどめたのである。(^^;
多分ハイカット(ローパス)フィルターによるAC分の分離が十分でないために、一部AC分で干渉があるためなのだろう。本当にDC分だけを帰還するようにすればより高機能なDCサーボアンプになるものと思うのだが、まぁ、別にその追求が目的ではないのでここではこれ以上やらない。
それはそういう機能を有するアンプが必要なメーカーに任せよう。
で、結局のところ、AOC(オートマチック・オフセット・コントロール)は、半導体に比べ概してゲインが小さく、また、残り少ない希少な素子であるために必ずしも厳密なペアを揃えて使う訳にもいかない真空管を直結アンプ形式で活用するが故に半導体式に比べて出力オフセットやドリフトが大きくなりやすいK式真空管DCアンプにおいて、そのオフセットやドリフトの安定性を高めるために導入されたものである。ただそれだけだ。と、私は思うのである。(^^;
さて、最後に毎度のお断りだが、以上のシミュレーション結果及びその解釈にはなんの保証もないので悪しからず。また登場したシミュレーションモデルについては何もお答えできないので重ねて悪しからず。(^^;
(2005年3月21日)