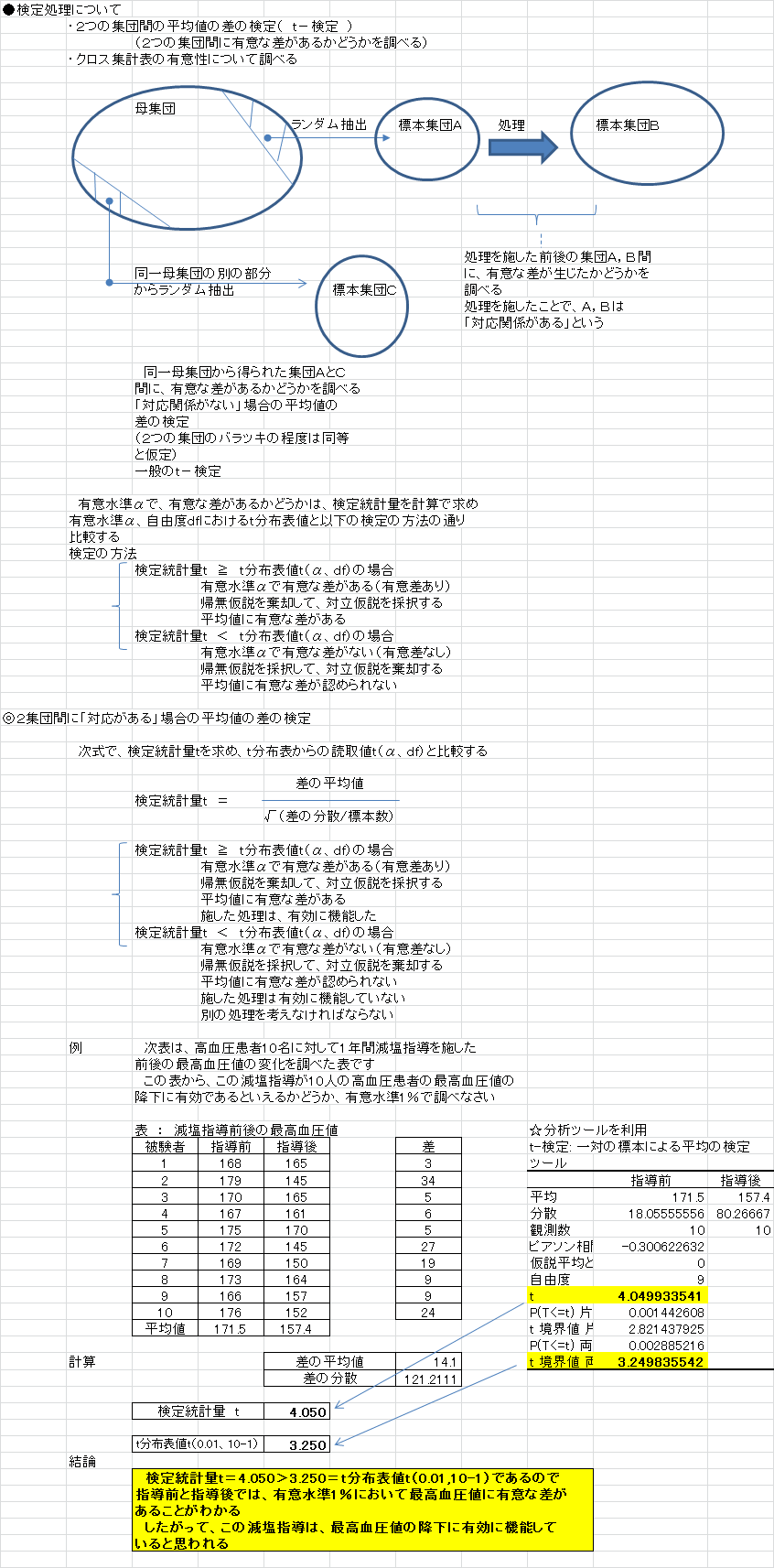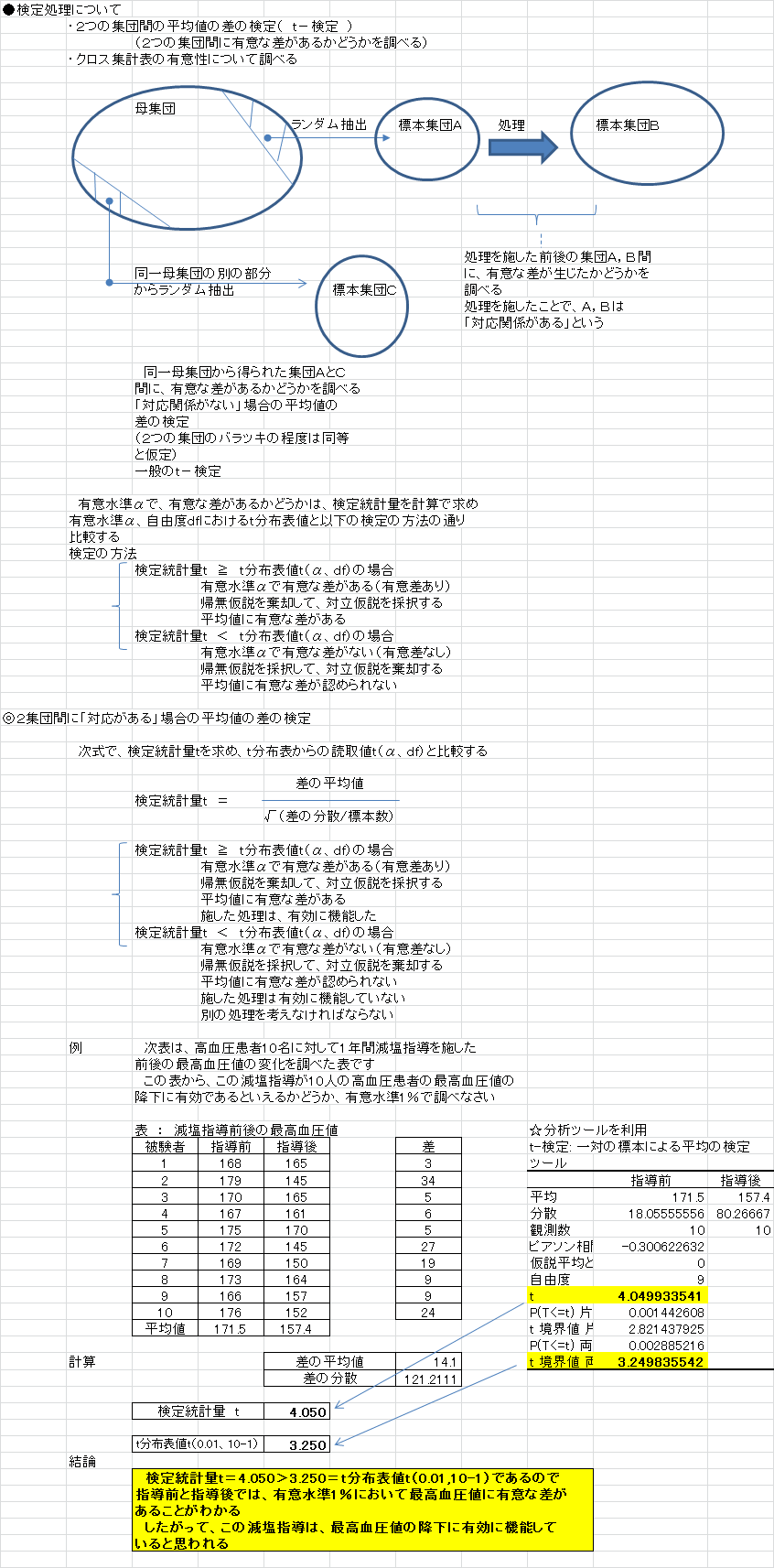《基 本 統 計 学 12》
●母平均値の推定処理
母集団 ----------------------------→ 標本集団
母平均値μ=? ランダム抽出 データ x1、x2、・・・ xn
母分散=? 標本数 n
標本平均値 m
↑ 区間推定する 標本標準偏差 Std
----------------------------------
ある統計的条件で推定する
その場合、使用する語句は以下
有意水準、危険率、信頼度(信頼水準)、α、もしくはp
また、統計学の慣例として、次の2条件で処理をする場合が多い
α=0.05、α=0.01
α=0.01の場合 ・・・・ 有意水準1%、危険率=1%、信頼度=99%
100個のデータのうち99個まではその様にいえるが、あとの1個について
はその様に言えるかどうかわからない。
α=0.05の場合 ・・・・ 有意水準5%、危険率=5%、信頼度=95%
100個のデータのうち95個まではその様にいえるが、あとの5個について
はその様に言えるかどうかわからない。
母平均値μについて、統計量(m−μ)/(Std/√(n))の分布は、自由度dfのt分布に従う事が知られている
そうすると、次の不等式が成立する
−t(α/2) ≦ (m−μ)/(Std/√(n) ≦ +t(α/2)
:
:
↓ μについて不等式を解くと
m−t(α/2)×Std/√(n) ≦ μ ≦ m+t(α/2)×Std/√(n)
m : 標本平均値
Std : 標本標準偏差
n : 標本数
α : 有意水準値
t(α/2) : 有意水準α、自由度dfにおけるt分布表値
例1 ある集団の平均値を推定したい。集団から16人をランダム抽出し、その平均身長と標準偏差を計算すると、そ
れぞれ170cm、12cmであった。
このとき、信頼度95%(有意水準5%)で、元の集団全体の平均値(母平均値)を区間推定しなさい。
解
データ
------------------------
標本数 16
平均値 170
標準偏差 12
有意水準 0.05
(信頼度95%)
------------------------
計算
t(0.05、16-1)のt分布表値 2.131 ←---- =tinv(0.05、16-1)
従って母平均値は
163.6 〜 176.4
=170−2.131×12/√(16) =170+2.131×12/√(16)
結論
信頼度95%では、元の集団全体の身長の平均値は、163.6cmから176.4cmと区間推定できる。
例2 ある母集団からの標本数20名について、タンパク質摂取量(g)を測定したところ、平均値が77g、標準偏差
は11gであった。
1)この集団のタンパク質摂取量を信頼度95%で推定しなさい。
2)この集団のタンパク質摂取量を有意水準1%で推定しなさい。
解
基本統計値
-------------------------------
標本数 20
平均値 77
標準偏差 11
------------------------------
計算
1)
信頼度95%におけるt分布表値
t(0.05、20−1)=2.093024 ←-------- =tinv(0.05、20−1)
従って母平均値は
70.7 〜 83.3
=77−2.093024×11/√20) =77−2.093024×11/√(20)
2)
有意水準1%におけるt分布表値
t(0.01、20−1)=2.860935 ←-------- =tinv(0.01、20−1)
従って母平均値は
68.4 〜 85.6
=77−2.860935×11/√20) =77−2.860935×11/√(20)
結論
1)信頼度95%では、元の母集団のタンパク質摂取量の母平均値は、70.7gから83.3gと区間推定でき
る。
2)有意水準1%では、元の母集団のタンパク質摂取量の母平均値は、68.4gから85.6gと区間推定でき
る。
例3 ある地区で無作為に抽出した40歳以上の男性の血清聡コレステロール値は、以下の通りであった。
この地区の40歳以上の男性の血清総コレステロール値の母平均値は、どの範囲にあるか、信頼度95%で区間
推定しなさい。
データ(mg/dl)
-------------------------------------------------
178 190 164 170 230 190 210
198 240 186 170 200
-------------------------------------------------
解
基本統計値
-------------------------------
標本数 12
平均値 193.8
標準偏差 23.594
-------------------------------
計算
信頼度95%におけるt分布表値
t(0.05、12−1)=2.200985 ←--------- =tinv(0.05、12−1)
従って母平均値は、
187.2 〜 200.4
=193.8−2.200985×23.594/√(12) =193.8+2.200985×23.594/√(12)
結論
信頼度95%において、この地区の40歳以上の男性の血清総コレステロール値の母平均値は、187.2か
ら200.4(mg/dl)と区間推定できる。
●t検定処理
二つの集団間の平均値の差の検定 ・・・・ 検定処理(t検定)
母集団 -----------------------→ 標本集団A ------------------------→ 標本集団B
ランダム抽出 ある処理を行う
母集団 -----------------------→ 標本集団C
同一母集団の別の部分から
ランダム抽出
・処理を施した前後の標本集団A,B間に差が生じたかどうかを調べる
・・・・ 2集団間に対応関係がある場合の平均値の差の検定
・同一母集団から得られた標本集団A,C間に差が有るかどうかを調べる
・・・・ 2集団間に対応関係が無い場合の平均値の差の検定
(2集団は等分散と仮定 通常のt検定)
有意水準αで有意な差が有るかどうかは、検定統計量(値)を計算で求めて、有意水準αと自由度dfでのt分布表値
と以下の検定の通り比較する
※検定の方法
検定統計量t≦t分布表からの読取り値 ・・・・ 有意水準αで有意差あり
(計算による) t(α、df) 帰無仮説を棄却して、対立仮説を採択
平均値に有意な差が認められる
検定統計量t≧t分布表からの読取り値 ・・・・ 有意水準αで有意差なし
対立仮説を棄却して、帰無仮説を採択
平均値に有意な差は認められない
☆p値を使用して検定する場合
p値≦有意水準α ・・・・ 帰無仮説を棄却して、対立仮説を採択
p値≧有意水準α ・・・・ 帰無仮説を採択して、対立仮説を棄却
なお、p値は以下の統計関数を用いて求められる
p値 ←-------------- =tdist(検定統計量t、自由度、2)
1 : 片側検定
2 : 両側検定
◎2集団間に対応関係がある場合の平均値の差の検定
次式で、検定統計量tを求め、t分布表からの読取り値t(α、df)と比較する
差の平均値
検定統計量t = -----------------------
√(差の分散/標本数)
検定統計量t≧t(α、df)の場合 ・・・・ 有意水準αで有意な差が有る(有意差あり)
処理前後で、平均値に差が認められる
この処理は有効に機能した
対立仮説を採択する
定統計量t≦t(α、df)の場合 ・・・・ 有意水準αで有意な差は認められない(有意差なし)
処理前後で、平均値に差は認められない
この処理は有効に機能していない
(別の処理を考えなければならない)
帰無仮説を採択する
t(α、df) : 有意水準α、自由度dfのt分布表からの読取り値
統計関数を用いて =tinv(α、df)
例 次の表は、高血圧患者10名に対して、1年間、減塩指導を施す前と後の最高血圧値の変化を表している。
この表から、この減塩指導がこの高血圧患者10名の最高血圧値の降下に有効であるかどうかを有意水準1%で
検定しなさい。
表 : 減塩指導前後の最高血圧値
-----------------------------------------------------------
被験者 指導前 指導後 差(指導前−指導後)
--------------------------------------------------------
1 168 165 3
2 179 145 34
3 170 165 5
4 167 161 6
5 175 170 5
6 172 145 27
7 169 150 19
8 173 164 9
9 166 157 9
10 176 152 24
-------------------------------------------------------
計算
差の平均値 = 14.1
差の分散 = 124.2111
検定統計量t= 4.049934
t(0.01、10−1)=3.250 ←------t分布表から読み取る
=3.249836 ←------=tinv(0.01、10−1)
◎分析ツールを利用
t-検定 : 一対の標本による平均値の検定ツール
----------------------------------------------
指導前 指導後
---------------------------------------------
平均値 171.5 157.4
分散 18.05556 80.26667
観測数 10 10
ピアソン相関 −0.30062
仮説平均 0
自由度 9
t 4.049934
p(T≦t)片側 0.001443
t境界値 片側 2.821438
p(T≦t)両側 0.002885
t境界値 両側 3.249836
-----------------------------------------------
結論
検定統計量t=4.050>3.250=t(0.01、10−1)より、有意水準1%で有意な差がある事が分かる。
従って、この減塩指導は、この高血圧患者10名の最高血圧値の降下に有効に働いていると結論付ける事
ができる。
詳細は下図を参照
【トップページへ】
【前のページへ】