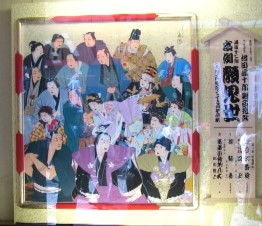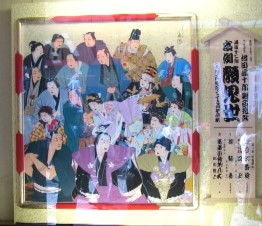「船乗込み」は、平成十三年の「坂東三津五郎丈」以来五年振りでした。名古屋での「船乗込み」は戦前は知りませんが戦後は初めての行事でした。「お練り」が、それまでに有ったのかどうかは私は知りません。
それ以降の「尾上松緑」「勘三郎」の「お練り行事」は、既に当HPの紹介してありますのでご覧下さい。
「市川海老蔵」は屋号に示される「成田山名古屋別院(犬山)」で平成十六年、餅撒き・参道お練りが行われ名古屋での行事は有りませんでした。
私は今回も、前回同様、納屋橋南の天王崎橋で州崎橋岸の緑の間から現われる姿を待ちました。
ここは南北の二つの橋を見渡せるカメラポイントで、TVも二局来ていました。今回はPRの遅れか、船到着時には一杯になりましたが見物衆は前回より少ないと思いました。納屋橋桟橋は前回の時は、まだ仮桟橋でしたが、今は船着場も拡充されそこには、かなり大勢の人が溢れていました。
混雑を避けるためか、今回は桟橋上道路に大型バスが待機、一行は「名古屋観光ホテル」まで移動。
そこから人力車に、藤十郎・翫雀丈が乗り込み御園座まで「お練り」が行われました。
橋上・川岸・沿道からは「山城屋ァー」の、大向こう(八栄会)の掛け声が響きました。
やたらと警察・警備員が多く、却って手間取り、進行が滞ったと思います。
三津五郎丈の時は、桟橋上道路から人力車に乗り広小路北へ渡り東へ進みました。混雑はあったものの、滞る事は無く、紙吹雪の中を付いて行けました。
今回はバスはなかなか来ないし広小路横断は規制されるし道中に付いて行けませんでした。
御園座挨拶会場では、藤十郎・翫雀丈と、松原名古屋市長、盛田(ねのひ)株式会社会長さん方がご挨拶。
初めて拝見したのは興行演目出演者の紹介口上、東西東西(とざいとうざあーい)から始まる独特の節回しで朗々と読み上げられ、「隅から隅まで御願い申し上げ奉りまーす」と析が打たれて挨拶に入りました.
藤十郎丈は「こんなに歓迎して頂いて本当に名古屋は良い所やなぁ、いっそ名古屋に住もうかと思います。二百三十一年振りの上方大名題坂田藤十郎襲名、新しい出発で御座います。ご贔屓の程をを宜しくお願い申し上げます」の挨拶。
長男翫雀丈も「父の七十を過ぎての襲名という、勇気と努力に皆様の応援を宜しくお願い致します」の挨拶。
名古屋市長の挨拶の後。「子の日」盛田さんの御祝儀の三本〆が行われ目出度くお開きとなりました。
|