![]()
![]()

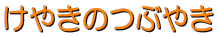
草土庵主のブログ
草と土を友として
蘭 人 一 如
2011.10.28記
またやってしまった!!
みっともない、恥ずかしい話である。
今朝のこと、とんでもないことに気付いて愕然!26日に更新した、ネットショップ5に載せた
「釘彫り風蘭古名六角鉢」の一箇所にミスを見つけた。
肝心な富貴蘭の文字の部分、乾蘭との間の縦線が抜けている。
年のせいでもの忘れやウッカリミスが日常的になった。
同年代の友人たちも同じ嘆きを口にすることが多いから、年相応の現象なのだとは思っているが、
これが仕事の方にも現れてきたので、何事にも念を入れてチェックするようにしている。
製作中の工程ごとにチェックするので、ミスを見つけるチャンスは、何回もある。
それでもこういうチェック漏れが生じる。
釉掛けの時にも気付かず、窯出しの際のチェックも通り抜け、写真撮影でもOKとされ、
更新後2日たってやっと気付いた次第。
それでも、よそから指摘される前に、自分で気付いたのがせめてもの慰め・・・、といってもやはりショックである。もしかすると、気付いていても指摘するのを遠慮された方がたくさんおられたのかもしれないが。
こういう使用上差し支えのないミスや、落款の押し忘れの作品をおもしろがって歓迎する向きもあるが(話のタネになる?)、それに甘えてはいられない。
ミスは多発するが、まだ技術的には衰えていない、と自分では思っているがどうであろうか。
進歩の自覚が持てなくなったときが怖いが、そのときはもう思い悩むこともない世界に、
片足を踏み入れているのかもしれない。いまから気に病むことはやめよう。
![]()
![]()
2011.10.12記
おもしろいは危ない
私は学生の頃、深大寺門前の楽焼き屋深大寺窯でアルバイトをしていた。
正確に言うとアルバイトの合間にときどき学校に行っていたということになる。
ときどきというのを正確に言うと、試験前だけ情報収集に行ったということである。
それで卒業できたというのも不思議なことである。
我が母校は、卒より中退の肩書きの方が大成し、有名になるという妙なジンクスのある学校である。
どっちみち卒の肩書きが役に立たない道に進んだのであるから、いっそのこと私も中退していたら、
もう少しましになっていたかもしれない。
この深大寺窯で土をいじる面白さに取りつかれたのが、この道に入った発端である。
ここで焼き物の世界に通じているOさんと親しくなった。
Oさんは度々瀬戸へ行き、ある有名茶陶作家と懇意になった。
そこで見聞きしたことをいろいろ教えてくれたが、そのなかで特に記憶に残っていることがある。
瀬戸では有名な先生であるから、よく若い作家が自作の陶器を見て欲しいと訪れるという。
そんなときに褒めるところがないと先生は
頭からけなすのは気の毒だが、よくないものをよいとは言えない、窮余の策というところであろうか。
おもしろいと言われて、はぐらかされたとは感じても、怒ったり絶望したりする人はいないであろう。
中には褒められたと思う人もいたかもしれない。
焼き物の方ではよく「おもしろい」という言葉が使われる。
例えば、窯の中で焼成中に、たまたま歪んだり、窯傷が入ったりしたものを、完成品には無いおもしろさがあると
評価したりする。また、無名陶工が作った民具の、巧まざる味わいを愛でるときにも、おもしろいといったりする。
文人作りの盆栽などに好んで使われる、南蛮鉢もこのおもしろさであろう。
これらは、危なげのないおもしろさである。
もうひとつ、正攻法ではなく、ひとひねりして、剽げた味を意図的にねらったものに対しても
おもしろいという言葉が使われる。
言い換えれば、形の美しさや品格を犠牲にして、ちょっとばかりくずしたところに味わいを求めた作品である。
ロクロは回転する円盤の上で、土を成型する道具であるから、当然器の水平断面はどこをとっても円形である。
口は平らになる。そこにおもしろさをねらって手を加えて、一部を変形させることが良く行われる。
この場合のおもしろさを肯定的に評価するか、否定的にとらえるか、そこが問題である。
そもそもこのような意図的な変形の元をたどれば、千利休の創意にたどりつくのではないだろうか。
利休はそれまでの、中国陶磁器の揺ぎ無い完璧さを最高の美とする価値観を根底から覆し、
不完全さの中に真の美しさがあると唱えた。
完成されて、寸分動かし難い器より、何かひとつ足りないところに美を見出すという新しい美意識の確立は、
利休の並外れた感性を持ってしてなし得た偉業といえる。
楽茶碗はそういう新しい美意識に基づいて利休が生み出した器である。ロクロを使わずに、手捻りで成型される。
そこに人の手のぬくもりを感じさせる肌合いが生まれる。
利休の指導を受けて実作した長次郎作の茶碗は、極めて抑制的な変形で、深い精神性を感じさせる。
利休の創始が茶室の中のみに限らず、その後の日本人の美意識に大きな影響を与えたことは言うまでもない。
しかし、後世の日本人は、それを歪んでいればおもしろいという、悪い方に捻じ曲げてしまった。
歪みはひとつ間違えれば下卑たものに堕する。
技を習得し美しいものを生み出せる者が、節度を持って変形させれば味になるが、一線を越えれば下手駄作である。
その境目は紙一重であろう。破調の美は紙一重が見分けられる達人が手掛けてこそのおもしろさである。
南蛮鉢も東南アジアの職工が安い工賃で数をこなした雑器であるから、使えればよいという野放図な荒っぽさを隠さない粗陶器であるが、それが無釉の土臭さとマッチして、特有の味を出している。
それを今形だけまねて作ると、妙なことになりがちである。
わたしは日本酒を好む。徳利は好きだが、お銚子というものが嫌いである。
大衆的な店で出るのは決まってお銚子である。口が不調和に大きく、三角に変形され、胴に2ヶ所凹みがある。
実に醜く、いやになる。観光地のお土産の陶器にもこの手のものが多い。
安価なものに限って余計なことをして、より見苦しくしている。
本来丸いものを、丸く作るのは没個性で、歪めるのが個性的と思うのであろうか。
個性は下向きにでなく、上昇志向で発揮したいものである。
何の世界でもそうであるが、変形というのは、まともなもののなかに一つ二つ交じっていて効果を生むものである。食器でもまっとうな形の器のなかに、巧みに捻った小鉢が取り合わせてあったりすれば愛嬌であるが、
グニャグニャ歪めたものや、故意に口を欠いた器ばかり並んだら食欲も失せるというものである。
器は、中に盛られるものと調和して、より美しく見せるのが使命である。
と同時にそれ自体も美しくなくてはならない。
器を作る者は、美しいものを生み出し、提供するべく努めるのが使命であり、務めである。
よく引き合いに出される話であるが、ある中国の陶芸家が日本の器を見て、
「きちんとした形ができないならば技が拙い、意図してやっているなら心が病んでいる」と言ったという。
病んでいることに気付かずに、病んでいる器を世に流すのはあぶないことである。
![]()
![]()
2011.10.4記
再びセンニンソウ
9月6日にセンニンソウが満開とブログに書いたが、もうタネが熟している。
9月のブログを読んでくださった方の中には、「このひとは野生ラン以外の植物については無知丸出し」と
思われた方もいらしたことと思う。 事実その通りなのである。
文中で「鳥がタネを運んできたのか」と書いたが、タネを見れば鳥が食べるような代物でないことが分かる。
一言でいえば、タンポポの種を小さくしたようなものである。
白い毛のかたまりから糸状のものが出て、その先に老眼鏡を掛けないと良く見えないような細かいタネがついている。風に乗って運ばれるタネであることは明瞭である。
この白い毛が和名のもと、仙人ヒゲと言われても、あまりピンとこない。
植物の名前には、実態にそぐわない大袈裟なものや、こじつけのような見立てがままあるが、
センニンソウもその手のひとつであろう。
近所の方からタネの所望があったが、もしご希望の方がいらしたら、あて先を書いた封筒に切手を貼って送ってくだされば、タネをお送りします。
発芽率はあまりよくないようだが、近所にセンにンソウの無い我が家にも生えてきたのだから、
出ないこともないと思うが。
前にも書いたように毒性があるので、間違っても口にしないでいただきたい。

![]()
![]()
2011.9.30記
やっぱり鉢だった!
前回ブログで偕楽園焼きの器の底穴について、あれこれ書いた。
その後再度ルーペでよくよく見て検討した結果、やはり最初から鉢として作られたものであるという確信を得た。
その根拠は以下の通りである。
①
底穴の断面が平滑、直線的でない。わずかな段差があり、表面が滑らかでない。
回転するドリルで後から穴を開ければ、こういうことはない。
② 高台の中に、元々くぼみがあったとするのは、この底部の形では不自然で
最初からルーペで丹念に調べていれば分かったことである。反省。
ということは、偕楽園焼きでは、同じデザインで香炉と鉢を作っていたということになる。
ここで、どちらが先かという疑問が新たに湧いてくる。
香炉として作られたものに穴を開けて、鉢にすることを思いついたのか。
それとも鉢としてデザインされたものに、穴を開けなければ香炉になると考えた陶工がいたのだろうか。
私としては、後者であると思いたい。鉢屋としての願望というだけではない。
偕楽園焼きが焼かれた文政10年(1827)~嘉永5年(1852)という時期は、間に天保・弘化を挟んで、
伝統園芸の最盛期である。
将軍・大名から庶民に至るまで、珍奇植物の収拾に血道を上げていた時代の、正に真っ盛りに当たる。
紀州徳川家の当主である治宝も、園芸に無関心ではいられなかったはずである。
仮に治宝が、当時の世相を嫌って、植物に背を向けていたとしても、藩の産物を贈り物として、
大名同士の懇親を深めることは、藩の外交上重要なことである。
親藩のお庭焼きの鉢を贈られるというのは、大名にとっては非常に名誉なことであったと同時に、
藩の安泰を約束されることと受け止めたであろう。 そういう計算は徳川治宝にもあったであろう。
そのために三つ葉葵の紋入りの鉢を、多数焼いたと推測することもできる。
というわけで、何とか鉢が先という方向に話を誘導したいのであるが、正直に言うと、自分でも少し無理があるかなと頭の片隅で思っている。
偕楽園焼き鉢の底部 底穴


![]()
![]()
2011.9.27記
あと穴について
あと穴とは、文字通りあとから開けた穴、植木鉢でないものに鉢として使うために、穴を開けたものをいう。
私はこれをあまり好まない。
土瓶や釜飯の器に穴を開け、山野草を植えたりするのを目にするが、こういうのは、まあ遊び心と思えば、
別に目くじら立てることもない。
ただ、晴れの舞台に上げるようなものではないとは思うが。
盆栽界では、あと穴がよく行われるようである。
穴開け用の道具も売られており、この世界では容認されていることなのであろう。
特に小品盆栽では、酒盃や煎茶器などのあと穴ものが使われている。
さすが鉢に神経を使う世界であるから、展示会では一見してあと穴と分かるものや、下手な物は見ない。
盆栽展に飾って違和感のないようなものを吟味して選んでいる。
それでもあと穴に気付くと、偽物が紛れ込んでいるのを見つけてしまったような気がする。
出品者が楽しんでいるのだから、とやかく言うことはないとは思うが、ご飯の中に紛れ込んだ砂粒のように、そのまま飲み下しにくいものがある。
私が気になるのは、廃品や安手の器ではなく、それぞれ作者が精魂込めて作った上手の器が、
作者の意図に反した使われ方をされているというところにある。
抹茶茶碗でご飯を食べるとか、徳利に野草を一輪さすとかというのとは違う。
底穴を開けるということは、作者の側に立てば、器を傷つけられることであり、二度と本来の使い方ができないようにしてしまう行為である。
もちろんこれは鉢を貶めて言うのではない。鉢にしたからではなく、別の使い方で活かすとはいえ、作者の意図が一方的に無視されることが公認?されていることに、ちょっとばかり違和感をおぼえるのである。
自分の持ち物をどのように扱おうと、所有者の自由といえばそれまでであるが、
器の作者の仕事が否定されているようで痛ましい。
私の鉢が、植物を植えられずに室内に飾られていても少しも気にならない。
植物を植える器でとして観賞していただけるのは嬉しい。
しかし、もし、底穴をふさいで、食器として使われたとしたら、これはあまり嬉しくない。
格が上がったとは考えられない。そいうことはありえないとは思うが。
私は古鉢も好きで、コレクションというほどではないが、若い頃から懐に合うものに出会うと買っていた。
そんなときに気にするのは、底穴である。あと穴であれば手を出さない。
あるとき、偕楽園焼(紀州徳川家のお庭焼)の紫交趾の鉢に出会った。
三箇所に大きく三葉葵の紋が入っているもので、状態もよかったが、底を見ると穴の縁が不自然である。
陶工は穴をあけたら軽く面取りをするか、ひとなでするもので、手を傷つけそうに鋭い角をそのままにはしない。
明らかに前述の穴空け機で、香炉にあと穴を開けたものである。
前々から欲しいと思っていた一品であるが、見送った。それから16年後に、同じ手のものに再び出会った。
今度のは状態はかなり悪かったが、その分安かったし、何よりあと穴ではなかったので入手した。
最初から鉢として作られたものを、鉢として使い、観賞することに意味がある。
交趾焼きは低温軟質の陶器なので、長く鉢として使えば傷ついたり、釉が剥げたりしやすい。
入手したものは実際に屋外で鉢として使用されていたのであろう。そう思えば、ひどい釉はげも許せる。
どういう人の手を経て、どいう使い方をされて来たかを想像するのも、古いものを持つ楽しさのひとつである。
我が家にひとつだけあと穴の器がある。
東京山草会の大先輩で、鉢にも造詣の深かった、O氏からいただいたもので片手に乗るくらいの、
伊万里の透かしの器である。
透かしの部分が多いために、高温に耐えられず、焼きゆがみが甚だしい。
窯出しの際に捨てられるべきものであるが、どういうわけか人の手から手へと伝えられてきたらしい。
その中の誰かが、富貴蘭鉢として使えば面白いと思ったのであろう。明らかにあと穴と分かるものである。
分からないのは、この器の用途で、O氏は虫篭ではないかと言われていた。
そういえば、口作りは蓋受けがあるようにも見える。蓋にも透かし鉢が入っていたのかもしれない。
その頃虫篭つくりに凝っていたので、あと穴の鉢としてではなく穴を開けられてしまった虫篭の参考品として、
有難くいただいてきた。
虫篭と思われる透かしの器。 底穴 あと穴を開けたときに、
穴の縁の釉薬が剥げ飛んだのが分かる


偕楽園焼き


どんでん返し
ブログに添える写真をディスプレイ上で選んでいて、ン?偕楽園焼きの底穴のアップ写真に目が張り付いた。
やられた!
穴の縁の内側にまで釉が掛かっているので、てっきり最初から穴が開けられていたものと思い込んだのが誤りであった。 釉は縁から2、3ミリのところで止まっており、その下の素地の肌が不自然である。
内側の穴の縁も変にぎざぎざしている。 あと穴である。そう思ってみれば他にも怪しい点がある。
やはり香炉として作られたものである。
穴の内側に釉が掛かっているのは、恐らくその部分が浅く窪んだ作りになっていたためであろう。
ソバ猪口の底のように。 巧みに穴を開けたものである。
肉眼では分からなかったので、ブログで取り上げなければ、ずっと鉢と思い込んでいたであろう。
考えてみれば、全く同じ形、デザインで、香炉と鉢があるというのも妙なことだ。
徳川家のお庭焼きで、そんな安直なことはことはするはずがない。
図らずも、思い込みは目を曇らせるという好例となってしまった。
![]()
![]()
2011.9.21記
懐かしい鉢
Y山草店に雪割草鉢の納品に行った。 この店の店主とは、趣味家だった頃からの長いつきあいである。
プロになってからは、欅鉢を扱っていただいている。他所では見られないような、珍しい野生ランがあるので、
それも納品の楽しみの内である。
「こんなのが入ったよ」といって、店主が思いがけないものを持ってきてくれた。
私が40代の頃(今は71))に作ったえびね鉢である。 鉄絵で葡萄の葉と蔓を、実を釉裏紅で描いている。
釉裏紅が黒く発色しているのにかすかに覚えがあり、見ているうちの記憶の底からよみがえってきた。
程よく時代が乗って、なかなかよい感じになっている。
私の手元を離れてから、鉢としての役割をしっかり果たしてきたようである。
使われて、まっさらのときより良くなるというのが、鉢のよいところである。
盆栽の世界では、新品は味わいに乏しいということで、故意に古びをつけたりする。 またそういう仕事もあるようだ。
旧作に遭遇し、昔里子に出した子が立派に成長しているのを見たような気分である。
内心連れて帰りたいと思ったが、納品に来て、自分の鉢を買って帰ったのでは笑われる。
ぐっとこらえて、写真だけ撮らしてもらった。 若い頃の自作の鉢を見ると欲しくなる変な癖は治りそうにない。


面白いのは、このランは花と葉が同時に地上に出ることがない。
ヒガンバナのように、花と葉とはいつもすれ違いであり、葉は自分の花を知らず、花はわが身を育む葉を見ない。
この点も風変わりなランである。
日本にもムカゴサイシンは自生するが、これはそれとは大分異なる。
日本産のムカゴサイシンの葉は地模様がない無地葉、花弁は茶褐色でかなり地味なものである。
それに対して、このムカゴサイシンは葉だけでも十分観賞に耐える。
ひいき目かも知れないが、群れ咲く花も妖精のように愛らしい。
平成2年に南西諸島産ということで、1球いただいたものであるが、後に図鑑で調べると、
台湾のムカゴサイシンに完全に一致する。
最初は南西諸島産と信じ、後に台湾産と確信していたのであるが、近頃もしかするとという気もしてきた。
何しろ、台湾のランと思っていた種が続々と国内でみつかり、日本のランと書き換えられている現状である。
中には熱帯アジアのランと思っていたものまで出てきている。
ランのタネは、ホコリのように細かく軽いので、風に乗って何処にでも飛んでいく。
ランには、国境は関係ないので、タネが落下した土地の環境・気候その他の条件が合えば、
発芽生育するのに何の不思議もない。
伊豆諸島には、南西諸島からタネが運ばれてきて定着したと考えられる種が少なくない。
いくつかのランの分布が、少しずつ北へ移動している事実からも、ランの北上の傾向が見て取れる。
つまり、私が栽培している台湾タイプのムカゴサイシンが、国産である可能性もゼロではないということが言いたいのである。
私は研究者ではなく趣味栽培家なので、長年こだわって作ってきたランのルーツが、二転三転する方が面白くてよい。かつて台湾のムカゴサイシンが持ち込まれて、少数でも流通したという事実があれば、雲消霧散する話である。
その後台湾タイプのムカゴサイシンが国内で見つかったと言う話もない。
たった1例というのが、この素人仮説の弱点であるが、実は過去に似たような話がある。
沖縄本島で、アリサンスズムシ(台湾に自生するスズムシソウの仲間)が1個体だけ見つかり、採取されている。
不幸にしてこの株は枯死してしまい、その後みつかっていないので、非公認に終わってしまった。
この話は採取者に極めて近い人から聞いており、その人もランに精通しているので、信じるに足る情報と思っている。
20年以上前の話であるから、もしその個体が人目に触れずにタネを散らしていたら、いまごろアリサンスズムシは日本のランとなっていたかもしれない。
一方は人に見つかって絶え、他方は人に採取されて、我が家の棚で殖え続けている、と言うことになれば、また話としては面白いのだが。どちらも日本のランになりそこねたという点においては遺憾であるが、これは仮定の話。
日本のムカゴサイシンは栽培困難で、手に負えないが、これは鉢栽培にもよく馴染み、また滅法増えもよい。
20年の間に、延べ100球以上に殖えている。
毎年ラン・ユリ部会が池袋西武百貨店の屋上で開いている、野生ラン展に即売品として出すが、
これが非常に人気があって、出しただけ必ず完売である。
なかには聞きつけて、ムカゴサイシン目当てに来られる人もいる。
西武屋上はランマニアが出没する場所であるとは知っていたが、正直これには驚いた。
この妙なランを好む人がこんなに多いのかと、恐れ入ると同時に意を強くしたことであった。
自然界では相まみえることのない花と葉を、栽培下では対面させる手がある。
通常冬季は温室内で最低5、6℃のところに置いている。 開花は3月である。
最近は暖冬なので、試みに1鉢を風除けだけの無加温で越冬してみた。
やや勢いは弱いが、5月に咲いた。 この頃温室で越冬した鉢は葉を展開している。
思惑通り、花と葉を同時に見ることができた。 元はといえば、野生ラン展に両方を展示するための試みである。
この行為はムカゴサイシンには喜ばれたであろうか。 葉は花を愛しいと感じたであろうか。
花は葉を慕わしいと思ったであろうか。 それとも余計なお世話と憤慨したであろうか。
ムカゴサイシンの葉 2011.9.9 ムカゴサイシンの花 2008.3.23


![]()
![]()
2011.9.12記
窯出し・納品・古鉢市
窯詰めをしてから焼くまでの間、ノロノロ台風の通過するのを待って1週間。こんなことは初めてである。
この間に2回も地震があり、肝を冷やされた。
すずき園芸のラン鉢展の納期も迫り、朝窯出しして、その日に納品ということになった。
窯の温度の上昇は順調で、焼き上がりもまずまずというところ。
期待していたつや消し釉の釉裏紅唐草文の寒蘭鉢は、またもやテストのような発色にならず不発。
杭州寒蘭(水晶寒蘭)用の鉢7点、富貴蘭鉢3点、野生ラン鉢2点(工房作品)、計12点を納品した。
すずき園芸には、古くからの欅鉢コレクターがいらして、見る目も厳しいので、いい加減なものは出せない。
当然そういう方々は定番の釉薬・技法の鉢は一通りお持ちなので、「これはある、あれも持ってる」
ということになりがちで、新作に関心を寄せていただくのはなかなか難しい。
寒蘭鉢というものは、線の美しさが命というところがあり、繊細で高貴な寒蘭の容姿からいっても
装飾は控えめでないといけない。つまり作り手に許容される遊びの幅が極めて狭い。
今までに思いつくことは皆やってしまい、アイデアの引き出しは空っぽに近い。
乏しい創造力を持ってしては、古くからのお得意様をして、「これは初めて見る鉢だ。是非コレクションに加えなければ」と言わしめるのは至難である。
その点富貴蘭鉢は透かしの伝統文様に様々なバリエーションが考えられる。
ひとつ新しい意匠が生まれれば、つる草が枝を広げるように、次々にアイデアがアイデアを呼び、
作る手が追いつかないことになる。文様と釉薬との組み合わせでも様々な変化がつけられる。
この時期毎年すずき園芸で行われる古鉢市に、40数点の欅鉢が並んでいて驚いた。
若い頃の最初期の鉢も何点か並んでいた。当然いまから見れば技術的にはつたないものであるが、
やみくもに先の見えない世界に飛び込んでいった意気込みがあるように感じられた。
こういうのを贔屓目というのであろう。見る人がみれば、ただの下手。
その頃の我が家の生活も思い出され、ちょっと感傷的な気分も心中をよぎるが、それ以上に、
いままで愛用してくださった鉢を、引き継いで大事に使ってくれる人の手にゆだねようとされる、
出品者のお気持ちがありがたい。美術骨董品とちがい、鉢は代が替わると、ごみとして処分されてしまうことも多い。すずき園芸の古鉢市は、鉢のリサイクルの場として機能しており、鉢屋にとってはありがたい企画である。
それにしても自分の昔の作品が店に並び、売れてゆくというのは、作者としては何とも妙な気分がする。
当時この価格で売れていたら、我が家の生活ももう少し楽だったかな、などとつまらぬことが頭をかすめたが、
値段は需要と供給で決まるもの、今までの自分の仕事への評価が、若い頃のつたない作品の、
この価格を支えていると思えば、物作りとして冥利に尽きるというものである。
正直にいうと、私自身が欲しいものが何点かあった。以前に自分の旧作を買ったこともある。
それも欲しくて買ってしまうのである。この辺のところが、われながら趣味が勝った仕事であると感じる所以である。
長年それを正業として飯を食い、家族を養ってきたのであるから、プロということになるのであろう。
しかし、心情的に言えばプロというよりは、趣味家に近いと思わざるを得ない。
趣味が仕事か、仕事が趣味か、渾然一体自分でも判別がつかないところがある。
それでよいと思っている。その方がよいとさえ思う。蘭鉢などという、世間とは少々価値観の異なる、
狭い深い世界でやって行くには、自分自身がその趣味の世界に、頭の天辺までドップリつかっているほうがよい。
だからこそ顧客の求めているものも分かる。
鉢作家は、陶芸家が鉢を作るより、蘭の趣味家が陶芸を学んだ方がよいというのが私の持論である。
自らが天職と感じていることを業として、いままでやってこられたことを、改めてありがたいことと思った古鉢市であった。
すずき園芸 古鉢展



![]()
![]()
2011.9.6記
センニンソウ
我が家のフェンスにからんだセンニンソウが満開である。
センニンソウはクレマチスの仲間の野草であるが、一族の末席に名を連ねるだけという感じで、
血筋から想像されるような華やかさはない。
自生地では、長い蔓が草むらをおおって這いまわり、花の時期になって、はじめて存在を知られる植物である。
鉢に収まらないせいかあまり栽培されないが、私は強い陽射しの下で白い小花が群れ咲くこの草が何となく好きだ。といっても、植えつけたわけではなく何処からかタネが運ばれてきたのか、2、3年前に生えてきたので、
抜かずにほうっておいたものである。
十文字形の花は鉢の連続文様にも使えそうである。
昨年はオガタマの木に絡み着いて、高いところで咲いたので、今年はフェンスに誘導したところ、
門扉にまでからんでしまったが、開け閉めに支障はないので、そのままにしている。
仙人も心得ているようで、閉門にする気はないらしく、そこでとどまっている。
節電になるとて、ゴウヤや朝顔が日よけ植物として人気であるが、旺盛に蔓を伸ばすセンニンソウも
そこに参加する資格があると思うがどうだろう。
ただしセンニンソウは有毒植物で、誤って食べるとひどいことになるというから、
あまり推奨しないほうがよいかもしれない。
和名の由来は、果実に生える毛を仙人のヒゲに見立てたというが、まだ見たことがない。
今年は蔓の一部を残して、仙人に対面してみよう。


![]()
![]()
2011.8.29記
透かし鉢のルーツ
ランの話題が続いたので、今日は鉢の話をしよう。
透かし鉢は江戸時代にすでに作られている。が、ここで言うルーツは、そういう話ではない。
欅窯の富貴蘭・長生蘭用透かし鉢の起源である。
どうということもない話なので、いままでどこにも書いたことがない。
昭和48年、33才のときに初めて家を建てた。
と言っても新築ではなく、それまで住んでいた古い家を建て直したのである。
それも、資金の関係で一度には無理なので、作業場のある南側半分だけを取り壊して建て直した。
そのときに、自分でランプシェードを作って新しい家を飾ってみようと思い立った。
陶器で作り、透かしを入れれば、透かし文様から光が漏れ、天井に写っていい雰囲気ではないかと考えたのである。
そのための配線もしてもらった。
どちらかというとアイデア倒れで、期待したほどの効果もなく、もう一度作り直す気もおこらず、
打ち捨てられたまま今も無駄に天井からぶら下がっている。
ランプシェードとしては失敗作であったが、この技法で風蘭用の透かし鉢をつくれば面白いのでは、
という方に発展し、これは予想以上に受けた。
透かし鉢は栽培上の利点というよりはイメージ的に風の蘭の名に相応しいところが、
愛好家の琴線に触れたのであろう。
今でも良く覚えているのだが初期の透かし風蘭鉢は1個1万円、これでも相当思い切った値をつけたつもりであった。まだ磁器には手を染めていなかった。
作ったもののほとんどが、身近にいたラン友たちの棚に納まったと記憶している。
もちろん後に透かし鉢が、欅窯の看板作品になるとは思ってもいなかった。
我が家には当時の透かし富貴蘭鉢は1個も残っていない。
もし今でも初期の透かし富貴蘭鉢をお持ちの方がいらしたら、是非「私のお気に入りの欅鉢」のコーナーに投稿していただきたいものである。
そんな経緯で生まれたものであるから、当時透かし鉢は欅窯のオリジナルであると思っていた。
後にいろいろ江戸期の伝統園芸や、和鉢について調べていくうちに、「金生樹譜」という当時の出版物に(お得意さんがコピーを送って下さった)、透かし鉢が出ているのをみつけた。
そこには二重鉢らしきものの図も載っていた。
もっとも、この当時透かし鉢が、どのように使われていたかは不明である。
富貴蘭が透かし鉢に植えられたという記録も見当たらない。
当時の錦絵を見ると、約束事として決められていた専用鉢というのはほとんどなく、それぞれが各自のセンスで、
自由にうわものと、鉢の組み合わせを楽しんでいたように見受けられる。
だからこそ和鉢の最盛期を迎えたのであろう。
ある意味では、専用鉢が和鉢を殺したという面も否定できない。
自分は独自に新しいスタイルの鉢を生み出していたつもりでいたが、実は無意識のうちに、
江戸期からの伝統の流れの末に身を置いていたことに気付いた。
以来、自分の仕事を江戸和鉢の流れの末にあり、これを伝承するものと強く意識するようになった。
個人の仕事という意識から、伝統園芸史の1ページの片隅に身を置いているという視点に変わったのである。
だから仕事の内容がどう変わったということもないが、気持ちの持ちようは一変したように思う。
その後過去に様々な透かし鉢が作られていたことも分かってきたが、全体が見えてくると、やはりいままでのものとは全く異なる”欅窯の透かし鉢”であることを改めて知った次第である。そのきっかけになったランプシェードを、それなりに遇してやらなければいけないかとも思うのだが、やはりこれからも使われることも、かえりみられることもなく、むなしく天井にぶら下がっていることあろう。
透かし鉢の元になったランプシェード。


当時の透かし鉢 はっきりした用途も考えず、ただ透かしてみたかった。

「金生樹譜」に載っている透かし鉢。 同二重鉢らしきもの。


![]()
![]()
2011.8.24記
ネバリサギソウ
奇妙な名前のランである。
名前の通りサギソウファミリーの一員であるが、中国、台湾に分布しており、国内には自生していない。
温暖化のせいか、台湾のランが西南部の島嶼で次々にみつかっており、このランもやがて
日本のランの仲間入りする日が来るかもしれない。
むかし台湾の野生ランが多量に入ってきた頃は、目にすることも多かったが、最近はみかけることが少なくなった。冬季最低5、6℃保てれば、栽培は難しくはないが、サギソウと違って、増殖は極めてゆっくりである。
全体に緑一色のやや大型のランで、華やかなところはないが、花の形がおもしろい。
林讃標「台湾蘭花植物」には「(花の)構造は甚だ奇異」と書かれているが、私には、この花は象のように見える。
側がく片は大きな耳、唇弁中裂片は長い鼻、反り返った2枚の側裂片は牙に見立てられる。
しかし、この見方はあまり支持されていない。
もう一つの特徴は、甘い芳香である。クチナシの香りに似ていると思うが、匂いに対する感受性は
個人差が大きいようで、この点もあまり賛同を得ていない。私のランの見方は、少し偏っているのだろうか。
少しじゃないという声も聞こえてきそうだが。
香りは夕方に際立ってくるので、サギソウ同様蛾を誘引しているであろう。
サギソウにしても、フウランにしても、蛾に授粉を任せているランは、白い花が多い。
言うまでもなく、夕闇の中で、蛾に存在を知らせ、子孫を残すためには緑より白い花の方が有利なためである。
それなのになぜネバリサギソウの花は緑のままにとどまったであろうか。
もし目立ちたがり屋の一群が、白い花をつけ出したら、遠い将来ネバリサギソウは白い花になるのかもしれない。
そうなったら緑花のネバリサギソウは、先祖返りの例として珍重されるであろうか。
その頃地球上に野生ランマニアと呼ばれる人達が存在すればの話であるが。
もうひとつの謎は、和名の由来である。そもネバリとは何を意味するのか。
植物体のどこを触れてもべとつくところはないから、「粘り」でないことは確かである。
残るは「根張り」か。地下には長さ7、8cmの、長楕円形の球根があるが、特に根が長いということもない。
上記の書には、「球根は土中に深く埋まっていて、掘り取るのは容易でない」という意味のことが記されている。これがヒントになるであろうか。長年考えているが答えが見つからない。
これで思い出すのは、「ニオイラン」の名である。
やはり台湾産の着生ランで、東京山草会ラン・ユリ部会にもかつてはよく登場していた。
そこで必ず出るのが、「匂いがないのになぜニオイランか」という疑問であった。
数年前、台湾の方に聞いて、初めて長年の謎が解けた。
ニオイランは台湾では香りのよいランとして人気があり、縁日などで売られているということ。
異郷の地につれてこられて、香りを忘れたということであった。
ネバリサギソウの名についての疑問も、いつの日か納得のいく答えが得られるであろうか。


ネバリサギソウ
![]()
![]()
2011.8.18記
美しくもはかない幽霊
長年愛培していたユウコクランが幽霊になった。といっても、枯らした栽培者を恨んで化けて出たわけではない。
いまはまだ枯れずに生きている。
葉や茎など、植物体全体の葉緑素が抜け落ちてしまう現象を、この世界では幽霊と称する。
葉緑素が欠如しているのであるから、光合成を行う能力がゼロである。当然遠からず消え去る定めである。
だから幽霊。植物にとっては、致命的な障害である。
芽出し時に葉緑素がなく、白い葉を展開し、後に葉元の方から緑が乗ってくる芸がある。
曙斑とよばれる、斑入りの一種である。明け方に現れ、日が上がると消えて行く曙になぞらえた名称であろう。
曙斑の場合は、「芽出しが美しい」と賞賛される。曙斑は芸として歓迎する趣味者にも、幽霊は嫌らわれる。
しかし、全身真っ白なランは、やはり美くしい。死に向うものの美しさであるかもしれないが。
消え去る前の一瞬の輝きを、美しいと言ってあげたい。
幽霊は、通常縞斑からよく生まれる。縞斑は不安定で、年により派手になったり、暗くなったり、よく暴れる。
派手の極限が幽霊で、こうなるともう元に戻らない。
大抵の場合、1株にいくつかの芽があるから、そのうちの1芽が幽霊になっても、株が枯れることはない。
写真のユウコクランは、一部にわずかに緑が残っており、完全に幽界に入っていない。
指一本で、足が地面にかろうじて着いている。このユウコクランは、もとは白大覆輪であった。
覆輪は安定するという常識に反して、しばしば縞に変わり、そうなると年々派手に移行する傾向が見られる。
というわけで、この1芽立ちの株は、今年が見納めになるであろう。
このユウコクランは、若くして亡くなったある野生ランマニアの遺品である。
記念にその若者の名を冠した銘で呼んでいる。死の影がつきまとうのも、そのためであろうか。
そう言えば、このユウコクランの性質は、前の持ち主に似ていなくもない。
追記
ブログ「ブドウ糖」の末尾、「8月のラン ミヤマウズラ」の説明に、「江戸時代はかもめらんと呼ばれた」と
記しましたが、これについて異論が寄せられましたので、ここに紹介します。
それによると、当時ミヤマウズラのなかの、斑入りや葉変わりの個体を「かもめらん」称し、
ミヤマウズラに当たる名は「籠目蘭」であったということです。「錦蘭」の雅名がまだなかった頃のことです。
これについては決定的な資料がみつからず何ともいえませんが、私は花の形からの命名という点で、
「かもめらん」が一般名という方に傾いています。

![]()
![]()
2011.8.15記
クモランが咲いた
奇妙なランである。姿形も奇妙であるが、性質も着生ランの中の変わり者である。
葉を生じず、根が葉の役割を負って、光合成をしている。花は米粒よりもっと小さく緑色。
気がついたらすでに花期を過ぎて、果実になっていたということもある。それくらい目立たない花である。
観賞上から言えば、花は咲いても咲かなくてもよいが、花つきは滅法よく、
生きていれば毎年盛夏の花期を忘れずに咲いてくれる。
「今年もクモランの花が見られたか。これが最後かな」という感じ。
私の命が危ないという意味ではない。危ういのはクモの方である。
日本の着生ランの中で、最も栽培困難なのはクモランであると、常々思っている。
寒冷地のものに、東京では栽培不能なものがいろいろあるが、それは主として気温の問題であり、
自生環境に近い所でなら栽培可能であろう。
クモランは気象条件に関係なく、本質的に栽培に馴染まない性質のランである。
写真のクモは、縁あって3年半程我が家に寄寓しているが、栽培できているという実感はない。
何故ならば、いまクモがしがみついている細枝が腐って崩れれば、それでお終い。
ヘゴやコルクに付け直しがきかないからである。たとえ5年持っても、6年生きていても同じことである。
いまのところクモランは栽培できないと言うのが正しい。そして、生かしておくにはえらく手間隙がかかる。
自生地から離されると、生きようとする意志がかなり薄弱になるランである。
やっかいな居候を抱えたような感もあるが、好きで抱えた以上は、あの手この手で、
出来る限り延命を図るのが務めである、というよりそれを楽しんでいるというのが本音である。
栽培者との対話を拒否し、意を迎えるそぶりも見せない。クモランのそういうところが気に入っている。
うまれた所から頑として動かず、所を変えて生き残るより死を選ぶという心意気がよい。
和名の由来は説明の不要であろう。
我が家では虫の蜘蛛も「よくも来ました」と厚遇しており、決して追い払ったりしない。



毎年秋の寒蘭に向けて、暑い盛りに寒蘭鉢を作ることになる。これが結構応える。
テレビで壷などをロクロで引いているのを見ると、土がするすると伸びて柔らかそうに見えるが、
それは名人がやっているからで、実際はかなり硬い土なのである。土練りだけでも、全身汗まみれになる。
寒蘭鉢くらいになると全力を手先に集中するので、60キロにみたない痩身の70老にとって近頃は
きつい作業になってきた。
そばで見ている助手が、「プチンと音がして、頭の血管が切れるじゃないかと心配になる」という。
長年やっていることであるから、やればできるが、翌日に疲れが出る。
外で何日が立ち仕事が続く窯詰めも、気候がよいときはさほど苦ではないが、夏はできればやりたくない。
楽な仕事というのはないと思うが、何もしないでいても高齢者が熱中症になる猛暑である。
日頃仕事と雑事に追われて、週1日の休みが取れるかどうかという生活なので、
この時期長期休暇をとっても許される・・・、とよいのだが。
食欲も落ちてきたので、水分補給のため度々飲む水に、ブドウ糖を加えた。
点滴や、登山の非常用に使われるようにブドウ糖は吸収が早く、エネルギー補給に手軽に使えて便利なものである。
植物に与えるためにブドウ糖は常備している。
コバイモやカタクリなどの生長期間の短い球根植物には、水1リットルにブドウ糖を茶さじ1杯ほど加えて
潅水に用いると卓効を現す。
特に鉢作りは難しいとされるカタクリは、ブドウ糖を与えていれば長期栽培も困難ではない。
実生の開花は未経験であるが。
また、暑さで体力を消耗したアツモリソウにも与えている。
植物用のブドウ糖をくすねたたわけであるが、喉の痛みも楽になることを知った。
とんだところで、「蘭人一如」を実現してしまった。
8月のラン ミヤマウズラ 江戸時代は「かもめらん」と呼ばれた。
そういえば、カモメの群れ飛ぶ様に見える。

![]()
![]()
2011.8.8記
釉裏紅
電気炉を開けた。瑠璃釉・青磁・風蘭古名鉢などは良好な上がりである。
釉裏紅のテストは何ともいえない結果になった。
いままで釉裏紅は専らガス窯で焼いていて、電気炉ではうまく発色しなかった。
小回りの利く電気炉で焼ければ便利なので、今回色々なテストをしてみた。
テストピースで行った4通りのテストは、それぞれまあまあの発色であったが、
もっとも確実と思って小鉢でもテストしたのは失敗。鍔の部分は色が出ているが、胴の色が飛んでいる。
これで見ると、水平の部分はよいが、垂直の部分は駄目ということになる。
小型の電気炉であるが、内部の火の回り方はなかなか複雑であるらしい。
釉裏紅に限らず小片でのテストがよかったので、期待を持って作品を焼くと失敗ということは、
しばしば経験している。急いで見こみ発車すると、後で泣くことになる。
また、新しく作った釉薬で1年程の間よいものがやけたのに、あるとき突然見るも無残な汚い色に
なってしまったこともある。
同じ材料で釉薬を作り直し、同じように焼いて見ても、それ以来頑として元の発色に戻らない。
どう考えても納得のいく理由が見つからない。窯に意志があるかのような現象である。
ランは生き物であるから意志があっても不思議はないが、無生物の窯にも意志があり、
そのときの気分次第で結果が左右されるとなると厄介なことである。
勘弁してもらいたい。
ネットショップ更新のために、富貴蘭鉢を中心に電気炉を焼いた。
ガス炉は煙突で外に排気するので問題ないが、電気炉には煙突がない。
そのため還元焼成(窯内の酸素を制限し不完全燃焼させる焼き方。磁器は還元焼成)すると、
濃厚な一酸化炭素が放出され、特有のいやな臭いが周辺に漂う。
臭いの強さは日によって異なり、余り臭わないときもある。
気象条件によると思われるが、よく分からない。
戸を閉めても、一酸化炭素は小さな隙間を見つけて、作業場の中にまで入り込み、
あまり気分がよくないが、避難するわけにも行かない。
悪臭は2階の居間にも侵入して、女房を悩ませる。 勿論窯の真上のアツモリソウ作場をも襲うわけであるが、
アツモリたちがこの事態をどう受け止めているかは分からない。
そう度々のことではないので、こらえてもらうより仕方ない。
昨年だったか、埼玉県で換気の悪い室内で、電気炉の還元焼成をして数人の方が、
一酸化炭素中毒で亡くなるということがあった。還元焼成はときに危険な作業である。
我が家の窯場は三方を囲まれているが、閉鎖空間ではないので中毒死することはないと思うが、
年とともに全てが散漫になっているので、注意するに越したことはない。
やり慣れているはずの仕事の上でも、手順を誤ったり、道具を取り落としたり、ウッカリミスが多くなっている。
今はまだ自分でそれに気付いているし、作品の質が落ちているという自覚はないが、
とんでもない物をジャンジャン作り続けるようになったら怖い。
長年自らを叱咤激励して、鉢作りを続けてきたので、そうなったら止まらなくなりそうな予感がないでもない。
次の更新では、これから欅窯の透かし鉢を使って見たいと思われている方のために、
ネットショップ限定の数点を出す予定。
思いがけないウッカリミスがなかったらの話であるが。
本焼を待つ素焼き状態の作品達

ただ今、還元焼成中 窯内は1,180℃


![]()
![]()
2011.8.1記
ムカゴソウ
ムカゴソウが咲いた。
この名前を見て、「あぁ、あのつまらない花か」とつぶやいた方は、相当の野生ラン通である。
我々の仲間内では、この手のランをツマランと称する。
ラン好きをもって任じる面々が、そういうのであるから、これはもうお墨付きのつまらないランである。
写真をご覧になれば、大抵の方が「ウム」と納得されるであろう。
「そんなつまらないものを何故栽培しているの?」と正面から聞かれると、一瞬返答に詰まる。
確かに普通趣味で植物を栽培するのは、観賞のためである。
ムカゴソウが美しいとか、可愛いとか思って長年栽培しているわけではない。
強いて言うなら「それがランだから」と言うほかはない。
ムカゴソウは、北海道から沖縄まで広く分布しているランであるが、一般的には(といっても仲間内の話。
そもそも全然一般的でない)沖縄のものが作られていて春に咲くが、写真の個体は福島産で今ごろが花期である。
沖縄産と違って耐寒性があり、温室に入れる必要がないので、栽培は楽である。
平成元年に福島の知人からいただき、以来結構気に入って愛培している。
情がうつるというか、気心が通じるというか、互いにいい関係を維持している。
そういう意味では可愛いヤツである。
植わっている鉢は、コンクリート鉢。
野生ランの神様、故鈴木吉五郎氏宅のゴミ捨て場にころがっていたのを拾ってきた記念の一品である。
「コンクリート鉢にはムカゴソウが良く似合う」と、何方かが言われた、と言うことは聞かないが、
入手以来この鉢がムカゴソウの指定席である。
ご本人もこの住まいが気に入っているようで、本来余り増えのよくないランであるが、機嫌よく増殖している。
はじめ、我々はこの鉢をセメント鉢と呼び、戦時中物資が不足していたころ、
焼き物鉢の代用として作られたものと解釈していた。
たまたま私が、戦前の実際園芸をめくっていて、コンクリート鉢の広告をみつけた。
代用品ではなく、当時お洒落な新しい素材の鉢として、売り出されたことが判明した。
園芸史の1ページを飾る、貴重な遺物といってはオーバーであるが、今では得がたいものとして大切にしている。
ムカゴソウの名前の由来は、地下にある球根が山芋のムカゴに似ていることによるとされるが、
ムカゴに似た球根を持つランは他にもいろいろある。
それなのに、何故このランにムカゴソウの名が与えられたのか。
他のランは、それぞれ花や葉などに目立った特徴を持っているから、それが名前もととして採用された。
ムカゴソウは、ムカゴ状の球根より他に、これという特徴がないので、ムカゴソウ。
昔のひともツマランと認めていた、というのは通説ではなく、自説で、あまり支持を得られないかもしれない。
コンクリート鉢に植わったムカゴソウ (福島産) ムカゴソウの花のアップ


![]()
![]()