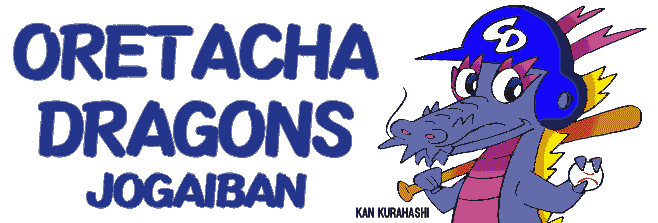
 中日スポーツ連載4コママンガ「おれたちゃドラゴンズ」のホームページ
中日スポーツ連載4コママンガ「おれたちゃドラゴンズ」のホームページ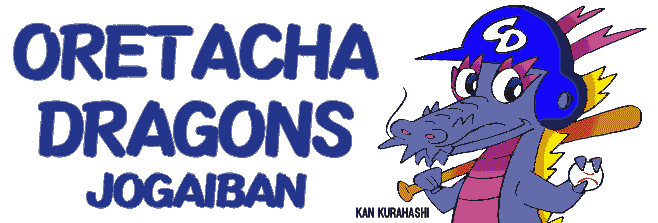
今年もおしまい 2015.12.15
前回書いた行事が終了して、もう1週間経ちましたが、まだちょっと何もやる気が起きませんねー。脱力状態が続いております。
ちょっとご紹介しておきますと、11/7の各務原市の各務小学校での「村国の郷ふれあいの集い」では、各務小の6年生が「村国男依の物語」を演じてくれました。あらすじを紹介するにも難しい話ですが、短期間によくセリフを覚えてくれたと思います。地元の子供が演じることで、大人のみなさんにも「そういう先人がいたんだ」と共感をもって理解されるのではと思います。学校の用務員の方が一人で衣装や小道具を制作してくださったとのことで、本当にありがたいことです。背景画をプロジェクターで投影する予定でしたが実現できず、その点は残念でしたが、今後に改善していければと思います。
劇の後は松田敏来さんが登場して「男依音頭」を歌い、地元の御婦人たちの踊りの輪ができました。男依づくしの催しになり、男依さんもご満足だったのではと思います。
それともう一つ、11月の中旬から12月の頭にかけて、4週連続で「日曜午後のフォークソング」という催しをいたしました。いつも地元の公民館で活動している小杁山フォーク会のメンバーで、1960年代から1980年代にかけてのフォークソング59曲を歌うという公民館講座です。事前に応募された20人ほどの方が参加されました。
最初は簡単に考えていましたが、聴いてもらうためにはそれなりのレベルにしなければならず、結局1年ほど準備にかかったことになります。60年代の歌はまだ簡単でいいんですが、後半に近づくにつれてアレンジが難しくなり手こずりました。私のリードギターもかなり怪しい曲がありましたが、参加された皆さんの温かい雰囲気で、ずい分助けていただきました。
毎週日曜に歌うというのは初めての経験だったので、1週間で声が回復しないというのにも驚きました。私はトーク役もやったので余計かもしれませんが、間の6日間はあまり話さないようにしたりと苦労しましたね。
皆さんのご協力で無事終了でき、好評につき(?)来年もまた秋に開催の予定となりました。しばらく休憩して、また選曲から始めなければいけません。大変ですが楽しい作業でもあります。
年が明けるとまた歴史関係の講演や講座の予定があります。漫画と関係のない行事が多くて、私の仕事は何なのか判らなくなりそうですが、お話をいただけるのはありがたいことなので、可能な限りご要望にはお応えしようと思っております。
そんなことで、今年は新しい小説にかかる余裕もなく過ぎてしまいました。来年はどうなりますか。
秋の催し目白押し 2015.10.27
ドラゴンズは3年連続でCS進出を逃し、今年もまた長いオフということになっています。
淡々と秋季練習から秋季キャンプと変化のない毎日が続きますので、漫画のネタもあまりありませんねー。私はといいますと、このところ漫画以外の所用がいくつかありまして、9月に地元のロータリークラブで30分ほど、さらにこの前の日曜には同じく地元の文化会館で2時間、講演をやらせていただきました。
地元ということで村国男依や蜂須賀小六、前野将右衛門のことを紹介しました。歴史に関心のある方は結構多くて、私などの話でも聞いてみようと集まっていただけるのでありがたいことです。
また11月7日には各務原市の各務小学校で、地域の人を招いて「村国の郷ふれあいの集い」という催しがあります。そこで各務小の6年生が村国男依の劇をするということで、私も出かける予定です。
僭越ながら私が台本を書かせていただきまして、これを子供さんたちがどう演じるのか非常に楽しみです。なにしろ修学旅行があったり地元の祭りで歌舞伎の稽古があったりで、劇の練習期間が1カ月というハードな状況の中、はたしてどんな出来なのか、これはもう子供さんの可能性に賭けるしかありませんね。
村国男依のゆかりの地で子供さんたちが男依の劇をするというのは、これはもう感涙ものですよ。きっと男依さんも感激されることでしょう。そして11月の中ごろからは、「日曜午後のフォークソング」という企画を4週連続で開催して、合計60曲ほどを演奏するということになっております。これは江南市の公民館の学習講座の一環で、1年ほど練習をしてきたものですが、さて無事に完走できますかどうか。
そんなことで少々忙しい時期が続きますので、このHPの更新も次回は12月かも知れませんが、ご容赦を。とりあえず今回はこんなことで失礼します。
今年のドラを見ての感想 2015.9.23
今年のプロ野球も大詰め。パ・リーグは圧倒的な強さでソフトバンクが優勝。一方のセ・リーグはレベルの低い争いながら、ヤクルト、巨人、阪神の3チームが最後のデッドヒートを繰り広げています。
中日はというと、相変わらずの最下位で横浜とこれまたデッドヒート。せめて最下位は逃れてほしいところですが、どうなりますか。
今年の中日は若手への切り替えを進めようと、捕手の桂、杉山、内野手の亀沢、遠藤、福田、高橋周らを積極的に使いました。この終盤まで残って結果を出したのは捕手の2人と亀沢でしょうか。
遠藤、福田もある程度の活躍をしましたが、1シーズン1軍で定着できる力がなく、その点が来季への課題ということでしょう。若手にチャンスを与えるのと同時に、これまでのレギュラーも使わなければいけないために、相手の投手の右左によってスタメンを代えるという策を取りました。一見、理にかなった起用法に見えますが、調子の良い選手でも次の日は控えになったりと、選手としては調子を維持するのが難しかったのではないかと思います。
なかなか左投手が来ず、控えが多かった荒木選手などは一番悔しい思いをしたのではないでしょうか。公表されていない怪我などがあるのなら別ですが。
ここ数年、若手の切り替えがテーマであった中日ですが、これまでのレギュラーにも配慮はすべきで、それは出場機会を平等に与えるということではないのではと今季の中日を見ていて感じました。
谷繁監督も「若いからといって優先して使うわけではない」という意味のことを言ってましたが、レギュラーが調子を落としたとき若手を使い、数少ないチャンスをものにして好結果を出せばその先も使うというのが一番納得がいく世代交代でしょう。若手が調子を落とせばベテランが出て、結果を出せばまたベテランを使うという繰り返しの末、若手が残るというのが良いのではと思います。
力があるのに、それまでのレギュラーがベンチで淋しそうにしているのは、見るに堪えられませんね。
さて、そろそろシーズンも終わるので、来季の飛躍に向けての再建策がいろいろと出てくることでしょう。
チーム打率も防御率もいいのに勝ちに結びつかないのは、やはり得点力が低いということですね。現状の打者では大きく向上するとは思えませんので、長距離砲の補強が必要でしょう。
また継投策が何度も失敗したように、投手陣の再建も必要です。もう一度、先発、中継ぎの適性を精査して再編するだけでも、かなりの向上になるように思います。一見、体力がありそうな先発投手型でも、3回り目で必ず打たれる投手はリリーフの方が良いかもしれません。若松のように速球派でなくても意外に先発が向いている投手が2軍にいませんか。もう一度、まっさらな目で見る必要があるでしょう。コーチ陣のテコ入れも今オフは必要でしょうね。とにかくファンが応援したくなるチーム作り、選手起用が必要ですね。そんなところが、今季のドラを見て感じた感想です。
最後に、引退する選手の皆様、お疲れさまでした。漫画での数々の失礼の段、お詫び申し上げます。
夏に漫画が面白くない理由、または言い訳 2015.8.22
お盆を過ぎて暑さも少し和らぎ、多少は過ごしやすくなってきました。
とは言っても相変わらず私はほとんど外出もせず、エアコンをかけた部屋に閉じこもっていて、冬眠ならぬ夏眠状態です。やはりこの酷暑では熱中症の危険がありますからね。室内にいても汗が出ないような危ない状態の時が、この夏一、二度ありましたよ。
気温の高い昼間をなんとか乗り越えて、夕方から仕事にかかろうと机に座って野球中継を見始めると、一日の疲れが出てきて、またエアコンの冷気も心地よくて、ウトウトと居眠りしてしまうんですね。 だいたい6時半から7時くらいの間で15分ほど意識がなくなって、「うわっ、いかんいかん」と目が覚めるわけですが、一度停止した脳は再稼働するのに時間がかかるようで、そんなときはさっぱり面白い漫画が思いつきません。締め切り時間もあるので、だいたい7時半には筋書きを完成させないとまずいんですが、そんな短期間には脳は復帰せず、つまらない漫画を描くことになります。
無理矢理でも落ちが思いつくのはまだ良い方で、思いつかない場合は仕方ないので、とにかく絵を描き始めます。下書きからペンを入れて2コマ目くらいまでは描き進めて、セリフだけ空欄のままにしておきます。あとは時間の許す範囲でジタバタして、無理にセリフをねじ込みます。
まあそんなことをやってますので、夏場は不本意な作品が多くなりますね。
昼寝するなり、夜にしっかり睡眠を取るなりすればいいんですが、特に夜は猫に二度ほど起こされますからねー、エサの催促で。そんなことで朦朧とした毎日を送ってますよ。とりあえず暑さが和らげば、もう少し状況も改善されるはずで、漫画も面白くなるんじゃないかと思いますが、そのままだったりして。
ドラゴンズもここに来て6連勝と、今シーズンで最高の波が来ているようです。
前回に八木をリリーフにして、中継ぎ陣を厚くすれば先発も立ち直ると書きましたが、調子を落とした山井がリリーフに回ったことで中継ぎが安定し、先発でも浜田達、ネイラーが加わり、大野にも勝ちがついて好循環になりました。
もう少し早く手が打てたとは思いますが、首脳陣も又吉、福谷を何とかしたいという思いだったでしょうから、あまりドライに切り替えることもできなかったのでしょう。
なんとかCSに進出できればいいんですが、順位とかそんなことよりも、現状のような良い緊張感を継続して勝っていく感覚を投手も野手も思い出して、また覚えて、来季につなげていくことが大事でしょうね。落合監督時代は、こんなヒヤヒヤ感を保ち続けて勝っていったものです。
さて、この秋は忙しくなりそうで、いつまでもダラダラしているわけにもいきません。できることから片づけていかないと大変なことになりそうな気配。なかなか次の小説にも手が付けられませんが、とりあえず迫って来る波から乗り越えていくしかなさそうです。
リリーフを固めろ! 2015.7.23
プロ野球はオールスターも過ぎて後半戦。とは言っても残り試合は60試合を切って、そろそろ各チーム、ムチが入り始める時期です。特に8月の暑さの厳しい中で6連戦が続きますから、戦力の薄いチームは脱落していくことになります。
ドラゴンズも昨年はこの8月に大きく負け越して沈んで行きました。今年はぜひ踏ん張ってほしいと思いますよ。最下位ですから順位としては落ちようがありませんけど、まだまだ首位から4ゲームほどなので首位争いをしているようなもんです。
現在のところ、攻撃面では平田、ルナ、和田が堅実な働きをして、チーム打率はリーグ1位。ホームランが6位なので得点は4位ですが、広いナゴヤドームのせいもあるのでやむを得ないところでしょう。
一方の投手陣は、防御率、失点で3位。まあそこそこの数字ですね。ほか失策が6位、盗塁2位といった数字です。
データではあまり他チームとの差がなく、実際、ゲーム差もほとんど僅差なので数字通りなのでしょうが、印象としてドラゴンズの弱点といえるのがリリーフ陣でしょう。特にゲーム終盤の競り合いで失点するケースが多いような気がします。かつてはああいった試合を競り勝って上位チームになっていたんですが、今はそれができていません。
現時点のリリーフ陣は、右の田島、祖父江、又吉、福谷、左の高橋聡、岡田というメンバーです。このうち田島、又吉、福谷が不安定ですから、当然継投も怪しくなりますね。たとえば八木をリリーフに回せば、左のサイドスローということでバランスもとれて継投のバリエーションも増えるのでは。サイドスローということで目先が変われば打者も打ちづらく、先発よりも短いイニングの登板の方が、持ち味を生かせる気がします。
そうなると手薄になるのが先発投手ですが、現在の大野、山井、若松に緊急補強のペレスとネイラーを加え、さらに小熊、吉見、山本昌、浜田達らを、うまくミックスしていくしかないでしょう。リリーフがしっかりすれば、力不足の先発投手でも勝ち試合になる確率は高くなっていきます。まずはリリーフを固めるのが先決と思いますよ。
それにしても、このところ投手陣の制球の乱れが目につきます。あれは何が原因でしょうかね。メンタル的なものなのか、技術的なものなのか。プロの1軍投手ですから技術的にストライクが入らないなんてことはないでしょうから、メンタルなのかと思いますが、数年前まではあんなことはなかった気がします。
投手陣の走り込み量が、落合時代から比べると高木時代にかなり減ったと聞きましたが、そうした影響が出ているのでしょうか。一度、2軍投手のトレーニング方法を取材してみたいと思ったりもします。
「武功夜話」問題 2015.6.27
昨日、私は各務原市の歴史サークルにお招きいただき、2時間ほどお話をさせていただきました。
3年前にも村国男依の話を2度にわたっていたしましたが、今回は「卍曼陀羅」の主人公、蜂須賀小六正勝と、盟友の前野将右衛門長康の話をしました。
二十数人のメンバーで私よりも年上の方ばかりですが、各地の史跡にに出かけたりと積極的に活動をしていらっしゃるようで、出不精の私などは大したものだなーと感心した次第です。
さてその蜂須賀正勝ですが、「卍曼陀羅」は尾張美濃時代の正勝をメインに書きましたので、地元で見つかった前野家文書「武功夜話」のエピソードも多く取り入れました。というよりも、正勝の業績というのは他の史料ではあまり記述がなく、「信長公記」はもとより「太閤記」などでも秀吉の業績として語られるばかりです。のちに中国攻めなどでは毛利との交渉文書に正勝と黒田官兵衛の署名がありますので、官兵衛の上司として任に当たっていたということは判りますが、特に青年期に何をやったかなどという記述は「武功夜話」以外では皆無と言ってもいいと思います。
私も江南市民ですので、地元の史料を活用しようということで、今回初めて「武功夜話」を読んで、それを小説に採用しました。通説と比較して、明らかに間違いと思われる部分は修正するなど、できるだけ公正な立場で書いたつもりですが、小説に採用する時点ですでに「武功夜話」肯定派ということになるのかもしれません。
歴史に興味のある方ならご存知でしょうが、この「武功夜話」に関しては内容に疑問があるなどの否定論があって、現在のところ史実として採用して良いのか悪いのか中途半端な状態になっているようです。
ですからお話する際にも「武功夜話ではこう書かれています」という話し方にならざるをえず、歯切れの悪さが付きまとってしまいます。早く検証が進んで、事実が明らかになれば良いと思うのですが。
私は基本的には中立のスタンスのつもりですが、いわゆる否定派の意見を聞いても、あまり納得できる決定的な指摘がないように感じます。現在のように情報が簡単に手に入る時代ではなかったわけですから、年代や人名、官職、年齢、地名など、それは間違いがあっても仕方ないというか当然に思えます。あれだけ長編の記述で全く間違いがないというのは神業に近いと、私の経験上、実感します。現在、パソコンで執筆して、検索機能もあって、何度も校正をして、それでも間違いは残るのですから。
間違いの指摘で多いのは、新人物往来社発行の「武功夜話」だと、一~四巻までと補巻との内容の違いがよく指摘されます。 この補巻というのは、著者の吉田雄翟(かつかね)が晩年に目を病んで執筆できなくなったために、娘の千代に代筆をさせたものということで、女性が語るような「~増(ます)る」という表現も使われています。
内容的にも、これは補巻というより一~四巻のダイジェスト版で、分量としても少ないものです。本巻があるのに補巻を作った理由は明らかではありませんが、長すぎる本巻では読みにくかろうとダイジェスト版を作った感じです。そしてこれは雄翟が目を病んだあとのものですから、やっと日常の手習いができる程度の女性に書かせる執筆作業は、難渋したことでしょう。
それを考えると、本巻と補巻とどちらの内容が優先されるかは明らかに思えます。私も「卍曼陀羅」では本巻の記述のみを採用するようにしました。
また当時は存在しなかった岐阜県の「富加」という地名が文中に出てくるという指摘もあります。
現在の富加町は昭和29年に富田村と加治田村が合併して富加村になり、昭和49年に富加町になったということです。これが戦国時代に出てくるわけですから疑わしいだろうということです。
ただ現在でも美濃市に富野という地名があってそこから加治田へ向かう道があります。このルートを富加道と呼んだのではないかという推測もできます。
「武功夜話」のこの部分を抜粋しますと「大ぶて山古代の貴人の墳墓なり。無数の小丘あり、南北大きく巾あり、巾下は深田あり、これより三町ばかり南方は大井戸渡り節所、多治見道なり。佐々内蔵助殿五百有余の人数取り固め候。堂洞の岸勘解由、犬山の十郎左衛門とは縁者なり。妻子ともに城内に楯籠り御手向かいなり。富加という所一筋道あり。尾張勢押し入り竹束担いて城山へ取り付け、惣構え打破り乱入候なり」という記述です。前半の「大ぶて山」というのは美濃加茂市南部のようで300メートル南に木曽川の渡りがあるという位置です。ここを渡って多治見へ向かう多治見道があると書いてあります。その大ぶて山は佐々成政に任せて、信長ら尾張勢は堂洞城へ向かいますが「富加という所一筋道あり」ということはその道から攻め進んだと読めます。尾張方面から堂洞へ向かえば南から攻めると考えるのが普通ですが、この堂洞城は山の上にあって攻め口としては南と北が考えられます。信長はあえて背後の北から攻めかけたということを書きたいがために、北側の「富加という所一筋道」から攻め込んだということを記したように思えます。
前述の富野と加治田を結ぶ道が、当時「富加道」と呼ばれていたとすれば、問題は解決します。あとは調査ですね。
他に、墨俣築城が当時の築城の常識と違うとの意見もありますが、立地場所の条件はそれぞれ違うでしょうから、特に墨俣のような難所にしかも急ごしらえで建てる場合、教科書通りの砦ができなくても当然のように思えます。
こうした疑問点を一つ一つ検証して、少しでも真実に近づいていければ、歴史愛好家としては歓迎すべきことです。あまり最初から肯定否定の立場を取らずに、まずは「武功夜話」を読んでみて、中立の視点から冷静に意見交換をしていただきたいものです。意外に元本を読まないうちに否定本を読んで否定派になっている方も多いように思いますが、あまり攻撃的で感情的な意見は、かえって説得力のない裏返しのように感じてしまいます。
定価で1冊9000円した「武功夜話」も、今は中古なら5冊セット1万円で購入できます。さあ皆さん、まずは読んでみましょう!
フォーク世代再燃? 2015.5.16
先日は珍しくコンサートに出かけました。伊勢正三「風」ひとり旅コンサートでしたよ。
伊勢正三さんというと'70年代に「かぐや姫」で活躍し、その後は「風」で活動。名曲の数々を生み出しました。私の小学校高学年から中学、高校時代がちょうど'70年代で、一番感受性の強い時期にフォークの全盛期だったために、どっぷりフォークに浸かった人間になってしまいましたね。このフォーク世代というのは面白いもので、10歳年上の人たちは'60年代のグループサウンズやアメリカのカントリーフォークで育った世代だし、10歳年下になると'80年代のバブル期のニューミュージックからコンピューターサウンドの時代になるし、ほぼ10年単位で聴いた音楽が違うんですね。洋楽に走った人はまた違いますが。
40代のころ、私のオリジナル曲を10歳くらい年下の女性に聴いてもらったことがあるんですが、いろいな感想のあと「でも何でフォークなんですか」って言われて愕然としたことがありましたね。ほぼ同年代と思っていましたから。
そんなことでコンサート会場にも、ほぼ同世代のお客さんばかりがいらっしゃってましたよ。
会場に着いてから私は「そういえば髪が長めで髭も生やして、これは正やんの真似と思われるんじゃないか」とビクビクしましたけれど、余計な心配でした。もっとそっくりさんがいましたよ。ちょっと背の低い小正やんでした。曲目をメモしつつ聴いていましたが、アンコールを含めて23曲。正やんとバックミュージシャンが3人の、どちらかといえば小じんまりとした布陣ながら、さすがにプロは見事なものです。「風」後期の厚めの音も遜色なく聴かせてくれました。
全曲歌えるコンサートというのも珍しいなあと思いつつ、それでも懐かしいという感じなしなかったのは、今でも正やんの曲が身近にあって、ギターを弾いて歌っているからでしょうね。
たしか30年以上も前になりますが、同じ会場で正やんのソロコンサートを聴いたことがありました。「風」を解散してソロアルバムを出した頃で、曲調も暗いものが多く、「この先、どうなるんだろうなあ」と不安に思いながら聴いたものです。
その予感どおり、時代の変化とともにフォークも下火になり、正やんの音楽も時代に合せようと迷走し、ついに活動休止状態になりました。吉田拓郎、井上陽水、松任谷由実、中島みゆき、小田和正など、自分のスタイルを確立して生き残った人もいますが、ほとんどのフォークシンガーは姿を消しました。それが10年ほど前にNHKのBSでフォーク特集をやったあたりから復活し、今ではゾンビのように皆さん生き返って歌っていらっしゃるのは嬉しいことです。回る回るよ時代は回るということでしょうか。今、こうした曲を耳にした若者がまたフォークに馴染んで、次のフォーク世代を作り出すのかもしれません。それよりも我々世代が、もう一度フォークの時代を作ったりして。各地でギターを弾いて歌っているおじさんおばさんは数多いですからね。
そんなことも思いつつ、今日もギターを弾く私ですよ。
予想はむずかしい 2015.4.13
ドラゴンズは現在1位タイ。調子がいいですね。
開幕前は下位予想が多かった中日、ヤクルト、DeNAが上位を占めて、面白い状況になっています。長いペナントレースですから、この先どうなるかは判りませんが、予想はむずかしいということですね。そもそも開幕前の順位予想はその時点での戦力比ですから、「開幕前戦力順位」という名称にした方がいいかもしれません。それなら評論家の皆さんも、さほど頭を悩ますことなく順位を決められるでしょう。
故障者が出たり、途中で戦力補強したりという要素は、まったく加味できないわけですから、最終的に順位が当たったとしても偶然の部分が多分にあるはずです。
かく言う私も、4月号の月刊ドラゴンズ「くらはしかんの画竜点睛」で、今年の開幕オーダーを描きました。
4月号ですが、原稿を描いたのは3月の始めですから、沖縄キャンプから帰ってきたころです。和田、平田、エルナンデスはほとんど北谷にいなかったため、私の予想オーダーは「大島、亀沢、荒木、ルナ、ナニータ、森野、藤井、松井雅、山井」という順でした。
2番ショートは当初、遠藤を考えていたところ外野へコンバートということになり、同じ左打者で俊足の亀沢で描き直しました。エルナンデスがこれほど打つとは、まったく想像できなかったですね。そのほか平田も、やはり力を発揮して開幕には、しっかり復帰しました。これで開幕投手まで外れていたら目も当てられませんが、ぎりぎり面目を保った感じでしょうか。
「私ならこうする! 2015ドラゴンズ開幕オーダー!!」というタイトルにして、予想ではないという逃げ道も作っておきましたが、あんまり現実と違ってもお話になりませんからねえ。
それでもまあ予想が良い方に外れるというのは歓迎すべきことですね。福田や亀沢といった若手がこれほど目立つとは想像できなかったし、八木やバルデスの新戦力も予想以上の働きぶり。浅尾の復調ぶりも予想以上で嬉しい限りです。
悪い方に外れたのは森野の骨折と、又吉、福谷の不安定ですが、これも仕方ありません。プラスマイナスいろいろな要素が合わさって今年の成績となるわけで、他チームも含めて予想不能の展開で楽しませてもらいたいものです。
新戦力と言えば、同じく私は2月号の「画竜点睛」でルーキーの遠藤を取り上げました。
雑音で惑わせることのないように、あまりルーキーは漫画に描かないことにしてるんですが、期待の大きさからでかでかと描きましたよ。これも描いたのは正月のころで、ルーキーたちは入寮もしてませんが、彼のプロフィールからこれはショートの穴を埋める存在になるに違いないと思ったわけです。大学、社会人とショートを守り、全日本のメンバーにも選出、さらに俊足の左打者となれば、当面は打てなくても2番でつなぎ役には最適です。しかしながら3月上旬に外野コンバートと報道されびっくり。その後また2軍でショートに戻っているようですが、あれは何だったのか。不安定な送球を矯正するためなのか、本人に危機感を持たせるためなのか。さらに不運なことに先日、手首に死球を受けて骨折と、波乱のプロ人生の始まりです。
現状ではショートはエルナンデスが絶好調で全く問題はないですが、いずれは若い選手が担うのが理想で、遠藤、亀沢、堂上らの中からレギュラーが誕生してほしいですね。
亀沢や堂上にしてもプロ入りから今日まで苦労してきましたから、遠藤も苦労を濃縮して体験してタフさを身に着け、ひと皮むけた姿でレギュラーを目指してほしいと思いますよ。
「卍曼陀羅」いろいろ 2015.3.15
「卍曼陀羅」出版の喧騒も、徐々に落ち着いてきました。
今回は出版までに時間の余裕があったので、献本先のリストを作ったり、手紙を用意したり、あるいは直接持参したりと、割と計画的に事を進めることができました。
マスコミ関係では地元の尾北ホームニュースと、中日新聞、中日スポーツに記事を載せてもらいました。尾北ホームニュースと中日スポーツには5冊ずつ読者プレゼントをさせてもらいましたが、ホームニュースには約110件の応募があったということで驚きました。やはり地元の歴史のことに関心をお持ちの方が、大勢いらっしゃるのだなあと実感した次第です。
蜂須賀氏ということで徳島県でも興味を持って読んでいただけるのではと徳島新聞にも送本しましたが、こちらは返事がなく、記事になった形跡もなさそうです。蜂須賀氏だけでなく、前野氏、生駒氏、稲田氏など、阿波徳島へ渡った尾張衆は多かったので、ルーツを知るにはちょうど良い小説かなとは思いますが、いかがでしょうね、徳島県の皆さん。
高校時代に担任だった現国の先生にもお送りしたところ、「これは文学というより郷土史だな」というご返事をいただきました。
たしかに物語としては不要な情報も結構書きましたので、筋を明確にしようとすれば切り捨てたほうが良い部分もありそうです。しかしそれも残したかったということは、自分としてもこの地域の戦国時代がどうだったかということに関心があって、それを順に追っていった作業だったと思います。その意味では郷土史の色合いが強いと言えるかもしれません。
先生は二度も我が家をお訪ねになり、「俺は辛い点をつけたが、俺の周囲ではやけに評判がいい」と妙な褒め言葉を残して、結局10冊もご購入いただきました。卒業後35年もたった生徒にお気遣いいただき、本当にありがたいことです。
そのほか、「2段組みであのページ数では読むのが大変だ」という声もいただきました。たしかに昨今の緩めで大きな活字の本なら上下2巻にしても良さそうな文量ですが、さすがに財政的にそれは難しいので、申し訳ないですが拡大鏡でも使って、ゆっくり読んでください。3日ほどで読んだという方もいらっしゃいましたが、いくらなんでもそれはちょっと無茶です。2冊分の内容だと思って味わって読んでいただければと思います。
どこで売っているのかというご質問もいただきますが、なかなか無名の作家の本は、どの書店にも並んでいるというわけにはいきません。書店さんも限られたスペースに、できるだけ売れる本を置きたいですから。
しかしどの書店でも注文すれば取り寄せてもらえますし、アマゾンや楽天市場などのネット書店なら自宅に居ながら入手できます。買うことが決まっている本なら、最近はネットの方が簡単ですね。
地元の江南市では、平積みで置いていただいている書店さんもあります。しかも前作とともに! ありがたいですね。恥ずかしいことに家族が記念に写真を撮ってきました。夢屋書店さん、ありがとうございます。全国的にというのは無理かもしれませんが、愛知、岐阜、三重あたりの歴史ファンには、ぜひ読んでいただきたいですね。
「卍曼陀羅」の装丁 2015.2.6
明けましてって、ちょっと遅いですね。
どうもこの周辺記の更新は、毎年2月からのような気がしますが、どうでしょう。調べるのも面倒ですが。1月は年末年始のゴタゴタで、更新する元気が残らないのかもしれません。
さて今年はそのゴタゴタに小説の出版も重なって、このところ慌しかったですねえ。本の発売は2月中旬なので、これからさらにゴタゴタかもしれませんが、とにかくホッと一息できたので更新します。
小説「卍曼陀羅」についてはTOPICSのほうで書きましたので、そちらをご覧いただきたいと思いますが、なかなかの出来栄えの一冊になりました。内容も良いですが、装丁が気持ちよくて、非常に満足しております。小説の内容を一番よく知っている自分がデザインしていますので、イメージどおりになるのは当然と言えば当然ですが、本当に素晴らしい。まさに自画自賛。実は何カ所かミスもあるんですが、それを差し引いても満足しております。
前作「赤き奔河の如く」もカバーデザインのイメージは自分でやって、使った写真も自分で木曽川の流れを撮ったものですが、時間的に余裕もなく少々満足のいかない部分がありました。今回は表紙、カバー、帯まで装丁デザインのすべてを終えてから出版社にお願いしましたので、納得のいく完成度になりました。何事も経験ですね。
この先、出版することがあるのか判りませんが、本の装丁というのも面白いなあと思いました。自分の興味のない本の装丁はできないでしょうけど。他の人の本を読むときにも、内容が良くても装丁がつまらないと「なんでこんなデザインなんだろう」と、ずっと気になるときがあります。意外に大手出版社の本でもそんな経験があって、あまりそういうことに留意しない方々も多いんでしょうが、私は気になりますねえ。結構な費用をかけて出版するわけですから、つまらないデザインではもったいないでしょう。私の場合、出版自体が自己満足みたいなものですから、デザインだって自分が満足しないと出版する意味が半減してしまいます。
このあと蜂須賀小六のパンフレットを作ったり講座の用意をしたりと、しばらくはこの本の余韻が続いて、次作に取り掛かる余裕ができるのは5月ごろかなと思います。前作では1年以上も次作に手が付けられなかったのですが、今回はそこまではないんじゃないでしょうか。
ボヤボヤしていると無駄に歳を取ってしまいますので、頭と視力が健在なうちに書きたいことを書いておかねばと思っていますよ。
BACK NUMBER 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998上期 1998下期