| 01 |
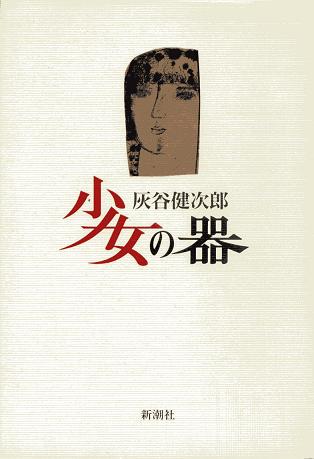 |
■灰谷健次郎 新潮社 1989 灰谷健次郎といえば、『兎の目』『太陽の子』『子どものの隣』などの作品も大好きですが、この『少女の器』は学生 時代に好んでよく読み返していた一冊です。灰谷氏が神戸の事件後の写真週刊誌の報道問題で新潮社と袂をわかったため、この新潮社版は絶版となり、現在は角 川文庫から出版されています。 主人公の少女・絣の理性と感情をとても丁寧に書いた作品です。「 」の会話を中心として展開されており、登場人物たちの会話の一つひとつに深い思い入れ を感じさせられます。物語の設定は、中学三年生の優等生の少女・絣、父・万三(版画家)と母・峰子(大学の美術教師)は離婚し、それぞれ新しい恋人と生活 しています。絣のボーイフレンドの不良少年・上野君は、父親が行方不明で、母親はアル中で入院中。設定を並べてみるだけで、絵に描いたような崩壊した家庭 ですね。その不安定な環境は、少女・絣の感受性をとても敏感にしますが、離れ離れの家族は究極的なところでお互いを深く理解し、その中で絣はゆっくりとし た成長を遂げていきます。 父・万三との会話で、「おまえは理性と感情のバランスのとれている方だと思うよ」というのが出てきます。絣の本質をよく理解した言葉だと思います。そし て、やがて父・万三を襲う盗作疑惑の事件。うろたえる娘・絣に母・峰子は「万三さん、苦しんでいるかもしれない。あなたのいう通りよ。だけど、その苦しみ は万三さん以外の人がどうすることもできない質のものなのよ。まわりの者がしんぱいしていることを知ると、万三さんはよけいつらがるでしょう。しばらく、 そっとしておいてあげることも思いやりのうちよ。今、あなたが万三さんに会いに行けば、あなたの気持ちはおさまるかもしれないけれど、万三さんはあなたの 気持ちもいっしょに背負って悩まなければならないでしょう」と語ります。 父・万三は、直接的、瞬間としての愛情よりも、人生を通じて十二分に人を愛し、十 二分に人の愛を受け、それゆえに人間足りえたという充足感と諦観をわがものとしたときこそが究極の自立と語ります。危うい中でお互いを理性的に理解し、繰 り広げられる家族の物語とともに、関西弁の不良少年・上野君とのやりとりがまた、絣の成長に大きく結びついています。 |
Jun-coo's LIBRARY