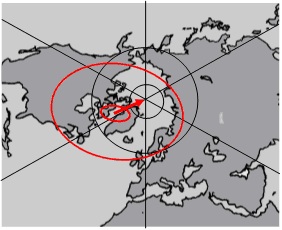第8章の解説 水門の決壊
第8章は本書のクライマックスである。
前の章でジブラルタル海峡が陸続きであったことにより、約20万年前にクレタ島の北側地域に住み着いた人族が現代人類に進化したと結論したばかりだが、本章ではいきなり1万2千年前の、地続きのジブラルタル海峡(ジブラルタル陸橋)の決壊の話に跳ぶ。
クレタ島の北側に住み着いた現代人類の祖先が、どんな具合に世界に拡散していったかを議論する前に、ジブラルタル陸橋の決壊前と決壊後では大陸の佇まいが異なるから、その差異を明らかにしないといけないからだと言っている。
|
第8章 3月初旬
庭の生垣の隅に生えている福寿草の花が開いた。毎年の事ながら、この花を見ると冬の寒さと春への期待が相まって、シンとした思いになる。元々寒いのは苦手だったし、事務屋で働いていた頃は年度末向けの経費節減指示に滅入ることが多かったので、春になるのを待ち詫びていたものだった。福寿草が咲くと救われた様な、そんな気持ちが湧いてくる。
今年の冬も寒かった。まあそうは言っても、今年は面白い問題に取っ組んできたので、それほどの寒さを感じないで済んだのは確かだが。
「寒いですねえ」生垣越しに山村君が声をかけてきた。
「あら、いらっしゃい。お元気そうですね。上がってくださいよ」
かみさんが書斎の掃除をしながら返事を返した。今日は寒いが天気は良かったので、書斎の掃除をしてくれている。上がってくださいとの事だから、掃除は終わったんだろう。
書斎にあがって前の資料を広げていたら、かみさんが朝のおやつを持ってきた。
「主人のお友達が定年になって田舎に帰られたのですが、その方が蜜柑を送って下さいました。“文旦”って名前ですが、とってもさっぱりしておいしいですよ。食べてくださいな」
「土佐ですね。前に一回食べたことがあります。久しぶりになりますが、ええ、確かに、蜜柑というより何か別のものですね。例えが出てきませんが」
文旦を食べながら、ついでにコーヒーも飲んだ。若干合わないなとは思いながらも、コーヒーは毎日の習慣だから、まあ贅沢は言えない。
「山村君、この前までで人類の発祥の話が大体落ち着いたから、今日は人族の拡散のルートをやってみるか。僕にもちょっとした意見があるんだが」
「そうですね。でもその前に切り落としの検討をしませんか。ちょっと気になっていることがありますので」
山村君は別の話を切り出してきた。
「可逆反応と不可逆反応の話は、化け学の時にありましたよね。どうもジブラタル海峡の決壊は不可逆反応に近い事象みたいなので、干上がった時と今とでは環境が違っているはずなのです。この前までの結論から、人類の発展というか、地球世界全域への拡散ルートはニュアンスが変わるかも知れません。」
彼の言わんとするところは分からなかったが、先ずは彼の考えを聞くことで、我々の検討を続けていった。
|
先ずは海水の慣性モーメントの話である。これが本書の三つ目のキーポイントになる。
ジブラルタル海峡が陸続きになったとき、2,000年ほどはかかるが、北半球では1023ジュールの回転エネルギーの低下が起き、南半球ではほぼ同じ値の1023ジュールの回転エネルギー増加が起きる。
この場合はゆっくりした変化だから自転速度だとか、地軸の傾きで吸収されるだろう。
但し・・・。
これが本節のまとめである。この、但し・・・、は2〜3節先送りになっている。
|
【水門構築の影響】
我々はジブラタル海峡部に水門を作ることを前に検討した。ジブラルタル海峡が陸続きの時と同じ事象の水門の構築によって、地球の海洋に対し7mの海面上昇が引き起こされる。そして氷河期の海面低下の時に検討したように、これによってもまた慣性モーメントの変化は起きる。
6,500万年前の隕石の衝突時と同じ程度の変化が起きるのか。幸いなことに、水門の構築時には同じような変化は起きない。
<力は単位時間当たりのエネルギーの変化量>だと山村君は言う。氷河期が終わるとされた時も同じだが、数千年から数万年の長い時間で起きる変化だと、自転速度だとか、地軸の傾きで吸収されるだろうと言うのが、彼の結論だった。だから影響は出るが、クオーツの時計やコンパスを持っていない連中にはそれほどのインパクトは無いだろう。
問題は切り落としの時だと、<決壊>の時だと、山村君は言った。
|
次はジブラルタル陸橋の切り落としである、単純計算では9ヶ月半で海水の注入が終わる。
|
【水は天から】・・・その1
明日の天気は雨でしょう。といった天気予報を聞くと、我々はやれやれ嫌だなとの感じを持つようになっている。晴天の慈雨だとか、恵みの雨というイメージがずいぶん少なくなったのが現代である。もう少し降水の有難さを思い起こすべきなのかも知れない。
・水ーは 天ーかーら 貰いー水・・・五木の子守唄
雨は数百メートルから千メートル位の上空から降ってくる。だが、煩わしいと思うことはあっても、雨に打たれることで打撃を受けることは無い。雨粒が小さいため、空気抵抗が大きく影響して、落下速度が極端に小さくなっているからである。
ジブラルタル海峡の水門の構築が世界的な反対を受け、構築の提案は却下されるだろうが、我々の唯一の前提は、過去におけるジブラルタル陸橋の存在である。従って、水門が完成して、<陸橋が存在を始めてから>、数十万年が経った後にこの水門を切り落とす、<陸続きであったジブラタル海峡部が決壊する>、この演繹を行っていく。水が天から落ちてくる。
高さ200mの水門を切った時、水平方向には最大で63m/s、平均して42m/sのスピードの海水が飛びだしていく。我々が紙上で構築したジブラルタル海峡の水門は、長さは25kmだが、直線距離では23km程度である。平均深度は大よそだが150mを見こんでいるので、流入速度の平均値を30m程度とすると、毎秒1億トンの海水が地中海に流れ込んでくる計算結果になる。
23km×150m×30m/s=1.0×108m3/s
単純計算すると、2千年かけて蒸発して減っていった水量「2.5×1015m3」を、僅か 2.5×107秒(290日)、 9ヶ月半で埋め合わせてしまうことになる。
|
陸橋の崩落だから、先ずは狭い範囲で切れて徐々に広がるだろう。最後の頃は高低差が無くなってきて流入量が減ってくるだろう。これらを考えると大よそ1年で海水の流入が終わって安定する。
蛇足だが、旧約聖書のノアの洪水も1年で安定した。
【水は天から】・・・その2
但し、この時間は2〜3の要素での補正によって若干長くなる。
まず、地中海の水面と大洋との水面差が300mより小さくなると、水門の最深部からの供給が無くなり、流入量が小さくなってくる。流入速度は海面差の1/2乗に反比例し、また海表面積は2乗で効いてくるので、最後の300mを埋め合わせるにはかなりの時間を必要とする。最後の20mの落差であっても、これまで時々発生してきた津波の影響力などを考えると、人の生活にとってはまだ重大な影響がある。
また、切り落とし直後を最大として、大量の海水蒸発が起きることにより、海水面の上昇速度が落ちることも考慮する必要がある。
更に、水門の切り落としのタイムラグも考慮する必要があり、「いっせいに切り落とす」として計算をしたが、通常オペレージョンであればまず何ヶ所かを切り落として、そのあと順次崩れていくのを待つ方が作業効率は良いだろうし、実際的である。これらの3要素を配慮すると、おおよそ1年程が想定される。
【2月17日・・大いなる淵の源は、ことごとく破れ、天の窓が開けて、雨は40日40夜、地に降り注いだ。・・水は150日のあいだ地上にみなぎった。・・150日の後には水が減り、箱舟は7月17日にアララテの山にとどまった。水はしだいに減って、10月になり、10月1日に山々の頂きが現れた。・・6百1歳の1月1日になって、地の上の水はかれた。・・2月27日になって地は全くかわいた。(創世紀第7章〜第8章抜粋)】
雨が40日の以後は降らなかったのかどうか、150日迄は水が増えたのか減ったのか、こうした部分は読み取れないが、旧約聖書のノアの洪水も約1年で安定したことは分かる。
|
この節はジブラルタル陸橋の決壊が地中海地域に及ぼす影響を推定している。
全面崩落になってからは、百メガトンの水爆を5分毎に地中海の西側海域に爆発させているのと同じ情況が続く。世界中の全ての核兵器を使っても8時間と20分で枯渇するが。
【水門の切り落としの影響・・地中海地域】・・・その1
切り落としによる影響については、かなりの困惑をきたしている。山村君も発生するエネルギーとその影響度に関しては、彼の想像力を越えている様に見える。
1,000mの海面低下が起きていた。従って、地中海に流入する水は垂直方向に対しても140m/sのスピードでぶつかることになる。水平方向の速度と合わせて150m/s程のベクトル和の速度で毎秒1億トンの水が降り注いでく。これだけの水量だから雨のように落下速度が低下することは無い。
風速50mは想像できるが、風圧と水圧では700から800倍程の違いがあり、かつ150m/sである。岩盤は豆腐の様に簡単に削られるし、大地の振動も相当なものになる。
別の面からみて見てみよう。切り落とし初期の頃のエネルギー発生量は毎秒1.0×1015ジュールになる。
運動エネルギー=0.5×1011kg×(140m/S)2=1015ジュール毎秒
位置エネルギー=1011kg×1000m×9.8m/S2=1015ジュール毎秒
(海水の水平方向エネルギー成分省略)
1メガトンの水爆が発生させるエネルギーは3×1015ジュールになる。だから、百メガトンの水爆が300秒毎つまり5分毎に爆発している状況に等しい。〔核の冬〕といわれる全面核戦争では10,000メガトンの水爆が使われることになるが、切り落としから3万秒後、8時間と20分でこれに相当する状態になる。ジブラルタル海峡の東側に広がる地中海の西側海域に、世界中で保有している核兵器を半日かけて、次々に投下していった状態だが、これが我々の辛うじてイメージを浮かべることのできる限界である。
この段階で3×1019ジュールのエネルギー量になる。最終的には総計1022ジュールのエネルギーの発生である。とても狭い地域に閉じ込めておくことはできない。大量の熱と水蒸気の発生はもちろんだが、大部分はまだ運動エネルギーのままで遠く拡散していく。しかも、真東に向かう。大西洋側からみるとジブラルタル海峡部はちょうどお碗状のへこみの中心部になっているので、大西洋から流入する海水の方向は一義的に決まってしまう。一種の鉄砲水のように東に向かって飛びだしていく。
大洋の海水が持っていた総計1022ジュールの位置エネルギーの低下分は、最終的には熱エネルギーと地中海内部及びその沿岸での位置のエネルギーに転化される。
山村君はスーパーコンピューターを使ってのシミュレーションをやって見たい、そんな誘惑に駆られていたみたいだった。だがそれは先の話にして、当面は非常に大雑把な推定で話を進めることにした。 |
大量の岩石流が、オラン地域からチュニジアのガベス湾あたりにまで押し寄せる。また、地中海東海岸のイスラエル、レバノン、シリアの地域はかなりの内陸、高地にまで影響を受け、凹面となっているトルコ−シリア国境付近の被害は相当のものとなる。
【水門の切り落としの影響・・地中海地域】・・・その2
約2割程度が位置のエネルギーに転化されるのではないかと我々は考えた。決壊箇所からの海水が押し寄せる真東にはアルジェリアのオランがあり、最大の被害を受けるのはこの地域になる。ジブラルタルとオランを結ぶ線上の中間点にアルボラン島があるが、落下した海水はまず海底をえぐりながら、このアルボラン島あたりで跳ね上がり、オランから現在のブドナ湖に向けて大きな影響を及ぼしたと考えられる。
お碗状の端から小さな鉄球を落とした場合、摩擦抵抗や空気抵抗があって鉄球はお碗の反対側を乗り越えることはない。しかし、お碗ではあってもデコボコがあり、また落とし込むものが連続した流水の場合は単純ではなくなる。2m程の高さの波が、5mの堤防を乗り越えて(勿論押し寄せる海水の一部だが)内陸に被害を及ぼすケースはいつもの話である。流入してくる海水は当然のことながら粗密な状況(高い部分、低い部分)をつくり、大量の土砂を伴ってオラン地域に押し寄せていく。この結果、我々はチュニジアのガベス湾あたりまで影響が及んだと想定した。大量の岩石流がオラン地域からガベス湾にまで押し寄せてくるだろう。
そして、地中海東海岸も時速540kmの海水と土砂の直撃に曝される。イスラエル、レバノン、シリアの地域はかなりの内陸、高地にまで影響を受け、しかも凹面となっているトルコ−シリア国境付近の被害は相当のものとなる。 |
ここは別の節(文明の崩壊)になっていたが、直前の節のまとめにあたる部分なので、タイトルを書き換えた。
エデンの園はこの時に消滅した。
【水門の切り落としの影響・・地中海地域】・・・その3
文明は海岸線と河川流域に集中するのが有史以来の特徴であり、人の活動面からしてその昔も同じであったと考えて、演繹を続けてきた。一昼夜でどこ彼処の国が滅びたとか、そういった記録によく出くわすが、クレタ湖の周辺に育ってきたであろう文明もジブラルタルの水門の切り落とし<ジブラタル陸橋の決壊>によって、1〜2日で簡単に破壊されたであろうことは容易に推測できる。
150m/sの水の速度は、落下地点では下向きだが、ほとんどその速度を落とすことなく、東に向けての流れになる。これを時速に換算すると540km時になる。地中海の東海岸のシリアまでは3,700kmあるが、途中の流速低下を考慮しても、切り落とし後の24時間以内には海水の衝撃が到達する。含んだ空気(風雨)とこの海水流のどちらが先になるか。水爆実験などの映像からすると、どうも風即ち暴風の方が先になるように予想されるし、 地震(地の揺れ)は更に速い。エデンの園と表現しえたクレタ湖周辺から見れば、西の方に明るい空が(或いは太陽とも見間違える程の光が)現れ、そして地の揺れが始まり、大雨が降り始め、そして最後は海流に飲み込まれる状況になる。水門の切り落としから少なくとも2日後には主力な文明地域は壊滅してしまう。
総計1022ジュールの大半は熱エネルギーになって消費される。この発生した熱は、我々の大雑把な計算では地球大気全体と、海水深度10m程度及びこれに相当する大地(約2〜3mの深さ)を約0.25℃上昇させる値となり得る。確かに、太陽からの年間供給エネルギーの4×1024ジュールに対して、1022ジュールは0.25%であり、地球全体ではそれほどの影響はないかも知れない。
しかし、ここ、即ちジブラルタルの水門近辺で集中的に発生する熱エネルギーが、平均して地球全体に広がるには、例えこの激変の時間が1年近くかかるとは言っても、さらに長い時間を必要とする。大きくは、北半球から南半球への熱の移動にかなりの時間を必要とするし、全体的には西から東に向かっての熱の拡散も時間を必要とする。従って中近東/アジア方面への影響度は年間の平均気温が4〜5℃上昇する程の影響をおよぼすものと考えられる。当然大量の降雨が伴う。
我々がエデンの園と想定したクレタ島の北側のエーゲ海の文明はこんな具合に、ノアの洪水の様に、消滅したと思われる。 |
前の節の「但し・・・」はここに繋がっている。決壊の影響は地中海地域だけの問題ではない。全世界が壊滅状態に陥る。なにしろ大陸がミシミシと動いていくのである。
ジブラルタル陸橋の崩落によって、北半球では1023ジュールの回転エネルギーの増加が起き、南半球ではほぼ同じ値の1023ジュールの回転エネルギー低下が起きる。しかもこの場合は1年で変化する。陸橋が出来たときの変化の2,000年と比べると3桁大きい力が働く。
大陸塊が縦の方向にシフトしてこの力が吸収される、というのが山村君たちの結論である。
【切り落としの影響・・スリップ】・・・その1
さて、以上が切り落とし<崩壊>による水量の影響(つまり、位置エネルギーの解放による総計1022ジュールの熱エネルギーの発生の影響)である。
更に、切り落としの影響には「大洋−地中海の海水分布の変化」による地球の慣性モーメントの変化が加わる。前の節で述べた、水門を構築した時に発生するのと同じエネルギー量、1023ジュールの回転エネルギー量、の変化である。
同じエネルギー量の変化だが、この水門の切り落としによる変化は自転速度だとか、地軸の傾きなどで吸収されず、地殻の移動に直結する。何しろ時間が短い。前の節の場合(水門の構築で地中海が干上がっていく場合)は、2,000年程のゆっくりした変化だったが、ジブラルタル海峡の水門切り落としの変化は1年以内で完了する。いわゆる、単位時間当たりのエネルギーの変化量が極めて大きい。つまり「力」が。
地殻はマントル対流の上に浮かんだ殻であって、今も少し揺れ動いている。現在の観測では、14ヶ月周期での10m程度の北極点移動が報告されており、海流や大気の移動がその原因とされている。
また大陸部はマントル部に対してより深く沈み込んでおり、地殻の底面とマントル面とは全くの球面接触になっている訳ではない。従って、この地殻の移動は大陸塊の縦の方向のシフトになるだろうと我々は結論した。
ただ、我々が以下の結論に至るのに苦慮したのもやはり確かである。
ここで出てきた1023ジュールの回転エネルギーの変化がどれだけの地殻移動を引き起こすのかは、実は我々には計算できてない。ただ、この数値から数千キロメートルの極点移動が起こり得るとは言える。以前からこの1023ジュールのエネルギー量が、折にふれては出現しており、白亜紀の恐竜絶滅の隕石衝突が地殻変動を引き起こした証拠は、ハワイ諸島から続く天皇海山列の折れ曲がり部分にも残っている。
我々が後で述べようと考えている、氷河期の消滅や、マンモスの氷漬けを証明するために先輩諸氏が考えた色々な原因系も1023ジュール近辺のエネルギー量を要求している。 |
大陸塊のシフトとは、「グリーンランドのバフィン湾のあたりを北極点(地軸の回転軸の中心)としていた決壊前の地殻が、北極海を極点とする現在の場所へ移動」、することだと。
【切り落としの影響・・スリップ】・・・その2
我々は次の点を考慮して、地殻移動を想定した。
- 大陸の形態は水門の構築に伴う海面上昇の影響は殆ど受けない。
- 地殻はマントル対流の上に浮かんだ卵の殻、(鉄球の上の油膜といった方が実情には近いが)の様なものであって、急激な、短時間の回転エネルギーの変化は地球の深内部(マントル)にまで影響を与えることが不可能である。
- 一方で、回転エネルギー(北半球で1023ジュールの回転エネルギーの増加、南半球ではほぼ同じ値の1023ジュールの回転エネルギーの低下)の補正は必須。この為には卵の殻の移動をもとにして、回転エネルギーの補正を行うしかなく、角運動量の大きい大陸部分がシフトすべきである。
- マントルの上に浮かんだ地殻だが、地殻の底面とマントル面とは全くの球面接触になっている訳ではない。大陸部はマントル部に対して深く沈み込んでおり、海洋部の沈み込みは浅い。従って、大陸の細長い方向に向かってのシフトになる。
これらの点から、我々はグリーンランドのバフィン湾のあたりを北極点(地軸の回転軸の中心)としていた決壊前の地殻が、北極海を極点とする現在の場所に移動してきただろうと想定した。つまり、西経60度、北緯70度の地点が北極点からシフトして、今の位置にきたと。
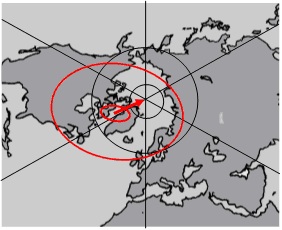
そして、当然のことながら、地殻の急速な移動は地球全体にわたって壊滅的な影響を及ぼした。
|
1万2千年前の、地続きのジブラルタル海峡(ジブラルタル陸橋)のこの決壊が人類の歴史のボトルネックの原因だと、この節でまとめている。
|
【歴史のボトルネック】
ミトコンドリアDNAの分布から、これまでに地球の人口が10万人規模にまで減ったことがあると言われている。
1022ジュールの、位置エネルギーから熱エネルギーへの変換は、地中海西部から膨大な粉塵が大気中に巻き上げられ地球を覆って気候の変化を引き起こし、地殻の急激な移動は地震や火山活動などを激増させた。
我々は、クレタ湖周辺・地中海周辺だけでなく、地球上の全文明が崩壊したと考える。高度マイナス1,000mの地域以外は生活面でのハンデキャップを持っており、環境の変化には極めて弱かったと考えるからである。
地球全体では、1023ジュールの回転エネルギーの変化により、西経60度と東経120度のラインが最も地殻移動の影響を受ける。バフィン湾から北アメリカの東を経て、ベネズエラ、ボリビア、南極大陸、西オーストラリア、インドネシア、フィリピン、東北中国、シベリアのライン上では一年で20度の南北シフトが起きる。北緯35度が15度になり、つまり温帯性気候から熱帯気候に変わり、逆に北緯35度の温帯地域が55度の寒冷地域に変わったりする。気候の変化が我々の祖先に直接与えた影響の他にも、生活の背景となる食料である植物や動物の激減が追い討ちをかける。
この年、人口は激減したであろう。よくぞ生き延びたと言うべきかも知れない。
個々に見ていくと、地殻の移動によって緯度方向の影響を受けない地域は有る。これはドイツ、ギリシア、エジプト、スーダン、ザンビアの線上であり、また、太平洋のハワイの東15度の線上になる。
これらからすると、人々の生活に余り大きな変化が起きなかったのはエジプト南部、スーダン地域しかなくなる。
ドイツ地域(北ヨーロッパ)はクレタ湖の周辺で獲得した我々現代人の特性からすると少し寒すぎた。地殻移動の前、今の温かいメキシコ湾海流が流れてないため、ここらの北ヨーロッパは現在より更に寒く、人類が住み着いていなかったはずである。また、地中海沿岸はこの地殻移動の影響は無くとも、決壊に伴って流入する海水や降雨、位置エネルギーの熱による局地的な高温化の影響を受けるため全滅したであろう。
従って、唯一残ったのはエジプト南部、スーダン地域であり、ここに歴史上の遺跡が多数残っているのはこうした理由によるだろう。
切り落としの<決壊>の時点で、我々現代人の祖先は進んだ文明を獲得していたはずである。しかし、エジプト南部、スーダンそして或いはイラク東部辺りが辛うじてその文明の一部を保持できただけであろう。そして恐らく、ミトコンドリアDNAの分布から想定されているように、生き延びた人類も10万人程度だったと思われる。
人類の発展は当然のことのように語られながら、未だに霞の架かるもう少し先の歴史のボトルネックはこの時点だろうと我々は結論した。
「・・・ジェノサイドか。・・・これくらいの規模の壊滅状態だと、生きのびた連中の相互間の通信と言うか、連絡の経路もズタズタになって、実際何が起きたかなんて事は全く伝わっていかなかったんだろうな。生存者のいた地域ごとに、その時のその場所の状況が語り継がれるに過ぎなかっただろうから」
いつの間にかだいぶ暗くなっていた。日が長くなってはきたが、日没後はやっぱり冷え込んでくる。
「つまり、今の南北関係で人類の世界各地への拡散が進んだと見ないで、切り落とし<崩壊>前の条件で検討しないといけない訳だ」
「そうです。地球儀にテープを貼って崩壊前の赤道ラインを見てみますか」
「そうだな。だけど、次回にするか。だいぶ暗くなったし、そろそろ晩酌の時間だしな。ちょっとビールにつきあってくれ」
山村君が切り落としの検討を先にやろうと言った理由はわかった。ジブラタル海峡の決壊前と後では地球全体の陸地の配置が異なるので、進出ルートを考えるときには決壊前の状況を前提にするのが筋だからだ。特に東アジア方向への進出には誤差要因を取り除くのに不可欠である。何しろ裸の猿なのだから。
|
ビッグイベントの検討は以上である。残るのはこの事件に先立つ人類の展開と、事件自体の証拠探しである。
|