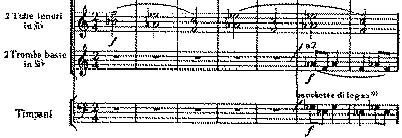
(ミニ・コンサート&D.ボストック氏講演他)
1998年10月23日、日本マルチヌー協会と合同で、第2回例会を開催いたしました。前半がマルチヌー、後半がヤナーチェクという構成でしたが、30名弱の参加を得て、盛況のうちに進行できました。
今回の例会の目玉は、指揮者ダグラス・ボストック氏による講演です。ボストック氏は、著名な指揮者マッケラスに劣らず、外国人にも拘わらずチェコ音楽に情熱を燃やしておられる方で、「新世界交響曲」の欧州初演を果たしたことで知られるチェコの伝統あるオーケストラ、カルロヴィ・ヴァリ交響楽団の常任指揮者を務める傍ら、世界各地で精力的な演奏活動されております。当日は、ヤナーチェクの傑作管弦楽曲「シンフォニエッタ」の構成と表題性等について、指揮者ならではの視点から、譜例を示し、CDで音を確かめ、時にパフォーマンス交じえながら、初心者にも分かり易く解説して下さいました。なお、例会終了後には会員とともにビアホールに繰り出し閉店まで付合ってくださいました。
ヤナーチェクはご存知のように1854年に生まれ、1928年に亡くなっています。この事実は、彼の錯綜したスタイルを象徴しています。すなわち、ブラームスが交響曲を作っていた時代から、ストラヴィンスキーが「春の祭典」を書いていた時期までが、ヤナーチェクの生涯に当たるのです。ヤナーチェクは、音楽史のなかで特異な位置を占めています。彼のスタイルは他の作曲家とは全く異なった極めて独特なもので、モラヴィアの歴史、チェコ=モラヴィアの音楽、総体としてのチェコの伝統(民謡、民族舞踊等)に深く根差しています。興味深いことに、ヤナーチェクはそれほど多くのオーケストラ曲を書いていません。声楽、合唱曲、後になるとオペラを数多く作っていますが、オーケストラ曲となると、初期では「弦楽合奏のための組曲」、「弦楽合奏のための牧歌」、「セレナーデ」、「ラシュスコ舞曲」、中期には「ブラニークのバラード」、「ヴァイオリン弾きの子供」等がある位です。そして、これらの頂点を成すのが、「タラス・ブーリバ」と「シンフォニエッタ」の2つの偉大な作品なのです。「ドナウ」交響曲に着手したものの、未完に終わりました。
さて、ここでは、私が指揮者として各地で何度も取り上げた「シンフォニエッタ」について、その経験と研究から得たものを、皆さんにご説明したいと思います。
まず、この曲が作曲された1926年時点での時代状況についてお話したいと思います。既にマーラー、ドビュッシーは、亡くなっていました。ストラヴィンスキーは、三大バレエを完成しており、この時期には新古典主義に傾いていました。シェーンベルク、ベルク、ウェーベルンは既に12音音楽を書いています。ラヴェルはなお創作を続けており、マルチヌーは、3年間のパリ滞在を終えています。こうしたヨーロッパ音楽のなんともエキサイティングな時代にヤナーチェクは晩年を迎え、20世紀の音楽の中でも最も個性的なものの一つを作り上げていました。この作品の初演は、1926年6月26日に、ヴァーツラフ・ターリヒ指揮チェコ・フィルハーモニーによって行なわれました。
この若々しく力強い曲が書かれたのは、ヤナーチェクが72歳の時であったということにまず驚かされます。この作品は、ヤナーチェクのスタイルの矛盾と、彼自身の矛盾を含んでいますが、彼としては稀なほど緊密な構成で書かれています。彼はシンフォニエッタの楽想を長らく暖めていたのですが、実際に作曲したのは極めて短期間、3週間ほどです。
ヤナーチェクは、往々にして外部の刺激からインスピレーションを得て作曲をしたのですが、このシンフォニエッタにおいても同様でした。彼は、1925年に女友達とピーセクの軍楽隊の演奏会を訪れ、兵士が立ったり座ったりを繰り返しながらトランペットのソロを吹くのを見て、最初の楽章の発想を得ました。第一楽章のファンファーレが、続く楽章を作り出す火花ないし触媒になったのです。より広く見るならば、ヤナーチェクは彼の愛したブルノの街に触発されてこれを書いたと申せましょう。ヤナーチェクは、チェコスロヴァキア独立(1918年)後、ブルノの将来について輝かしいビジョンを抱いていました。
シンフォニエッタの物語のはじまりは、いささか錯綜しております。ヤナーチェクはこの作品を何と名付けるかが、決められなかったのです。当初、彼は、ソコル体育祭のために作曲したため「ソコル・シンフォニエッタ」と呼びました。ついで、第一楽章のトランペットゆえに「軍隊シンフォニエッタ」と呼び、チェコスロバキア軍に献呈しようとしました。また、楽曲全体を「祝祭ファンファーレ」と呼んだこともあります。しかし、ヤナーチェクは、結局これを、英国人女性ローザ・ニューマーチに献呈することに決めました。彼女は、ヤナーチェクをイギリスへ招待した恩人です。そして、彼はこの曲を単に「シンフォニエッタ」と名付け、何も連想させないようにしました。第一楽章に入る前に、ヤナーチェク自身がこの曲に対して述べたことを読んでみましょう。
「シンフォニエッタがあらわしているのは、我々の時代の自由な人間、その魂の美、その喜び、またその勇気、勝利への意志である。」
ヤナーチェクは、この曲の名前を変え、形式を変え、何度も考え直したのですが、上述の主題に関しては一貫していました。初演のあいだにヤナーチェクは、各楽章の表題を書いていますが、これはあまり知られてはいませんし、楽譜にも印刷されていないことが多いようです。しかし、ヤナーチェクがその弟子に語ったところでは、この曲の鍵を知りたければ、かつて書いた表題をみるがよいということでした。
さて、第一楽章に入りましょう。この楽章は、きわめて風変わりな楽器編成でできています。シンフォニエッタ全体は、大編成のオーケストラと13の金管楽器のために書かれています。これは、特異にしてかつ、いかにも色彩を好んだヤナーチェクならではのことです。そして、オーケストラの外に置かれている金管バンドだけが、第一楽章で使われるのです。ヤナーチェクは、祝祭の色合いでこの楽章を奏でています。しかしながら、ティンパニを使うことで、このバンドとオーケストラをつないでいます。極めて厄介なことにティンパニは、バス・トランペットと全く同じ音符を叩いているのです(譜例1)。
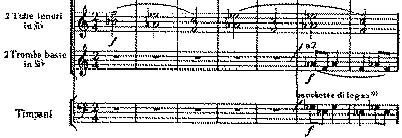
この点は、音楽家の方々にとっては面白いことでしょう。これは作曲者の手稿ですが、フレーズの長さを表しています。ここのスラー記号は、典型的なモラヴィア民謡のフレージングを作り出しているのです。ティンパニをレガートで叩くことは不可能です。しかし、作曲者の手書きならびにこの版スコアでは、レガートが付けられています。これはレガートではなく、フレーズがこう続いていることを表しているのです。これで楽節の長さを示そうとしたのです。これはほんの一例ですが、他にも楽譜の毎ページに、指揮者にとってのパズルとトリックが仕掛けてあります。
では、第一楽章を聴いていただきましょう。1926年当時、これがどんなショックだったか、ご想像下さい。大オーケストラがステージに乗っていながら、第一楽章の間ずっと沈黙しているのです。小さな断片を積み上げて楽章全体が書かれています。簡潔ですが、印象的な第一楽章です。最初のページにある小さな主題が、シンフォニエッタ全曲を支配することになります。時にはこれが巧妙に姿を変えて登場します。第一楽章で活躍した金管バンドは、最終楽章まで出番がないので、これを用意しなければならないオーケストラの事務方にとっては、なんとも厄介な曲でもあります(笑)。
より重要なことは、最初に登場した金管楽器を終曲近くまで沈黙させておくというやりかたです。これにより理想的にはすぐに続けて演奏されるべき第二楽章の冒頭は、全く異なった色合いを持つことになります。このようにヤナーチェクは、色彩の変化を好みました。映画で場面が変わるようにです。
第二楽章は、通常印刷はされていませんが、「城」と名付けられています。第一楽章が祝祭のファンファーレで終わり、今度は中世の城が登場するのです。ここでヤナーチェクは、幼少の頃から知っていたブルノの城(シュピールベルク)を描いています。ここでのオーケストレーションは、ヤナーチェクの典型であり、また大変巧妙に書かれています。4本のトロンボーンに弱音器を付けて低音で吹かせたのは、彼だけです。これで暗く、ミステリアスな音を出したのです。そして他方、クラリネットがせわしなく、まるで蜘蛛が巣を張るように動き回っています。 弦楽のピチカートが古城の雰囲気を出しています(譜例2)。

クラリネットが奏でているのが、チェコ=モラヴィアの民謡です。次に街の忙しそうな雰囲気になります。これはブルノの城のまわりで忙しく働く人達を表現しています。音楽はせわしくカラフルかつアクティブに続いていきます。そこからもっとロマンチックなメロディーへ移りますが、城の貴婦人を描いているのでしょう。最初の蜘蛛のような旋律も出てきます。その後いろいろなエピソードが登場します。ヤナーチェクにとって典型的なことですが、音楽がパステルのように、あるいは小さな包みを開くように、音色もテンポも突然変わっていきます。そして、それらが一体となって、ドラマチックな導入が作り上げられます。ここでは、バンドではなく本来のオーケストラのトランペットが活躍します。
ここのトランペットは、第一楽章冒頭のファンファーレを思い出させます。城の遠景をあらわしています。その幻想が破れたかと思うと、また帰ってきます。そして今度は、幻想がすっかり消えて、初めの陰鬱な雰囲気へ戻ります。次の楽章へ移る前、2楽章の最後の部分は、色彩のコントラストが鮮烈です。以上が、いかにもヤナーチェクらしいオーケストレーションを持つ城の楽章=第2楽章です。
さて、第3楽章へ。トテモキレイデスネ!(←ここだけ日本語)ロマンチックな尼僧の姿です。第3楽章は「女王の修道院」とタイトルが付けられているのです。この楽章の冒頭では、修道院を描いた安らいだ雰囲気を聴くことができます。第3楽章冒頭では、この曲で初めてハープが用いられます。この女子修道院の静かな雰囲気を出すためでしょう。しかし、先へ進むと、修道院とは似つかわしくないトロンボーンが鳴るようになります。
その理由は以下の通りです。、ヤナーチェクが少年のころ、ブルノへヴァイオリンのレッスンに行っていたのですが、いつもこの修道院の横を通っていたのです。ところで当時コレラが流行していて、少年ヤナーチェクは人々が死体を運ぶのに忙殺されているさまを見せられ、そこを駆け出して逃げ去っていました。この修道院の静けさと、恐ろしいまでにアグレッシブな音楽との奇妙な対比は、ここから出てきたものです。幼いヤナーチェクにとっては、何とも楽しくない体験だったことでしょう。オーケストレーションでもうひとつ面白いのは、コントラバスがこの楽章のほとんど終わり、第80小節まで出番がないことです。そこまで来たら奏者を起こさなくてはいけませんので、私はスコアの1小節前にメモしてあります(笑)。オーケストラの基底であるコントラバスを使わないことで音楽に軽味が生まれます。第2楽章の終わりから聴いてみましょう。楽章の初めと同じスタイルで終わります。これはヤナーチェクだけが作れるものです。ヤナーチェクは、オーケストレーションの極端なまでの対比を好んでいました。トロンボーンの低音とピッコロとフルートによる最高音が、強烈なコントラストを形成しているのです。もうひとつ、チェコ=モラヴィアの音楽につきものですが、「タター、タター、タター」という短長音の組み合わせが聴かれます。これはチェコ語に由来します。ここからチェコ=モラヴィアの民謡のリズムが生まれ、この箇所でのトロンボーンがまさにそれを奏でているのです。それから再びロマンチックな部分に帰ります。
音楽はテーマを展開しつつ進行します。その後、オーケストラ音楽の中でも例外的なページに行き当たります。
ここでもトロンボーンが短長のリズムを繰り返しています。テンポ指定はプレスティッシモです。他方バイオリンとビオラが対称的な音形を弾いていますが、これが実は第一楽章冒頭の主題の変形です。もしも楽譜をお読みになれなくても、このあたりに音符がどっさりと書いてあって譜面が真っ黒なことはわかると思います。ヤナーチェクは往々にして、テンポ指定にあまり神経を使っていなかったのですが、ここは極端に速く、1小節1拍です。これではフルートが全く演奏不能になってしまいますので、ここは半分のテンポで演奏するしかありません。このようなことは、ヤナーチェクではよくあることです。このあたりから楽章の最後までが、色彩の変転のピークでしょう。
第4楽章は「街路」というタイトルが付けられています。子供の頃、ヤナーチェクはブルノの賑やかな通りがあまり好きではありませんでした。しかし後年、ブルノを拠点に活動し、この町の重要人物になると、ここの雑踏を好むようになります。この楽章はオーケストラのトランペットで始まりますが、このメロディーは、第一楽章のものと関連があります。人々が気忙しく通りを行き交います。まもなく教会の鐘が聞こえてきます。ほんの短い2小節の間、我々は雑踏を離れて教会へと赴くのです。再び街路へ戻ります。また教会が現れます。そして街頭でおしゃべりをするご婦人方。先程の修道院を思い出させるような部分もありますが、再び賑やかな通りでこの楽章は閉じられます。
さて、最後の楽章へとやってきました。この楽章は「市庁舎」と名付けられています。後になってヤナーチェクは、子供の頃自分は陰気でおぞましい市庁舎が大嫌いだったと回想しています。しかし、やがてこの建物を気に入るようになります。この楽章は、陰鬱な感じでスタートします。これもやはり第一楽章のあの主題に関連しています。指揮者にとっては、この楽章は組み立てるのが大変難しい曲です。というのも、各声部のテンポが様々に異なっているからです。この楽章でもヤナーチェクはオーケストラの最高音と最低音部のコントラストを際立たせています。例えばピッコロとトロンボーン。このクラリネットは、何かを求める魂のようです。
一匹狼のヤナーチェクが真実と美を捜し求めている姿のようでもあります。しかしここで、この曲全体でも最も天才的ともいえる一撃が振りおろされます。第一楽章の最初が帰って来て、音楽によるアーチが架けられて全曲を閉じます。美と真実の探究の答えとして、バンドのファンファーレが鳴り響くのです。ただし今度はバンドのみならず、全オーケストラがこれを奏します。
シンフォニエッタは、オーケストラ曲の中でも最も美しい作品といえます。これは演奏が甚だ難しい曲でもありますが、演奏効果の高い曲です。あらゆるチェコ音楽の中でも、というより世界の音楽の中でも特異な地位を占める作品と思うのは、私だけではないはずです。東京で演奏されることがあれば、是非お聴き下さい。たぶん私もこれを東京で指揮する機会があるかと思います。
1955年イングランド生。シェフィールド大学で指揮、音楽学、作曲を学び、ロンドンでA.ボウルドに指揮法を師事。その後、ドイツのフライブルク音楽大学でF.
Travis に師事。1979-93コンスタンツの音楽監督に就任。1982年から西南ドイツ・フィルはじめBBC交響楽団、プラハ交響楽団、チェコ放送交響楽団、ハレ交響楽団などに客演した。1991年には、カルロヴィ・ヴァリ交響楽団の常任指揮者に就任する。1993年には、アメリカデビューし、コロラド、シカゴ交響楽団などを指揮した。1994,95年には来日し、群馬交響楽団、芸大オーケストラを指揮(マルチヌー:交響曲第4番、A.ドヴォジャークの謝肉祭など)。1995年からは、「プラハの春」音楽祭、指揮者コンクールの審査員を務め、指揮のレッスンにも意欲的に取り組んでいる。
主要なレパートリーはチェコ音楽、20世紀フランス、イギリス音楽のほかアメリカやスカンジナビアの作曲家など。最近はネドバルらの作品を録音している。
付記:以上の講演録は、講演者の了承のもと、当日の録音から編集したもので、若干の割愛、要約を含んでいます。なお、当会の関根日出男顧問の御友人の増田紘一氏に、この英語講演の通訳をお願いいたしました。当日講演とともに録音された同氏による訳がなければ、この講演録の作成は到底不可能であり、増田氏の御尽力に厚く御礼申し上げる次第です。しかしながら、本講演録の文章にいささかでも不備があれば、その責任はすベて編集側にあることは、いうまでもありません。