大株の植え替えは、数年に一度で大丈夫ですが、尺を越える鉢を使用する様な大株は、
地中根が退化して、根鉢が小さく成っている場合が多く、株と鉢のバランスを保つために、
根鉢より大きな鉢を使用する結果になり、用土を多量に使用する事になり、大きな鉢では、
鹿沼土なら2袋以上も入ってしまうことが有ります。
幸いな事に、私は鹿沼土の産地が身近に有り、比較的安価で入手できるのですが、
市販の用土を使用する場合は、用土の費用も負担が大きいと思います。
また全てを鹿沼土などで植えつけると、重量も重くなり移動も困難に成ってしまいます。
その様な事から尺鉢を越える大物の植え付けは、皆さんそれぞれに工夫をされています。
以下に私の知りえるいくつかの方法を、参考までに紹介します。
|
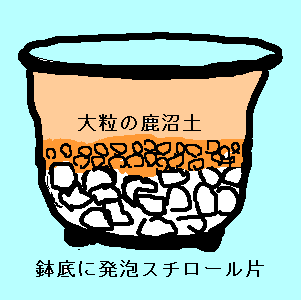 |
この方法が一般的で最も多く多くの方に 用いられている様です。 前にも述べましたが、大きな古株では、 地中根は意外と少なくなっている物が多く、 鉢底まで届くほどの根が無いのが実情です。 大きな鉢を使用する場合には、鉢底には 魚箱等に使用される、発泡スチロールを 適当な大きさに割って入れます。 其の上に大粒の用土を敷き詰めてから 巻柏を置いて見て、高さの調節を図ります。 良ければ其の位置から、植え付けの用土を 入れて植えつけます。 |
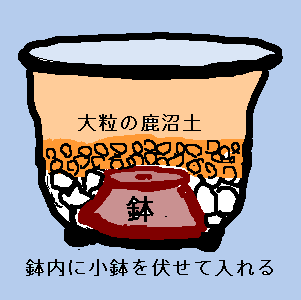 |
この方法を用いると、発泡スチロールが 巻柏の重量で潰れて沈む事が無くなります。 大きな鉢の底に駄鉢を伏せて入れるのですが、 中に入れる駄鉢の縁が、大鉢の鉢底に密着 してしまうと、水が捌けなくなってしまうので、 大鉢の鉢底と駄鉢縁の間に、鉢のかけら等 を入れて隙間を作り、水捌けを計ります。 中に入れた駄鉢の周囲には、鉢の高さより 低めに、発泡スチロール片を入れます。 其の上に大粒の用度を入れて、高さの調節を 計り、良ければ植え土で植え付けます。 私はこの方法を用いています。 |
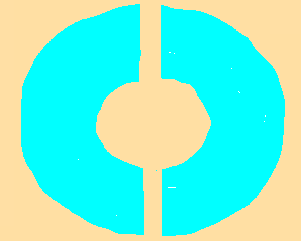 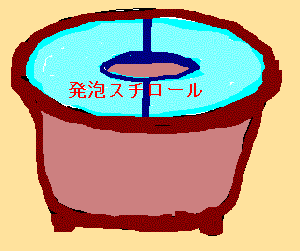 |
この方法は少数の方が実施しております。 全く植え土を使用しないので、用土の費用も 全く掛からず、古い土も出ない訳ですから 市街地にお住まいの方でも、古土の処理に 困る事も無く、良い面もあるのですが、 私の考えとは相いれない部分が有りますので、 私は行って居りません、理由は後述します。 私は実施した事が無く、完成品を拝見して おおよその手順を推測して紹介するもので、 あるいは誤った部分が有るかも知れませんが、 ひとつの方法として紹介致したく思います。 手順は、厚めの発泡スチロールを用意し、 鉢の内径と巻柏の根塊の太さに合わせて、 左図の様な形に切り抜いて準備します。 巻柏の地中根の部分を切除します。 鉢の中には、水分を含む事の無い軽量な 材料で、巻柏の台になる物を入れます。 台の上に地中根を切除した巻柏を立てて、 前記で準備した発泡スチロールで挟み付け 巻柏が倒れないように押さえつけます。 |
| 以上ですが必要に応じて、発泡スチロールの上に、化粧砂等を乗せて押さえ板を隠すと、 見た目には植え付けてある物と同じに見えます。 この方法は前記したような利点もあるのですが、私の考えには相容れない部分があり、
私は実施に踏み切れません。
この方法を否定するつもりは有りませんが、私が実施しない理由を以下に記して見ます。
1、湿度を保つ植え土が無く、地中根も無く全く活躍しない訳ですので、根が地中の水分を
吸い上げて、根塊の湿度を維持保湿する術が無いので、乾燥が激しくなると思われます。
2、頻繁に水を与えられない場合は、乾燥を防止するために、必然的に株間に詰め物を
する等の対策が必要になります。
3、詰め物を多用する結果になれば、詰め物内で新根が活躍を始め、葉は若返って
一時期は元気になりますが、機能しなくなった本来の幹(根塊)の死滅を招きます。
4、 特大株の根幹ですから幹(根塊)は太く、死滅しても相当の年数は持ち応えるでしょうが、
死滅した根塊は、やがては朽ち果て、ばらけて倒れてしまうのではないかと思われます。
5 少しでも地中根が活躍している幹(根塊)は、永久に生き続けると思われますので、
私は少ない地中根でも大切にしたいと思い、あえてこの方法は実施せず、用土に植えて、
地中根が少しでも多くなる事を願いつつ管理しています。 やむおえず私の手を離れる時が来ても、愛培を引き継いでくれる趣味家の手によって、
この巻柏が永久に生き続ける事を願って、将来を見据えた管理をしています。
|