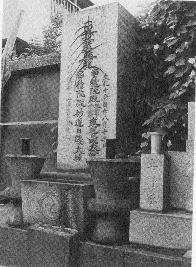矢部定謙(さだかね またはさだのり)
通称彦五郎、官名左近将監、駿河守。 天保時代に勘定奉行、町奉行などを勤めた旗本で、岩瀬忠震、川路正漠とならぶ幕末の三俊(川崎紫山)にあげられるほど、能吏としての評価も高いが、一方、敵も多く毀誉褒貶の多い人。 最後には自ら飲食を絶ち餓死するという壮絶な最期を遂げている。
300俵という小身旗本の家に生まれたが、堺奉行から大坂西町奉行として実績をあげた。 大坂時代に部下の与力大塩平八郎の建策をとりあげ大坂市民の飢饉対策を行ったという。
天保飢饉のさなか、7年(1836)江戸に戻り、勘定奉行に抜擢されるが、西の丸再建問題で老中水野忠邦と意見が合わず、西の丸留守居役に左遷される。
やがて水野と和解、南町奉行に就任するが、天保改革を進める水野忠邦と改革の進め方で再び対立する。
水野のもとで改革を実行する鳥居忠耀の策謀により就任わずか8ヶ月で町奉行を罷免され寄合(無役)となる。
4ヶ月後の天保13年3月、評定所で改易を申渡され、伊勢桑名藩へお預けとなる。 幽閉先の桑名では水野、鳥居などへの憤りから自ら飲食を絶ち餓死したと伝えられる。
左は矢部の和歌短冊「述懐」
桑名市博物館「桑名藩矢部駿河守預り関係史料」より
たかへしと心のみこそいたまるれ
罪をたたすも神ならぬ身は 定謙 |
矢部定謙関連年表
| 寛政元年 |
1789 |
誕生。 父は旗本矢部定合。通称彦五郎。
幼少期に父が堺奉行を任命されたため堺に住んでいる。 |
| 文政6年 |
1823 |
御小姓組から小十人組頭 |
| 文政11年 |
1828 |
先手鉄砲頭、後に火付盗賊改加役 |
| 天保2年 |
1831 |
堺奉行 |
| 天保4年 |
1833 |
大坂西町奉行 |
| 天保7年 |
1836 |
勘定奉行、500石加増 |
| 天保9年 |
1838 |
西の丸留守居役 |
| 天保11年 |
1840 |
小普請組支配 |
| 天保12年 |
1841 |
4月28日 南町奉行
6月2日 奉行所内刃傷事件
8月12日 左近将監から駿河守に改称
10月3日 老母看病のため月番 北町に交代、
10月5日 老母葬式
10月29日 忌明け 吟味再開
12月21日 南町奉行罷免
|
| 天保13年 |
1842 |
3月22日 評定所で改易の申渡し、桑名松平家にお預け
5月13日 桑名に到着
7月27日 桑名城内で死亡 |
仁杉五郎左衛門との関わり
矢部が南町奉行に就任する前と後で五郎左衛門との関係が一変する。
西の丸留守居役の閑職にあった矢部は、何とか返り咲きたいと5年も前のお救い買付の顛末を調べていた。 勘定奉行の職にあるときに五郎左衛門達が担当したお救い米の買付けに賄賂や不正があったのではないかと調べがあったが、これは職権だった。しかし西の丸留守居役での調査はは職権外である。にもかかわらず買付にあたった関係者を呼びつけるなどして執拗に調べた。
商人の仙波太郎兵衛、五郎左衛門の部下堀口六郎左衛門などの関係者の口を割らせるのに姑息な手段を使ったとする小説もあるほど、この職権外の調査は異常であったが、買付に不正があったという報告書が老中に提出された。
5年も前の些細な賂や商人に対する強制は普段なら問題にもならないが、折から天保改革を進めようとする水野にとっては改革の姿勢を世に示す格好の「戒め」になると考えたか、これをもって南町奉行筒井伊賀守を罷免し後任に矢部を充てた。
ここまでは五郎左衛門にとっては、5年も前の事をあばこうとするいわば敵方であった。
しかし、矢部が奉行になると立場が一変する。
新任の奉行にとって奉行所内を掌握する支配与力の五郎左衛門はナンバー2として矢部を支え立場になった。五郎左衛門達の強引とも言えるお救い米の買付けは、江戸市民の飢餓を何とか救おうとするやむを得ない状況であった事がわかると、五郎左衛門達の処分を何とか「謹慎」程度の穏便なものにしたいという立場になった。
6月になって佐久間伝蔵が堀口六左衛門の息子を殺害するという奉行所内刃傷事件が起きたが、これもお救い米事件が原因しているにも関わらず、佐久間の乱心ということで済ませ、五郎左衛門たちに波及しないように計らった。
いわば五郎左衛門達の擁護に回ったのだが、これが後に鳥居の付込む理由となり、奉行就任わずか8ヶ月で引きずり降ろされ、鳥居が後任の奉行となった。
翌年3月には同じ評定所で五郎左衛門は「存命なら死罪」、矢部は「改易、松平家にお預け」という武士にとって屈辱的な判決を申し渡された。
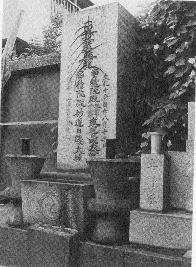 |
父矢部定令の墓所(東京江東区浄心寺)
後に許されてこの墓所に改葬されたという。 |
三田村鳶魚の見方
水野と矢部の対立
水野、矢部の対立の始まりは天保9年(1838)の江戸城西の丸の新築問題だったという説がある。
11代将軍家斉は50年の君臨の後、天保8年にようやく隠退して西の丸に移った。
ところがこの西の丸が翌9年の3月に全焼した。水野忠邦は家斉へのおべんちゃらから、諸大名から寄付をつのって新築しようとはかった。
これに対し矢部は、連年の凶作で全国諸藩は疲弊しているから、とても西の丸新築に協力する余力がない。この際、大御所はご不自由でも三の丸に移っていただくことにしたらどうか、と水野に進言した。
しかし三の丸は狭い上に低湿の地で、家斉がいやがっていることを知っている水野は、矢部の進言をしりぞけて西の丸新築に踏みきった。
これが水野、矢部対立の第一歩だという通説になっている。
しかし、これはおかしい。西の丸炎上は九年三月、矢部が勘定奉行を罷免されたのがその前の2月である。西の丸再築の問題が出たときには、矢部はすでに西の丸留守居という閑職に飛ぼされていて、とても幕政に発言できる立場ではなかった。
水野、矢部の関係についてはもう一つの説がある。それはあるとき矢部が水野に会い「城内に、ご老中が何千両かの賄賂を取ったという説が流れている。ご注意ありたい」といった。
水野は「自分のまったく知らないことだが、家臣の中にそういう悪事を働いている老がいるかもしれない。調べてみる」と答えた。
帰邸した水野はすぐに金座の後藤三右衛門をよびよせ、その何千両かを調達させて賄賂の相手に返却した。翌日、水野は矢部をよんで「あの話は家臣を調べたところ、一人該当老がいたので直ちに処分し、金は返さした」といった、というのである。
この話のポイントは、矢部の耳打ちを水野がどう受けとったかにある。
賄賂のうわさという火種の広がらぬうちに早くもみ消してしまいなさいという、水野のためを忠った好意的な忠告と受げとるか、あるいは「こいつは、あなたの弱点を知っていますぞとおれを脅迫している」と受けとるかは水野自身の心境による。
水野はどうやら矢部の脅迫と受けとったようで、これが後の矢部断罪という苛酷な処分の伏線となったらしい。
以上の二説は当時の幕臣の間に広く信じられていた風説だが、もう一つ、これは問違いないという両人対立の史料がある。それは「三方領地替え」問題である。
三方領地蔓というのは、家斉の死の直前の天保11年11月1日に布告されたもので、家斉時代末期の幕政の腐敗の見本のような事件であった。
事の起こりは川越藩で、藩財政のやりくりに音をあげた川越藩が、もっと実入りのいい土地への移封を計画して庄内藩に目をつけた。
この実現にはお定まりの賄賂と大奥への働きかけがあり、川越藩は庄内へ、庄内藩は越後の長岡へ、長岡藩は川越へと、玉突きのような領地替えが命令された。このときはすでに水野忠邦が老中首座についていて、領地替え決定の責任は忠邦にある。
三方領地替えで最も頑強に反対したのは庄内地方の藩士と領民であった。酒井家が庄内地方を領してからすでに200年を越している。
この2世紀の長い年月の問に藩士と領民たちの問に深い人間関係、経済関係が生まれている。これを一片の幕命で切り離して移封だといわれても、すぐには承服できない。藩主の酒井左衛門尉忠器は、藩士や領民に幕府の移封命令におとなしく従うようにとたびたび布告を出しているが、反抗の騒ぎは一向におさまらず、かえって激化していった。
この騒動の最中に、矢部定謙は南町奉行に復活していた。
先に矢部は勘定奉行から西の丸
留守居の閑職に飛ぼされ、さらに2年後の天保11年に小普請支配に移った。
この職は、小普請組にいれられて非役でくさっている連中の訴えや勤務の希望を聞くのが役目で、3、4千石級の旗本から選ばれる(定員8名)。
人材発掘が仕事というのは昔の話で、のちにはヒマな閑職となっていた。
矢部が町奉行に返り咲いたのは天保12年4月28日である。
水野忠邦が本当に天保改革のスタートを切ったのは5月である。
いよいよ上からの強権による改革を始めるには幕府の人材を身近に揃えて、上の命令を推し進める布陣をかためねぼならない。
忠邦ばさきに矢部を勘定奉行の地位から追ったが、いざ改革の仕事とするとなると、実力と信用を兼有している人物を必要とする。矢部がその選にはいったのではないか。
町奉行就任後の8月11日、酒井忠器の家臣二人に対して、矢部の名で処罰が下されている。一人は同家の留守居役・関茂太夫で「主家のためと一方的に迷いこんで、自分一人の判断で元お側役の水野美濃守(忠篤)家来たちに賄賂を使った」ので押し込め。もう一人は同藩郡代の石川儀兵衛で「庄内藩の百姓どもが11月に江戸に出て、幕府要人に駕籠訴したのに対し、石川は自分の判断で手当金をくれた。
そこで百姓どもはよくやったとほめられたものと勘違いしてまた駕籠訴をした。これはまことにけしからん行為」なので押し込め。
矢部はこのように酒井家の家臣の移封反対運動をおさえる行動をとっているが、内心は別で、水野忠邦に対し、三方領地替えの再審を始めるよう進言した。大塩平八郎の公憤による激語を理解した矢部定謙らしい心情がここにも生きていた。
面白くないのは水野忠邦だった。手足となって命令どおり動くものと期待して起用した矢部に裏切られた。
天保12年7月13日、つまり三方領地替え中止決定の翌日、忠邦は胸痛を理由に登城せず、かわりに同僚の老中・土井(大炊頭)利位に書状を送った。
「昨日の御決定は、人心も敬服し、国家もますますおだやかとなり、まことによろこばしい。しかし幕府において一度決定した移封の件が取りやめにたったというのは、元和以来まったく前例のないことである。
これはつまるところ私の前調査の不ゆきとどきの結果だと深く恐縮している。
右の不調法をやりながら、退職もしないでおれば衆人の批判のマトとなり、上の御威光にもかかわり、諸大名支配という重い任務に対して何の面目があろうか。
したがって老中の職を辞退することに決心した。よって今日よりは病気と申したててひっこみ、身を慎んでいたい」
忠邦は老中辞職を申し出たのである。これに対し家慶将軍から「3家移封の件は越前守の取りはからいが不ゆきとどきというわけのものでないから、辞職というような心配をせずに、ただちに今日から出勤するように」との言葉があった。
忠邦には自分の一存で唐津から浜松に移封した経験がある。だから他の大名、とくに譜代の大名なら、主人の徳川家より一時お預かりした封土を、主家の命令により替えるというのは当然あり得ることで、藩士や領民の反対などあってはならないことなのである。この意識がのちの上知令にも出ていて、これが天保改革と忠邦自身の命取りとなった。
ともかく三方領地替え問題が矢部定謙の運命を決めた。
町奉行に再起用された4月28日より僅か8カ月後の天保8年12月21日に矢部はその職を追われた。そしてさらに翌年3月には罪囚の人という厳罰が待っていた。
矢部の罪とは何か
矢部定謙を死に追いやった厳罰には、もちろん水野忠邦の意図が働いていたに相違ない。
町奉行という重職にあった者に、家名断絶、本人は他家預けという重罰を課するのは、幕府の歴史においてほとんど前例がない。
ここまで異常な手段をとったというところに、老中首席という最高実力者の意図の反映がうかがえるし、矢部に対する忠邦の憎悪の深さを感じとれるのであるが、同時に、矢部の罪状形成に働いた人物、つまり目付の鳥居耀蔵の存在を見のがすことができない。
矢部定謙を厳罰に処する□実としたその犯罪とは何か。矢部はよほどの犯罪をおかしたようにみえるが・それを天保13年3月21日に彼に下された判決書にみると、それはつぎのような内容で、奇怪きわまる文書である。
天保7年のころ・南町奉行所属の与力に仁杉五郎左衛門という男がいた。
天保7年の9月には矢部はまだ大坂町奉行で、もちろん仁杉なる人物と何の関係ない。
9月末には江戸に戻って勘定奉行になったが、仁杉は町奉行所の与力だから、もちろん無関係である。ところが矢部の判決書
1)仁杉五郎左衛門は去る7年、市中御救米取扱掛をつとめていたが、その米の買付を町方御用達の仙波太郎兵衛ほか二人に申し付けた。
この時、仁杉は反物などを受け取った。さらに太郎兵衛の米買いつけが遅れたとき、厳しく遅れた理由を問いただしはしたし、太郎兵衛が持ってきた金子入りの菓子箱は返しはしたものの、これらのことを上司に報告しなかつた。
さらに仁杉は・買いつけ米の方のはかがいかないからといつて、自分の一存で、深川佐賀町の又兵衛という男を太郎兵衛に紹介して、太郎兵衛の手代という名目にして越後にいかせた。
又兵衛から米代金為替を送るよう知らせがあったとき、仁杉は太郎兵衛に大金の調達を申しつけて、それができなければ太郎兵衛の沽券を取りあげて、それを担保に金をつくるなどと強圧的に出て、とうとう1万両の為替をつくらせた。
又兵衛の買いつ米は500俵余りになつたが、この米の売却金と、以前からの米との相場違いで浮いた金から仁杉は200両を受け取つた。
2)さらに買いつけ米の勘定書をつくるとき、太郎兵衛ほか二人に、又米兵衛が越後で買い付けた米が延着してその時の相場より安値の場合、不足金は勘定のほうに組み込んで、事実と相違する帳簿をでっちあげた。
さらに、買い付け米を江戸であつかって価格操作に協力した本材木町の孫兵衛たちには、新規に米問屋の中に加えられるようにとの願書を差し出させ、仁杉はこの願書に筆まで加えてやり、やがて願書どうりに東国米穀問屋の名が許可された。
このお礼として問屋たちから、鰹節一箱、具足代65両が仁杉に送れれた。その後毎年、仁杉と妾へ2両2分ずつおくられていた。
また彼が大坂に旅立ったとき、餞別として50両を受け取った。
3)仁杉の息子の鹿之助が与力見習い中に突然家出した。
武州瀬戸村の藤助方にいるという話を聞いた仁杉は、部下の同心、佐久間伝蔵ほか1名を同村にやって鹿之助を連れ戻した。
また鹿之助は身持ちが悪く金を使うので仁杉も金に困り、孫兵衛から融通を受けることがあった。
このように、仁杉は御救米掛の幹部連を指揮する立場におりながら、公儀を欺く手段をとったことはまことに許し難い。生きているなら死罪を申し付けるところだが、病死したとのこと。しかし死罪の旨は承知せよ。
右のように、判決書の前半は与力・仁杉五郎左衛門の生前の、御救米買いつけ担当時の不正をあばいて糾弾している。天保の飢饉がこんな形で汚職を生んでいる。
また米の買いつけと江戸集中ということでは大坂も同じ被害者で、これが大塩平八郎の乱を生んだ。
飢饅は餓死者を生むと同時に、官僚と御用商人の結託という図式をもつくり出している。
それはそれで時代解明の史料だが、それと矢部定謙とどういうかかわりがあるのか。
4)さて矢部駿河守、彼が町奉行を勤めていたとき、部下に与力仁杉五郎左衛門、同心堀口六左衛門ほか5人がいた。
この者どもが去る天保7年、御救米取扱掛を勤めていた際いろいろの不正を働いたことの内容については駿河守も知るまい。
しかし、以前に勘定奉行在任中に、町方御用達の仙波太郎兵衛より右御救米勘定書の写しを内々に受けとっているし、さらにまた西の丸留守居のとき堀口六左衛門をよんで、こつそり調べている。
それなら町奉行に就任したならば早速厳重な取調べがあって当然なのに、一向にそんなことがなかった。
5)右の六左衛門伜の貞五郎を、同心の佐久間伝蔵が殺害し、高木平次兵衛にも傷を負わし、伝蔵自身は自殺したという事件のとき、六左衛門と妻かねに何か心当たりはないかと駿河守自身が聞いたところ、御救米勘定のことで六左衛門たちが自分らの不正をかくすために、あれは伝蔵が主として担当していたことだといいふらしたものと誤解して伝蔵が刃傷におよんだことだろうとの書面が提出された。
6)すべては仁杉五郎左衛門の不正より起こっているのに、駿河守は、彼は凶年の危急を救うという緊急の際に格別に骨を折った者であるから、寛大な処分を願いたいというねらいで、お暇(いとま)で押し込めぐらいで済むとの内意を、本人に伝えていた。
ところがいろいろ仁杉らを調査し審問したところ、不ゆきとどきの一切を白状したので、本人は死罪、そのほかの者どももそれぞれ仕置きされた。
7)右の一件において駿河守は、まず第一に町奉行就任以前には白分の管轄以外の者たちと話し合い、調べをやるという筋違いのことをやっている。
第ニに町奉行に就任後はかえって犯罪を取りつくろうようなやり方を進めていた。
とくに初めに事件のことを矢部に尋ねたときは、まるで覚えのないことだといい、再度の尋ねには、そのとおりだと答えたのは、まことに不明朗な態度である。
8)さらに右の取調べ中は、とりわけ身を慎んでおるべきなのに、みだりに懇意の考たちへ、こんどのことは無実の罪だなどとの書簡を送り、または御政治向きや諸役人のことをいろいろ誹謗した。
この誹謗は自分に同意する者たちの口から方々に流したりしたが、これは人心をまどわせ、たぶらかす行為というもので、その身分に似合わぬものであり、心底不ゆきとどきの至りである。これによって松平和之進へお預げを申しつける。
右の通り、今日評定所において、大目付初鹿野美濃守殿、町奉行遠山左衛門尉殿、御目付榊原主計頭、お立合いで申し渡す。
軽い罪に重い罰
右の罪状認定判決文によると、矢部の罪状たるものは、長文の判決文の終段のところにちょっとあるだけである。
それは第一に矢部が勘定奉行および西の丸留守居のときに筋違いの調査をしたこと。
第二に、町奉行就任後、以前の仁杉五郎左衛門らの犯罪に対して重罰の判決を下すべきところを、かえって取りつくろって罪一等を減ずるよう態度に出ていたこと。
第三に、矢部は最初の尋問には事実無根といい、再尋間には事実を認めているが、これは「彼是れ以って御後闇き致し方」という非難をされている。後ろ暗き行為というのは当時の武上用語で、現代には適当な訳語がない。
第四に、取調べ中は言動に注意すべきなのに、逆に知人らに無実を宣伝している。
これは高い身分の老に似合わない行為で、精神のあり方がなっていない、というような罪状判定である。
武士倫理は別のものであり、かつ倫理と法令とがいりまじっていた当時としても、この矢部に対する罪状認定は不当のものであり、それによる他家預けという判決は、前代未聞の重課である。
第一の筋違いの調査という点は、幕府の高級官僚となれぱ、交際上からいろんな情報が耳にはいるし、勘定奉行としては御救米に関する勘定書の不正は、むしろ役目上知っておかねぼならぬことである。
第二の与力らの犯罪に対し、取りつくろって軽い刑罰で処理しようとしたのがけしからんというが、判決の重い軽いは判断の問題であり、とくに死罪かどうかの判決には慎重でなけれぽならぬ。矢部は容疑者の死を救うという方向をとったもので、これを「取りつくろい侯取りはからいぶり」といって、矢部を非難している。
また最初の審間で「身に覚えがたい」といい、再審では「事実そのとおり」と罪状を認めたのは武士にあるまじき後ろ暗い態度だと批判し、罪状の一つに数えている。
しかし矢部は、もし自分が何かのことで疑惑を受けたときには、初審には実を述べてすべてに隠しごとをしないが、再審三審にはいいわけは一切しないで審間に服するという信念を持っていた。
これは大坂町奉行のときに自分に課した信念だが、事実ではないといって尋問の疑点を否定するのは、上(将軍)の不明を証明することになるから、という武士道の倫理観に立つものである。判決書にはこの点をまったく反対に解釈して、罪の一つに数えている。
取調べ中の矢部が、冤罪だという書簡を親しい人に書いたことがどうして断罪の材料になるのか。
「心底不行届の至り」と判決書にしるされている。どれもこれも矢部を罪に落とすに値しない些細なことであるし、そもそも与力仁杉五郎左衛門のお救米不止事件は天保7年に起こったことで、当時の仁杉の所属した南町奉行・筒井(伊賀守)政憲が責任を負うべきものである。
筒井は文政4年から天保12年までの丸20年間も南町奉行を勤めていた。仁杉の事件はまさに筒井の在任中に起こったもので、矢部定謙にとつて、自分の町奉行葎五年前の、前任蕎井のときの事件に責任を負わされてはたまったたものでない。
同時に筒井は仁杉事件の後5年問も平気な顔で何もせずに奉行で居座っていたことになる。
筒井が町奉行をやめたのは老齢(63歳)が理由で西の丸留守居に移された。
矢部審問のときに筒井も調べられたが、筒井を狙った事件ではないのでたいした処分にもあわず、嘉永7年(安政元1854年)には76歳で大目付に復活、幕末外交に働いた。
おとなしく上の命令どうり動いておれぱ、かくも高齢で幕府の第一線で働いておれるという見本のような人物である。
実質的な責任者は筒井政憲であるのに、こっちのほうはほったらかしで、事件をもっぱら矢部
定謙のほうに持ってきたのは、これで矢部を町奉行から追放するだけでなく彼の幕臣としての
生命を断つという陰謀があったからである。
矢部追放の口実さがしの探索に当たる者としては、南の矢部と同役の北町奉行の遠山景元がいる。たしかにと遠山は、矢部の判決において評定所の立会人として名をつらねている。
しかしこれは評定所の構成人として町奉行が一人必要だからであって、遠山が本心からこの判決に賛成したとは考えにくい。
遠山はこのすぐ後に、天保の改革の反対派に回り、鳥居耀蔵、いや南町奉行鳥居甲斐守のスパイ攻勢を受けるのだから。
陰謀に動いた人々
南北の町奉行所が連前からも実際からも動かないとなると、矢部の探索に働く者は目付だけとなる。
目付の下には徒目付、小人目付、黒鍬の老などの探索の専門家がそろっている。
鳥居耀蔵は水野老中から「矢部の後はお前だよ」と耳打ちされたに相違ない。
矢部の町奉行罷免発令が天保12年12月21日で、その一週問後の同月28日に耀蔵が後任となっている。耀蔵は町奉行昇進とわかっていただけに、矢部の探索には欣喜雀躍して当たっただろうと想像される。
もう一人、矢部の探索に当たった考としては、評定所の判決の立合い人として名をつらねていかずえのかみる目付の榊原主計頭忠義が考えられる。
立合い人の目付としては鳥居耀蔵が名を出して当然なのに、榊原となっているのは「榊原が出ておれぼ同じことだ」という耀蔵の意図が感ぜられる。榊原ははっきりした鳥居派であったからである。
川崎紫山の『矢部駿州』によれぽ、矢部が追放地の桑名で絶食しているとの報で、将軍家より奥医師の中川道玄がつかわされた。
矢部は中川の調合した薬を固辞して、ただひとっ頼みがあるといい「自分は上への恨みはまったくないが、ただ三人だけに恨みがある。その三人とは、水野越前守、鳥居甲斐守、榊原主計頭である。この人びとの末路を必ず見とどけてくれ」と中川にいったという。
ここに榊原の名が出ている。矢部を罪に落とすことに実質的に働いた人びとの中に目付の榊原がいたことは、当時の人びとの常識であった。
ただし鳥居耀蔵が矢部追落しに具体的にどのように働いたか、という証拠となるべき史料はない。
矢部への罪状判決文の後段に「(仁杉五郎左衛門に)御暇、押込め申しつける方に内意申し聞かせ侯につき、吟味遂げ候ところ、品々不行届きの始末、白状におよび…」という一節がある。この「吟味遂げ候ところ」の吟味はだれがやったのか、主語が抜けている。
「御目付.鳥居耀蔵と榊原主計頭が吟味遂げ候ところ」とすれぱよくわかる。
矢部定謙にもう一人、深い恨みを抱いている人物がいた。金改役の後藤三右衛門である。
のちのことになるが、天保15年(弘化元年)9月の、水野忠邦罷免直後に三右衛門が、つぎの幕閣の実力者と狙いをつけた側用人の堀親■(ちかしげ)に必死の思いをこめて提出した陳情書の中に、矢部に対する恨みが述べられている。
それは天保7年、矢部が勘定奉行になった年に、金銀両座と蔵前札差に対し50万両の上納金を申しつけたことである。
両座と札差たちが集まってどうしようかと相談したとき、三右衛門の譜代の家来で80歳近くになる井田芝山という経済通が進み出て「この命令はかれこれ評議することなく、すみやかにお請けになるべきである。上より暴虐の命令があるときは、必ず後年にわれらに吉事がある前兆であるし、上には必ず悪事が報いとしてくる」といったので、すぐにお請けの返事をして、三右衛門や家来たちが家財を売り払ってまでして、その年のうちに10万両を上納した。
三右衛門は、この天保7年の上納金という暴政のむくいで、幕府にはつぎつぎに凶事が起こっているとして20項目の実例を挙げている。
ここのところがのちに三右衛門死刑判決の一つの根拠となったのだが、ともかく幕府方の天罰20番目に挙げられているのが矢部定謙の失脚である。
「上納金取り立ての大棟梁矢部駿河守、改易絶命。7年目に至りて因果ことごとく元に帰し仕り侯」と書いている。
矢部の上納金下命は老中の決定を、勘定奉行という職務上から代表して申し渡したに過ぎない。それを三右衛門は矢部個人のせいにして恨みつらみを並べている。
この恨みつらみは、日ごろ懇意にしていた上に、金銀貨改鋳問題で意気投合していた鳥居耀蔵(当時目付)にもぶちまけられたであろう。町奉行・矢部追落しの謀略には、耀蔵が後藤三右衛門に扇動されたという面があったに違いない。
「妖怪」の出現
矢部追落しに耀蔵がどんな働きをしたかは当時の幕府人に常識としてわかっていた。
目付陣も10人前後はいたのだから、耀蔵がどんな仕事をしているかは、同僚として見当がっく。
南北町奉行所にも大勢の与力、同心がいる。旗本のことには関与しない建前だが、このお救米事件には町人が関係していたのだから、そっちのほうを調べれぽ町奉行所にも内容がわかる。また当の被害老の矢部定謙の口からも、だれが、どんな調べをしたかが洩れてくる。そしてヒマを持てあましていた江戸城の役人たちに話が伝わり、広がっていく。
幕末に軍艦・外国両奉行を勤め、維新後は『郵便報知新聞』に拠って健筆をふるった栗本鰻(鋤雲)は、鳥居耀蔵にっいてつぎのように書いている。
「刑場の犬は一度、処刑された罪人の肉の片はしを食べるとその味が忘れられなくなり、その後は人を見れば噛みっくようになる。
そのためにっいには僕殺されることになる。鳥居甲斐のような人物はこの刑場の犬のようなものではないか(中略)。
(蛮杜の)獄は、他の目付役ではとても立件できるものではたかったので、(耀蔵は)同僚中に評判が高く、本人も大いに得意になっていた。それ以来、彼ははとかく聡明なる頭脳を用い過ぎて、人を陥れて告訴することを目的とするようになり、網を張り、罠を設げてしばしば疑獄を起こし、無実の人に惨苛をこうむらしめた。
矢部氏の事件などは最もにくむべき行為であって、天保13年は同7年より7年も後たのに、さかのぼって仁杉五郎左衛門の罪を審問して、この犯罪を不問に付した当時の町奉行筒井氏の罪は罷役という程度にとどめ、後任の矢部は仁杉に課した罪が軽すぎるという理由で、禁鋼、没籍とは何という処罰なのか、非理もまたひどいものである。
思うに、甲斐は矢部の才識や人望が自分の上に出ているので常日ごろこれを嫉妬していて、なんとか傷をつげようとねらっていたが、そのスキがなかった。
たまたま仁杉の断罪が軽すぎるという問題が出てきたので、初めて宿志を達するときがきたとし(中略)、百方に人をあざむいて、とうとうこの獄をつくりあげるに至った。
栗本鋤雲は鳥居耀蔵が矢部定謙追落し疑獄の張本人であることに何の疑いも持っていない。
そして、刑場の犬が腐肉の味を忘れないようなものだと耀蔵を酷評している。
矢部定謙は家は改易、身は桑名藩(11万石)にお預げという切腹一歩前の極刑に処された。
徳川の旗本としてこれ以上の恥辱はない。
彼は禁鋼先の桑名において絶食して死を選んだ。壮烈な死とも、哀れな死ともいえる。
その反動として、幕府人の非難が耀蔵に倍加してはね返ってくる。
耀蔵は南町奉行に発令されると同時に甲斐守となった。
このころ小普請奉行に曲淵甲斐守という人物がいて、この家では代々甲斐守を名のっていた。曲淵家は甲斐の武田家の出であるから、甲斐守はこっちが正統であり、世問によく通った名であった。
そこに鳥居甲斐守が出現したので曲淵と区別するため、「耀蔵のほうの甲斐」といい、それがつまって耀甲斐となり、ついに「妖怪」とよぼれるようにたった。
幕府のヒマな連中は仕事には役に立たないが、こういう風刺文や風刺語の作成となると、才能を発揮する。
また町奉行が連続して二人、改易・他家預けになったというのは徳川幕府260余年の間にこれが唯一の例である。
天保の改革という異常な時代を背景に、その中から一人の異常な人問が生まれたことによって異常な例が生じた。
改革という政治的事業はそれにふさわしい偉大な人物によって成しとげられる。凡庸な大名たちの中で、多少頭が切れ、性情酷薄でやり手であるという程度の老が政治改革をやったんでは失敗する。
水野忠邦がいい例で、鳥居耀蔵の起用という人事上の失敗も、忠邦自身の頭脳の欠陥の一つの証拠で、資格のない老が改革をやると、改革の副作用のために失敗し、自減する。
鳥居耀蔵の人物評については、後に挙げる後藤三右衛門の言葉が、同時代人であり、かつ常に親しく相接し、盟友ともいうべき関係にあった者が歯に衣着せず吐露したものとして最も信用すべきものと思われるが、さらに栗本鋤雲のほかに、当時およびその後の幕府人の平均した耀蔵観とLて、木村芥舟の評言をつぎにあげる。
「鳥居忠耀は若いときから英特の人物との評判が高かった。
天保12年目付より町奉行に抜擢され、勘定奉行を兼務した。革新の事を自分の任務とし、市井遊惰の民を懲戒して毛筋ほども許さなかった。しかし積年の余弊が人心に食い込んでいて、一般の人びとは不便を訴え、怨みの声が街に満ちた。
彼は目付だったときから西洋の学風が大嫌いであって、その砲技を否定し、あるいは洋書を読む者は国家に大害があるとして、力を尽してこれを根こそぎにしょうと骨折った。
また改革の事についても、自分と意見の合わない者があるときは、ときに陰険の手段を用いて排除した形跡がなくはない。
この点はこの人のために深く惜しむところである。
しかしその剛硬不撓の気性の終生変わらなかったのは他人の決しておよぶところでない。
|