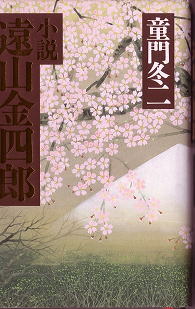|
景元の実父景晋は、旗本永井筑前守直令の四男として、宝暦2年(1751)に生まれる。 母は鈴木氏。天明6年(1786)、景晋は遠山景好の養子に入ったが、問もなく養父景好に景善という実子が生まれた。
| 遠山左衛門尉 年表 |
| 寛政 5(1793) |
遠山景晋の長男として生まれる。 幼名通之進 |
| 文化 6(1809) |
金四郎と改名 |
| 文政 8(1825) |
祖父景善の順養子
初お目見え
|
| 文政12(1829) |
御小納戸役 |
| 天保 3(1832) |
西の丸小納戸頭取格
大隈守 |
| 天保 6(1835) |
小普請奉行 |
| 天保 7(1836) |
左衛門尉 |
| 天保11(1840) |
北町奉行 |
| 天保12(1841) |
お救い米事件取調べ |
| 天保13(1842) |
同上判決申し渡し |
| 天保14(1843) |
北町奉行免、大目付 |
| 弘化 2(1845) |
南町奉行 |
| 弘化 4(1847) |
引退 |
| 安政 2(1855) |
死亡(63歳) |
景晋は、旗本永井筑前守直令の四男として、宝暦2年(1751)に生まれる。 母は鈴木氏。天明6年(1786)、景晋は遠山景好の養子に入ったが、問もなく養父景好に景善という実子が生まれた。それで、景善を景晋の養子として遠山の相続人たるべく手続きを済ました直後に、寛政5年(1793)9月、金四郎景元が誕生した。10歳のとき金四郎は景善の養子として享和2年(1803)出願し、8月晦日許可となった。
景元の幼名は通之進。景善の養子となり、文化6年(1809)正月金四郎と改名した。文政7年(1842)養父景善は部屋住のまま没したので、翌8年正月祖父(実は実父)景晋の順養子(嫡孫承祖)として承認され、金四郎は遠山の家督を継ぐこととなったが、すでに37歳だった。
文政8年(1825)3月、将軍家斉に御目見、同12年御小納戸役、同11年景晋隠居により家督相続、御膳番を経て天保3年(1832)西ノ丸御小納戸頭取格となり、大隅守に叙任、同6年小普請奉行、同7年左衛門尉、さらに作事奉行、勘定奉行を経て、天保11年(1840)町奉行(北)に任ぜられた。
翌12年老中水野忠邦の「天保の改革」が断行され、江戸市政の改革は主要改革の目標の一つであった。
水野忠邦の改革令は、町人階級には、生活統制という形で強行された。衣食住のすべてにわたって華美なるものの排除が指示され、庶民の娯楽のすみずみにまで干渉した。
南町奉行の鳥居耀蔵は、改革令に違反する者を徹底的に取り締まり、庶民の苦痛も意に介さず、次々に細かい統制の策を打ち山したが、世情に通じる遠山は、江戸庶民を不安にさせるこうしたやり方に反対し、ことごとに鳥居と対立した。このため、天保14年2月町奉行を免ぜられて大目付に転じた。しかし「天保の改革」が失敗して水野・鳥居らが退くと、弘化2年(1845)3月再び町奉行(南)に復活した。 嘉永5年(1852)3月まで8年にわたり勤役したが、病気のため退役し、翌4月隠居、剃髪して帰雲と号した。
以後は悠々自適の生活を送ったという。
 2度の合計11年にわたる町奉行在任中、手がけた裁判はおびただしい数になるが、その中でことに目立つものはない。しかし金四郎は、市井の生活をよく知っていたので、下情に通じ、鮮やかな裁決を下した。そのことが今なお高い人気を得ている原因であろう。 2度の合計11年にわたる町奉行在任中、手がけた裁判はおびただしい数になるが、その中でことに目立つものはない。しかし金四郎は、市井の生活をよく知っていたので、下情に通じ、鮮やかな裁決を下した。そのことが今なお高い人気を得ている原因であろう。
安政2年(1855)2月29日、病いを得て世を去った。63歳であった。
墓は日蓬宗本妙寺(豊島区巣鴨)にあり、都旧跡指定となっている。墓銘には
遠山氏六代目左衛門尉景元 帰雲院殿
従五位下 金吾校尉松擢日亭大居士
安政2年乙卯月29日卒
とある。
父景晋〈静定院殿光善楽土大居士〉は天保8年(1837)7月22日没、86歳。
童門冬ニの「小説遠山金四郎」
この小説には何と仁杉五郎左衛門の弟が登場する。 仁杉六郎右衛門という名前で北町奉行所の与力である。遠山が奉行に就任したときに用人兼筆頭与力に抜擢されたという設定。
この本のほとんどの部分ところは忠実に歴史上の出来事を描いているが、何故こんな実在しない人物を登場させたのだろうか。
狙いは「五郎左衛門的な人間であった六郎右衛門が遠山と付き合っていくうちに人間が変わって行く様子を描きたかったのかも知れない。
ここでいう五郎左衛門的な人間とは「世間智」「世渡り巧者」「処世術に堪能な男」から、北町奉行と遠山左衛門尉ではなく、人間遠山金四郎に次第に惹かれて行き、信頼される部下になって行く。
なお筆者は五郎左衛門の事を
「南町奉行は仁杉五郎左衛門の意見をきかなくては仕事ができない」
あるいは
「大坂に大塩あり、江戸に仁杉あり」
と表現している。
|
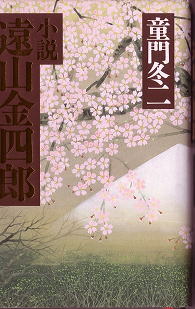 仁杉五郎左衛門の関連する部分抜粋 仁杉五郎左衛門の関連する部分抜粋
(前略)
再び例規集に目を戻した時、
「おい」
突然肩を叩かれた。はっとして振り向くと、脇に用人兼筆頭与力の仁杉六郎右衛門が立っていた。
(中略)
遠山金四郎はこの奉行所へ赴任した時、本来なら用人は自分の家に仕えている部下を連れて米るのだが、そうしなかった。
「奉行所と住居は接続している。職場と住まいが一緒なのに、わざわざ別なところから用川人を連れて来る必要はない。用人は表と裏の橋渡しをしてくれる人間なのだから、むしろ練達な与力の万がいい」
といって、仁杉六郎右衛門を用人に任命した。
(中略)
今日の仁杉六郎右衛門はその事とは別な屈託があるらしく、暗い顔をしている。金四郎はみとがめた。
「仁杉、どうした?」
ときいた。仁杉は、チラと金四郎を見たがすぐ眼を伏せて、
「兄の身にちょっと面倒なことが…-」
といって言葉を濁した。
「兄というと、南町にいる?」
「はい」
六郎右衛門はうなずいた。仁杉六郎右衛門の兄は五郎左衛門といって、南町奉行所にいる。やはり古手の与力だった。弟の方も結構やり手だが、兄の方はさらに輪をかけてやり手だった。
「南町奉行は仁杉五郎左衛門の意見をきかなくては仕事ができない」
とまでいわれていた。ちょうど大坂東町奉行所の与力人塩平八郎が、厳然とした実力者であったのと同じである。
「大坂に大塩あり、江戸に仁杉あり」
とまでいわれていた。その仁杉五郎左衛門に何が起ったのだろうか。いつも快活で何でも茶化してしまう六郎右衛門を知っているだけに、今日の暗い表情は珍しい。
(中略)
「一同様、お役目ご苦労に存じます。では南町奉行矢部定謙様に対する疑惑についてご説明申し上げます」
そう切り出した。鳥居の説明によれば、
・天保七年は全国的に米が不作だった。
・そういう時に、南町奉行所与力仁杉五郎左衛門は、同心の堀江六左衛門他五人と語らい、商人に金を立て替えさせ米の買占めを謀った。
・事件が発覚し、勘定奉行扱いとなったが、時の勘定奉行矢部定謙は何らの処分もしなかった。
・矢部定謙はその後南町奉行になったが、勘定奉行時代に扱った仁杉の買米事件を不問に付した。
・たとえ五年前の事件とはいえ、不届き至極である。
・よって、南町奉行矢部定謙に対し厳しい処罰が加えられるべきだ。
中略
南町奉行所の仁杉五郎左衛門の買米事件が糾弾されはじめると、北町奉行所にいた弟の仁杉六郎右衛門は、ある日、金四郎の所に来て、
「用人の職を退きとうございます」
と辞任を申し出た。金四郎は目をあげて仁杉を見た。
「なぜだ?」
「ご承知の通り、南町におります兄が目下渦中の人物となり、かつて犯しました過ちを質されております。所管は違っても血の繋がる第として、このままお奉行の身近なご用を果すのは何とも恐れ人ることでございます」
「その心配は無用だ」
金四郎は微笑んでいった。
「は?」
仁杉六郎右衛門は伏せていた顔を半ば上げて、上目づかいに金四郎を見ながら不審な表情をした。
「兄は兄、弟は弟だ。おまえはわたしのために身を粉にして尽くしてくれている。兄の仁杉が罪を咎められようと、おまえには関わりがない。いままで通り励んでくれ」
この言葉をきいて仁杉六郎右衛門は信じられない評定をした。やがてその顔がゆがんだ。肩をクッと振らせると、いきなり、
「はっ」
とその場に平伏した。 肩がゆれている。嗚咽しているのだ。まさかこんあ言葉を金四郎からかけられるとは思っていなかったからだ。
というのは、仁杉六郎右衛門も兄の世渡り巧者を真似て処生術に堪能な男だ。そして、うまくやることこそ世の中を鮮やかに渡り歩き、さらに立身出世につながると考えてきた人物だ。が、その世渡り巧者の兄がいま世間の注目の的になっている。それも悪事によってだ。
そうなると奉行所雀の批判は厳しい。
「あまりいい気になりすぎたからだ」
「何でも世渡りの技だけでことがすむと思ったら大間違いだ。人にはやはり目がある。天網恢恢疎にして漏らさずというのはこのことだ」
などとしたり顔で指弾する。いっている本人たちも、結構いままでは仁杉の生き方をうらやましがってきたくせに、状況が変るとそういう風にクルリと批判側に回る。これが奉行所雀の姑息なゆえんだ。
(中略)
南町奉行所の与力仁杉五郎左衛門の買米事件は天保12年の春に処分が決った。仁杉五郎左衛門はこの事件が世に現れて以来、入牢させられていた。しかしやがて獄中で死んだ。
「毒を盛られたのだ」
という噂が立った。真偽は確かめようもなかった。その直後矢部定謙と筒井政憲に刑が下された。
筒井は、
「お役御免の上差し控え」
で済んだ。しかし矢部は、
「桑名藩松平家お預けとする。家禄は没収する」
ということになった。矢部は痛憤し、桑名へ行ったがそこからもしきりに、
「わたしは無罪だ」
という紙のつぶてを発し続けた。
一座連累のしきたりによれば、兄の不祥事は弟にもその罪の飛沫が飛ぶ。しかし、北町奉行遠山金四郎は必死になって仁杉六郎右衛門を庇った。その減意が通じて仁杉六郎右衛門には「お咎めなし」ということでケリがついた。仁杉は金四郎に感謝した。ガラリと人が変った。
「いままでのわたしは、実に浅はかでした」
と、処生術一辺倒の生き方を変えた。金四郎はそのまま仁杉を用人として使い続けた。
この頃から金四郎は仁杉六郎右衛門と、与力の山田冶兵衛と同心の砂山市三たちを、暇をみては川たつの店に行かせた。
仁杉、山田、砂山というコンビがしきりに川たつの店に出人りしていることを嗅ぎつけた貝川は、自分の判断で川たつの店に出人りしていた。三人のだれかと鉢合わせをすることがある。しかし、貝川扇次郎もこの頃は少しずつ考えを変えていた。かれが模範としてきた南町奉行所の仁杉五郎左衛門がああいう目に遭い、しかもその弟で兄の生き方巧者を貞似ていた六郎右衛門もこの頃ではすっかり人が変ったようになっている。
|
|
 2度の合計11年にわたる町奉行在任中、手がけた裁判はおびただしい数になるが、その中でことに目立つものはない。しかし金四郎は、市井の生活をよく知っていたので、下情に通じ、鮮やかな裁決を下した。そのことが今なお高い人気を得ている原因であろう。
2度の合計11年にわたる町奉行在任中、手がけた裁判はおびただしい数になるが、その中でことに目立つものはない。しかし金四郎は、市井の生活をよく知っていたので、下情に通じ、鮮やかな裁決を下した。そのことが今なお高い人気を得ている原因であろう。