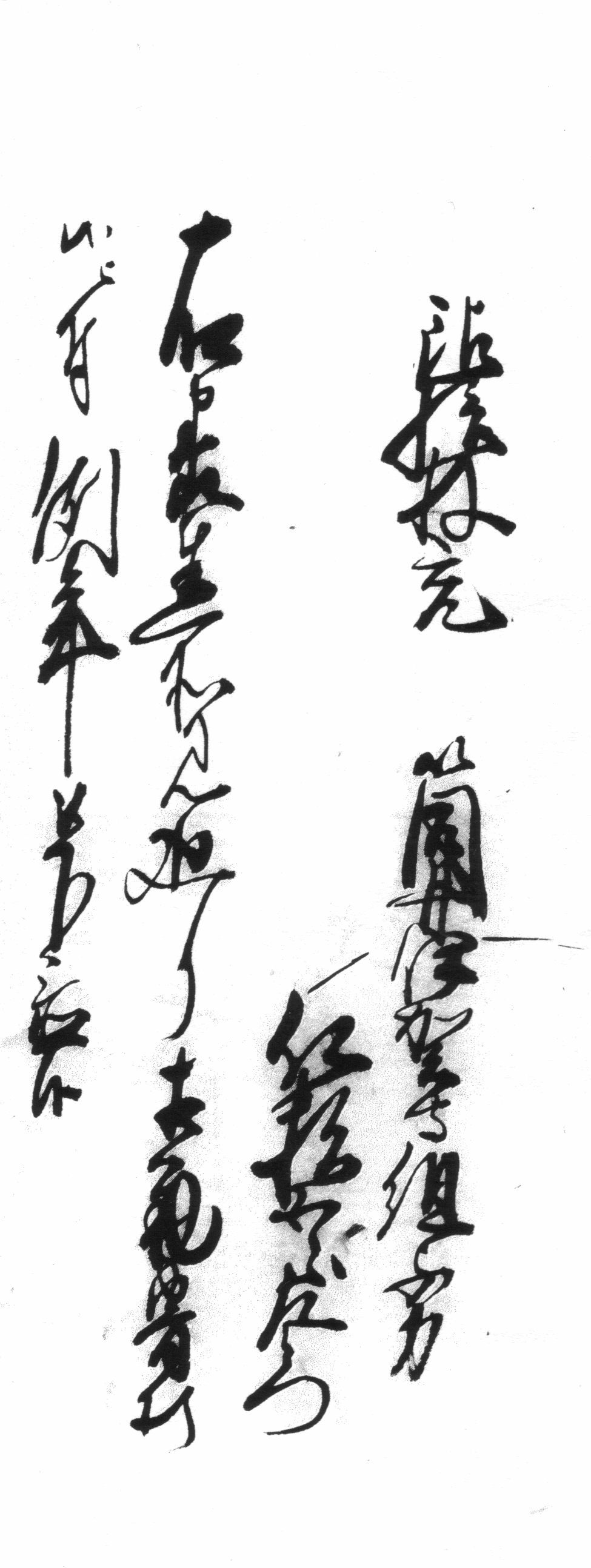与力の分課
町奉行所の業務は行政、司法の多岐にわたり、所属する与力・同心はそのうちのいくつかの分課を受け持つ。 中でも与力では年番方、吟見方(御詮議役、同心では三廻りが花形であるが、この役に就くには能力と経験が必要である。
また与力の分課はいわば現在の都庁あるいは警視庁の局または部の責任者であるから、経験のない若い与力が就任することはない。 分課につかない与力は番方といって奉行所の当直や訴訟の受付などを担当していた。
奉行所の与力・同心がどんな役目についていたか、その序列がどうであったかなどが町鑑に詳しく掲載されている。
文化文政時代の町鑑を見ると、五郎左衛門は文化4年、10年では無役である。一方分家の八右衛門は御詮議役(吟味役)という陽のあたる役についている。
文化15年の町鑑を見るとようやく牢屋見廻役についている。牢屋見廻役の定員は与力1人、同心2人。小伝馬町にある牢屋敷の担当であるが、牢屋そのものの見廻りではなく、牢屋敷を管理・運営している囚獄石出帯刀以下の役人が規則通り職務を遂行しているかどうかの監察が主たる役目である。
文政5年の町鑑でも牢屋見廻となっているから、五郎左衛門は最短でも5年、最長14年だと牢屋見廻り役を務めたことになる。
牢屋見廻りとして牢屋敷に赴けば、おそらく下にも置かない扱いを受けていたであろう五郎左衛門が、後にこの牢屋敷に投獄されることになるとは何とも皮肉である。
町鑑に見る五郎左衛門、八右衛門の分課
| 和暦(西暦) |
南町奉行 |
名前 |
番組(序列) |
分課 |
年番方 |
| 文化 4年(1807) |
根岸肥前守鎮衛 |
与兵衛
幸信⑨
同 |
1番組(5) |
|
原兵左衛門
小原惣右衛門 |
| 八右衛門幸■① |
5番組(4) |
御詮議役 |
| 文化10年(1812) |
根岸肥前守鎮衛 |
五郎左衛門幸信⑨
同 |
1番組(3) |
|
佐久間次郎太夫
小原惣右衛門 |
| 八右衛門幸■① |
5番組(4) |
御詮議役 |
| 文化15年(1818) |
岩瀬加賀守氏紀 |
五郎左衛門幸信⑨
同 |
1番組(2) |
牢屋見廻り |
小原惣右衛門
由比源八郎 |
八右衛門幸■①
五郎八郎幸雄② |
5番組(3) |
御詮議役 |
| 文政 5年(1822) |
筒井和泉守政憲 |
五郎左衛門幸信⑨
同 |
1番組(2) |
牢屋見廻り |
中村又蔵
中村八郎左衛門 |
八右衛門幸■①
五郎八郎 |
5番組(1) |
御詮議役 |
| 文政 9年(1826) |
筒井紀伊守政憲 |
八右衛門幸■①
五郎八郎幸雄② |
3番組(1) |
年番、同心支配役、御詮議役 |
中村八郎左衛門
仁杉八右衛門 |
五郎左衛門幸信⑨
同 |
1番組(2) |
本所改役 |
|
|
牢屋見廻役
五郎左衛門が番方から役方になって最初に就任したのが牢屋見廻役と見られる。
伝馬町の牢屋敷と浅草、品川にあった溜(病人の牢)は世襲の石出帯刀が牢屋奉行として管轄していたが、その運営を監査するために南北町奉行所から与力各一人が任命され、その下に同心が二人づつ付属した。
同心は毎日牢屋敷に出張したようであるが、与力は定期的な見廻りと、囚人の死罪、入墨、叩き、釈放などの仕置に立会い、牢役人の監察、取締を担当したようである。
下に嘉永年間に北町奉行所の与力・三村吉兵衛が書いた牢屋見廻役の業務内容の書付を示す。時代によって多少の違いはあるが、おおよそこのような業務を担当するのが牢屋見廻役である。
五郎左衛門はこの牢屋見廻役を少なくとも5年以上勤めているが、この20年後には本人が罪を得てこの牢屋敷に入牢し、そのまま獄死することになるのはなんとも皮肉である。
| 牢屋見廻役勤方 三村吉兵衛の書付 |
牢屋見廻勤方之儀申上候書付
三村吉兵衛
一、牢屋見廻之儀前々者一両日も間を置、又者ニ三日も相続見廻申候処、近頃御用多日々見廻り薬井御賄飯汁其外致見分・病人手当等医師鐙役江申渡、諸事御届向相調夫々差出申候
一、御目付衆丼加役方牢屋敷江見廻候節者詰所江罷在、役所向見廻候節者玄関二而会釈仕候
一、毎月朔日六ケ月以上華之者井前月中落着人数石出帯刀立合取調、御月番明ヶ之方江書付差出申候
一、前月中牢屋御入用帳石出帯刀方二而相調、私共見届小印仕、御世話番之方江差出、御金者御金蔵より町年寄方江相渡、鑑役差遣為請取申候
一、前年分惣囚人高井落着居越高帳面相仕立、翌年二月中書上申候
一、医師共薬代宿代金御内借井研屋附人女江被下金銭、例年十二月十八日御内寄合江罷出相伺申候
一、例年十二月廿五日囚獄組之もの役向御褒美金私共石出帯刀取調申上、帯刀より夫々江申渡頂戴仕候
一、御仕置もの有之候節者都而立合、死骸之儀者私共差図仕候
一、諸御掛遠嶋被仰渡在牢もの春二月秋八月両度名前等相調申上、被下銭之儀者出帆前取調申上候
一、御赦之もの有之候得者、前日御掛御番所二而御赦之趣被仰渡、前夜牢屋敷江罷越出役与力江引渡、御番所江差出申候
一、佐州もの差立二相成候節者、於牢屋敷佐州地役人江引渡申候
一、御様有之候節者於番所江罷出申候
一、牢屋敷被損所出来候節者取調、御修復等相伺申候
一、牢内相改候節者石出帯刀立合、私共江御渡被置候御書付之趣同人組同心下男共江読聞、井囚人江者牢内法度書申渡、其度々御届申上候
一、牢死之もの有之候節者致見分、其段御届申上候
一、例年七月御双方より被下鯖代人数二応し金銭取調申上、惣囚人月代摘之義石出帯刀より相伺候上、立合見分仕侯
一、牢舎病人江冬分相渡候徳利暖補代銀翌年取調申上、其外都而御番所金二而出来候分糺方いたし、私共より相伺申候
一、牢屋御入用前年分勘定出来候得者出役与力立合、請帳取調差出申候
一、非常之節者牢屋敷江罷越手当申付、病人ハ駕籠持籠等二乗セ見計両御番所又者本所回向院江為立退申候、尤急火二而見合無之節ハ先例放遣申候、右者両溜も同様二御座候
一、毎月両溜江見廻其「外」(抹消)「段」(朱書)御届差出申候
一、下役之儀者御双方六人二而昼夜三人ツ\牢屋敷江詰切、玄関見張内外取締方心付、井牢舎もの食事品物其外牢内江入候節者為見廻申候、尤勤方之儀時二臨ミ私共申付候儀も御座候
右之通御座候、以上
酉二月 三村吉兵衛 |
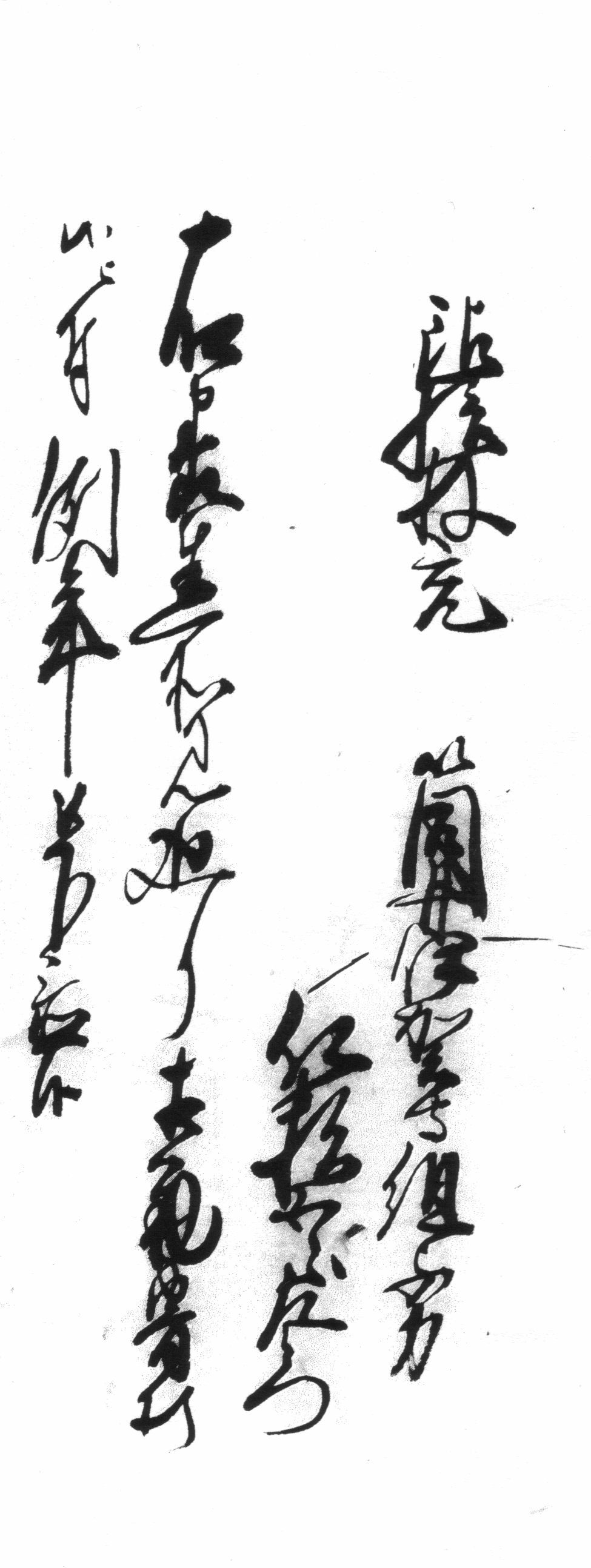 |
銀拾枚宛
筒井伊賀守組与力 仁杉五郎左衛門
右は養生所見廻り相勤骨折候に付例年被下置候 |
旧幕府引継書・南撰要類集 152-11
与力暮御褒美一件(文政6年)
但養生所御医師御褒美共 |
養生所見廻役
上記の町鑑では「牢屋敷見廻」の後「本所改役」についているように見えるが、実はこの間に「養生所見廻」を勤めていたことが最近わかった。
養生所は8代将軍吉宗の時代、享保7年(1722)12月4日に開設された幕府の病気治療施設である。
この画期的な福祉施設は享保の改革を進める吉宗が庶民の声を吸い上げるために設けた目安箱に小石川伝通院の医師・小川笙船が貧しい者の病気を治すための療養所を作って欲しいという訴えたことから実現した。
訴状を読んだ吉宗は腹心である町奉行・大岡忠相に命じて小川笙船と面談・調査をさせ、江戸小石川の薬草園内への設立を提案して実現した。
養生所の経費は全部幕府から支出されたので、その運営管理が正しく行われているか監察する業務が町奉行所に委託され、南北各二人(後に各一人)の与力が養生所見廻役に任命されるようになった。
享保撰要類集の記録によると、享保18年と19年の大岡越前守組(南町)の養生所見廻役は仁杉幸右衛門(曽祖父)となっている。
旧幕府引継書・南撰要類集に文政6年に五郎左衛門が養生所見廻役として褒美を受けている文書がある。
左の文書によればその褒美は銀十枚。 同時に北町奉行所の養生所見廻役の米倉某も受領している。
これは特に大きな功績があった訳ではなく、大過なく勤めれば毎年暮に褒美と与えられるものであり、いわば手当のようなものと考えられる。
この養生所見廻役の後に本所改役(または本所見廻役)に就いている。
本所見廻役
本所深川に住む人達は大川(隅田川)の向こうに行くときは「江戸に行く」と言ったといわれるほど「江戸であって江戸でない」特殊な地域で、以前は町奉行所の管轄ではなく、本所奉行所という別の役所があった。
しかし、将軍吉宗の時代、享保4年に本所奉行所を廃止して町奉行所管轄そし、新たに本所深川見廻役が設けられた。
本所見廻役は名前の通り本所一帯を管轄とし、南北それぞれ与力一人、同心3人が任命され、本所松井町にあった番屋を本拠としていたようだ。
「本所」の範囲は一般的には、両国橋以東、深川の北一帯をさすが、北は桜の名所・向島の墨堤あたりから、東が竪川を下り、中川まで、西は大川端、南は海辺まで、という広い地域である。
南撰要録に次のような記録があり、北町奉行中山出雲守時春配下の満田作左衛門、南町奉行大岡越前守忠相配下の中田■左衛門が初代の本所深川見廻役に任命されたことがわかる。
本所見廻役
享保四年四月本所奉行所差止に付井上河内守殿へ相伺候上同年九月十七日本所深川見廻役として月番中山出雲守へ両組与力召呼申渡之此度奉行所廃止被成候に付向後町奉行支配に被仰付候只今の諸受負屋敷被召上右地代■代之料を以本所深川筋御修復被仰付候筈に候依之両人へ右御用申渡候間諸事致吟味可相勤旨申渡す
但本所深川諸事御用務方之所懸り之与力方に之有
享保四年
中山組 満田作左衛門
大岡組 中田郷左衛門 |
この本所見廻役には五郎左衛門の曽祖父幸光、祖父の幸右衛門幸計が下記のように何回も就任している。
| 和暦(西暦) |
名前 |
当時の奉行 |
| 元文3年(1738)ー4年(1737) |
仁杉幸右衛門幸光 |
松波筑後守正春
水野備前守勝彦 |
| 延享2年(1745)-4年(1747) |
仁杉幸右衛門幸光 |
島 長門守祥正 |
| 寛延2年(1749)-4年(1751) |
仁杉幸右衛門幸計 |
馬場讃岐守尚繁 |
| 宝暦2年(1752) |
仁杉幸右衛門幸計 |
山田肥後守利延 |
|