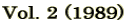
【論文 Article】
1 A glimpse of the diatom-vegetation at some stations of the southern littoral
zone of
Lake Baikal
[NEGORO Ken-ichiro, IKUTA Miwako]
バイカル湖の南部湖岸帯の数カ所における硅藻植生(英文)
[根来健一郎,生田美和子]
diatom-vegetation, Lake Baikal
バイカル湖南部湖岸帯から14属30種の硅藻を見出した.狭い範囲でありながら固有種,準固有種が著しく多い特異な植生であり,特にMelosira baicalensisはバイカル湖の「生きている化石」とも言うべき種で,注目される.
2 宍道湖・中海及び美保湾底質中の重鉱物分布とその起源について
[正岡栄治,水野篤行]
heavy minerals, relict sediments, Lake Shinji-ko, Lake Naka-umi, Miho-wan
Bay, hornblend to hypersthene ratio
宍道湖・中海・美保湾の砂質堆積物中の重鉱物の分布と起源を検討した.各水域の重鉱物の量,組成比,分布には特徴がある.分布の第1要因は流入河川の重鉱物型,第2要因は水域内での移動等(普通角閃石とシソ輝石の量比関係は重鉱物の「成熟度」の指標となる),第3要因はウルム氷期最盛期以降の海水準上昇時に堆積したレリクト堆積物である.
3 中部更新統二宮層群産サガミヒメオウギガニの化石
[武田正倫,増渕和夫]
crab fossil, Nanocassiope alcocki, Middle Pleistocene, Ninomiya Formation
神奈川県大磯丘陵の二宮層群より,カニ化石が産出した.全周縁部を欠くが,甲域の細部の状態及び顆粒の形状等からサガミヒメオウギガニと同定できた.また,現生種について再検討を行い,Nanocassiope granulipesとされていたサガミヒメオウギガニは,インド洋産のN. alcockiと同種であるとの結論を得たので,学名をN. alcockiと変更する.
4 町田市金井・川島に露出する鶴川層からの魚類耳石
[大江文雄,増渕和夫,秋葉知子]
marine fish-otolith, Pleistocene, Tsurukawa formation, Kazusa Group
東京都町田市鶴川層のシルト泥層から得られた魚類耳石20個について,科ごとに現生種と比較考察した結果,8科13属13種を同定した.大半は大陸棚底とその周縁種であり2種のみ浅瀬種であった.
5 多雪地におけるブナの樹幹にみられるコケ植物の分布様式
[種村清作]
bryophytes, snowdrift, Fagus crenata, distributional pattern
日本海側の多雪地帯ブナ林4箇所(長野県,新潟県)でコケ植物のブナ樹上分布と積雪の影響を調査した.確認された種は84種で,分布は4様式に分類できた.また,樹幹の山側にコケが少ないのは樹皮に接してできた氷の作用であり,谷側のコケの豊かさは,張り出したブナの枝により集められた雨水などで湿度が高いためであると考えられた.
6 神奈川県川崎市多摩区宿河原産Davidiaの種子化石
[大澤 進]
Davidia, Pleistocene, fossil, Kawasaki
宿河原の上総層群飯室層から産出したDavidia involucrataの種子化石は,報告例の少ないものである.現生種は中国南西部の山地にのみ分布するが,更新世には日本に広く分布していたと考えられている.飯室層堆積期の気候は,同層から産出した哺乳類化石などから,現在と同じか幾分冷涼な時期も含まれていたと推定され,現生種の分布と一致する.
7 ブキット・スハルト保護林の哺乳動物相(Ⅱ) [安間繁樹]
Bukit Soeharto, mammalian fauna, II
前報発表後に生息を確認した17種について報告する.前回の報告とボルネオ島全域に普通に生息する種を考慮すると,ブキット・スハルト保護林には約100種の哺乳動物が生息すると考えられる.この豊かさは,当保護林のまわりには良い森林がないこと,樹冠層が連続した状態で残っていること,様々な植生があることのためと考えられる.
8 市川市妙典に生息する帰化動物マスクラットの生態調査
[小田切敬子,小田切則夫,麻布大学動物研究会]
muskrat, ecological behavior
千葉県市川市の湿地帯でマスクラットを調査し,捕獲個体の外部計測,生息個体数の確認,生態調査,行動観察を行った.頭胴長は16.5-30.0cm,尾長は15.0-24.5cm,体重は230-1,080gであった.食痕の確認された植物は14種で,動物質はなかった.糞は緑褐色で楕円形であった.巣は地面を掘ったものと水生植物を積み上げたものと2種類確認された.
9 長野県入笠山におけるニホンアナグマの巣穴について
[山本祐治]
Meles meles anakuma, sett, nesting requirement, rate of use, dung pit
アナグマの巣穴の場所の選択性と使用頻度の決定要因及び巣穴と糞場の関係について検討した.営巣場所の斜面方位,斜度の選択性は,日照時間と関連すると考えられる.巣穴の形態は土穴型,岩山型,床下型などの5タイプに分けられた.糞場は巣穴から10m未満の距離に多く,使用頻度の高い巣穴近くの糞場は利用頻度が高いことが認められた.
【資料 Data and Notes】
10 実験林追跡調査報告(その1) [箕輪隆一]
forest-vegetation, Tama Hill, conservation
神奈川県川崎市の平岡環境科学研究所実験林で行っている雑木林復元作業につき,整備前の植生から工事後初年度までの状況を報告する.当初モウソウチク優占,常緑樹優勢であった山林を夏緑広葉樹林に誘導するため,29種168本の残存種に105本の夏緑広葉樹の補植を行った結果,山林は暖温帯の伐採跡地に見られる二次遷移初期の様相を端的に示した.
11 日本に於けるマスクラットの野生化の経緯と俗名の考察
[斎藤正寛]
Ondatra zibethicus, fur industry, laws, Edogawa ward, muskrat-breeder
日本の毛皮産業について,関係法令と軍需産業との関連を考察しつつ再検討し,東京都江戸川区のマスクラット養殖業者について調査を行うとともに,マスクラットの俗名「ドイツネズミ」の由縁と,その野生化の経緯について検討した..