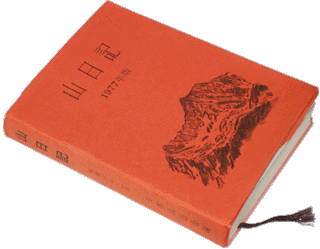
「山日記1977年版」(日本山岳会編)を手にし、最初につけた山行記録です
写真はありません
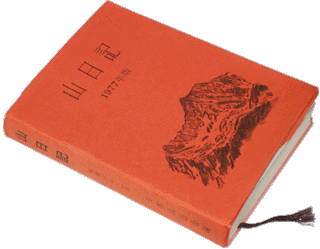
「山日記1977年版」(日本山岳会編)を手にし、最初につけた山行記録です
写真はありません
丹戸のバス停から出発。しばらく暖かい日が続いたので積雪量が気になっていたが、少し行った八木川に下る狭い道からもう深い雪に悩まされた。冬合宿の北八ヶ岳では踏んでも固まらない乾いた雪だったが、ここの雪質はかなり異なる。初めのうちは踏み応えの感触が馴染めなかった。
麓の里には相当の積雪量が残っているが、振り向いて見上げる鉢伏山は、稜線に沿ってかなり雪解けが進んでいた。
棚田が続く東尾根の北斜面を消えかかったトレースに従ってゆっくり登っていく。体重、ボッカの量によっては、足場をさらに踏み抜くこともある。踏み抜いた穴の下に小川が流れていたりすると少しばかりひやっとする。
途中の展望の良い棚田の上にテントを張る。近くに小川があり、水量も豊かなので水を得るのは冬のことを思い出せば非常にたやすい。
夕暮れまで時間的に余裕があってのんびりできた。向かいに見えるスキー場からにぎやかな音楽が聞こえてくる。天気晴れ。風弱く陽のあたるテントの中は明るく暖かい。
穏やかな合宿スタートの様子は、去年と同じパターンだと先輩が言う。春合宿の氷ノ山パーティーは特に過酷な山行で、1年生が地獄の苦しみを味わい、人間性が歪められるのだそうだ。
これから始まる山行への期待と一抹の不安をいだいて狭いテントに寝る。
高曇り。昼間はぬかるみだった所にも薄く氷が張る。気温は氷点下だろうが、風がないので寒くはない。雪もよく締まっていて歩きやすい。
川にかかる橋の上に積もった雪がスノーブリッジのようになっている。別になんともなかったけれど、昼間なら乗ると崩れてとても通れないだろう。
しばらくして急な登りになるが距離はたいしたことなく苦しくなる前に東尾根の上に出た。後方からスキーを担いだ3人組のパーティーが続いてくる。軽い足取りですぐに追いつかれ、この急登であっけなく抜かれてしまった。
左に朝日を受け、狭い稜線を進み、まもなく広い高原のような稜線に入る。千本杉の杉木立は北山の杉のように鬱そうと密集するのではなく疎らにあって、白い雪原の上に開放的な明るい感じである。冬は樹氷がすばらしいそうであるが・・・。大きな杉の木の根元にツアースキーヤーのテントがあった。
神大山岳部千本杉ヒュッテは今来た稜線から少し下ったところにある。このヒュッテはシャッターのついた2階が冬期の入口のようだが、2つとも閉まっていて、その他どこにも入れそうな所はなかった。
ヒュッテの横に雪洞を掘る。3人は楽に横になれる如何にも居心地のよさそうな横穴式雪洞ができた。SLの安原さんがこの上で走り回ったがびくともしない。
予定ではこの付近で一泊するはずだったが、あまりに早く着いたので、さらに先を進むことになった。
氷ノ山山頂はツアースキーヤーの人だかりだった。櫓のある三角点の周囲だけは雪がなかった。曇りがちで遠望できないが、周囲の近い山々は見渡せた。
ここからコシキ岩まで直線的に下り、その横を滑落しないように注意してまいていく。そのすぐそばをスキーヤーが楽々通過していく。やはり氷ノ山はツアースキーの山だった。
雪庇に注意しながら稜線伝いに氷ノ山越にたどり着くと、そこから先は下の林道まで楽しいシリセードである。立ち木を避けて快調に高度を下げる。この途中で誰かさんはカメラをなくし、誰かさんは小さなクレバスに落ちて足だけ残し逆さ吊りになった。
滑り降りて着いた林道にテントを張る。近くに水場がある。遠雷が聞こえ、夕方から夜にかけて雨が降った。平木さんが作った趣味の雪洞は、雨天のためキジ場になった。
朝からガスがかかっていた。テントの外に置いていたコッヘルのふたが見当たらないので、そのあたりを見回したがどこにもない。風にさらわれるわけはないと思っていたら意外にも遠くまで転がっていた。ふた捜索のため予定より出発が少し遅くなった。
今日のコースは前半は林道、後半は上り下りの続く稜線歩きで、最も時間がかかるそうである。
サイト地を出発して、所々土砂が崩れ落ちて赤茶けた雪の上を行く。桑ヶ峠を過ぎていよいよ雪に沈むようになったが、それでもワカンは使わない気配だ。林道から陣鉢山分岐の入口あたりが不明瞭で、このようなガスの濃い日に初めて来ると、まず道に迷うと思う。
分岐から急斜面を下ると、難関のやせ尾根である。右側は滑落するとどこまで落ちていくかわからない。左側は木や薮が少しあるものの、右と大して変わらないようだ。雪が部分的に融けた稜線上はブッシュ、アイスバーン、雪庇と危険を感じずにはいられない。大キスを背負ったパーティーには噂にたがわぬ難所だ。
去年は誰かさんがここで滑り落ちそうになって木に引っ掛かったそうだ。バランスを失って滑落しそうになったら、左側に倒れろとPLの竹内さんが言った。今年は、誰かさんがサングラスをなくし、誰かさんが木立に額をぶつけて、なんとか通過できた。
それからあとはふつうの尾根伝い。ラッセルと小さな上り下りがめんどうなだけ。周囲の景色がガスにさえぎられて見られないためか、印象に残るようなものはない。
三ツ谷ノ頭の手前の鞍部につくころ、ガスが切れ青空が広がり始めた。展望が開け、陽がさしてずいぶん明るかった。今日はここでテントを張り一泊。昨日と今日とで予定の4日の行程を終えた。
起床の番に当たっていたが寝過ごす。ふつう4時半起き2時間発である。
三ツ谷ノ頭あたりからガスが出てくる。雪庇に注意して青ガ丸への長い登りを行く。頂上はやや広く、この下りのコースはしっかり見定めておく必要がある。誰かさんが滑って木に引っ掛かったのはこの下りだそうだ。
シリセードで一気に下りたかったが、方向を誤るとどこへ下っていくかわからないので、ゆっくり進んだ。この下りあたりからガスが消えはじめ陽がさして急に明るくなった。
中ノ丸、切石はめだたない丘陵で、これを過ぎるとだらだらした下りが続く。ラッセルのトップに立って開放的な樹林帯の中を快調に進む。なだらかな下りだからラッセルもたいして苦にならない。その反動で、シブキ山の登りが少々辛かった。
どこが諸鹿峠かわからないような雪原を通り、左にこんもりした二ツ山を見ながら、判然としないなだらかな稜線を急ぎ足で登っていく。途中にテントがあったが、人影はなかった。
扇ノ山の稜線に取り付く手前の鞍部でテントを張る。予想外に早く着いたのでテントの中でのんびりくつろぐ。
しばらくして扇ノ山方面からサブザックを背負った大教大ワンゲルのパーティーが下ってきた。風弱く雲一つない穏やかな午後の青空は、春を感じさせる。
近くの斜面に雪洞を掘る。後藤、松原と後藤さんがこの晩そこで寝た。テントの中は5人でスペースはゆったりとれたが、あいにくこの晩は特別寒かった。
高層雲のため、夜明けの月はおぼろげであったが、日の出は美しい朝焼けになった。扇ノ山までピストンの予定だったが、ザックを担いだまま頂上まで行く。
山頂は広く、屋上が展望台になったコンクリート造りの避難小屋がある。ここから氷ノ山と今まで通ってきた山稜や周辺の山々がごく間近に見えた。苦労した割には、遠くから歩いてきた感じがない。日本海、大山などは見られなかった。天気はもうひとつよくない。
展望台に残った後藤と安原さんを標的に、残りのメンバーが雪合戦を始める。童心に返ってしばらく夢中で雪玉を投げ合う。竹内さんのが誰かさんの顔に命中したところで終了した。朝の固く締まった雪玉は、当たるとかなり痛そうだ。
大ヅッコを越えて、高原状の起伏のない稜線を北上していくと、すぐに小ヅッコ小屋に着いた。小ヅッコ小屋は2階建ての鉄筋造りで小屋というより、むしろヒュッテといった感じ。冬期は2階が入口で、それに梯子がついている。
入口からすぐに階段を降りると、話に聞く例のストーブがあった。その横にはストーブ買い替えのカンパを募るビニール袋が吊り下がっている。ワラや柴や薪が十分あるほか、除雪用にスコップが3つ、ウィスキーまである。
ストーブに点火し、紅茶で一息つけると、暇つぶしに雪洞堀りを始めることにした。
後藤と私の二人で掘り始めた横穴式雪洞は、途中で木の枝が現れ始め思うように掘り進められなかった。最終的に完成した空間のほぼ3倍の量を掘り出した。
平木さんの雪洞は、一人で掘ったにもかかわらず、入口を広くとらずに効率よく掘り進めて、かなり大きなものを作った。
その横で、後藤さんが掘り出された雪のブロックを積み上げイグルーを作っていたが、別にスノースコップを使って四角く雪のブロックを切り出して積み上げた松原のイグルーの方が様になっていた。
1年生3人と後藤さんとでワカン競争をする。小屋から少し離れた斜面から後藤さんのイグルーの上を通って小屋前まで。着順は、後藤、松原、後藤さん。私はドン尻。
この後夕食。雪洞を仕上げて夜食。雨が降り始めたため、小屋の2階で寝ることになった。
霧雨。出発して少し下ったところでワカンを着ける。霧雨から霧になり、ショーブ池でセパレーツを脱ぐ。内側は蒸れ、濡れていないのは外側だった。
西ノ丸をトラバースして高原のような広い尾根を2つ越える。濃霧に包まれて、現在の位置がよくわからない。偵察をしばらくして、コースが確認されると、立ち木のない雪原を北に進んでいった。杭のようなものが雪の中から少し頭をのぞかせていたので、その周りを掘り下げてみるが、道標ではないようだった。
ゆるやかな下りが続く。やがてガスが薄れてくると下界の展望が開けてきた。西に大きな稜線が雲の下面から出て北に伸びて前方の山並みに続いている。その手前にも小さな稜線が平行していた。地図を広げて確認する。
林道に出る。所々雪が消えているが、まだ車の入って来れる状態ではない。ラッセル続きで後藤のワカンの細引きが切れた。この林道で救われたかも。
展望の良い曲がり箇所で休止。どんよりした曇り空に霞雲のかかった山々や、海上の集落が遠くに見える。色彩の乏しい風景は、まるで水墨画のようだ。
ワカンを外す。林道と林道の間の斜面をシリセードしたり、田畑の中を横断したりすると、林道歩きも変化に富んでいて、けっこう楽しかった。
海上に着くと、そこから先は除雪された道が続く。走るように歩く。海上口のバス停への最後の坂は全速力で駆け下りた。
バスが来るまで、まだ1時間余りあった。泥の跳ね上がったスパッツとオーバーズボンを脱ぎ、スパッツは道路横の水路を流れる雪解けの水で軽く濯ぐ。
一息ついたところで紅茶を作る。雪を融かして作った水を今までに何度も飲んできたのに、明るいところではっきり見るのは初めて。その水で作った紅茶の中には、何かしら小さなものがいっぱい浮遊している。
バスで浜坂まで行く。浜坂駅構内にある待合室のストーブでしばらく暖をとってから、鳥取へ行った。喫茶店で反省会、それから中華料理店へ。大阪駅まで特急、着いたのが午後9時半ごろ。
この合宿で自分の体力に絶対の自信が持てたのは確か。