 Return to
Return toFeature story
Home
 はるか昔、何もないところに空間と時間がうまれました。そこにいまの銀河や恒星が誕生しました。初期の恒星では生命は存在していなかったといわれています。星の生死の繰り返しによって宇宙が誕生して100億年の後、銀河系の端に三世代目の恒星の太陽系が誕生しました。その中に生命にかかわる重い原子を含む地球という惑星も誕生していました。原子が有機物を形成し、その自己複製により生命の種がうまれました。さまざまな環境の変化の中で淘汰を繰り返し生命は進化していきました。そして、地球上でたまたま生き残った子孫がわたしたち人類です。
はるか昔、何もないところに空間と時間がうまれました。そこにいまの銀河や恒星が誕生しました。初期の恒星では生命は存在していなかったといわれています。星の生死の繰り返しによって宇宙が誕生して100億年の後、銀河系の端に三世代目の恒星の太陽系が誕生しました。その中に生命にかかわる重い原子を含む地球という惑星も誕生していました。原子が有機物を形成し、その自己複製により生命の種がうまれました。さまざまな環境の変化の中で淘汰を繰り返し生命は進化していきました。そして、地球上でたまたま生き残った子孫がわたしたち人類です。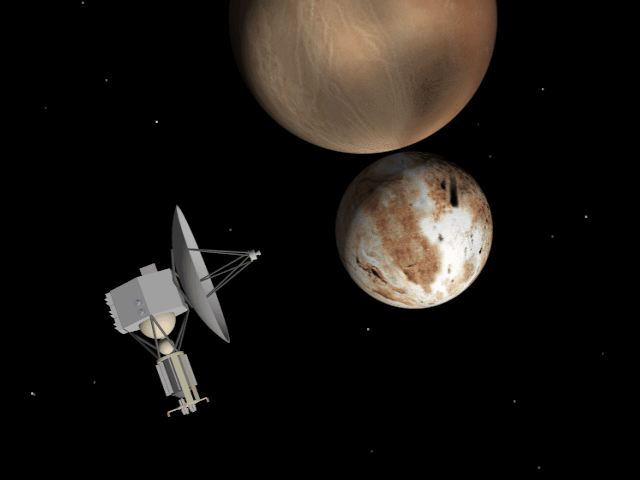 1957年10月4日、旧ソ連が世界初の人工衛星スプートニク(直径56センチ)を打ち上げたことによって、米ソの宇宙開発競争が本格化します。
1957年10月4日、旧ソ連が世界初の人工衛星スプートニク(直径56センチ)を打ち上げたことによって、米ソの宇宙開発競争が本格化します。| 1962年2月20日 |
アメリカはジョン・グレンを乗せたフレンドシップ7で アメリカ初の軌道周回飛行を4時間56分したのち帰還します。 |
| 1963年2月 |
アポロ計画を推進したケネディ大統領は ダラスで凶弾にたおれましたが、 その意思はそのままジョンソン大統領、 ニクソン大統領と引き継がれていきました。 |
| 1963年6月16日 |
旧ソ連は世界初の女性宇宙飛行士V・テレシコワを乗せた ウォストーク6号を打ち上げます。 |
| 1964年10月12日 | 旧ソ連は世界初の三人乗り宇宙船ボスホート1号を打上げます。 |
| 1965年3月23日 | アメリカはアメリカ初の二人乗り宇宙船ジェミニ3号を打上げます。 |
| 1965年3月 |
旧ソ連の宇宙船ボスホーク2号が打ち上げられ、 アレクセイ・レオーノフが初の宇宙遊泳にも成功しています。 |
| 1965年6月3日 |
アメリカは宇宙船ジェミニ4号を打ち上げ、 エドワード・ホワイトが、21分間の宇宙遊泳を成功させます。 |
| 1965年12月15日 |
アメリカはジェミニ6号と7号の世界初の30センチの ランデブーを果たします。 |
| 1966年3月 |
アメリカのジェミニ8号はアジーナ衛星とのドッキングを 成功させました。 |
| 1964年10月12日 |
世界初の三人乗り宇宙船ボスホート1号を 打上げに成功します |
| 1965年3月 |
宇宙船ボスホーク2号が打ち上げられ、 アレクセイ・レオーノフが初の宇宙遊泳に成功します |
| 1965年11月 |
予定されていたボスホート3号の打上げは設計長 S・P・コロレフの手によって進められていましたが コロレフ設計長の急病により延期されました。 (搭乗予定搭乗員ボリノフ(船長)、カチス(機関士)) |
| 1966年1月14日 |
外科手術を受けたコロレフ設計長が死去し、 ボスホート計画は大きく変更されることになりました。 (搭乗予定搭乗員はボリノフ(船長)、ショーニン(機関士)に変更) |
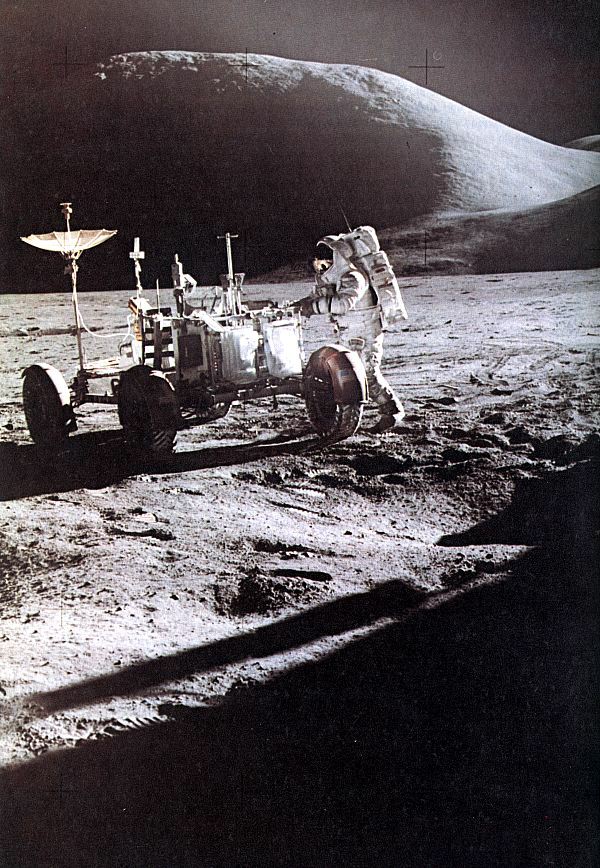 1969年7月16日月着陸を目指してアポロ11号が打ち上げられます。19日には月の軌道にのり、打ち上げから100時間後司令船コロンビアから、着陸船イーグルが切り離されました。
1969年7月16日月着陸を目指してアポロ11号が打ち上げられます。19日には月の軌道にのり、打ち上げから100時間後司令船コロンビアから、着陸船イーグルが切り離されました。| 1973年5月14日 | アメリカはアメリカ初の宇宙ステーション スカイラブ1号を打上げます。 |
| 1975年7月17日 | アメリカのアポロ18号と旧ソ連の ソユーズ19号がドッキングに成功 |
| 1981年4月12日 | アメリカがJ.ヤング、R.クリッペンが 乗組み世界初のスペースシャトル コロンビア号が打ち上げます。 |
| 1983年6月18日 | アメリカ女性初のS.ライドが宇宙飛行します。 |
| 1984年7月17日 | 旧ソ連、サビツカヤがソユーズT-12で 世界女性初の船外活動 |
| 1984年10月5日 | アメリカ、K.サリバンが 米国女性初の宇宙遊泳に成功 |
| 1986年1月28 日 | アメリカ、チャレンジャー号が 打上げ直後の爆発事故をおこし 7人の乗員が死亡 |
| 1986年2月19日 | 旧ソ連、ミール、宇宙ステーション 打上げ |
| 1988年11月15日 | ソ連、スペースシャトルブランを エネルギアにて無人試験飛行 |
| 1990年12月2日 | 秋山豊寛さんがソユーズTM−11、ミールにより 日本人初の宇宙飛行を体験 |
| 1992年9月12日 | 毛利衛さんが日本人初の科学宇宙飛行士・ スペースシャトル飛行士としてエンデバー号に搭乗 |
| 1994年7月8日、 | 向井千秋さんが日本人初の女性宇宙飛行士として コロンビア号に搭乗 |
| 1995年2年6日 | アメリカのディスカバリー号と ソ連のミールがランデブーに成功 |
| 1995年6月29日 | 米アメリカのアトランティス号と ソ連のミールがドッキング |
| 1996年1月11日 | 若田光一さんが日本人初の ミッションスペシャリストとしてエンデバー号に搭乗 |
| 1997年11月19日、 | 土井隆雄が日本人初の船外活動を行うため コロンビア号に搭乗 |
| 1998年10月29日 | 向井千秋さんがディスカバリー号に 乗組み2回目の宇宙飛行 |
| 2000年2月 | 毛利衛さんがエンデバーに乗組み 2回目の宇宙飛行 |
 Return to
Return to
Feature story
Home