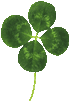はじめに
脳性小児マヒの障害を得て生まれると、成人以降、たいてい二次障害を発症する。これは生まれた時点から頸骨に異常な負担をかける障害であるためだ。時期に関してはすごく個人差があり、特定は難しいが四十代から五十代でなるものが多い。そのむかしは寿命も短く、二次障害が発症する前に亡くなっていたが、高齢化の波は障害者にまで及んでいる。これから書くレポートは、あくまで個人の経験によるもので、すべての二次障害を発症している人たちに当てはまるとは限らない。ひとつの情報として参考にしていただきたい。
発症
例えば、うがいや薬を服用するとき、首を仰向けるとカラダ全体にシビレが走る。これが最初の自覚症状で、この頃から異常な肩こりなども感じるようになる。そして、これらを放置しておくとだんだん歩きにくくなったり、手に力が入らなくなる。
しかし、体に激しい変調をきたす前には、必ず首に激しい負担をしいる出来事(例えば、転んで、思いっきりアゴを打つなど)が起きる。それからは時間経過と共に体は動かなくなり、シビレや痛みは燃えるように激しくなる。
例えば、転んで、体がなんだかおかしいな、と感じているときに適切な手術を受ければ、もとの障害程度に戻ることが多い。
医師の説明の問題点
大抵の医師は「首の骨に変形がきています」と言われる。この言葉は医学に通じているものと全くの素人とでは、受け取り方がまるで違う。
少なくとも自分は『首の骨がとちらかの方向にズレて、中枢神経に当たっている』と思い込んでしまった。しかし、本当の意味は『骨と骨をつなぐ軟骨、または骨の上にできてしまった軟骨が内側に角が突き出るように変形してして中枢神経を脅かしている』ことなのだ。
つまり、我々が常識的に理科室においてある骸骨の標本が「骨」であると思っている。しかし、その「骨」は変形することはない、というのが医学の常識らしい。もし、その「骨」の変形があれば、それは奇形ということになるのであろう。
もうひとつ知っておいて得するのは『中枢神経は、頸骨から尾骨までの背骨内の真ん中に一本の管として通っている。それを傷つけないため髄液がその周りを取り囲んでいる。髄液はクッションの役割と同時に常に循環していて中枢神経の鮮度を保っているらしい。そして、突き出た軟骨が神経に当たると髄液の循環もとどこおる』ということだ。
そして病名をはっきり知るのも大切なことだ。「頚椎軟骨症」または「頚椎症性脊髄症」と言われることが多い。そのとき「それは、どんな病気ですか? 詳しく教えてください」と尋ねれば、意味を取り違えることもなく、正しく自分の体に起こっている問題を理解することができる。
検査
MRI または、脊髄に造影剤を入れレントゲン CT などで簡単に判明できる。
手術
従来の手術方法=固定手術法
首の骨をボルトやワイヤーで動かないように固定することで、突き出た軟骨が中枢神経をこすり続けることをふせぐと共に、軟骨が今以上に成長しないようにする手術。この手術方法が今現在も主流である。
しかし、これには問題が多い。
まず、原因である軟骨がそのまま残っていること。それにより髄液の循環も妨げてしまっていること。
それにもましての問題は、手術後の固定にある。二週間から四週間の絶対安静。それも首は1㎝も動かしてはいけない。咳やくしゃみはもちろん笑うことも出来ない(笑って再手術した人もいる)。
これは普通の健康な人でも大変なことだが、脳性マヒのものにとっては、健康な人がまばたきをしないでその間いなさい、と言われるようなもの。現在は、介助のもと少しは動けるようだが。しかし息をするのも慎重にしなければならないだろうし、どうやって食事をするのだろう?と思う。自身にとっては死ぬより大変なことだと感じる。
それから、ゆるやかな固定を経て、完全に骨が固まるまで6ヶ月かかるらしい。そして、ようやく全体が自由になる。それだけの間動かないと関節も筋肉もすぐには動かないので、リハビリがこれまた大変になる。
大変づくしのあとに普通の生活になるのだが、首を動かそうとする力はものすごく、いずれはボルトなら折れ、ワイヤーなら切れてしまう。そうすると、再手術で、また同じ苦しみが待っている。
最先端の手術方法=椎弓手術法
これは、ボルトやワイヤーなどを使わずに、頚椎の一部をなんらかの方法ではずし、変形している軟骨だけを取り除き、また元に頚椎をもどす、という画期的な手術法である。
手術後は何の固定もないし、即、首も自由に動かせる。リハビリも手術した翌日から始まるので、関節が固まったり、筋肉が衰えてしまうこともない。
二次障害を発症した脳性マヒのものにとって夢のような手術方法なのだ。
この手術方法が行われている病院は、自身の知る限り、京都では、京都府立大学病院、整形外科と 京都第二日赤病院、整形外科 である。
この手術方法が早く多くの人々に知られ、主流になることを切に望む。
リハビリ
新旧いずれの手術を受けても、そのあとには必ずリハビリが待っている。脳性マヒのものは、ほとんどが理学療法士、作業療法士によるリハビリを受ける。
ここでの問題点は、一般にリハビリを受ける人たちのほとんどは、健康な人の骨折やヘルニアの術後の方、脳梗塞、脳出血による後遺症の方、寝たきりを防ぐための老人である、ということだ。そのため、どちらの療法士も脳性マヒに必要なリハビリの理解が出来ていない、または知識の少ない先生が多い、ということだ。
従って、脳性マヒのものは、専門家だから任せておけばよい、とは思わないことだ。
勉強家の療法士には、同じ療法を二週間して効果がなければ、別の療法に変えこるとを繰り返して対応をしてくれるが、こういう療法士は希有である。
一般的な療法士は、現在持っている技術をフル回転させて、脳性マヒに対応してくれる。しかし、本人の希望が本人の状態により容易でない場合は、療法士の持っている技量で大きく異なるし、希望はおざなりになる。さらには、本人に相談なく、医師と療法士だけで勝手に「ここまで」と決め、諦めさせてしまうこともある。
こういう場合、障害者本人がしっかりと自分の状態を理解し、限界を自覚し、常に希望を持ち続け、主張していくことが大切である。それに加えて、療法士をかえてもらったり、転院なども視野に入れておこう。
自身の場合は、「歩く」という強い希望を持っているにもかかわらず、電動車いすを乗りこなしていたため、療法士が「歩かなくても生活に支障がない」と思い込み、強い希望が忘れられてしまった。退院の一ヶ月前くらいに改めて「歩く」主張をすると、あわてて歩行訓練が始まった。こんなことが往々にしてあるので、注意したい。
あとがき
昨年9月、私は京都第二日赤病院で八田陽一郎先生に手術をしてもらった。幸運にも養護学校の先輩がこの手術をしていて、紹介してくれたからだ。激しく発症してから二年、ボルトやワイヤーでの固定に抵抗があり、手術を迷っていた。もう少し早くこの情報を知っていれば、完全復帰していたに違いない。術後一年を過ぎ、神経は順調に回復しているが、完全に元にもどるのは難しいだろう。
障害者は限られた環境で生活しているものが多く、こうした情報は得にくい。ここに紹介することで少しでも二次障害に苦しむ人たちの役にたてれば、と願う。
|