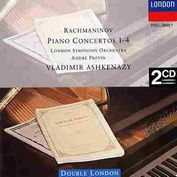
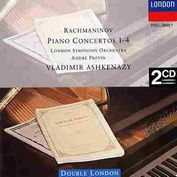
| ○ | ヴラディーミル・アシュケナージ(ピアノ) |
| アンドレ・プレヴィン指揮 | |
| ロンドン交響楽団 | |
| (録音:1970年) |
|
全体的に、ピアノ、オーケストラともに重厚でふくよかな音色が特徴。また、両者の見事な一体感が聴くものを感動させます。
第1楽章の、特に第1主題の弦楽器はすばらしいです。重く、暗く、どろどろネバネバとした雰囲気がまさに私好みの演奏でした。というより、こういう演奏の方が、第1主題の性格にマッチしているのではないかと思います。 第2楽章、第3楽章はアシュケナージの独壇場です。第2楽章のアシュケナージのまろやかで温かみのある音色は、もう、右に出る者がいないのではないかと思わせるほどの美しさです。第3楽章は冒頭からわりと飛ばしていますが、何事もないかのようにサクサクと進んでいくので圧倒されます。サクサク進む割に、低音がよく効いていてドッシリとしているので安心感がありますね。 また、第3楽章のコーダのピアノとオーケストラの見事な一体感は天下一品です。鳥肌もんです。 |
[是非一度聴いてほしいCD]
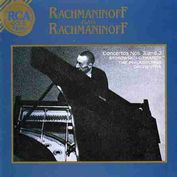
| ○ | セルゲイ・ラフマニノフ(ピアノ) |
| レオポルド・ストコフスキー指揮 | |
| フィラデルフィア管弦楽団 | |
| (録音:1929年4月10、13日) |
|
作曲者自身のピアノによる歴史的な名盤。録音年代が古いため、ノイズがあったり音量の幅が狭かったりしますが、それは仕方がないです…。
いったい作曲者はどんな感じで弾くのだろう、感情移入は激しいのだろうか…などとかなり期待しながら聴きましたが、なかなかに度肝を抜かれる演奏です。とにかく「速い」のです。 また、今日ではたいていゆったりと歌われている甘美なフレーズも、ラフマニノフは何事もないように素通りします。これは意外でした。 ただ、いくら録音状態が悪いといっても、ラフマニノフの強靭なヴィルトゥオージティは鮮明に伝わってきます。細かなパッセージの見事な演奏や、どこからそんな音を出してんねん、と言いたくなるほどのパワフルなフォルティッシモは痛烈でした。全体的に重く、ドッシリとした印象を受ける演奏です。 |
[他のCD]
| ○ | スヴャトスラフ・リヒテル(ピアノ) |
| スタニスラフ・ヴィスロツキ指揮、ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| (録音:1959年4月) |
このCDもベスト盤として推したいところです。録音年代はかなり古いですが、ステレオ録音である上に驚くほど音質が良いです。 |
| ○ | アンドレイ・ガブリーロフ(ピアノ) |
| リッカルド・ムーティ指揮、フィラデルフィア管弦楽団 | |
| (録音:1989年) |
冒頭からガブリーロフの強靭なタッチが炸裂しています。 第1楽章は、特に展開部後半から再現部に至るまでのスリリングな展開が聴いていて飽きません。第3楽章ではガブリーロフのヴィルトゥオーゾぶりがいかんなく発揮されており、特にコーダ後半の、ハラハラさせるほどの急速なテンポで疾走し、猛烈な勢いを保ったまま曲を締めくくるところが魅力的です。 |
| ○ | ウラディーミル・アシュケナージ(ピアノ) |
| キリル・コンドラシン指揮、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| (録音:1965年) |
アシュケナージ28歳の時の録音です。後のプレヴィン盤などと、演奏上の解釈は基本的に変わっていないと思います。テンポのとり方やイントネーションのつけ方などほとんど同じように聞こえます。 |
| ○ | ミルカ・ポコルナ(ピアノ) |
| イジー・ワルトハンス指揮、ブルノ国立フィルハーモニー管弦楽団 | |
| (録音:1968年) |
まず、一つだけ言っておきたいのは第2楽章。録音後の編集作業の過程でミスしてしまったのでしょう、途中、ごっそりと抜け落ちてしまっている箇所があります。まあ、それほど不自然でもないので許せなくもない範囲のミスですが、この楽章を知っている人からすると、かなり違和感があるかと思います。 |
| ○ | リーリャ・ジルベルシュテイン(ピアノ) |
| クラウディオ・アバド指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| (録音:1991年) |
とても安定していて、何か「安全運転」といった印象を受ける演奏です。 スリリングな面白みには欠けますが、落ち着き払った雰囲気が逆にすごかったりします。 |
| ○ | ラン・ラン(ピアノ) |
| ワレリー・ゲルギエフ指揮、マリインスキー劇場管弦楽団 | |
| (録音:2004年) |
骨太なピアノの音と、エネルギッシュなオーケストラが印象的な名演です。 |