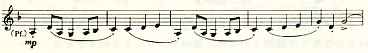この曲にハマりだした頃、完全に第1楽章中毒とも言えるような症状になっていました。家に帰ってくるとこの曲を聴かずには
いられなかったし、いつでもどこでもあのリズミカルで冷たさの漂うメロディーが頭の中で
流れつづけました。大学の試験時間中のような、余計なことを考えている暇のないような時ですら「タッタ タッタ
タッタ タッタター ター ター ター…」というメロディーが私を邪魔しました。
タッタ タッタ…というメロディー
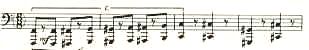
そんなお騒がせなこの楽章の好きな所、聴き所を挙げたいと思います。
まずは冒頭のファンファーレのようなフレーズの後に現れる、強烈なリズムで不協和音を叩きつける場面。

この気持ち悪さが逆に気持ちよい。ストレスを発散してくれます。
次は穏やかな第2主題。温かいのだか冷たいのだか分からない、どっちつかずな雰囲気の楽想が展開されます。
不思議な雰囲気を楽しむのがいいだろう。
この第2主題を終えると再びアレグロの主題に戻るが、ここが個人的に最高の聴き所ですね。もう何が何だか分からない
狂気の音楽。しかしそれでいて、あの「タッタ タッタ…」という独特のリズムは常に失われずに生きていて、
音楽に躍動感を与えつづけています。これぞまさにプロコフィエフ!! 最高!!、と感嘆の声を上げずにはいられない。
ハチャメチャやっているくせに規律はきっちり守っている、頭のいい不良、みたいな感じですね。たまらん…(笑)
そして最後の最後も気持ち悪く締められます。悪趣味にもほどがあるが、何度も言うように、この気持ち悪さが
この曲の良さだと思います。
とにかく私を虜にしたこの楽章ですが、やはり私にとって一番の魅力は、リズミカルな音型と、それによってもたらされる
圧倒的なスピード感です。指自体はそれほど速い動きをしているとは思えませんが、そのくせぐいぐいと引き込まれる
スピード感に溢れています。
また、時たま顔を出す旋律っぽいフレーズも魅力。ほとんどが無調的であるがゆえに、そういった旋律らしきものがより
いっそう魅力的に聴こえてきます。
兎にも角にもハマってしまった楽章です。