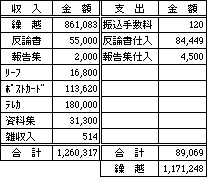![]() 1999年度活動総括
1999年度活動総括![]()
![]() 1999年度活動総括
1999年度活動総括![]()
◆ 上告され二年目を迎えた昨年5月に松谷訴訟弁護団は、厚生省の主張を打 ち崩す「上告理由反論書」を作成、最高裁に提出しました。これで主張が出 そろい、最高裁判所がいつでも判決を出せる状況ができました。しかし、最 高裁でのたたかいは、裁判の進行が全く見えないために運動は思うように前 進しませんでした。支援する会の会員が自覚的に行動しようとしても、どう したら良いのかわからない状況も生じています。また、新ガイドライン関連 法や年金改悪などをはじめとして、私たちの「くらし」「いのち」を脅かす、 政治的・社会的課題がかつてないテンポで次々と押し寄せています。こうし た情勢の中で、上告棄却を求める署名も他の様々な運動の影に隠れるという 事態も生まれています。
◆ 私たちは、運動に節目を設定し、全会員の知恵を結集した運動を工夫し、 マンネリから脱却した全国各地での行動に取り組むことを方針に掲げて活動 してきました。いくつかの県で、署名活動の前進や会員の増加など、大きな 成果もあがっているところもありますが、事務局として全国へ向けての具体 的取り組みを提起できませんでした。これは、たたかいの舞台が遠くの東京 (最高裁)へと移ったことにたいして充分な支援体制が取れなかったことで あり、これまでの最高裁係争事件の支援運動の教訓を学習し学ぶ事の重要性 を示しています。
◆ しかし、このような困難な中でも、全国の会員の大きな力添えを得て、オ ランダ・ハーグで開催された「世界市民平和会議」へ松谷英子さんを送り出 し、被爆者として、原告として訴え、被爆者の実相と松谷訴訟を全世界に知 らせることができました。
松谷さんと支援する会のたたかい、そして、京都原爆訴訟の原告Aさんの たたかいに続いて、6月東京で、10月には札幌で被爆者が原爆症認定訴訟 に立上がりました。4つの裁判支援にも表れているように、国民の中に核兵 器廃絶・被爆者援護連帯の声は大きく高まっています。
◆ こうした中、9月末日本の原子力施設が集中している茨城県東海村で決し てあってはならない臨海事故が起き、新たな被爆者を生み出し、不幸にして 一人の方が亡くなるという痛ましい結果となりました。唯一の被爆国であり ながら、原子力の安全神話の虚構にしがみつき、ずさんなチェックを行って きた政府の姿勢が問われる事件でした。
Ą.裁判所に対するとりくみ € 地裁、高裁段階で支援を頂いた以外の個人・団体へも支援をよびかけ、最 高裁への「厚生省の上告棄却を求める署名」運動を推進しました。今年度、 ネットワークを中心に4次にわたる要請行動を行い、14万の個人署名、約 2千の団体署名、176通の上申書を提出しました。しかし、一日も早く個 人署名100万、団体署名2万をという目標は達成できませんでした。
昨年度に比べ、署名への協力をよびかけた「にゅうす」の発行を増やし集 約団体が広がるなか、個人署名は昨年度の約半数にとどまりました。このよ うな中、一人で1万を超える集約をしている会員の方もいて、支援する会は 大いに励まされています。
署名などの最高裁への提出状況は、以下の通りです。
| 行動日 | 個人署名 | (累計) | 団体署名 | (累計) | 上申書 | (累計) |
| 5月6日 | 68,658 | 389,604 | 739 | 1,904 | 77 | 306 |
| 41,000 | 114,000 | 568 | 1,181 | 77 | 263 | |
| 7月22日 | 20,886 | 410,490 | 996 | 2,900 | 72 | 378 |
| 11,213 | 125,213 | 970 | 2,151 | 0 | 263 | |
| 9月21日 | 23,600 | 434,090 | 75 | 2,975 | 23 | 401 |
| 18,371 | 143,534 | 71 | 2,222 | 10 | 273 | |
| 11月25日 | 26,581 | 460,671 | 149 | 3,124 | 4 | 405 |
| 15,000 | 158,534 | 98 | 2,320 | 0 | 273 |
署名運動とともに、具体的な被爆の実相と被爆者の願い、国民の思いを届 ける「最高裁判官への手紙(上申書)運動」は、取り組みを広げきれず、提 出数は昨年度を下回りました。上申書は署名とともに、たいへん効果のある ものであるにもかかわらず、その重要性を広く伝えることができませんでし た。
¡ 4回の最高裁要請行動(最高裁職員へのよびかけ、書記官への要請、署名・ 上申書の提出)には、ネットワーク構成団体が参加しましたが、地元である 関東地域の団体・個人会員が参加するまでには至りませんでした。
˘.支援運動強化の取り組み 100万署名を推進するために、運動の担い手となる会員を各地で増やす取 り組みを行いました。また、全国規模で行われる「3.1ビキニデー」「原水 爆禁止世界大会」を節目とし1万人会員達成に努めました。入会者の多くは 「原水爆禁止世界大会」開催中に、参加県の代表団会議に招かれ、その中で松 谷さんの話を直に聞いた人達です。さらに大会後に、静岡県・千葉県の諸団体 に招かれ支援要請行動を行いました。行動に伴う財政は、オルグ先のそれぞれ の県で募金運動を行い賄いました。
€ 会員拡大を重視し様々な取り組みを行う中、291名の新会員を迎えまし た。しかし、退会者が新会員を上回り、結果として13名減となったことを 厳しく受け止めねばなりません。なお、団体会員は5団体増、2団体減で計 413団体となっています。 現況は、次の通りです。
新会員 291名 退 会 304名 不 明 35名 〃 18名 〃 35名 〃 5名 個人会員合計9057名 団体会員合計413団体 *下段は、長崎で内数。期間は、1999年2月1日〜12月末まで。
3か月ごとに『支援する会にゅうす』を発行しました。(4月30日、7 月3日、10月25日、12月20日)発送作業はたいへん負担のかかる作 業のために1〜2週間を要しています。より多くの地元の団体・個人会員の 協力が必要です。
地元の団体会員を中心に「署名推進・団体会員にゅうすイン長崎」を毎週 ファックス送信し、支援する会の活動を伝えてきました。送信先の団体は県 外にも増え、50団体余になっています。100万署名を達成するには、全 国の諸団体に向け『推進ニュース』をさらに広げることが必要です。
¡ 全国各地はもとより、東京での最高裁勝利をめざす「キャラバン行動」な どの取り組みについては提起までにはいたりませんでした。
¤ 都道府県単位に「支援センター」づくりをめざす働きかけができませんで した。働きかけているところも結成には至っていません。
¦ 松谷訴訟弁護団は5月6日、300ページに及ぶ「上告理由反論書」を最 高裁へ提出しました。この「上告理由反論書」を使った学習会を各地で行う ことを計画しましたが、実施には至りませんでした。9月26日の提訴11 周年記念拡大役員会では、この学習会を行いました。
© 98年9月より専従事務員が配置され、実務処理も回復されつつあり、事 務局会議の開催、事務局内通信、各団体への働きかけができるようになりま した。しかしながら、運動と情勢に見合った事務局を確立することができず、 活動の日常的な点検や問題点の把握の不足、全国の会員諸団体への運動の提 起などは不十分なものとなっています。
また、役員会については、役員の多忙さもあり定例化が困難で問題提起を するときだけの開催なってしまいました。
ª 最高裁が舞台となり財政活動は一層重要となっています。募金については ハーグ募金を加え前年度水準を確保しましたが、会費の納入率は大幅に低下 しています。これは事務局の働きかけ不足によるもので至急改善が必要です。
« 松谷裁判ネットワークの支援は大きな力です。ネットワークとは2か月に 一度の最高裁要請行動を一緒に取り組み、行動後は学習会やネットワーク事 務局との打合わせなどを行いました。
昨年5月、100年ぶりに市民平和会議がオランダのハーグで開催され、 支援する会は、国際連帯、国際的規模での支援運動を展開するために、松谷 さんと牧山次長を「つたえようヒロシマ・ナガサキ」の一員として派遣しま した。
この会議で松谷さんは、日本被団協の被爆者とともに被爆体験を語り、現 在たたかっている裁判闘争について訴え、日本政府が、唯一の被爆国であり ながら、被爆者にたいし「戦争だったんだからガマンしろ」と言っているこ とを明らかにしました。
世界各国から参加していた若者たちは、松谷さんをはじめとする各地の核 実験被害者の被爆体験を涙ながらに聞き、当時激化していたコソボへの爆撃 に核が使われるのではないかと憂慮し、被爆者と一緒に「ゲンバク、ハンタ イ」と叫びながらデモ行進をしました。被爆者の訴えは、核兵器のない21 世紀を実現する、大きな現動力になることを改めて示したできごとでした。
® 毎週土曜日に地元の繁華街で続けている街頭宣伝・署名行動は今年度も着 実に実行し、市民、特に小学生・中学生・高校生などの若い世代の関心を喚 起するうえで大きな役割を果たしました。また、節目の行動の一環として、 11月には繁華街で9時間に及ぶロングラン行動を行い、署名1227筆、 募金18,474円の成果が得られました。こうした街頭宣伝は、地元の団 体会員に依拠し分担しながら取り組んできました。社会情勢の厳しい中で各 団体会員は、事情の許す限り当番日に参加し行動を成功させてきました。し かし、地元団体会員の参加状況で行動の成果が大きく左右されることは否め ません。会員の意見を聞きながら、より効果的な行動へと改善が必要になっ ています。なお、団体会員の中には、地域での独自の行動をすすめたところ もありました。
年間の実施回数は、昨年2月から21回です。参加者は最高18名、最低 で4名、署名合計2289筆、募金39,731円でした。
Ł.弁護団との連携など
「上告理由反論書」の作成には、各地の弁護士をはじめとする学者や専門家、 ネットワーク各団体、支援する会からも複数参加し議論を重ねました。本文は 300ページからなるものですが、内容をより広く普及するためにもダイジェ スト版の作成が必要になっています。
動きの見えない最高裁での裁判闘争では、弁護団の経験と見通しのアドバイ スを受けながら、原告・支援者が運動を進めることがこれまで以上に必要です。 弁護団会議への支援する会の参加や支援する会役員会への弁護団の参加などの 連携をはかってきましたが、決して充分ではありませんでした。
原爆症認定を求める裁判が、京都に続き東京・札幌で始まりました。支援す る会は、「にゅうす」で全国に紹介するとともに、メッセージを送ったり、傍 聴に参加するなどして連帯してきました。
今後の連携を、どのように進めていくのかが課題です。
![]() 2000年度活動方針
2000年度活動方針![]()
被爆55周年、2000年の節目の今年は、最高裁でのたたかいも3年目を 迎えます。今年中に、勝訴で決着することをめざし、ネットワークをはじめ、 全国の支援者と一体となり、あらゆる取り組みを行います。
さらに、「21世紀を核のない世紀」にする取り組みと連帯し、昨年と同様 に国内外の組織と力を合わせ行動します。
Ą.最高裁判所への取り組み €さらに多くの個人・団体への働きかけを強め、最高裁への厚生省の上告棄 却を求める署名運動を推進します。そして、1日も早く個人署名100万、 団体署名2万の目標を達成するために全力を上げます。
署名運動とともに、具体的な被爆の実相と被爆者の願い、国民の思いを裁 判官に届ける「手紙(上申書)運動」をくり広げます。
¡最高裁への要請行動(最高裁職員へのよびかけ、調査官・書記官への要請、 署名・上申書の提出)を成功させます。
˘.支援運動の強化 役員会を定例化し、裁判勝利をめざすあらゆる取り組みを、全会員および支 援者に提起し生き生きとした活動を展開します。役員会の提起を実行するため に、事務局体制を強化し、実務に精通し、運動にたいしても提起・実践・点検 を確実に行います。
€会員1万人を超える「支援する会」をめざして、会員拡大に努めます。ま た、加入された会員との連携をいっそう強め、署名・会費納入などの協力 をお願いします。
『にゅうす』の定期発行(年4回)に努めるほか、情報・宣伝活動を重視 し、運動推進のため「団体会員ニュース」を拡充し広く配付します。
¡運動の節目を設定し、全会員の知恵を結集した行動を工夫し、全国各地で 行動決起集会・学習会・講演会・宣伝行動などに取り組みます。
¤各地の個人・団体会員は、相互に連携し都道府県単位に「支援センター」 づくりをすすめます。「支援センター」は、支援する会との連携のもとに その地域での集会・行動を実施、会員の拡大、署名運動の推進など裁判支 援の運動に取り組みます。
¦長崎地裁・福岡高裁判決、上告理由反論書、さらには京都地裁判決などに ついて学習し普及に努めます。
©松谷裁判ネットワークとの連携を密にします。
ª国際連帯、国際的規模での支援運動を展開します。
«地元長崎県内での署名運動を強化します。
大阪高裁、東京地裁、札幌地裁などでたたかわれている「原爆裁判」と連 携を強めます。 Ł.弁護団との連携など 弁護団との連携を一層密にし、支援運動の前進をはかります。特に、原告・ 弁護団・支援する会の三者が一体となった運動をめざします。
Ľ.財政基盤の充実 会費の納入を促進するための事務局の働きかけを強めます。また、恒常的な 募金活動を推進し、財政基盤の充実に努めます。
![]() 1999年度決算及び2000年度予算
1999年度決算及び2000年度予算![]()
1999.1.1〜1999.12.31
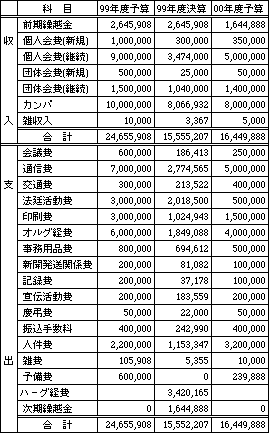
事業会計報告