<CD - Baroque #09>
「管弦楽組曲」
| ライプツィヒの聖トーマス教会にいた後期の作品の中から管弦楽曲を紹介したいと思います。管弦楽組曲はフランス様式の音楽の一つの典型のようですが、フランス風序曲がが冒頭に来ていくつかの舞曲から構成される作品です。全体としては1時間半以上にも及ぶ大作です。でも実際には作曲時期も作曲意図も違う曲を組み合わせた組曲になっています。中の曲単体やその中の楽章単位でも演奏されることがあるので、皆さんもどこかで聴いたことがあるかもしれません。一番有名なのは第3番の第2楽章の「アリア」でしょう。「G線上のアリア」としても有名な曲です。でも、全部を一度に聴くとさすがに疲れる。曲単位で休み休み聴くのがいいかもしれませんね。でも、一度に一気に聴いてしまわないとなんとなく途中で終わってしまっていつも最後まで行かないなんてことがありますけどね。 by Masa |
| J.S, Bach: Orchestral Suites Comment::まずここで紹介するどれをとってもそれぞれにいい面があって、なかなかの名演奏だと思います。曲自体が華麗な感じですので、明るい感じの演奏がいいですね。 以前はパイヤールが一番だと、喰わず嫌いで他の演奏を聴いていなかったのですがどれもなかなかのお気に入りの一つになりそうです。やっぱり試さずに思い込んではいけないですね。 |
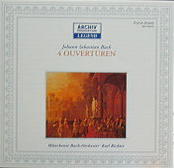 |
Karl Richter& Munchener-Bach orchester 1960-1961年録音 |
リヒター指揮ミュンヘン・バッハの演奏もなかなか素晴らしいです。荘厳さや重厚さではこれですね。「アリア」は個人的にはこの演奏が一番好きです。これもリヒターの出世作と言われているようです。 |
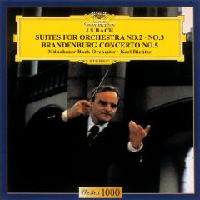 |
Karl Richter& Munchener-Bach orchester |
|
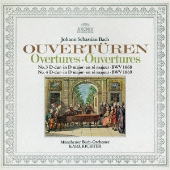 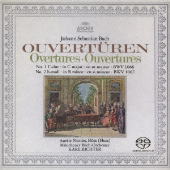 |
Karl Richter& Munchener-Bach orchester |
シングル・レイヤーのSACD盤です。 録音は上のアルヒーフ盤と同じかと・・・。 |
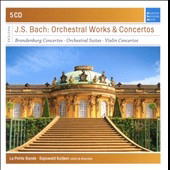 |
指揮:SigiswaldKuijken アンサンブル:LaPetite Bande |
Orchestral Works and Concertosの5枚組セットですが、この中に含まれた「「管弦楽組曲」では、通常より大きい編成(オーボエは4人)をとっており、他の古楽器演奏にはない厚めな音を再現。 |
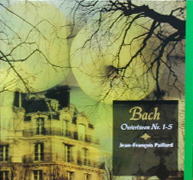 |
Jean-Francois PaillardOrchestra 1962年録音 |
昔から好きでLPでも持っていたのは、パイヤールの演奏です。曲自体がフランス風の曲ですし、軽やかさがあって舞曲らしさがでているし、フランスの香りが漂う演奏が合うのかも。 とにかくパイヤールを一躍有名にした曲でもあり、とっても馴染みやすい演奏だと思います。誰にでもお薦めできる演奏だと思います。この盤、ちょっと変わっているのは組曲が5曲構成になっているところです。但し、第5番は「偽作」と表示があります。これは、以前はこの組曲5曲構成と言われていたのですが、第5番が偽作だと言われるようになって、通常は第5番を除くようになったらしいです。そういえば、LPでは4曲だった気がするな。 |
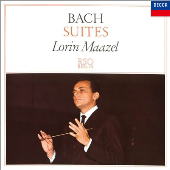 |
ローリン・マゼール指揮 ベルリン放送交響楽団 |
|
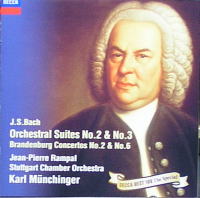 |
KarlMunhinger & StuttgartChamber Orchestra |
|
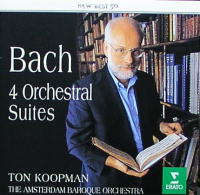 |
TomKoopman & TheAmsterdam BaroqueOrvhestra |
|
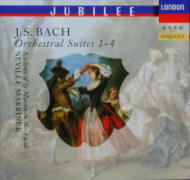 |
NevilleMarriner & Academy of St. Martin-in-the-Fields 1970年録音 |
マリナー指揮、アカデミーの演奏は通常テンポが速くどんな演奏でも、ちょっと演奏が雑に感じてしまいます。でもここではそのテンポが舞曲にあっているのか、逆に好印象があります。ゆったりしたテンポが合う「アリア」等の曲ではちょっと荒さがでてしまう気がします。でも決して悪い演奏ではないのです。他のものと比べないでこれだけ聴いていれば、そんなに大きな不満はないかもしれません。 |