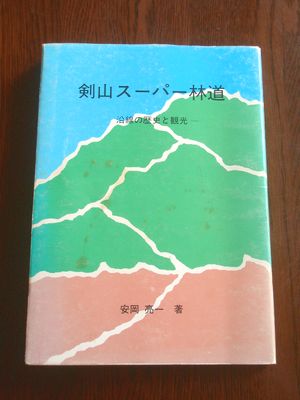剣山スーパー林道(2009年5月6日記) |
|||||||
先日、5年ぶりに那賀川で渓流釣りを楽しみましたが、釣り場選びのために地図を見ていると、やたらと見覚えのある地名が出てくるので、この本を思い出し、久しぶりに読み返してみました。 私は昔話や民話などの民俗本や民俗小説が大好きです。若い頃、柳田國男の「遠野物語」を読んでワクワクしました。笹山久三の「四万十川」では山村生活や子供達の遊びの情景がありありと浮かんで、自分が経験してないにもかかわらず何か懐かしい気持ちになりました。ネットでも私が釣りによく訪れる地域の昔話・伝説などを探しては読んでいます。 私には現代社会の便利さや快適さがどうも性に合わず、自然と共存して苦労しながら生きる昔の山里人の姿に共感や憧憬の念を覚えます。この気持ちの表れが、渓流釣りなのでしょうね。 さて、本書から面白い記事を紹介します。ただし、剣山スーパー林道自体の紹介よりも、周辺地域の自然や伝承の話が主になることをお断りしておきます。10年以上前の私の剣山スーパー林道ドライブのスキャニング写真と共にお楽しみください。
もちろん、平家伝説もありますが、日本各地の伝承と重複しますのでここでは割愛します。 昔話や民話といっても、平家伝説など大昔のものは創作や脚色が多くロマンの域を出ませんが、明治以降のものはある程度想像できますし信憑性も高いので、意外と面白いものです。そのなかから3点。
次に、前述した焼山(神山町の焼山寺ではない)では終戦後バクチ場があったらしいということです。「神戸から来た男に焼山のことを聞かれた」とか、「焼山では何かが行われているに違いない」とかいう噂があったようです。著者も一度訪れたようですが、とてつもない山奥でヘトヘトに疲れたと書いてあります。 さらに興味深いのは、その焼山で殺人事件があったことです。昭和19年頃、「焼山の山小屋にいた武岡がおらん。」という噂が広がりました。ちょうどその頃、木屋平村の武岡氏の甥のところへ「宮崎県に出稼ぎに来ているから心配しないように」というハガキが届きました。ところが、甥は「武岡は他県へ出た経験は一度もない。無断で九州まで行くのは妙だ。」と、脇町警察署へ届け出ました。鷲敷署員が猟師の案内で焼山付近を捜索したところ、槍戸川で白骨の一部を発見しました。その後、宮崎県に潜伏していた香川県出身の善生豊という男が捕まり、武岡になりすましていたことを白状しました。善生は前科三犯で、金に困り徳島県の金のありそうな家を物色していたところ、奥山で一人暮らしをしている武岡氏の噂を聞きつけて、山小屋に押し掛け、猟銃で射殺し、現金数十円と三百数十円の貯金通帳と印鑑を盗んで宮崎県へとび、山小屋に潜伏しているところを逮捕されたのです。甥にハガキを出したり、宮崎県にいることをほのめかしたりして、稚拙な犯行の感は否めません。あまり頭の良い男ではなかったのでしょう。
スーパー林道開通記念に書かれた本書は、当林道が引き起こすであろう弊害に関する記述はさすがに書いてありませんが、新聞記者の著者らしく、ダムや発電用の取水堰に関しての批評は随所に見られます。旧木沢・木頭村はかつて桃源郷と呼ぶにふさわしい山村でしたが、那賀川の長安口ダム建設に始まる開発により往年の雰囲気が失われたことを嘆いています。特に、発電のために多くの支流・小谷にダムや取水堰を作りトンネルを通してはるか離れた発電所に集めるため、ダムや取水堰下流のかつての名滝・千本滝や新居田の滝などは水量が減ってしまい見る影もなくなったということです。また、長安口ダムの少し下流の小浜大橋の下では、かつて上流からバラ流しされてきた木材をここの大岩で止めて筏に組んで流していたそうです。昭和30年までは那賀川の一大風物詩と言われていた筏流しも、長安口ダムができたせいでいまでは知る人も少なくなったということです。 このように、奥深い山村でも不便で貧しい生活の中にさまざまなドラマがあったに違いありません。しかし、必死に生きているからこそ、家族の絆も強く、コミュニティーの結束も固く、人々が助け合い、思いやりがあったに違いありません。快適で便利な現代社会で失われた、自然・風俗・人々のつながりに思いをはせるのは単なる私の懐古趣味なのでしょうか。 |
|||||||
| (出典:「剣山スーパー林道~沿線の歴史と観光~」安岡亮一著) |