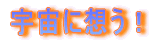
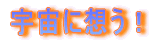
◇転生を知ると何が変わる。しかし・・・
転生については、何度か書いてきましたが、ここで改めて考えてみたいと思います。
転生が真実であると人類が知ると、何が変わるのでしょうか?
良い点としては、死別した人への寂しさが軽減する。
死期が近づいた人でも希望が持てる。
かつての知人と転生先で再会できる。
死期が近づいても生に執着しないことから、転生がスムーズに行われる。
などが考えられます。
悪い点としては、生の軽視につながりかねないということでしょうか。
しかし、この悪い点というのは、転生を正しく理解していないことから起こることであると思われます。
これをなくすためには、転生の法則の意味について誰もが理解できるよう整理しておく必要があります。
また、良い点に書いてある〝生に執着しない〟については、悪い点になる可能性があるわけですが、やはりこれも正しい理解がなくてはなりません。
人は生まれ、様々な役割を果たし死を迎えます。
その期間の長い人もいれば、短い人もいるわけですが必ず死を迎えます。
しかし、それで終わらないというのが宇宙の法則なのです。
死というのは、あくまで肉体という物理的な死です。
肉体(心)と合体している人間の魂は、意識体であり死ぬことはありません。
宇宙の意識の分与であるのが人間の魂ですから、記憶がリセットされることがあっっても死なないのです。
その理由は、どこにあるのか?
宇宙の意識が生み出した宇宙という物理的な世界の中で、その手足となって、意識のイメージの実現へ向けて奉仕をし続けるためなのです。
これは、光栄でありかつ大変楽しい事なのです。
このように解釈しなければ、人が転生することが祝福であると理解し、その良さを生かすことはできないでしょう。
転生を認められるようになると、それぞれ過去世を想いだす人も出て来るでしょう。
その際、良き事ばかりでないことから、拒絶するような人も出てきます。
ここもやはり、正しい理解ということが必要になってきます。
過去が立派であっても厄介ものであっても、それを正当に受け入れ、その結果が今日にあることを理解しなくてはなりません。
そして、その先に未来の自分はいるのです。
こうしたことを考えると、地球人が転生を認める社会は、少し先の時代であるように感じます。
地球人はまず、いろはのいである、宇宙に摂理があることを理解し、自分の社会へ生かす考え方ができなくてはならないのだと思います。
こうしたことができるようになった先に、転生を認められる社会が誕生してくるのかもしれません。
転生が認められると、先述のようなものが認められ社会は大きく変わると思われますが、やや時間はかかるもののいずれそのような社会が来ることは必然で
あると思っています。
2025.2.9(日) K・W
◇「PB規律」なぜ、そうなった?
PB(プライマリーバランス)規律とは、社会保障や公共事業をはじめ様々な行政サービスを提供するための経費(歳出)を、税収等(歳入)でまかなえるかどう
かを示す指標のことで、単年度において、歳出が歳入を超えてはいけないという考え方です。
これを大蔵省時代から今日の財務省に至るまで、なぜ厳格に守ろうとするのか?
歳入が足らなければ国債を発行すればよいと考える人もいますが、国の借金(地方を含め)が1,200兆円(現1,400兆)でその86%は国債であるから、そ
れはできないと言われ続けています。
これに対して、国債の発行は問題がないという人々もいます。
それによると、財政の穴埋めに発行した国債を日銀が買えば、その時点で事実上政府の借金は消えるという。
例えば元本を10年ごとに日銀に借り換えてもらい、永久に所有し続けるということです。
すると政府の返済の必要がなくなるという。
発生する利息は、政府が日銀へ支払うが、全額国庫納付金として戻ってくるという。
但し、市場との関係で限度はあるということですが、まだまだ余裕があるようです。
詳細はわかりませんが、これらのことが成立するということです。
これが可能なら、歳出見込みが増えようと、しばらくは消費税やその他の税を上げなくても国の歳入歳出は安定するとみられます。
これについては、先日亡くなられた森永卓郎獨協大学教授が主張していたことですが、高橋洋一数量政策学者なども国債発行は問題ないと主張しているよう
です。
それにしてもなぜ、財務省は厳格にPBを主張し続けるのか?
直ぐに増税議論となって、国民のためにならないその主張はどこからくるのか?
もちろん、法に基づいているというものの改正されないことが不思議に思っていました。
ところが、藤井聡京都大学大学院教授が、「致知」2月号に次のように書いていました。
「国債の発行を禁止している国家は日本以外にほとんど存在しません。なぜこうした理不尽な規律を取り下げられないのか。それは、先の大戦で日本が敗戦
しGHQの支配下に置かれた時に作られた財政法の第四条に、国債の発行を禁止する条文が入っているからです。」
そしてその理由について、「・・・再び戦争を始めてしまうことを防ぐために導入された・・・」と、国会での答弁を引用しています。
しかし、建設国債の発行だけは認められ、戦後の高度経済成長を果たせたということです。
そして、この建設国債の発行も禁止の対象としようというのが、「PB規律」で財政法第四条よりさらに厳しい規律を小泉内閣が導入し、それが現在も日本を縛
り続けているという。
つまり、戦後GHQにより作られた財政法第四条が元凶であり、小泉政権下でもおそらく何らかの圧力があったのかPB規律が成立しているようです。
すべてに理由があるわけですが、他国を攻め込む意思のまったくない日本は、法の趣旨に対応しないわけですから経済発展の足かせとなる古い法令等は、
速やかに改正された方が良いのではないでしょうか。
2025.2.20(木) K・W