機関紙v18です。
ボランティア家族連絡会・帰国報告会
3月6日(日)午前中ボランティア家族連絡会を開催し、6家族10名の参加がありました。午後は帰国報告会を開催し、帰国報告は宮下武さん、雨宮律子さん、後藤美和子さん、曽根亨一さん、大野紀子さんの5名が行いました。会場は今までにない大勢(50名以上)の人が集まり大好評でした。
平成16年度定期総会開催
4月17日(日)午後5時から、平成16年度の定期総会を開催しました。詳細は別添の定期総会報告書を見て下さい。(総会に参加した人には報告書は入っていません。)
平成17年度JICAボランティア春募集説明会
JICAボランティア春募集説明会を行いました。隊員の活動ビデオ、JICA事業説明、体験談(帰国隊員)の後、OB、OGの協力により、分野別説明会を行いました。
大勢の方の協力を得て参加者の満足のいく個別相談ができたと思います。また、今回の説明会からJICAfe(ジャイカフェ)がスタートし、ブラジルコーヒー、ウーロン茶、チャイ、スリランカ紅茶他各国のお菓子を用意しリラックスした雰囲気で個別相談ができました。春の応募の結果は、シニア海外ボランティアは0名、青年海外協力隊は15名でした。
OB、OGのみなさんどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
① 4月17日(日)10:00~11:30 シニア海外ボランティア説明会
参加者 10名
② 4月17日(日)14:00~16:00 青年海外協力隊説明会
参加者 9名
③ 5月12日(木)18:30~20:30 青年海外協力隊説明会
参加者 13名
(国際協力推進員 雨宮)
フェア・トレードデー参加
5月14日(土)11:00~14:00国際交流センターで、国際フェア・トレードデー「世界の食とファッション フェア・トレードってなに?」が開催されました。
「主催:コープやまなし、(財)山梨県国際交流協会、やまなしインターナショナルネットワーク(YIN)」
国際協力団体ブースでは、JICAも参加しました。JICAブースは、机を3つ用意し一つは曽根さん(ブルキナファソ14-2ソーシャルワーカー)に依頼して、任国の民芸品、布、洋服等を展示、販売してもらいました。
今回は、JICAブースはOB会にお願いしてさまざまな国の紹介をするよりも一つの国の物を大量にそろえている方に個人的にお願いしました。展示品は珍しいもの、可愛いものがたくさんありすべて目を引くものばかりだったので、皆足を止めて曽根さんに物品の質問をしたり、国の様子を聞いたりしていました。また、ファッションショーでは、ブルキナファソの民族衣装を着た曽根さんが飛び入り参加をして場を沸かせていました。
もう一つは、JICAボランティアの募集期間でありますので、募集要項やパネルを貼り、海外ボランティアの質問、紹介コーナーを設けました。数名募集要項を持っていく方、話しを聞きに来た方もいました。JICA事業の広報、協力隊OBの活動内容や国の様子を熱心に質問される方が訪れ大盛況でした。もう一つの机では、ピース・ハートプロジェクト用に用意しました。パネルの色が鮮やかなので目を引き子ども連れは、家族で参加してくれたりグループで参加してくれたりしました。子どもには、絵を描いて参加してもらいました。新しいカードは、シールを貼った後でポストカードとしても使用することができるのでゴミも出ずに持ち帰ることができるので好評でした。 (国際協力推進員 雨宮)

説明する曽根さん

平成17年度第1回JOCA評議員会・総会に参加
5月28・29日、(社)青年海外協力協会(JOCA)の評議員会・総会が虎ノ門パストラルで行われ、出席してきました(JOCA とは、OB会の全国組織と言えるものです)。いずれも重要な案件がなかったため、議事はスムーズに進行し、終了しました。
なお、協力隊40周年記念事業が、10月29日(土)14時から、NHKホールで開催されることになりました。後日、JICAから全OVにご案内が送付されるとのことです。(野崎)
平成17年度山梨県研修生歓迎会
去る6月17日金曜日交流センターの3階に於いて平成17年度の研修生の歓迎会が行なわれました。今年は研修生みずから料理を作り朝から歓迎会を準備してくれました。
当会からはお寿司が提供され、あちこちからの差し入れのお酒もたっぷり有ったので日付が変わるまで楽しい時間を過ごしました。今回の研修生は8名と少ないせいか皆仲良くまとまっております。私も週末時間が有る時にはいつも顔を出しています。皆さんも時間が有りましたら遊びに行って見て下さい。 (高石)
研修生歓迎さくらんぼ狩り
6月19日(日)午後2時より、今年も研修生歓迎さくらんぼ狩りを中込農園で行いました。研修生の方には全員参加していただけました。さくらんぼ狩りのピークは過ぎていましたが、「サトウニシキ」は昨年に比べとても甘く、楽しんでいただけたと思います。
OB、OG、知人も大勢参加し研修生との良い交流ができました。
帰国報告
ブルキナ・ファソにおける活動
曽根亨一(14-2 ブルキナ・ファソ ソーシャルワーカー)
私は、2002年12月から2004年12月までの約2年間を派遣国ブルキナ・ファソで職種ソーシャルワーカーとして路上で生活する青少年達(ストリートチルドレン)の対策支援に従事してきました。その活動報告を簡単に述べたいと思います。
ブルキナ・ファソの子ども達。
悩みや問題、障害を抱えていても抱えていなくても子ども(ストリートチルドレン)は子ども。みんな同じ!
でも、私の所属していた施設には、何故か大人まで出入りしている!?
子ども達は、音楽が聞こえるとすぐに踊りだす程、歌と踊りが大好き!
三度の飯よりサッカーが好き!?ただ、御飯を食べるだけのお金がないだけ・・・。
だから、疲れている時や空腹の時は、ひたすら寝る。
物乞いや盗み、タバコ・シンナーもやるけれど、働く時は働く。
挨拶は欠かさない。
私が市内を歩いているだけで、すぐ声を掛けてきてまるで仲間のような勢いである。
私は、そんないい加減だけど素直で優しい彼らが好きである!!
(大好きとはつけない。なぜなら、小憎らしいこともするからだ!)
ブルキナ・ファソは、西アフリカに位置し、ニジェールやマリ、コートジボアール、ガーナ、トーゴ、ベナンの6カ国に囲まれた内陸国です。現地言語のモレ語で「清廉潔白」を意味する「Burkina」とディウラ語で「土地」を意味する「Faso」を合わせた国名です。人々は、とても穏やかで、奥ゆかしい国民性です。自らをブルキナベと呼び、自国に対しての誇りを持って生活しています。
その一方で、一人当たりのGNP(国民総生産)は、240ドルと言われ、世界最貧国の一つに挙げられています。
ブルキナ・ファソの青少年達の抱えている問題も、貧困から生じる生活困窮や家庭不和、里親関係の不和、教育の不均衡などが考えられます。そのような中で、様々な問題を抱えた少年や少女が村から出てきています。国そのものが発展途上の段階であり、被援助国であることから生活に困窮している人々が多く存在し、貧困対策としての生活改善が当面の課題であると言えます。
私は、このような社会状況の中で、以下のような活動を実施してきました。
①配属施設内の環境整備(施設内の清掃や修繕、廃品・廃材の再利用)
②衛生および識字教育(手洗いの習慣、アルファベットの読み書き)
③職業/作業訓練内容の考案、実施(木工や絵画教室、ポストカード作り)
④工芸品、木工品の展示販売の促進
⑤市内巡回および青少年の所在把握(青少年達との接触、窃盗・麻薬等犯罪防止の注意
喚起)
特に、私が中心的活動に当たったのは、絵を描く機会を失った青少年達に絵画に取組む機会を設けたことと、オリジナルポストカード作りのための資金をカナダの支援団体から配属先の上司とともに獲得し、作業訓練の再開を果たしたことの2点です。
これらによって、要請内容にあった路上で生活する青少年達に対して、施設での活動に参加する機会を作ることができたと言えます。しかし、2年間という期間限定の中では継続した活動へと発展させることが出来なかったのもまた事実です。
協力隊活動は、これからもこの分野における課題が残っていると言えます。今後もソーシャルワークの更なる活動に期待するとともに、私自身も日本および世界のソーシャルワークに当たっていきたいと思っている次第です。
ブルキナファソでの活動報告
後藤美和子(14-2 ブルキナファソ 看護師)
私は、看護師として西アフリカの内陸国、ブルキナファソに2年間派遣されました。仕事内容は、住民約1万人を対象とした診療所で、現地人看護師たちと、患者の診療・治療、助産業務、村々を周っての乳児予防接種、保健教育を行っていました。
最も多い疾病は、マラリアです。放っておくと死に至る場合があります。遠いと、片道15Kmも歩いて患者を連れてこなくてはなりません。また、村人は貧しく、治療費が払えない人がほとんどなので、伝統治療に頼り、手遅れになってから診療所に受診する人がたくさんいました。小さな傷にしても、清潔が保てず、すぐに化膿してしまい、大きな潰瘍になってから来る人も多かったです。分娩も、お母さんが力むことができず、死産となってしまう場面も何度も見ました。
住民に疾病予防の知識を与えることを目標としてきましたが、昔からの習慣や教えが根強く、理解できるようになるまでの難しさをつくづく感じました。
人々は、気候のせいか、とても明るく、問題があっても重要視せず前向きに生活しています。なので、仕事の進みはおそく、問題解決には時間がかかります。いつも笑って、「どうにかなるよ」と返事をされ、悔しくもあり、その楽天さがうらやましくもありました。
「この国は、どうしたら君たちのようなお金持ちの国になれるんだ。僕は次に生まれる時には、この国はいやだ。」と言った同僚の言葉が忘れられません。「私は、日本よりもこの国のほうが好きだよ。」と答えました。海外旅行もできず、外国の話を聞く事しかできない彼らは、毎晩見る星いっぱいの夜空や、澄んだ空気、美味しい鶏肉、などを素晴しい持ち物だと思わなくなっているのでしょう。
水を大きなたらいで頭に載せて運ぶ事ができなかった自分、炎天下で畑仕事ができない自分、自然の知恵を全く知らない自分、夜に懐中電灯なしで歩けない自分、たくさんの事が日本人の私にはできないことを知り、くやしかったです。
彼らは、強くて素敵でした。
彼らが今後、発展してほしいような、このまま変わらずにいてほしいような、複雑な気持ちです。
たくさんのことを感じ、学んだ2年間でした。これから私がブルキナファソのために何ができるか考えているところです。
隊員活動報告書 安達三枝(15-3 スリランカ 体育)
インド洋に浮かぶ島国スリランカ。小さな国土のも関わらず多様な気候、民族、豊かな自然、資源に恵まれた美しい国。ちょうどインド亜大陸が一粒の涙をこぼしたようと言われている。スリランカとは「光り輝く島」と言う意味人々は誇りを持ってこの国名を口にする。
私は、青年海外協力隊としてスリランカへ平成15年4月~17年4月の2年間「高齢者の余暇活動の一環として体操を取り入れ精神的にも身体的にも健康で充実した生活を送る手助けをする。」という目的で活動してきました。主に老人ホーム・デイケアセンターの巡回を行い 高齢にレクリエーション・簡単な体操を指導してきました。機会があれば、施設のスタッフへの体操指導も行い余暇活動の推進に努めました。
高齢者になって体操・レクリエーション(この言葉さえ知らない)をすると思ってもいない人たちの中活動を始めていくことは、とても困難でした。毎日毎日施設を回り「体操をしようよ!一緒に遊ぼうよ!」と誘っても、「今日は、具合が悪い・腰が痛い・頭が痛い・外人が何か言っている?物でもくれるのか?」こんな答えを聞く毎日を送りました。受け入れてもらうのには、時間かかる!分かっていても自分を責め、皆が参加しないのには、自分のしている事がつまらないから興味があることをすれば少しでもやろう!という気持ちになる。自分の力不足、自分は必要とされていない。と落ち込む事もありました。高齢になっても健康でいよう!と誰でもわかること、それを実行する事は、難しい。できる人だけがすればいいと気持ちを切り替える事ができて、肩の力抜け活動が苦にならなくなりました。気長の活動が少しずつ受け入れてくれる施設も増え、おばあちゃん・おじいちゃんから、「楽しかったよ!今度はいつ来るの」という言葉と笑顔が私の活動の支えになりました。

ある時、お年寄りと薬の話をしていると血圧の薬を飲んでいる人が多いという話題になった。一般的に、高齢になると血圧が高くなりやすく血圧を下げる薬を飲んでいる。血圧の値はどれくらいあるの?深い意味は無く問いかけた 「知らない!ただ高い」と何でも無いように答える高齢者達に絶句した。そこで健康にも関心を持ってもらい、体操・レクリエーションの推進に繋がるのでは無いか?と考え血圧測定と簡単な血圧の説明を始めることにしました。案の定血圧を測ったことも無い人や、血圧の意味・標準値も知らない人ばかりでした。これをきっかけに少しでも健康に関心を持ち、レクリエーションへの参加が増えることを期待したがそこまでは結びつくのには、時間がかかるようで血圧の値が良かったらそれでいい!というだけで予防していこう 健康を維持していこう とは考えてはいないようでした。しかし、少しでも健康に関心を持つきっかけになったのなら、この活動にも意味があったと思います。
私の2年間の活動は大きな成果はありませんでしたが、異文化の中色々な問題とぶつかりながら活動してきたことにはとても私の財産になりました。
3年ぶりのスリランカ
野崎進(3-3 スリランカ 考古学)
2度目のスマトラ沖地震が起こった3月28日、私はスリランカのコロンボにいた。
その日、来スの目的であるスリランカ人の結婚式を終え、隊員らと夕食を済ませ、後輩のシニア隊員の家に戻ったのが夜の10時過ぎだったと思う。地震発生後約1時間たった11時過ぎ、シニア隊員の携帯に地震の第一報が入った。しばらくして、全隊員に地震の情報が流れ、南部に海岸近くに宿泊していた一般短期の隊員は内陸部の寺院に避難したらしいと情報が入った。それからは大変だった。果たして津波は来るのか。ネットの情報では、M8.2という情報しか入らない。BBCのニュースが一番早く報じ、その後ローカルの放送局が報道し始めたが、津波の情報はまったくなかった。シニア隊員が南部の隊員に連絡するが、携帯は通じないし、ネットからも新たな情報を得られなかった。日本へ無事のメールを書いたものの、サーバーの状態が悪いのか、送信されない。私はあきらめて、3時半ごろには眠り、翌朝かつての任地へ出発したため、M8.7で25cm程度の津波がきたという情報を得たのは、その日の夜ホテルで一緒に食事をした隊員からであった。
昨年12月26日に起こった津波の映像は、繰り返し報道された。市街地が川のように流された箇所は、きれいに修理がなされ、その面影はまったく感じられなかった。一方で脱線し流された列車は、一時は写真撮影のポイントだったようだが、今は3両だけが残っていた。コロンボから南部へ向かう幹線道路は、日本の企業によりいち早く後片付けがなされたが、道路の西側に広がる海岸線近くにあった建物は、すべてが流されているわけではなかった。流されたところでは床だけが残っており、その上にテントが建てられていたが、私が訪れた頃は1年のうち最も暑い季節であるため、日中はテント内にいるのには辛いものがあった。また、雨季の走りのため雨が降り始めて、あちこちで木造の仮設住宅の建設ラッシュだった。仮設テントはあくまでも仮設で、豪雨には耐えられないという。また、テントの周囲に溝を掘っていないため、中が泥だらけのテントも見かけられた。
観光地のヒッカドゥワでも復旧が進んでいた。11年前友人の結婚式が行われたダイビングショップも被害を受け、改修工事が行われていたが、隣のホテルは保険の関係で修理のめどが立っていないという。12月にオープンしたばかりの店の親父は、2m近くの水が来たと言っていたが、幸いにも新しかったため建物そのものは無事だったが、店の中は無茶苦茶になったという。
約3年ぶりのスリランカ。コロンボには車や目新しい店が溢れていた。洒落た喫茶店やベルギーワッフル屋さえもあり、隔世の感を覚えた。その一方で、被災地では避難キャンプに暮らす人々がいる。そのキャンプも2年で閉鎖されると聞いた。仕事が無くて将来が不安だと訴える人々。同期が働いていた障害者施設では、多くの重度の入所者が犠牲になったことにより、手厚い援助の手が差し伸べられ、復興景気に湧いているように感じられた。隊員の有志や一般短期隊員は、被災者支援の活動に携わってきた。今後も一般短期が派遣されるようだが、スリランカ政府の動きは明快ではない。スリランカ政府が、タミル人との政争の道具にする限り、被災者は等閑にされてしまう。
行ってらっしゃい 平成16年度3次隊
3月28日に山梨県庁で、シニア海外ボランティア小澤輝芳さん(パラグアイ・野球)と青年海外協力隊内藤和歌子さん(エチオピア・料理)の2人が、表敬訪問を行いました。
それぞれの任国の事情等を話し、2年間の活動への決意を新たにしていました。
また、2004年12月に帰国した、14-2 曽根亨一さん(ブルキナファソ・ソーシャルワーカー)14-2 大野紀子さん(中国・看護師)の紹介、挨拶、帰国報告も行うことができました。現職教員特別参加制度で派遣された、15-1黒澤宏至さん(ベトナム・小学校教諭 )も表敬訪問参加予定でしたが、帰国オリエーテンション中の為、不参加になりました。
今回は、JICA八王子からも職員が出席し今後の山梨県におけるボランティア間の連携についても説明がされました。
その日の夜は、ネットカフェ「SHOW 人」に於いて、育てる会と合同で壮行会が行われました。
青年海外協力隊
内藤 和歌子さん( 南アルプス市 エチオピア 料理 )
シニア海外ボランティア
小澤 輝芳さん ( 北杜市 パラグアイ 野球 )

左より内藤さん、小澤さん
今後の日程
月 日 事 項 場 所
7月23・24日(土日) 国際協力体験キャンプ 県立八ヶ岳少年自然の家
8月4日(木) 国際理解・開発講座(教員向け) 県立国際交流センター大会議室
9月4日(日)午前 帰国隊員研修会 県立国際交流センター大会議室
9月4日(日)午後 国際理解教育研究会 県立国際交流センター大会議室
10月上旬 海外研修員交歓会 ボーリング大会
11月12・13日(土日) 県民の日 小瀬スポーツ公園
お帰りなさい
青年海外協力隊
安達 三枝( 市川大門町 14-3 スリランカ 体育 )
黒澤 宏至( 笛吹市 15-1 ベトナム 小学校教諭 )
シニアボランティア
中嶋 俊 ( 北杜市 チュニジア 家具 )
推進員挨拶
皆さんこんにちは、雨宮律子です。4月から山梨県国際協力推進員として働いています。青年海外協力隊隊員として約2年間パラグアイで活動をして去年の5月に日本に帰ってきました。
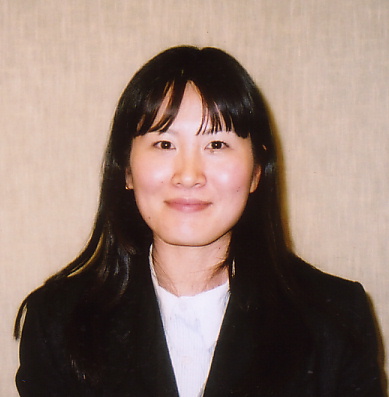
推進員って何だろう?という疑問に今回はお答えしたいと思います。そして、もう一度自分で推進員について確認したいと思います。国際協力推進員は、国際協力機構(JICA・ジャイカ)と自治体や地域のNGO・NPOとの連携を推進するパイプ役として全国の地域国際交流協会に配置されており、山梨県国際交流協会では平成15年5月から活動を開始しました。主に、青年海外協力隊や国際理解教育支援など、JICA事業に関する情報をみなさんにお送りするのが仕事です。海外でボランティアをしてみたい。JICAって何をやっているのか知りたい。海外ボランティアの話を聞きたい、県内で国際協力に関する活動をしたい。などを希望する方は、どうぞお気軽にご連絡ください。
国際協力に対する想い、考え、いろいろなアイデアを活かして、山梨県というフィールドで積極的に活動していきたいと思います。皆さんどうかよろしくお願いします。
連絡先
〒400-0035 甲府市飯田2-2-3(財)山梨県国際交流協会内
電話 055-228-5419 FAX 055-228-5473
E-mail : jicadpd-desk-yamanashiken@jica.go.jp
JICA 国際協力推進員 雨宮 律子
編集後記
任国に派遣されていた時に、帰国する隊員からテレビ+ビデオ+CSチューナ一式が安く譲ってもらえるというので、国内旅行も兼ねて電車8時間、バス5時間を乗り継ぎ、テレビはパラボラアンテナと一緒に背中に背負って亀みたいな格好で引き取りに行ったことが懐かしく思います。地元山梨で働いていると東京でも遠く感じるようになってきました。
帰国隊員の報告を聞くと、自分が帰国した当時の初心に戻されます。 (石原)
先日、知人の画家の個展を、銀座の画廊に見に行ってきた。画伯と知り合って10数年になるが、その間画風の転機が2回あった。1回は大作から小品に変わり色使いが明るくなった時で、さらに昨年、抽象画から具象画に転換した時にはビックリした。画伯によれば、個展が終わると頭の中はリセットされ、書きたい作品はまた一からスタートするという。この考え方には、原稿を書き上げるまではリセットされない私と通ずるものがある。
一方、先日訪れたスリランカでは、10数年以上も隊員が派遣され続けている配属先があり、その後輩たちと先輩隊員の話をする機会があった。協力隊活動は個々の活動そのものは断片的かもしれないが、継続こそが力となり、任国に対する援助になっているのだと痛感した。その協力隊も今年で40周年を迎える。前述の画伯とも協力隊が縁で知り合い、その作品の1つを毎日眺めている。 n