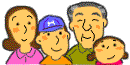
吾が父 多田健太郎
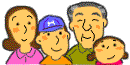
これは今を遡ること12年前にご恩のあるお方からの依頼により、とあるラジオ番組へ寄せた父への想いである。
昔、小学生だった私に父はドイツ語のサヨナラはアウフ・ヴィーダー・ゼーエンといって、「またお会いする日まで」という意味だと教えてくれました。
父は民間企業の研究者であり、職場を転々と変えてきたため、幼い頃から幾度もサヨナラの悲しみを味わってきた私に更にこう説明してくれました。「ドイツはキリスト教の国でドイツ語のサヨナラの意味は人は絶対に罪の中に死ぬ。でもキリストを信ずる者は救われて天国で生きることができる。死ぬ時のドイツ語のサヨナラは永遠の別れではなくて、天国でまた会うための挨拶なのだよ」当時、その意味はほとんどわかりませんでしたが、子供心にドイツ語のサヨナラには思いやりがこめられているな、という印象を持ったものです。
父は私に医学への道を勧めたのですが、私はどんどんドイツ語への想いが大きく膨らんでいきました。そんな私の気持ちを察してか、父はドイツ語を専門とする私立の中学校へ入ることを許してくれました。父はすぐにお金を生むお金だけが大事だという実利主義を嫌って、つましく暮らすことをモットーとしていまして、よく「人間本来無一物、ただ空なのだ。空とはむなしさではない。空とは無、即ち本来の姿、仏なのではないだろうか。だから片時もただむなしく無駄に生きてはならない。贅沢はするな。自己を磨き、世界に羽ばたき、世の中のお役にたたなくてはならない」と言っていました。
常に世界に通用する化学研究を心がけてきた父は1972年、60歳の誕生日を迎えたその年の人工皮膚の発明をいわゆるクリエーティブな研究の限界と感じたようです。その10年位前から少しずつ勉強していたイタリア語、ハングル語、スワヒリ語の学習や読書に一層の情熱を傾けるようになりました。
父は様々の外国語を学習することや書物との関わりをこんな風に語っていました。「人間の大脳皮質にはいつまでも生きようとする性質がある。語学、化学、禅やキリスト教そしていろんな教養の書は心の糧となるもので、私は与えられた生命の終わるまで勉強をし、本を読み続ける」
そんなある日、父は突然こう言ったのです。「社会に出てから化学研究一筋の道を辿って60歳を過ぎた。振り返ってみるに何一つ社会的な貢献もしていないことに気がついて、空虚な感じで胸がいっぱいになった。さて、この歳になって何をしたらよいのか。ふと医者である弟の『最近は解剖体が少なく、医学生の勉強・研究に支障がある』との言葉を思い出して、医学の発展を願って献体することにした。私も研究者として基礎科学知識の習得が先決であると考えるのと同じく、いかに薬学、治療医学が進歩しても人体組織構造を十分に把握していなければ医師の本領は発揮できないと思う。学生諸君は私を敬虔な気持で解剖し、その構造を熟知し、栄光ある医学者としての道を歩まれると思う。これが私の念願である」
そしてやがて70歳に手が届こうとする頃、父は東京から盛岡に移り住んでからも時を惜しむように沢山の本を読む傍ら化学書や研究論文を読みあさり、私たち息子一家とともにどうにかこうにかの生活をしていました。しかし、献体の準備もしたら静かに死を待つだけか、とどこか片づかない想いがあったようです。その時「マニラの貧しい家庭の子供達をせめて小学校だけでも卒業させてあげよう」という盛岡マニラ育英会の小さな記事が父の目にとまったのでした。父は一人の里子を持つことになりました。彼女からの手紙は英文とタガログ語であるため父は80歳になってタガログ語を勉強し始め、英文のなかにタガログ語を入れてなんとか文通していたようです。
その父が85歳の春、胃癌と診断されました。「先のない私はもうこれで終わることができるかと思うと、むしろ安心立命の心境だ。心静かに保ち、病にはどこまでも抵抗しながら献体の日までガンと共存していく積りである。治療に関しては全てお医者様にお任せするけれど、延命の為の治療は無用」と言い放った父は玄米、大豆製品、野菜、海藻食一辺倒に食生活を改め、その後は食事も進み87歳まで普通の生活を送ってきたのですが、ガンは静かに進行していました。暑い夏の日、大木が静かに倒れていくがごとく病の床に伏し、やがてきたいまわの際にその心境を「アーメン」とたどたどしいローマ字で綴り、息をひきとりました。