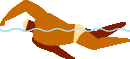
スキューバダイビング
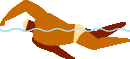
羽田からの出発は10数年ぶりである。息子は東京駅から羽田への道順を知らない。勝手を心得ている私がカミさんと息子を難なく羽田へと誘導した。羽田では旅行会社の社員が何人も看板を掲げて一同を待っていて、それぞれに航空券を手渡してくれた。沖縄で別の社員が待ち構えているとのことであった。仕事とはいえご苦労さまである。程なく搭乗手続きが始まって機内に乗り込む。何人か乗り遅れているとのことで10分ほど離陸を見合わせた。いざ飛び立って飛行機は雲の上をふわふわと南下した。沖縄にはバスが出迎えていた。私たちのバスは8号車だ。すべて息子が勤務する会社の負担ということだが、全部で10台のバスというのだから相当の社員と家族を招待することになる。聞けば全国から600人ほどが招待されているという。ならば沖縄や九州の社員はどうなるのかと要らぬ心配をしたが、そちらは北海道への慰安旅行とのことである。ホテルで部屋に落ち着いて夕餉の時間まで暫く時間がある。東シナ海が臨める展望風呂がるというので3人で風呂を浴びることにした。通路にいる従業員に風呂には手ぬぐいはあるかと聞いたが、入ったことがないので分からぬと言う。行ってみると手ぬぐいとバスタオルを渡され、驚いたことに一人600円取られた。用意された宴会場にはすでに多くの人たちが席についていた。端には幼子のための滑り台なども用意されていて、ここにも紺色のスーツを着込んだ旅行社の社員が何人か待機していている。至れり尽くせりである。沖縄らしくアメリカ風のシャンペングラスの底に微かに溜まっている泡盛による乾杯で宴が始まった。テーブルにはあれこれお料理が運ばれてくるもののこれが一流ホテルの料理かと首を傾げるものばかりである。そのお陰かオリオンビールが幾らでも飲める。このビールはいささか甘さがあるがその口当たりが心地よい。お料理はそれぞれ一口だけ食べて、そのうちシークワ―サーの酎ハイも取り合わせていつまでも飲んで腹を満たした。
翌朝は程よい空腹感で目が覚めた。暫くして起きだしたカミさんを伴って朝食会場に出かける。和食、中華、西洋の3軒のレストランの中から選べるとのことで第1日目は和食にしようと決めていた。腹が空いているせいかどれもこれも不味くはなかった。やがて息子も起きだして一人して朝食を済ませたようだった。第1日目の予定として私たちは生まれて初めてスキューバダイビングを選んでいた。11時に所定の場所に集まって、潮風ですっかり錆びついた自動車に乗せられて目的地へと向かった。沖縄の海で私たちは生まれて初めてスキューバダイビングを体験することになる。11時に所定の場所に集まって、潮風ですっかり錆びついた自動車に乗せられて目的地へと向かった。まずは初心者たる私たちに向けての講習会である。あれこれ海の中での決まりについての講釈を聞いたのだが、インストラクターの話は右から左へと流れて行ってきちんと頭に残らない。残っていたにしても果たしてその指示通りに出来るのかどうかわからない。講義を聴いている学生の気持ちが何となく分かってきた。話が終わっていよいよウエットスーツを着込む。右の足をぎゅうぎゅうと押し込んでいたら息が切れた。考えてみるにズボンにしても、靴にしても私は右足から履くし、踏み出すのも右足からのような気がする。いつもの仕来りを変えることにして息を整え、今度は左足を入れたのだが、右足を入れようとするだけで疲れたせいかこれが容易ではない。悪戦苦闘しているところに大阪の出と思われるインストラクターが声をかけてきた。「お父さん、それ手をいれるとこだっせ!」道理でこの図太い足が入らなかったわけである。ようようの思いで下半身がそのゴムのスーツに収まった。今度は足ヒレである。身長から靴のサイズ、視力も既に旅行社に伝えてあるので、私サイズの足ヒレが用意されてはいたのが、これまたどう踏ん張っても入らない。くだんのインストラクターが「サイズがあわへんようですな」と云って少し大きなサイズのものをもってきてくれて、それで漸く収まった。問題は長さのサイズではなく足の甲の厚みだったようだ。泰子の足ヒレを見ると親指の先がきちんと垣間見えるのだが、私の親指は影も形も現わしていない。
私たちは又もや自動車に乗りこんで、国道を渡った途端に海辺についた。今度は船に乗り換えて少しばかり沖合に出る。メンバーは次々とインストラクターの指示で海に入っていった。ダイバーと同じように船の縁に腰を下ろして後ろ向きに飛び込む者もいれば、足からドボンと入る人もいた。最後に私の番となったが、一人私よりも歳は若そうだが、それでもやはり年配の男性が下から押し上げられてきた。どうにも苦しくて無理だ、と言っていたが、私がここで怖気づくわけにはいかない。私も後ろ向きに飛び込もうとしたが、「下にダイバーがいないので足の方から降りてくれ」と言われていくらか心が安らいだ。船の縁が一瞬にして海の中の景色に変わった瞬間に私の体はふわふわと船べりに浮いていた。梯子に掴まって顔を海水につけるように促されて下を覗きこんでボンベの酸素をハ―と吸ってはフ―と吐きだしてみる。「大丈夫なようですね」と云うインストラクターの声が聞こえてきた。ここでインストラクターもマスクを咥えて、今度は手の仕草で下に潜るよう指示してきた。体を横にしたり捻ったりしながら潜って行った。下ではすでにカミさんはじめ何人かの仲間が海の底の砂に膝をついて待っていた。そうだ、この座り方も教わったのだった。私も膝をつこうとするが思うに任せない。仰向けになってしまって船の底が見えたかと思えば、尻もちをついたような格好になってしまう。私たちのインストラクターは私を含めて4人を操る手はずになっていたが、一人が他のグループに吸収されることになった。インストラクター同士で「一人もらいます」とホワイトボードめいた小さな板に字を書いて連れていったのである。一人が私の片手を握ってくれて、ようやくあちらこちらに揺らめいていた私の体は静かになって私の心も落ち着いた。左手を握る手の軍手が赤い。カミさんだった。インストラクターに誘われて私たちは底の砂を這うように泳いでいった。イソギンチャクがゆらめいて、その中に色とりどりの魚が入っては出てくる。岩の割れ目のようなところに指を触れると、ゆっくりとその割れ目の口が閉じられた。珊瑚礁が生きていることがわかる。海中遊泳にも慣れてきた。それでもカミさんとはしっかりと手をつないで、思うが儘に泳ぎ回った。時に息子が目の前に現れる。魚の群れに出会うとインストラクターは小さなホワイトボードに魚名を書いてくれる。それでインストラクターがきちんと私たちを見ていてくれることがつかめた。しばらくして私たちの酸素ボンベに手がかかっているのが目に入り、実は私たちが思う存分に泳ぎ回っていたのではなくて泳がされていたことに気が付いた。