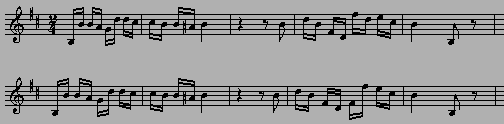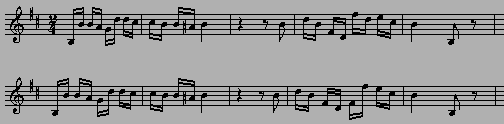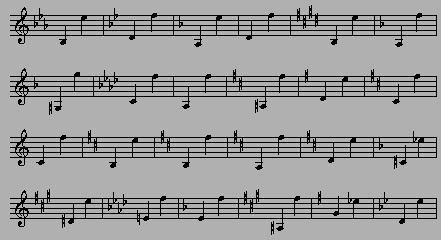冬の旅聞き比べ
どうしてそんな気に成った?
以前、HAMPSONのCDが発売されたとき、レコ芸の喜多尾道冬さんの評に、(さほど酷評では無かった様に思うのですが)伴奏者にSAWALLISCHさんが付いていながらこの調性の選び方はどうしたことだ?と言うような 一文が載っていました。
私のような素人だと、歌いにくいからとしょっちゅう調性を変えてしまいますが、プロのましてやOPERAをも歌う歌手達が楽譜通りの調性では無く変えてしまうなどとは夢思わなかったので、驚きました。勿論歌曲集で連作なのだから、前の曲との流れから、あまり好き勝手に変えてはイケナイのは解るのですが、少しくらい変えたからどうだと言うのだろうと意味を完全に理解も出来ないまま、ずっと、気になって いたのが根底に有りました。
またかなり以前FM放送で「糸を紡ぐグレートヒェン」を数種類聞き比べると言うのをやっていて、同じ曲を何種類も同時に聴くと時代により、歌手によりこんなにも違う表現が有るのだなぁと感心した、これもきっかけの一つにはなっていると思います。
一体我が家には何種類有るんだろう?
幸いというか、何と言うか我が家には、あふれかえるほどの「冬の旅」の録音物が存在致します。沢山聞いた方が違いが解るかも知れないし、半分以上は過去に聞いたように思いますがしっかり、一気に意図を持って聞いたことが無かったので一度やってみても面白いかもと取りかかった次第です。
英世からCD、LPなどで48種類は有ると聞いていましたが、その後、過去30年間の間にFMで放送されたSCHUBERTIADEのライブ録音テープ、テレビで放映された日本でのライブなどなど、出てくる、出てくる・・・。最終的には70種にも及びました。
聞き比べって一体どういう風に?
これだけの数、ボーッと聞いていたのでは、何も成らないし、何かテーマを以て聞いた方が良いとは思うけれど悲しいかな素人の考えること。あまり高尚な事は無理だし、どうしたら良いのかな?。仕方が無い、とにかく始めてみれば、浮かんで来るかも知れない。とお得意の出たとこ勝負。単に思いつくまま”私なりのテーマ”と称してスタートです。取り敢えずは
- 誰がどの曲をどの調性で歌っているのだろうか。
勿論これが動機ですから。
- 各曲それぞれの時間はどれくらい違うのだろうか。
昔の演奏の方が全体的にゆっくりしているんじゃ無いかな?
スタジオ録音とライブではきっと違ったテンポに成る気がする
- 同じ歌手が違う年代に歌ったらどう変わるのか?
20代と60代だと違って当然だろうな?
- また同じ歌手でもピアニストが変わるとどの様に違うのだろうか?
絶対相性とかピアニストの持っているテンポとの絡みも有るに違いない
実にいい加減な発想ですがこのあたりに的を絞って聞いてみることにしました。
その2の時間ですがCDは良いとしてLPは各曲ごとの時間の表示が無いものも有る。又ライブは放送からテープにダビングしているので、当然自分で計らなければなりません。
ちょっとこれは大仕事になりそうだなぁ。
最初の第1歩
数の少ない女声から始めたのですがこれは大失敗でした。
歌っているのは、Ludwig、Fassbänder、白井光子、Price、Lehmann の5人ですが、声域は違う、聞き慣れない、調性も誰一人同じ物は無いなどバラバラなので、最後に聞き直しをしなければ、殆ど、良く解らないという感じです。
これはやはり、スタンダードな、また一番録音数の多いDieskauからの方が解りやすいと思い、方向転換です。 聞き始めてからCDに付いている解説書も出来るだけ読もうと思いましたが、輸入盤で日本語が無いと大変なので全部は読み切れませんでした。参考のため家に有った、ディスカウ、プライ、ホッターの著書も読みました。
- ハンス・ホッター
- ペネロペ・チューリング著、住田健二訳
音楽の友社
- ヘルマンプライ自伝 -喝采の時-
- ヘルマン・プライ著、原田茂生・林捷共訳
メタモル出版
- シューベルトの歌曲をたどって(冬の旅の章のみ)
- フィッシャー・ディスカウ著、原田茂生訳
白水社
- フィッシャーディースカウ(冬の旅に関する部分のみ)
- ケネス・S・ホイットン著
東京創元社
中でもプライの書いた「喝采の時」は御自身が冬の旅に対するイメージ、取り組み方また「遙かな恋人」を歌う際の調性を選ぶ時の事を書いた章が有り聞き比べる上で、とても参考になりましたし、人柄も含めて今更ながらどっぷりはまってしまいました。(以後本からの引用は字体を変えています。)
予備知識1 詩の順序と曲の順序
SCHUBERTがヴィルヘルム・ミューラーの詩を見つけ作曲したわけですが、
前半12曲はミューラーが定期刊行物に発表した詩の順に従って曲をつけました。その後詩集の形に纏められた物から取ったのですが其処では詩の順が大幅に入れ替えられていました。SCHUBERTは既に作曲していたものを除いた残りの詩にその順序のまま曲をつけた
とCDの解説書(西野茂雄氏)には有りました。
では詩の順に曲を並べたらどうなるか?は気になりませんか?。
ディスカウの本には
ハンス・ヨーアヒム・モーザーやギュンター・バウムはときおり、演奏会でミュラーの詩の順序を再現する事を試みたが調性関係やシューベルトが意図した演劇性が乱されてしまった
と有りまたこれはうわさ話の類なのですが、嘗てヘルマン・プライも詩の順番で歌って披露したそうです。あまり評判は良くなかったらしいです。
プライなら挑戦しているというのは本当かも知れないと思い、試しにプライ・ゲージのコンビのCDをシャッフルして作って聞いてみました。
| 作曲順 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 詩の順 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
13 |
6 |
7 |
8 |
14 |
15 |
16 |
| 作曲順 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 詩の順 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
9 |
10 |
23 |
11 |
12 |
22 |
24 |
当然調性の流れなど作曲順の方が聞きやすいのは確かだとは思います。私的には5→13、21→9、12→22、22→24は変でした。
最近の機械を使えば簡単に出来ることですので、一度やってみては如何でしょうか?
予備知識2 いろんな版が有ります
ディスカウの著”シューベルトの歌曲をたどって”の中、冬の旅の章に依りますと
この歌曲の完全な手稿は2つ残されている。そのうち最初のものは訂正と書き込みの為読みに難く成ってしまったので、シューベルトが病で床についているとき、写しを作ることになり、それを後にシューベルトが手直ししたのであるが、その際さらに重要な変更が加えられた物もある。特に第2曲がそうである。この訂正を加えられた写本は長年姿を消していたため、ハスリンガーに続く出版者、フリートレンダー、マンディチェフスキー、シェッファーは残っていた最初の手稿を根拠にして、実際にはシューベルトが初版のために変更した多くの物を誤りとしたのであった。
STRAßENとWEGENどっちが正しい?
ディスカウを聞き終わった頃、聞き比べでは無くHAMPSONのライブのものを、楽譜を見ながら飛ばしながらいい加減に聞いていたのですが20曲目(Der Wegweiser)の中の3節?ですが
Weiser stehen auf den wegen
のwegenの箇所をstraßenと歌っているので、えっ?HAMPSONは間違って歌っている!と驚きました。
私の持っているのは全音楽譜(昭和28年第1刷の年代物)と音楽の友(かなり古い)の2冊でそのどちらもwegenと成っていました。(PERTER版も見ましたがwegenです)。また英世がミューラーの原詩を検索してくれたらそちらもwegenになっています。これはお手本とも言うべきディスカウ&プライを聞けばはっきりすると思って確かめましたらなんと二人ともstraßenと歌っているでは有りませんか!!。既に聞き終わっていたCDをもう一度聞き直して見ましたらwegen有りのstraßen有りので確かに意味からすればどちらであろうと大した違いは有りませんが(本当はかなり違うのかも知れません)気にはなりますので以後その箇所を注意して聞くことにしました。
複数録音しているROBERT HOLLやゲルネはどちらも使っていますし、中にはレーベルが作ったリブレットと実際の歌詞が違っているケースも3つほど有りました。
つい先日書店に行き最近の冬の旅の楽譜を見てきましたが全音楽譜しか見あたらずそれにはwegenと印刷されており、註にstraßenでも良いと有りました。
でも最近では圧倒的にstraßenで歌う人が多くwegen→straßenに変えた人はいてもstraßen→wegenに変えた人はいないのだから楽譜もstraßenと記入した方が良いような気がします。
全部聞き終わって、もう一度ディスカウの著を読みましたら見逃していたこの文を発見しました。
シューベルトが加えた変更は音楽と緊密に結びついていて、それを元に戻すことは許されない。元に戻しても良いという、わずかなの例外をあげるならば次の3つで有る
第4曲の Mein Herz ist wie enfroren (gestorben)
第9曲のUnsere Freuden、unsere Wehen (Leiden)
第20曲 Weiser stehen auf den Straßen (wegen)
この段階でいろんな楽譜や版が有って、一種類では無いことに初めて気が付いたというお粗末です。(予備知識として先に載せています)
メロディーだって違うのが有るのです。
此方は10曲目 Rast のケースです。これで歌っているのはPETER SCHREIER,PETER PEARSの二人で共にテナーです。此方のメロディーの方が原典版のようです。
気が付かなかっただけで他にも有るかも知れません。
原調は高声なのに歌っているのは・・・
元々この曲集の原調はSCHUBERT自身がテナーだったし、テナーでもかなり高い声をイメージして高声用の調で書かれている。ただしここで頭に入れておかないといけないのはSCHUBERTが書いた時代の音は現在より半音近く低い
と言うことです。
改めて音域を見てみると、OPERAと違って意外と音域は狭いので、これをrecordingするくらいの歌手で有れば声が出ないから移調しなければ成らない曲は少ないのだと思います。
(1--->)
どの調で歌えば自分の一番響くまたは曲に合った声で歌えるかと、その調性が曲の流れを遮らないかとの兼ね合いで選んで行く
ようです。
私が聞いた70の中で、女声が6、テナーが12残りがバリトン、バス52で圧倒的に中声及び低声ですし、テナーでも原調どおり歌っているのはプレガルディエン、PETER PEARS2人のみです。シュライアーはより高い調を使用しています。ディスカウに依れば原調の上さらに原典版のメロディーを使用しているPEARSが一番忠実に再現していると言うことに成ります。
ハンス・ホッターってバス?・バリトン?
勘違いをしがちなのですが、テナー、バスは高音が、低音が、出る出ないとかで決まる事が多いとしても音域の広い人は場合は音が出ないと言うことより何処でも出るけれど、テナー、バスより中音域が綺麗に響くからと言う声の質又はオペラの役柄などからも決まって来るのだと言うことです。解りやすい例で言えばモーツアルトのフィガロの結婚の伯爵とフィガロや、ドン・ジョバンニのジョバンニとレポレッロは音域からするとどちらでも歌えるので両方歌っている歌手もいるのですが、響きから少し喉に負担を掛かると思う人や迫力に少し欠ける綺麗な響きの人だとフィガロ、レポレッロは避けるようです。ソプラノとメゾソプラノの場合も同じです。それを頭に入れておかないと調性の選び方でちょっと、混乱してしまうケースも多かったのです。
ハンス・ホッターはリートを歌っているLP、CDなど録音物には殆どバリトンと書かれていますがワグナーのヴォータン、ドン・カルロスの宗教裁判長など演じるときはバス・と称される事も有ったようです。ちなみに、バスと言われるROBERT HOLLよりホッターの方が低い調性を使用している曲も有ります。
LP以前の人たちが早く歌うのは?
古きよき時代、演奏だって昔の人はゆっくり歌っているんだろうな?と予測したのに、驚きの早さです。SPをLP化したのを聞いたこの3人のケースです。
特に第1曲目 GUTE NACHT を
HANS DUHANは1節省略で4’06”
GERHARD HÜSCH は1節省略で3’57”
LOTTE LEHMANNは1節省略で4’19”
一番早いテンポで歌った白井光子さんは4’29”ですが一番遅いテンポで歌ったROBERT HOLL など7’10”もかかります。ごく普通にテンポを想定すれば4分50秒から5分30秒位になるだろうと思います。ところがこの3人は早い上に必ず1節飛ばしているのでこの時代のはやりなのかと思ったのですが、答えはLPの解説書の中で中山悌一さんと村田さんが対談しておられる中に有りました。GERHARD HÜSCH さんから直接お聞きした話で「あの時代は1曲の収録時間が4分15秒前後だったのでそれに収まるように早く歌った実にひどいものだった」と言うのです。そう言われれば5曲目、6曲目など遅い曲ほど早く歌っていることに気が付きます。
実際の歌を聴けない私達にそんな録音物を残さないで!と思いたくも成りますが、それでもやはり素晴らしい歌手達の一部を聞き知る唯一の手段だと有り難くも感じます。
そうした録音をする事を嫌だとは思わなかったのだろうか?と仲間で話し合いましたが、コンサートほどにはrecordingに重きを置いていなかったのでは?と言うことに成っております。