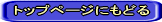『複数の沖縄』を読む
『複数の沖縄 ディアスポラから希望へ』西成彦・原毅彦=編/人文書院2003.3
「本書は2000年6-7月にかけての立命館大学国際言語文化研究所が主催した連続講座『複数の沖縄』をもとに」して出版されたもの。
「複数の沖縄」? 目次を見ていただければ、多岐にわたる問題が様々な視角で論じられていることがわかる。「反復帰論」から約30年、琉球弧のアイデンティティの問題群が総体として浮上しているにもかかわらず、<主体>の有り様が錯綜していることに対応するかのような刺激的論究が並んでいる。
仲里効は「〈内国〉植民地の誕生──大東島・開拓と植民のインターフェース──」と題する文章の末尾にこう書く。
“複数の〈根〉をして語らしめなければならない。その時、巡回するノマドはカリブ海のディスクールが編み上げた〈クレオール〉を近傍から色づかせるだろう。民俗の濃さや風土の備蓄のない移民の島、「非琉球的琉球」な時空、〈内国〉植民地のねじれを生きたシュガーランド。私の中の〈島〉は複数の沖縄として再読されなければならない。”
ここでは印象に残った幾つかの文章を引用するにとどめたい。<共同性>であり、<移民>であり、<コロニアル>である。ただ400年を遡及する琉球弧にこだわった<奄美>の論考は捨てがたい。
ちなみに<目次>を掲げておく。
暴れるテラピアの筋肉に触れる 西 成彦
*Ⅰ*非対称な出会い
地域自立と石垣島 中村尚司
水兵たちと島人たち、あるいは〈治外法権〉の系譜学 石原 俊
沖縄社会の地縁的・血縁的共同性とハンセン病問題 中村文哉
〈内国〉植民地の誕生 仲里 効
〈コラム〉近代沖縄とシェイクスピア受容 鈴木雅恵
*Ⅱ*海と人の動線
海南小記逍遥 原 毅彦
沖縄県の海外出漁 片岡千賀之
〈コラム〉南洋ノート──踊り 仲程昌徳
「植民地は天国だった」のか 星名宏修
「小使」の位置 仲程昌徳
〈コラム〉ブラジルへの沖縄移民史をめぐる二つの小説 浅野卓夫
*Ⅲ*漂うひと、流れる歌
基地、都市、うた 東 琢磨
いくつもの「故郷」へ/いくつもの「故郷」から 崎山政毅
ブラジルの琉球芸能と主体の構築 森 幸一
〈コラム〉親子ラジオと島うた 高嶋正晴
*Ⅳ*島々のプレゼンス
越境の前衛、林義巳と「復帰運動の歴史」 森 宣雄
奄美─〈島尾の棘〉を抜く 大橋愛由等
二〇〇一年夏 沖縄 大空 博
マルチニックから沖縄へ 西川長夫
へテロトピアの沖縄 新原道信
沖縄社会の地縁的・血縁的共同性とハンセン病問題/中村文哉
ハンセン病患者を排除したのは、患者と地縁的・血縁的な利害関係をもつ人たちであった。沖縄社会では、地縁・血縁というゲマインシャフト的な構築物と、職業上での社会関係というゲゼルシャフト的な構築物が重なっているため、地縁的・血縁的なしがらみから自分の身内や親戚筋のなかのハンセン病患者を排除しなければならない現実が生み出されてくる。しかし、患者たちが入園後に築き上げていった地域的な絆も、血縁的なそれも、きわめて沖縄的な構築物であることにかわりない。「社会」から排除されたハンセン病罹患者が生きる社会関係も、やはり地縁的・血縁的なつながりによる。ここに、沖縄社会における地縁的・血縁的関係のもつ両義性が示されている。愛楽園の入園者の社会関係からは、地縁的・血縁的なつながりがもつ残忍さと温かさの両義性を垣間みることができる。
「屋部の焼き討ち事件」が起きて以来、はじめて屋部の人たちが愛楽園を公式に訪れ、エイサーを披露したのは、今から数年前である。そのときに屋部のエイサーを見たある入園者は、「とても土俗的なエイサーで、感動的だったよ。屋部の人たちは、あの事件のことを気にしていて、今回、愛楽園に来て、やっと胸のつかえがとれたよといっていた」と語っていた。ここから、おそらく屋部と愛楽園の新しい絆が芽吹いていくのであろう。
〈コラム〉ブラジルへの沖縄移民史をめぐる二つの小説/浅野卓夫
ブラジル人としての「ナショナル・アイデンティティ」を積極的に前面に出すとき、ジルベルト・フレイレの「混血の美学」を援用する傾向は、日系二世の知識人にひろく見られる現象だが、そう考えれば、「東から来た民」におけるフレイレへの言及は、山里アウグストの「ブラジル人性」の表現ともとれる。いずれにせよ、このような混血的世界像を基盤に据えた「沖縄系ブラジル二世」の作家ならではのダイナミックな話法こそ、沖縄の作家大城立裕の小説「ノロエステ鉄道」との大きな対比点だ。ほぼ同じような主題と取材源(大城立裕が小説のモデルにした人物からは山里アウグストも詳細な聞き書きを行った)を選びながら、大城立裕があくまでも沖縄移民女性個人の声と内面にこだわるのに対し、山里アウグストは沖縄移民の若者が参入するブラジルの文化的多様性の世界を描き尽くそうとする点に、それは明瞭にあらわれているといえるだろう。
※大城立裕『ノロエステ鉄道』(文芸春秋社1989)
山里アウグスト「東から来た民」(『ニッケイ新聞』1998.10.14~2002.7.2)
越境の前衛、林義巳と「復帰運動の歴史」/森宣雄
復帰決定直後の喜びに湧く奄美のもようを伝える一方で、沖縄の新聞には、「沖縄在住の大島群島出身者も沖縄から大島へ帰還したらどうか」との建言や、復帰を揶揄する投稿寸評、「大島の復帰 パン助の補充を考えねばならぬゾ──基地経済」も載せられた。ちまたでは「奄美出身者 は奄美に帰れ」との声が急速に広まり、沖縄市町村長会もこれを要望。こうした世論も背景にして、奄美側から琉球政府に要請された多方面にわたる引継業務などの特別の配慮は大方却下され、逆に補助金や交付金の支給は停滞させられ、債権債務の整理取り立てが厳しく迫られた。
そして在沖奄美出身者については、米軍政府・琉球政府がそれぞれ公務員・軍労務者の継続勤務は不可能と発表、解雇通達と離職勧告を発し、また沖縄に本籍を移すための厳しい条件(高収入など)も示され、さらには引き揚げる場合の所持金制限も当初予定の日本円10万円から7200円に大幅圧縮されていった。これらの措置は、つまるところ財産や既得権益をすべて捨てて出ていけというに等しかった。
こうして奄美復帰後の沖縄社会における奄美出身者差別が始まった。
このいわゆる「沖縄の知られざる差別」についてはこれまで、意図的に黙殺されるか、それとも、ヤマト向けの「沖縄のこころ」の看板が隠蔽しようとする沖縄の排他的なシマ社会の暗部を照らしだそうとする真摯な告発において光を当てられるか、そのどちらかだった。
この戦後沖縄の抑圧的発展の内部に構造化された「大島人」差別とその人間性の収奪・破壊、それが奄美復帰の移行期における野放しの集団的排斥行動の是認をへて、奄美復帰後には在沖奄美人差別として制度化され沖縄社会に常識化されていったのであった。
日米同盟の、そして東アジアの冷戦構造の矛盾の集積地として、〈基地沖縄〉の社会に暴力と抑圧が集中し渦巻いていたからこそ、この抑圧基地の内部において「沖縄人」は「大島人」に対する収奪構造に加担する差別と抑圧の主体として編制された。「大島人」差別はシマ社会の民俗的暗部に神秘化されるべきではなく、戦後琉球・沖縄の歴史経験のひとつとして歴史化されるべきである。
対ヤマトの「沖縄のこころ」の称揚における奄美差別の隠蔽については、新崎盛暉が前掲『戦後沖縄史』366頁における大田昌秀批判で指摘している。新崎は日本社会における/対する少数者の立場・独自性に徹することによって「沖縄の歴史的体験」が、単なる被害者意識にとどまらずに、根源的解放や連帯につながるとの当為や「願望」を語ってきた(新崎「湾岸戦争と沖縄」と同論文をめぐる共同討議『新沖縄文学』88号、1991年参照)。だが「弱者敗者被支配者の歴史的体験」を「強者勝者支配者」のそれと切り離し対比させる歴史認識と差別構造論の設定には、素朴で直感的な民衆の歴史意識がもつ可能性に寄り添おうとする判断(『ウチナーンチュは何処へ 沖縄大論争』実践社、2000年、76頁)があるにしても、大きな限界と背中あわせになる問題性がある。新崎は沖縄の「弱者敗者被支配者の歴史的体験」が保証するであろう「認識における優位性」が、ヤマト化による「脱南入北」によって捨て去られてきたことを慨嘆するが、それでは復帰以前、ヤマト化以前の沖縄を平板な被支配者の平等の地平で神話化させる自己矛盾に接近する。もしも沖縄の歴史経験が「弱者敗者被支配者」の像に塗りこめられるならば、その「認識における優位性」は被害者意議の城を越えられない。
重要な批判もだされているものの、外在的なレッテル貼りに牽引されて議論の背景と核心に踏みこみえていない点で、これまでの沖縄イニシアティブ批判はほぼ過去の達成と到達点の再確認にとどまっており新たな力を生みだしえていない。むしろ論敵の見やすい過誤と粗雑をやりこめるなかで、濃淡の差こそあれ、戦後沖縄の「伝統」護持の姿勢が立論にもぐりこまされ、巨悪を論破する必要の名の下に、沖縄「革新」(むろん歴史論を含む)に内在する形骸化や抑圧、自壊作用が免罪され放置されかねないところにこそ、この歴史論争の危機と限界は露呈している。文化(論)の政治性を批判するならば、その上澄みだけでなく、政治や権力に向かう人間の懊悩とその文化をも同時に対象化し、人間と政治のあり方にえぐりこんでいくべきである。それがもしあるとするならば知識人、歴史研究者の社会的役割であり、権力批判に向かうときに落ちこみやすい陥穽に敏感であるべきだ。論敵を矮小化することで情況認識を狭隘にし、また自己剔抉の契機をなくしていくという陥没が伝染・連鎖していく事態(これが権力のもっとも悪質な罠だろう)をこれ以上繰り返さないためにも、高良らにむけられた「現状追認」だという批判は、その真っ当さのためにこそ思想の問題において跳ね返ってこなければならない。
奄美──〈島尾の棘〉を抜く/大橋愛由等
近世の薩摩による植民地支配が終わって後も、明治以降は鹿児島県の差別的な政策に永年忍従を強いられ、反鹿児島感情を蓄積しながらも、日本への同化を積極的にすすめてきた奄美(人)ではあったが、1946年に沖縄と共に米軍統治下となり、日本から分離されてしまう。米軍統治下では、一転して沖縄と同一の行政区にくくられることへの違和を奄美(人)はいだくようになる。そこで、1953年に奄美単独で日本復帰を果たすまで、高揚した復帰運動の最中に、シマンチュが日本復帰の正当性として“錦の御旗”として揚げたのは、戦前まで奄美は鹿児島県に属していたという“事実”であった。この時のシマンチュは、東京都や兵庫県、宮崎県に所属してはどうかとの少数意見を放ちながらも、現実として選択したのは、反鹿感情を圧殺しつつ「元・鹿児島県大島郡」に復帰するという結果であった。この心の屈折は、復帰運動の成果の自讃に隠れがちではあるが、奄美民族のトラウマになっているのではないだろうか。
奄美(人)は常にアイデンティティに揺れている。島尾はその揺れを敏感に察知して、〈琉球弧〉〈ヤポネシア〉を奄美から発想することでシマンチュに「勇気」を与えてきた。しかし〈ヤポネシアのコインの裏側である日本〉という側面がある以上、〈ヤポネシア〉は日本の国体を「補完し、強化するイデオロギーとして機能」することによって、反対に奄美が日本の“辺境”でありつづける現状に対して、自ら加担することになってしまうのである。
奄美は2003年と2009年に大きな歴史の節目を迎えることになる。日本に復帰(施政権返還)して50周年の節目となる2003年は、復帰運動を推進してきた人たちにとっては祝賀の対象となるだろう。一方で、「奄美の復帰は時期尚早だった」と唱える前利潔の言説が、論戦の舞台にあがることが期待される。2009年は1609年の琉球への薩摩侵攻以来、400年後にあたる。これを機に、1609年を「奄美処分」の第一回目とする主張があり、薩摩──鹿児島に支配されてきた来し方を批判的に総括していこうとする、森本眞一郎を中心とした動きがある。しかし、これを鹿児島側が「奄美併合」を正統化する“400年祭”にまつりあげる可能性も否定しきれない。
このページのトップにもどる