RED MITCHELL
モゴモゴとしたプアな増幅サウンドが哀しくもある
"LIVE AT PORT TOWNSEND"
GEORGE CABLES(p), RED MITCHELL(b),
1992年7月 ライヴ録音 (CHALLENGE JAZZ CHR 70107)
RED MITCHELLというベーシストは1927年に生まれ、このアルバムをレコーディングした4ヵ月後の1992年11月に亡くなっている。従って、この録音時65歳ということになる。かつては白人のRAY BROWNとも言われ、強靭なピチカートが持ち味だった。
しかし、このアルバムでは強靭なピチカートを持つベーシストとは言い難い。それが年齢からくるものなのか意図的にそうしたのかはわからない。
このアルバム、僕は辛い点をつけざるを得ない。その理由としては
1.先にも書いたように、多分、意図的にアンプの増幅を大きくしているのだと思う。年齢的にも握力が昔ほどなくなっていたのではないか。アンプの増幅を頼りにブリッジを低くして若かりし頃の達者な指運びを見せたかったのかもしれない。残念ながら、ピチカートでの強いビート感やアタック感はブリッジを低くしていては生まれてこない。だから、何故、自分の個性まで捨て、更には、ピアノとのバランスを犠牲にしてまでもアンプの増幅を上げてこのように弾いたのか分からない。モゴモゴとしたプアな増幅サウンドが哀しくもある。また、録音の狙いも、デュオというよりはベースがメインであったのかもしれない。ピアノは「刺身のつま」という感じだ。
2.デュオ・アルバムであるが、3-1=2という結果になっている。即ち、ピアノ・トリオからドラムスがいなくなっただけ。ドラムスがいない分をベースとピアノが補って、その密度を上げていくのがデュオとしてのコラボレーションだと思うのだが、これでは、単なる引き算でしかない。
3.ベースが主役になったためピアノが引き立っていない。というか、GEORGE
CABLESの実力としてはこんなものかもしれない。
というようなことで、期待はずれの1枚であった。
①"AUTUMN LEAVES" この曲と④の"BODY AND SOUL"の2曲は、同じくベースとピアノのデュオ・アルバムであるTERJE
GEWELTの"HOPE"(JAZZ批評 275.)にも入っているので比較してみるのもいいだろう。一目瞭然というか一聴瞭然とでも言いたくなる完成度の違いがお分かりいただけると思う。ピアノが輝いていないデュオはデュオとは言えない。この2枚のアルバムの違いは、ピアノとベースのデュオのあるべき姿を示唆した結果になっていると思うのだが、いかがだろう?
②"DON'T BLAME ME"
③"TANGERINE"
④"BODY AND SOUL"
⑤"STELLA BY STARLIGHT"
⑥"BIG 'N' AND THE BEAR" まあ、ご愛嬌というところだろう。誰もヴォーカルまでは期待していないと思うのだが。
JAZZ批評 286.のLARRY FULLERのアルバムでは72歳のRAY BROWNが必要以上のアンプの増幅に頼らず、己がピチカートに全力を傾けていた。多少の指のもつれがあったが、これを潔しとしよう。
最近、もう1枚、時を同じくしてゲットしたデュオ・アルバムがあるので、次回そのアルバムを紹介したいと思う。それは今年亡くなったNIELS-HENNING ORSTED PEDERSENとKENNY DREWのデュオ・アルバムだ。 (2005.09.01)
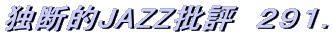


![]()